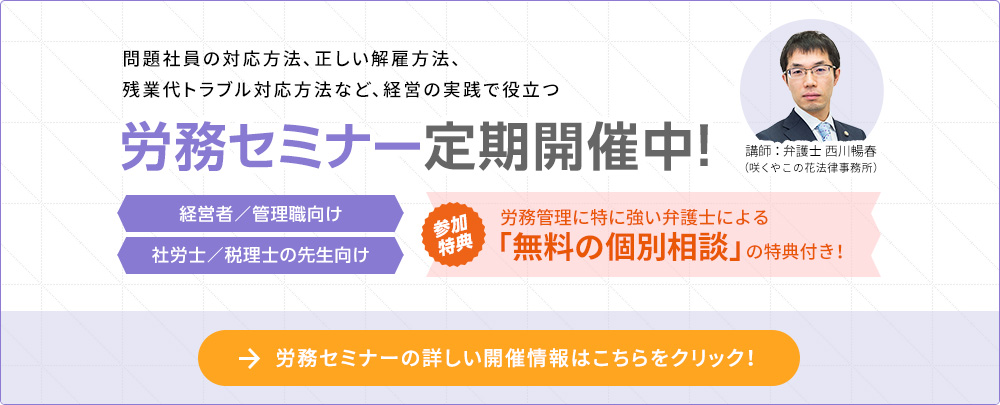パワハラと正当な業務としての指導との境界線はどこにあるのでしょうか。
参考になるのが、岡山地裁の平成24年4月19日判決です。
この事件は、岡山市に本店のある銀行の50歳代の元従業員が上司からの叱責がパワハラであるとして、銀行に対し約4800万円もの損害の賠償を求めた事件です。
この元従業員は、支店長代理、サポートセンター長、人事総務部長代理の3名からパワハラを受けていたと主張しましたが、裁判所は支店長代理による叱責のみをパワハラと認め、110万円の損害賠償を銀行に命じました。
最近は、厳しい指導をするとすぐに「パワハラである」と主張する従業員も増えており、弊事務所でもそのような従業員からのパワハラの主張を心配してご相談に来られるケースが増えています。
パワハラか正当な指導なのかの線引きが難しく、なかには会社側が神経質になりすぎているケースも見られます。
この事件でパワハラが認定された支店長代理は、元従業員がミスをした際に、「もうええ加減にせえ,ほんま。代弁の一つもまともにできんのんか。辞めてしまえ。足がけ引っ張るな。」「足引っ張るばあすんじゃったら,おらん方がええ。」「あほじゃねんかな,もう。普通じゃねえわ。」などと頻繁に叱責を続けていたことが問題とされています。
判決を読む限り、単に仕事ができないことを厳しく指摘するだけの叱責であり、なんら今後の業務改善につながるようなものではないこと、しかもその叱責がその元従業員に対する嫌悪の感情をこめてされていることがうかがえます。
このように従業員に対しての叱責が、今後の改善のための合理的な内容でなく、しかもそこに個人に対する感情が込められている場合、パワハラと判断される傾向にあります。
パワハラには、「叱責・暴言」のほかにも「無視」や「業務上必要のない作業をさせる」などのケースがありますが、いずれも、業務の改善につながるものでなく、従業員に対する人格的な攻撃であるという点で共通しています。
一方で、個人的な感情をまじえず冷静に業務の改善を促す場合、それが厳しい内容を含むものであっても、パワハラにはなりません。
パワハラと主張されることを恐れるあまり従業員に対して必要な指導をしなければ、従業員が成長の機会を失ったり、組織としての強さを失う危険がありますので、必要な指導はきっちりとしていかなければなりません。
パワハラなどのトラブルでお困りの方はぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。一緒にトラブルを解決して、より良い会社を作っていきましょう。
▼ この記事を読んでいただいた方にお勧めの記事はこちらです。 ▼
○ 部下に対する監督責任を理由に懲戒処分をする場合の注意点 https://kigyobengo.com/blog/2923
○ セクハラの訴えがあった場合の社内調査の注意点 https://kigyobengo.com/blog/2893
○ 労働問題でお困りの方はこちら http://roumubengo.com/
○ ご相談はこちらから https://kigyobengo.com/contact
○ ブログの一覧はこちらから https://kigyobengo.com/blog
ご相談はhttps://kigyobengo.com/contactから気軽にお申し込みください。
顧問契約をご希望の経営者の方の面談を随時行っておりますので、https://kigyobengo.com/adviser.htmlからお申し込みください。
なお、このブログの内容はメールマガジンによる配信も行っております。
https://kigyobengo.com/mailmagazinにメールマガジン登録フォームを設けておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。
 06-6539-8587
06-6539-8587

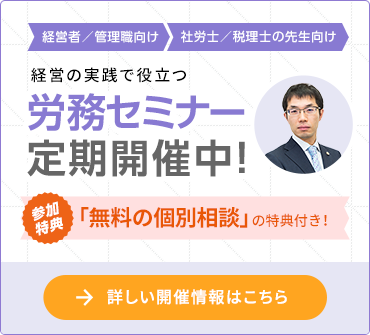



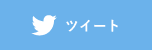

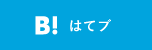
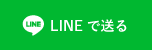

 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る