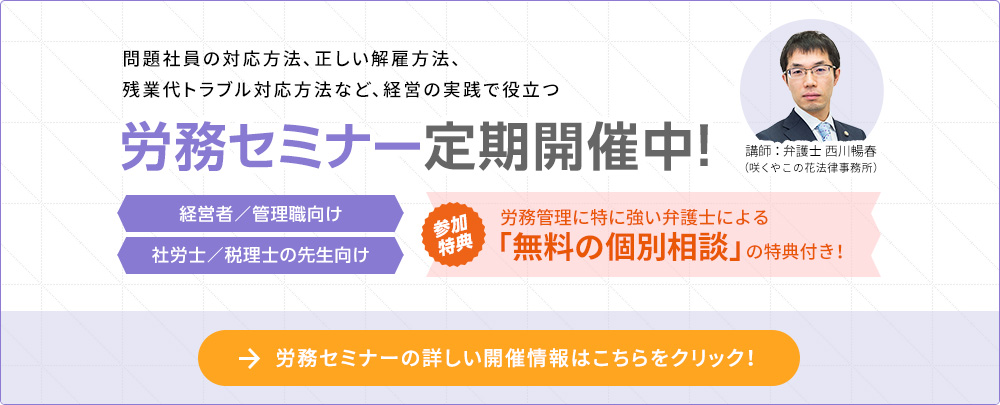前回のブログ(https://kigyobengo.com/blog/it/1439をご参照ください)では、システム開発などを受託するときには、必ず、開発するシステム等の要件定義を十分に行い、制作するシステム等の仕様を明確にしておかねばならないというお話をさせていただきました。
そうして仕様が決まったシステムをベンダーが完成させ、ユーザーに納品すると、ユーザーは「検査」(検収ともいいます)を行います。
今回は、この「検査」について、契約書で定める場合の注意点をお話しさせていただきます。
あまり意識されていないことですが、実は、この「検査」というのは非常に重要です。
たいていの契約書では「検査」に合格してはじめてベンダーに代金が支払われることになっているからです。
つまり、おかしな理由で「検査」を不合格にされると、代金を支払ってもらえないという悲惨なことになるのです。
よくトラブルになるのが、
ユーザーが検査した結果、当初予定していなかった仕様の変更や機能の追加を求めてきて、検査の合格通知をしない
というトラブルです。
この場合、ユーザーは「まだ検査に合格していないから代金の支払いは待ってくれ」と言ってきます。
もちろん、そのユーザーからの仕様の変更や機能の追加が常識の範囲内であれば、ユーザーの希望をきくのがよいでしょう。
しかし、ユーザーが常識の範囲を超えて、次々と仕様の変更や機能の追加を求め、そのために納入物が「検査」にいつまでも合格せず、システム制作代金の支払いが先延ばしになると、ベンダーの資金繰りが厳しくなってきます。
なぜ、このようなトラブルが起こるのでしょうか?
そもそもユーザーはベンダーとの協議により確定した仕様のシステムの開発をベンダーに発注したのですから、その仕様の通りにベンダーが開発を終えれば、「検査」は合格としなければなりません。
「やっぱり追加で機能をつけてほしい」とか「当初予定していた仕様を修正してほしい」といったユーザーの要望は、本来は検査に合格した後の、追加・修正の要望なのです。
ユーザーは、ベンダーが納入したシステムが、発注したシステムの仕様と一致していれば、検査は「合格」として、代金を支払わなければならないのです。
ところが、ユーザーがこのことを理解していないため、検査のときに、
「やっぱり追加で機能をつけてほしい」とか「当初予定していた仕様を修正してほしい」
といった理由で合格を先延ばしにされて、トラブルになります。
そこで、そのような事態を防ぐため、納入されたシステムについてユーザーが検査することができるのは、
「納入されたシステムが最初に決めたシステムの仕様と一致しているかどうか」という点
についてだけであるということを契約書で明確にしておかなければなりません。
ユーザーが検査を不合格とできるのは、納入されたシステムが最初に決めたシステムの仕様と一致していない場合だけだということを、契約書の中ではっきりさせておかなければならないのです。
さらに、ユーザーに検査をしてもらっても、その結果をベンダーに通知してもらえないと、のちのち、検査の結果について争いが生じます。
そこで、ユーザーからベンダーに対して、検査の結果を通知してもらうことを、契約で決めておかないといけません。
このとき、ユーザーが検査の不合格を通知する場合には、不合格となった理由も一緒に通知してもらうようにしておかねばなりません。
ユーザーが何も理由をつけずに完成されたシステムを不合格とできるのであれば、検査の対象を、最初に決めたシステムの仕様との一致・不一致に限った意味がなくなってしまうからです。
ユーザーがベンダーに検査の不合格を通知する場合には、不合格の理由も一緒に通知すること、不合格の理由とすることができるのは、最初に決めた仕様との不一致だけだということを契約書の中で明確にしておかなければならないのです。
そして、「検査に合格すれば、ユーザーからシステム制作代金を支払ってもらえる」ということも、はっきりさせておかなければなりません。
また、ユーザーがいつまでも検査を行わないと、いつまでも検査に合格せず、ベンダーにいつまでもシステム制作代金が支払われないことになってしまいます。
そこで、ベンダーが制作したシステムをユーザーに納入してから、例えば「7日間、ユーザーが具体的な理由を示して不合格の通知をしない場合には、検査に合格したものとみなす」という規定も設けておく必要があります。
これらをまとめると、「検査」について契約書に入れておくべき条項は、たとえばおおむね次のようになります。
ここでいう甲とはユーザー、乙とはベンダーのことです。
第△条
1 甲は、乙が本件契約に基づいて開発したシステムを甲に納入した後、速やかに、当該システムが第○条に定めるシステムの仕様に合致しているか検査する。
2 甲は、前項に基づく検査の完了次第、検査結果を速やかに乙に通知するものとする。
3 甲は、乙が本件契約に基づいて開発したシステムが第1項の検査に合格しない場合、その旨のみならず、不合格となった具体的な理由も併せて乙に通知しなければならない。但し、不合格の理由とすることができるのは、納入物と第○条に定めるシステムの仕様との不一致に限る。
4 乙が本件契約に基づいて開発したシステムを甲に納入した後、7日間が経過するまでの間に、甲が何らの異議を述べない場合、本件システムは、本条所定の検査に合格したものとみなされる。
このように、ベンダーの制作したシステムがいつまでもユーザーの検査に合格せず、いつまでもシステム制作代金を支払ってもらえないという事態を防ぐために、契約書の中でユーザーの検査対象を限定しておくことは、非常に重要なことなのです。
もちろん、ベンダーとしてはシステム開発の過程で、進行の程度を定期的にユーザーに報告し、システムの仕様の変更が必要なら、その都度ユーザーとベンダーが協議したうえで、修正・変更をしていくべきです。
しかし、このようにしてベンダーとユーザー間で確定した仕様を、ベンダーが完成させたのに、ユーザーがさらに修正や変更を言ってきて、いつまでたっても、代金が支払われないという事態を防がなければなりません。
そのためには、契約書の中で、きっちりと法的な防御をしておかなければならないのです。
顧問契約をご希望の経営者の方の面談を随時行っておりますので、https://kigyobengo.com/contact.htmlからお申し込みください。
なお、このブログの内容はメールマガジンによる配信も行っております。
https://kigyobengo.com/mailmagazinにメールマガジン登録フォームを設けておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。
 06-6539-8587
06-6539-8587

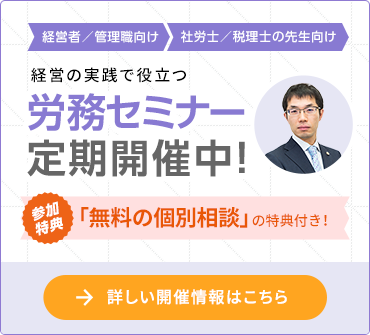



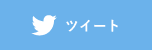

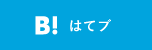
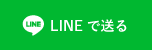

 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る