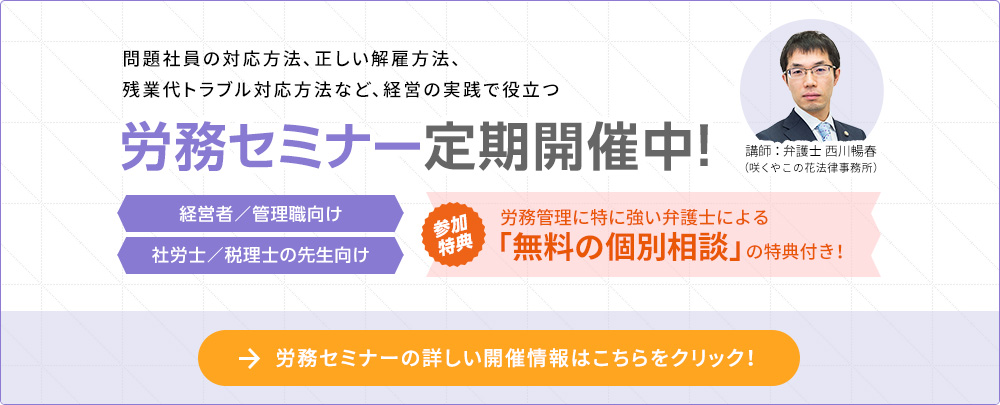インターネット広告の市場が成長するにつれて広告をめぐるトラブルも増えています。
たとえば、インターネット上でバナー広告などの広告スペースを提供したが、後日、広告主の事業が詐欺的商法だったことがわかった場合、 広告スペースを提供した業者はどのような責任を負うのでしょうか。
この問題をインターネット上の広告について判断した裁判例はまだ見当たりません。
ただ、新聞広告などの伝統的な広告手法の分野では、広告主の事業が違法な内容であったことが後日判明した場合に、 広告主だけでなく広告媒体を提供した新聞社等が訴訟の被告とされるケースがあり、多くの裁判例がでています。
これらの裁判例はインターネット上の広告についても参考になります。
最高裁は、詐欺的事業に広告を提供した新聞社の責任について「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって 読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得た場合には、 真実性の調査確認をして虚偽広告を提供してはならない義務がある」としています。
少しわかりにくいですが、おおざっぱに言うと、 「広告の際、広告スペースを提供する者はその広告内容が適法かどうかについて徹底的に 調べるまでの義務はない。しかし、通常の法律知識とをもって審査していれば怪しいと感じることができたのそれに気づかずに広告を 載せてしまった場合は、消費者に対して損害賠償責任を負うことがある」 ということになります。
今後はインターネット上の広告についても、後日虚偽広告などの事実が判明した場合に、広告主だけでなく、 広告スペースを提供した アフィリエイターや広告代理店などが訴訟の被告とされるケースが増えると思われます。
広告の申込みがあった場合にどこまで広告内容を審査しなければならないかはケースバイケースです。
たとえば、FX業者など営業に許可がいるような事業主に広告枠を提供する場合、その業者がちゃんと許可を得ているかどうかなどについては 事前に調べてから広告枠を提供する必要があるでしょう。
「この広告はちょっと怪しい」と感じた場合はぜひ法律専門家に相談してください。
無用なトラブルを避けることが事業発展の第一歩です。
 06-6539-8587
06-6539-8587

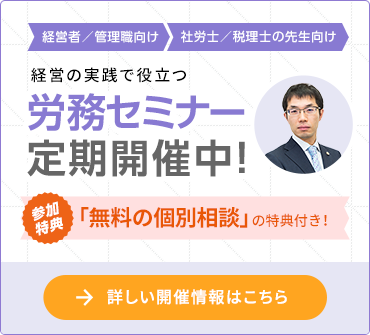



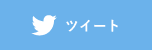

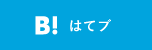
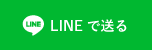

 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る