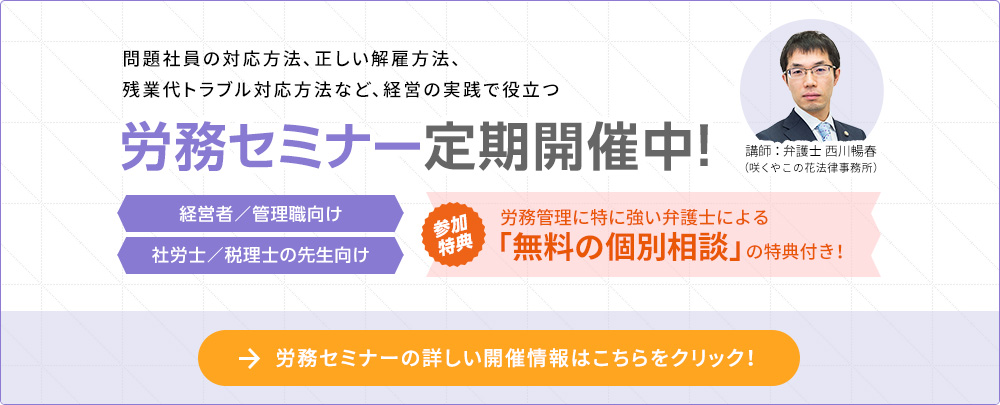モバイルゲームやオンラインゲームに関するご相談が大変増えています。
特に、GREEやモバゲーのサービスのユーザーが増え、ゲーム業界のすそ野が広がっていっているのを日々感じています。
いままでゲームの業界に手を出したことがなかった方が、新しくゲーム業界に入ってくるということもかなり増えているようです。
ただ、ゲームについては著作権や契約の処理が複雑で、トラブルも大変増えています。
このブログでもトラブルをなくすために何が必要なのか、まずは基本的なところから書いていきたいと思います。
ゲームを作る場合、自社だけでなく、フリーのスタッフに頼んだり、あるいは制作会社に外注に出すことも多いと思います。
このようなときに注意しなければならないのは、
① 外注に出したゲームのプログラムや映像の著作権をちゃんと自社に移転しているかどうか
② 外注に出したゲームのプログラムや映像の著作人格権をきちんと処理できているかどうか
③ 外注するゲームの仕様をきちんと特定できているか
という3点です。
実は③についてのトラブルが一番多いのですが、今回は一番基本の①についてお話します。
A社がゲームの製作をB社に外注するケースで考えます。
この場合、B社が制作したゲームの著作権は原則としてB社に帰属します。
ということは、A社はこのゲームの著作権をB社から譲り受けることを契約書で明確にしておかなければなりません。
よくありがちな誤解は、「製作費を支払ってるんだから、契約書にわざわざ書かなくても著作権は移転しているのがあたりまえだろ」という考え方です。
この考え方は成り立ちません。「B社が著作権を維持したうえでA社にはゲームとして使うことを認めるだけ」という権利関係もありうるからです。こういう権利関係は「利用許諾」と呼ばれます。この場合も当然製作費は支払うのですから、「製作費を支払ったこと=著作権を移転したこと」にはなりません。
では、A社はB社から著作権を移転してもらえれば安心でしょうか。
実はそうではありません。
B社はもしかすると別のC社にゲームをさらに外注しているかもしれません。あるいは会社に発注しなくても、フリーのスタッフDに外注しているかもしれません。
この場合、ゲームの著作権は原則として、C社やDに帰属することになります。
ですので、「BからAに著作権が移転する」と契約書で書いていても、そもそもCからBに著作権が移転していないと、結局Aは著作権を取得できません。
B社とC社の間でトラブルが発生するなどした場合、Cが自社が作ったゲームを勝手にA社が公開した、とA社を訴えてきたらA社は負けてしまいます。
このリスクについての対処をどうするか考えなければなりません。
すぐに思いつく対処方法は、B社とA社との契約書で下請けを禁止にしてしまうことです。
しかし、この方法はB社がこっそり外注してしまったり、あまり意識せずにフリーのスタッフに頼んでしまった場合には対応できません。
では、どうすればよいでしょうか。
通常、こういうケースでは、B社とA社の契約書の中で、B社に発注したゲームの著作権がすべてB社にあることを保証してもらったうえで、それをA社に移転させるという処理をしています。
もし、ゲームの著作権の処理で困られた時は、顧問弁護士にご相談いただくか、当事務所までご相談ください。
咲くやこの花法律事務所では企業のリスクについて解説した漫画をつくりました。https://kigyobengo.com/manga
から是非ご覧ください。
 06-6539-8587
06-6539-8587

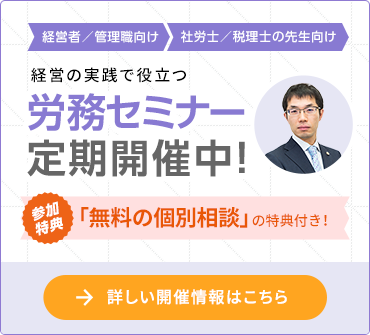



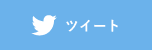

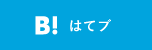
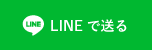

 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る