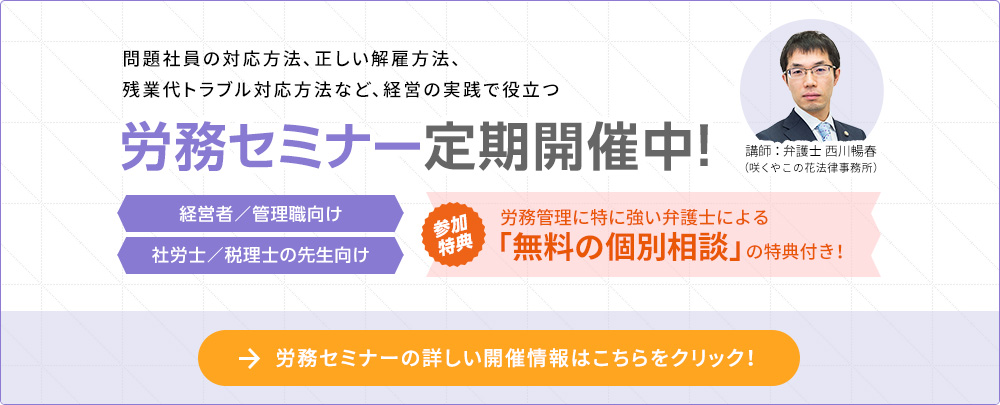前回に引き続き、Webサービスの利用規約を作るときに注意すべきポイントについて(https://kigyobengo.com/blog/1558をご参照ください。)お話させていただきます。
今回は、②の
「消費者契約法に配慮して、免責条項を定めなければならない」
という点について、詳しくお話させていただきます。
Webサービスを提供していると、サーバーに負担がかかってしまった場合などに、サービスを停止しなければならない場合もあり得ます。
そして、サービスの停止によって、Webサービス提供者が予想さえしなかった大きな損害がユーザーに生じ、ユーザーからその賠償を請求されることがあり得ます。
Webサービスを提供する場合、このようなサービスの停止等によりユーザーが被った損害を全部賠償することはできません。
そこで、Webサービスの利用規約の中に、
「会社は、サービスの利用に関連してユーザーが被った損害を賠償しない」
という内容の条項を入れておく必要があります。
これを、法律的には「免責条項」と呼びます。
ただ、ユーザーが一般消費者である場合は注意しなければならないことがあります。
というのは、一般消費者に対するサービスについては、消費者保護を目的とした「消費者契約法」という法律があるからです。
この「消費者契約法」のなかに、
「会社や事業者が、消費者である個人と取引したときに、会社や事業者が損害賠償責任を負ってしまった場合、その損害賠償責任の全部を免除する契約条項は無効とする」
という条文があります。
そのため、仮にWebサービスの提供する会社が「サービスの利用に関連してユーザーが被った損害を一切賠償しない」と利用規約に定めても、この条項は無効とされてしまうおそれが大きいのです。
そこで、免責条項の内容を、損害賠償責任を全部免除するような内容にするのではなく、
「会社は、サービスの利用に関連してユーザーが被った損害については、○○円を上限として賠償する」
というように賠償責任の上限を定める方法をとらなければなりません。
具体的には、利用規約の中に、次のような条項を入れておくことになります。
第○条
第1項
弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、ユーザーに損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
第2項
弊社の賠償額は、賠償の原因となる事由が発生した時点から○○○円を限度とします。
第2項で定める限度額は具体的に金額を定めてもいいですし、ユーザーが支払った利用料金の総額の何パーセントという決め方でもいいでしょう。
ただし、消費者契約法上、このような損害の一部を免除する規定についても、事業者に故意または重過失(故意に匹敵するような重大な不注意をいいます)がある場合は無効になるとされています。
ですので、この条文はつまり重大な過失がある場合は対応できません。
しかし、実際には「重大な過失」にあたるような事案はほとんどありませんので、賠償額の上限をあらかじめ決めて利用規約に盛り込んでおくことは、いざユーザーとトラブルになった時の交渉におおいに威力を発揮します。
これに対して、さらに強い効果を求めて、「一切責任を負わない」と書いてしまうと、前述のように消費者契約法により無効になってしまい、賠償額を制限する効果が全くなくなってしまうのは皮肉なことです。
消費者契約法に配慮していざ交渉になった時にも実際に効果を主張できる責任限定条項にしておくことが大切です。
▼ この記事を読んでいただいた方にお勧めの記事はこちらです。 ▼
○ 契約トラブルを回避できる契約書の作り方② https://kigyobengo.com/blog/174
○ インターネット上のトラブルでお困りの方はこちらから
https://kigyobengo.com/internet
○ ご相談はこちらから https://kigyobengo.com/contact
○ ブログの一覧はこちらから https://kigyobengo.com/blog
ご相談はhttps://kigyobengo.com/contactから気軽にお申し込みください。
顧問契約をご希望の経営者の方の面談を随時行っておりますので、https://kigyobengo.com/adviser.htmlからお申し込みください。
なお、このブログの内容はメールマガジンによる配信も行っております。
https://kigyobengo.com/mailmagazinにメールマガジン登録フォームを設けておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。
 06-6539-8587
06-6539-8587

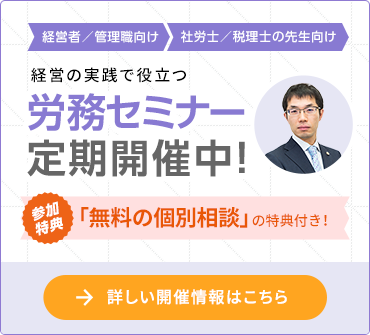



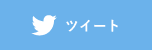

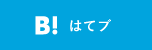
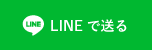

 一覧ページへ戻る
一覧ページへ戻る