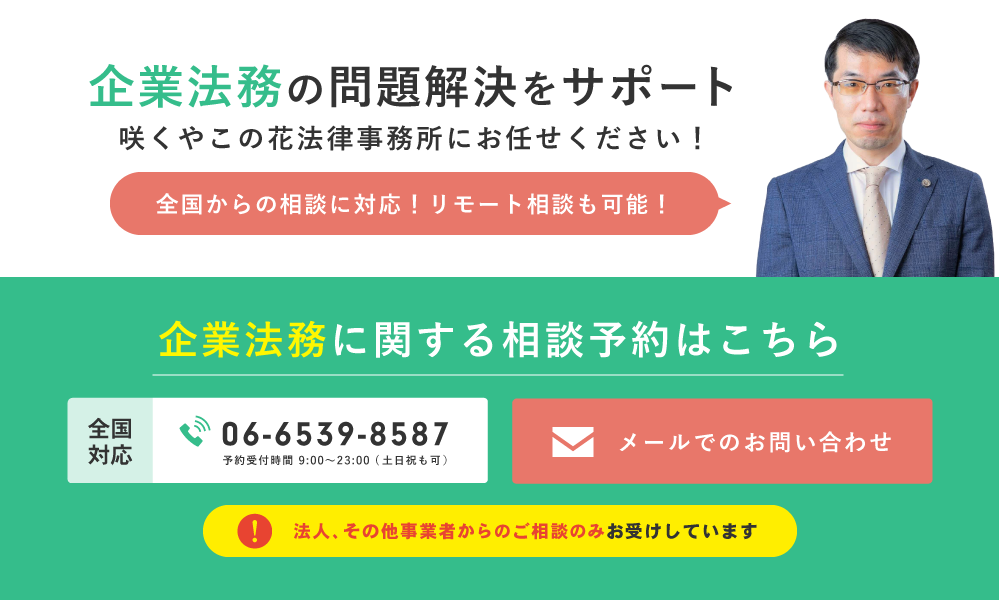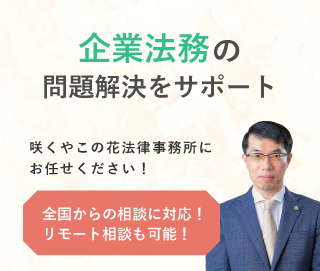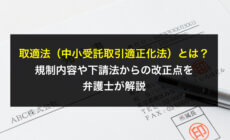こんにちは、咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
事業承継の場面で活用されることが多いのが、黄金株(拒否権付株式)です。
上手な使い方をすれば、後継者に経営を譲った後も、前経営者が経営の重要事項については拒否権を持つことができ、後継者が意思に反するような経営をした場合に歯止めを効かせることが可能です。
一方で、黄金株には、以下のような注意点がありますので、導入するかどうかについては慎重に判断する必要がありますし、黄金株の内容自体も慎重に設計することが必要です。
- 拒否権を持つ人が正常な判断能力を失い会社の経営を阻害することもある
- 黄金株の内容が登記により公開される
- 事業承継税制の活用に支障を生じることがある
この記事では、黄金株(拒否権付株式)とはそもそも何かということから、具体的な活用方法、黄金株のデメリット、発行手続きなどについてご説明していますので、黄金株活用の際の重要な注意点、留意事項について理解していただくことができます。
また、最後に咲くやこの花法律事務所の黄金株に関するサポートに内容についてもご案内しています。
それではみていきましょう。
黄金株の発行の手続きについてはこの記事でも詳しく解説していますが、手続に間違いがあると黄金株が無効になるなどの問題が生じるため、実際の手続きは弁護士にご依頼いただくことが必要です。
咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしておりますのでお困りの方はご相談ください。
▼黄金株(拒否権付株式)に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,黄金株(拒否権付株式)とは?

黄金株とは、株主総会決議事項または取締役会決議事項について拒否権をもつ株式をいいます。どのような決議事項について拒否権を持たせるかをあらかじめ定めることができ、例えば、取締役の選任や解任、取締役の報酬の決定、会社組織の変更、事業の譲渡、合併などといった様々な決議事項について、拒否権を持つように設計することが可能です。
別名「拒否権付種類株式」などとも呼ばれます。英語ではgolden shareと呼ばれます。
▶参考情報:種類株式とは?
黄金株は、「拒否権付種類株式」などとも呼ばれることからわかるように、「種類株式」の一種です。種類株式とは、普通株式とは権利の内容が異なる株式をいいます。「黄金株」は、一定の株主総会決議事項または取締役会決議事項について、拒否権があるという点で普通株式とは権利内容が異なる種類株式です。
(1)会社法の根拠条文
この黄金株は、会社法第108条1項8号により認められている制度です。
▶参考情報:会社法第108条1項8号
第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。(以下略)
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
・参照元:「会社法」の条文はこちら
この条文からもわかるように、「黄金株」については、株主総会決議事項または取締役会決議事項について、通常の株主総会または取締役会での決議とは別に、黄金株をもつ株主だけによる株主総会(「種類株主総会」と呼ばれます)による決議が必要であるというのがその正確な権利の内容になります。
黄金株の保有者が1人であるという典型的なケースでは、「黄金株をもつ株主による決議が必要」ということは、すなわち、「黄金株をもつ株主の同意」が必要ということになり、黄金株を持つ株主に拒否権があることになりますので、拒否権付種類株式と呼ばれます。
2,事業承継の場面での黄金株(拒否権付株式)の活用方法
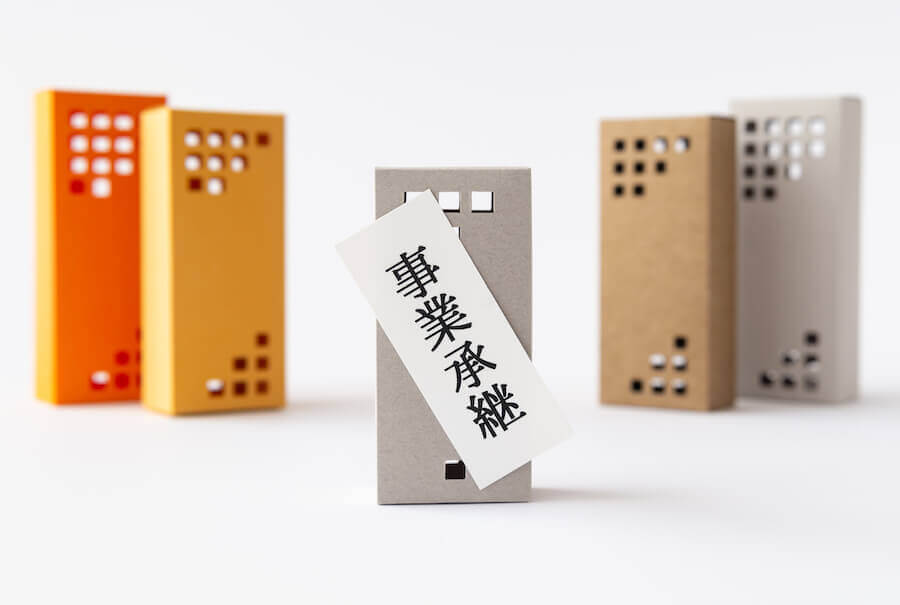
黄金株は、企業の経営を後継者に受け渡す事業承継の場面で活用されています。
例えば、企業の現経営者が後継者に経営を承継させ、株式も譲渡する場面で、黄金株1株だけを自分に残すことで、事業承継後も後継者による経営に対して拒否権を持ち、コントロールを効かせることが可能です。
以下では活用の具体例をいくつかご紹介したいと思います。
(1)取締役の選任や解任についての拒否権をもつ黄金株の場合
取締役の選任や解任は株主総会の過半数による決議で行われます。
そのため、事業承継の結果、後継者が過半数の株式をもつようになると、後継者が自由に取締役の選任や解任をすることができてしまうことになります。
これについて一定の歯止めをかけておきたいという場合は、事業承継後も、現経営者が黄金株を1株だけ保有することで、後継者による取締役の選任や解任について、拒否権を持つことができます。
(2)取締役の報酬の決定についての拒否権をもつ黄金株の場合
取締役の報酬の決定は株主総会の過半数による決議で行われます。
そのため、事業承継の結果、後継者が過半数の株式をもつようになると、後継者が自由に役員報酬を決めることができてしまい、高額の役員報酬を設定することにより、会社財産の減少を招くおそれがあります。
このような事態を防ぐためには、事業承継後も、現経営者が黄金株を1株だけ保有することで、後継者による役員報酬の決定に拒否権をもつことができます。
(3)事業譲渡や合併についての拒否権をもつ黄金株の場合
事業譲渡や合併は株主総会で3分の2以上の賛成を得る特別決議で承認されます。
そのため、事業承継の結果、後継者が3分の2以上の株式をもつようになると、現経営者としては意思に反する事業譲渡や合併であっても、後継者の意向でできることになります。
事業承継後も、現経営者が黄金株を保有することで、事業承継や合併の承認に拒否権をもつことができます。
(4)黄金株で拒否権を設定できる項目の具体例
その他、さまざまな項目について拒否権を設定することが可能です。
主な例は以下の通りです。
| 役員に関する事項 | ・取締役の選任や解任 ・取締役の報酬の決定 ・代表取締役の選任や解任 |
| 会社財務に関する事項 | ・重要な会社財産の譲渡 ・多額の融資を受けること |
| 会社の人事・組織に関する事項 | ・事業譲渡や合併 ・新株の発行 ・会社の組織に関する変更 ・重要な従業員の人事 |
3,黄金株(拒否権付株式)のデメリット
黄金株についてはそのデメリットもよく理解しておく必要があります。
デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
(1)拒否権が会社の経営を阻害することもある
黄金株のデメリットとしては、拒否権が万が一、不合理に乱発されることになると、会社の経営にとってむしろマイナスになってしまうということがいえます。
例えば、会社の組織の変更について、黄金株による拒否権の対象とした場合に、黄金株の保有者が適切な判断能力を失ってしまい、本当に会社にとって必要な組織変更であっても拒否権を行使してしまい、会社の経営を阻害してしまうということも考えられます。
そのため、このような事態になったときは、黄金株を会社が強制的に買い取ってしまうことができるように黄金株を制度設計しておく必要があります。
例えば、黄金株発行時に、一定期間経過後は、会社が取締役会決議により黄金株を時価で強制的に買い取ることができるという条項を定めておくことが考えられます。このような条項は「取得条項」と呼ばれます。
(2)事業承継税制の活用に支障を生じる
事業承継税制の活用については、先代経営者等黄金株不保有要件という条件が定められています(経営承継円滑化法施行規則第6条1項第7号リ等)。
その結果、黄金株を後継者以外の者(例えば先代経営者)が持っている場合は、事業承継税制の適用を受けることができません。
そのため、事業承継税制の活用を考えている場合は、黄金株は発行しないか、または発行したとしても事業承継税制を活用する前に普通株式に転換したり、あるいは後継者に譲渡することを想定しておく必要があります。
▶参考情報1:「経営承継円滑化法施行規則第6条1項第7号」については以下も参考にご覧下さい。
リ 当該中⼩企業者が会社法第百⼋条第⼀項第⼋号に掲げる事項についての定めがある種類の 株式を発⾏している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中⼩企業者の 代表者(当該中⼩企業者の経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
・参照元:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」の条文はこちら
▶参考情報2:事業承継税制の先代経営者等黄金株不保有要件については以下のPDFの17ページをご参照ください。
・参考URL:「-中⼩企業経営承継円滑化法申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度】令和2年4⽉施⾏」(pdf)
▶参考情報3:事業承継税制全般についてはこちらをご参照ください。
・参考URL1:中小企業庁「事業承継税制(一般措置)の前提となる認定」
・参考URL2:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」
(3)黄金株の内容は登記により公開される
黄金株で設定した拒否権の内容は会社の商業登記により公開されます。
そのため、例えば、経営に関する重要事項のほとんどが黄金株による拒否権の対象となっている場合、その内容が登記により公開される結果、取引先によっては、後継者に実権がなく、事業承継が進んでいない会社というとらえ方をすることも考えられます。
(4)拒否権対象事項について決めるときに手間がかかる
黄金株を1人の株主にのみ交付するという典型的なケースの場合、黄金株による拒否権の対象となる項目について決める際は、黄金株の保有者の同意が必要になるということが黄金株の拒否権の内容になります。
そのため、例えば取締役の選任が拒否権対象事項になっている場合、通常必要になる株主総会決議だけでなく、黄金株保有者の同意を書面(より正確には種類株主総会の株主総会議事録)でもらう必要があり、会社にとっては手間になります。
特に、黄金株保有者が高齢になり、スムーズに書面での手続きができなくなった場合や、黄金株保有者が高齢で判断能力を失ってしまった場合、同意の取得に手間がかかることが懸念されます。
この点については、前述のとおり、例えば、黄金株発行時に、一定期間経過後は、会社が取締役会決議により黄金株を時価で強制的に書いとることができるという条項を定めておくことで、ある程度リスクを回避しておくことが可能です。
(5)黄金株が相続されると会社の経営に支障が生じる
黄金株の所有者が亡くなった場合には、黄金株が相続人に相続されます。
しかし、黄金株の相続人が会社の経営について正しく判断できるかどうかはわからないため、基本的に黄金株が相続されるという事態はさけるべきです。
この点については、相続が発生したときは、会社が黄金株を時価で強制的に書いとることができるという条項を定めておくことで、リスクを回避しておくことが重要です。
4,メリット、デメリットを踏まえた検討が必要
ここまでデメリットについてご説明しました。
一方で、黄金株活用のメリットとしては、黄金株を活用することで事業承継を円滑に進めやすい、事業承継に早期に着手しやすいということがあげられます。
企業の経営者が後継者に経営を承継させる際に、黄金株を活用すれば事業承継後も後継者による経営に対してコントロールを効かせることが可能になります。
そのため、一気に後継者にバトンタッチするよりも、現経営者にとって事業を譲ることについての心理的な抵抗が少なくなり、事業承継に早期に着手しやすく、事業承継のプロセスも円滑に進みやすいと言えます。
このような黄金株活用のメリットとデメリットを踏まえたうえで、黄金株を導入するかどうかの検討が必要です。
5,黄金株(拒否権付株式)の発行手続き・発行方法
黄金株の発行手続きには、大きく分けて、以下の2通りがあります。
- (1)現在発行されている普通株式の一部を黄金株に変更する方法
- (2)現在発行されている株式とは別に新たに黄金株を発行する方法
以下で順番にご説明したいと思います。
(1)現在発行されている普通株式の一部を黄金株に変更する方法
こ場合の手続きの流れは以下の3ステップです。
Step1:
株主総会を招集して定款変更を行う
定款変更して、黄金株の内容について以下の点を定めることが必要です。
- 黄金株の発行可能株式の総数
- 黄金株に拒否権を与える項目など黄金株の権利内容
▶参考情報:定款変更とは?
定款とは会社の基本規則のことで、全ての法人で設立時に定款が作成されています。黄金株を発行する場合はこの定款でその内容を定めることになりますので、定款の変更が必要になります。定款の変更は株主総会の特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要)により行うことができます。
Step2:
黄金株に変更することについて株主との合意書を作成する
普通株式を黄金株に変更することについて、株式の内容が変更になる株主と会社の間で合意書の作成が必要です。
Step3:
変更登記をする。
以下の点について変更登記を行います。
- 黄金株の発行可能株式総数と黄金株の内容
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
上記が基本的な手続ですが、黄金株を発行する以前に、既に黄金株を発行している場合は、既存の黄金株の保有者全員の同意が必要になります。
また、既に黄金株以外の種類株式が発行されている場合で、黄金株の追加により、種類株主に損害を与える恐れがある場合はその種類株式の種類株主総会の特別決議が必要とされています。
(2)現在発行されている株式とは別に新たに黄金株を発行する方法
現在発行されている株式とは別に新たに黄金株を発行する場合は、黄金株の内容を定める定款変更を行ったうえで、募集株式の発行手続(第三者割当増資)を行うことになります。
▶参考情報1:募集株式の発行とは?
募集株式の発行とは、会社設立後に行う株式の追加発行を言います。
▶参考情報2:第三者割当増資とは?
第三者割当増資は、募集株式の発行のうち、特定の第三者に株式を割り当てる方法です。
募集株式の発行は、第三者割当のほかにも、不特定多数から株主になる人を募集する「公募」、すべての株主に平等に株式を割り当てる「株主割当」がありますが、黄金株発行の場面で行われるのは、旧経営者など特定の第三者に株式を割り当てる第三者割当増資です。
現在発行されている株式とは別に新たに黄金株を発行する方法の対応手順は以下の通りです。
Step1:
株主総会を招集して定款変更と募集事項の決定を行う
定款変更して、黄金株の内容について以下の点を定めることが必要です。
- 黄金株の発行可能株式の総数
- 黄金株に拒否権を与える項目など黄金株の権利内容
さらに、募集事項の決定を株主総会で行います。
募集事項の決定とは、新たに発行する募集株式の内容などを決めることを言います。
具体的には以下の点を株主総会で決議します。
- 発行する株式の種類および数(例えば、黄金株1株など)
- 払込金額(黄金株の発行に対して株主が会社に払い込む金額)
- 払込期日(株主が会社に払込みをする期日)
- 増加する資本金および資本準備金に関する事項
Step2:
黄金株の引受けについて申し込みを受ける。
前述の通り株主総会で決めた募集事項を黄金株を引き受ける相手に通知して、黄金株の引受けについて申し込みをしてもらいます。
Step3:
黄金株を割当てて払込みを受ける。
払込期日に前日までに、申込者に対して、割り当てる株式の数を通知して、黄金株を割り当てます。
そのうえで払込期日に払込みを受けます。
Step4:
変更登記をする。
以下の点について変更登記を行います。
- 資本金の額
- 黄金株の発行可能株式総数と黄金株の内容
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
上記が基本的な手続ですが、黄金株を発行する以前に、既に黄金株を発行している場合は、既存の黄金株の保有者全員の同意が必要になります。
また、既に黄金株以外の種類株式が発行されている場合で、黄金株の発行により、種類株主に損害を与える恐れがある場合はその種類株式の種類株主総会の特別決議が必要とされています。
6,黄金株(拒否権付株式)の相続税評価額
事業承継の場面では黄金株の相続税評価も気になると思います。
黄金株の相続税評価は普通株式と同じです。
拒否権を考慮せずに普通株式と同様に評価されます。黄金株だからと言って評価額が高いということはありません。
7,黄金株に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に黄金株についての咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご説明します。
(1)黄金株の導入、設計、発行手続きのご相談
咲くやこの花法律事務所では、黄金株を発行するかどうかのご相談、黄金株の内容の設計に関するご相談、発行に必要な手続きの代行のご依頼を承っています。
黄金株の発行には、株主総会の招集を正しく行ったうえで、適切な定款変更案を作って定款変更を行うことが必要です。
この記事でご説明したような黄金株のデメリット面にも配慮し、リスク回避策を講じておく必要があります。
また、現在発行されている株式とは別に新たに黄金株を発行する方法を採用する場合は、第三者割当増資の手続を正しく行うことも重要です。
これらの手続きに不備があると黄金株が無効になってしまいますので、発行手続きは弁護士にご依頼いただくことをおすめします。
咲くやこの花法律事務所では企業法務に精通した弁護士が黄金株についてのご相談をお受けておりますのでご相談ください。
黄金株の導入、設計、発行手続き等に関するご相談費用
●初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)
(2)事業承継全般のご相談
咲くやこの花法律事務所では、黄金株の導入だけでなく、事業承継全般のご相談もお受けしています。
株式の承継方法、金融機関や取引先との関係の調整、株式を分散させないための対策、遺留分対策など、事業承継の各種課題についてのご相談が可能です。
咲くやこの花法律事務所では事業承継に精通した弁護士がご相談をお受けします。
事業承継の成功のためには早めに正しいスタートを切ることがまず重要ですので、早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
事業承継に関する相談費用
●初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)
▶参考:なお、事業承継における弁護士の役割については以下の記事で詳しく解説していますので併せてご参照ください。
8,咲くやこの花法律事務所の弁護士へ問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
9,黄金株(拒否権付株式)に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
黄金株(拒否権付株式)に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年7月28日
 06-6539-8587
06-6539-8587