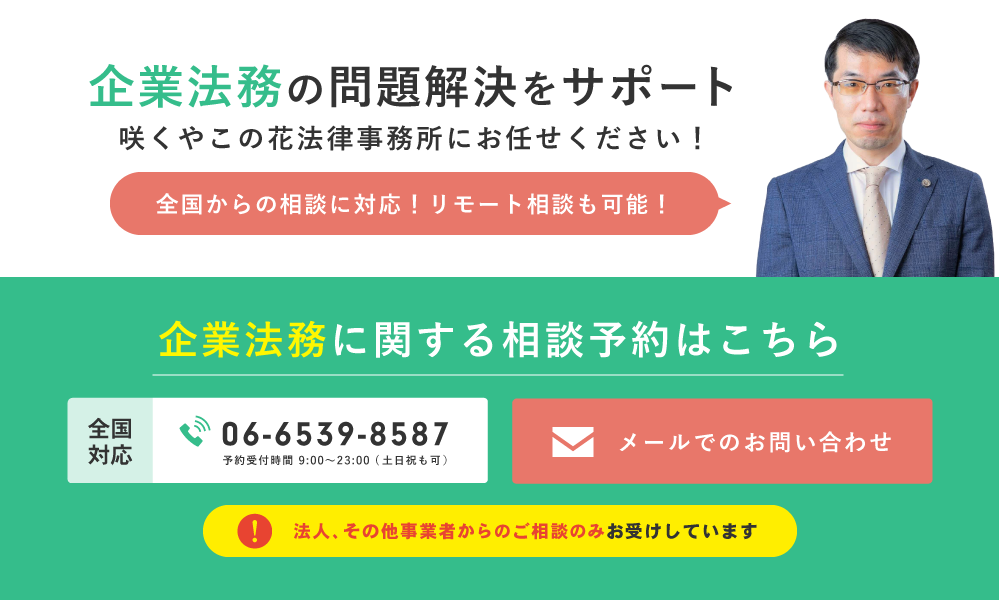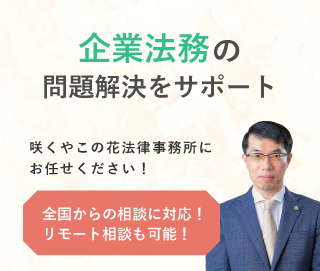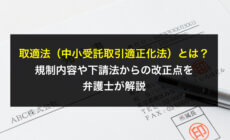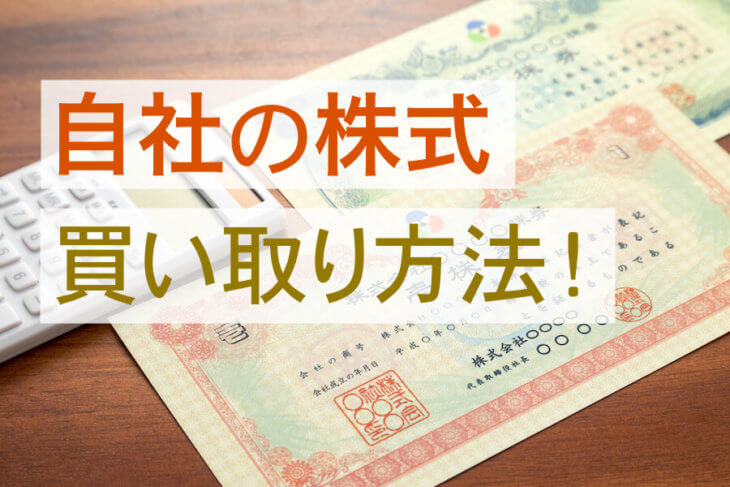
こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自社の株式を買い取りたいけれどもその方法がわからずに悩んでいませんか?
あなた、あるいはあなたに賛同する人があわせて3分の2以上の議決権をもつ場合は、相手の同意がなくても強制的に買い取りが可能です。
一方で、議決権が3分の2未満の場合は、強制的な買い取りはできません。その場合は、少なくとも3分の2以上になるまでは、相手と交渉しながら買い取りを進めていく必要があります。
ただし、どちらの場合であっても、法律上のルールを理解したうえで買い取りを進める必要があります。手続の不備があると、あとで株式の取得が無効と判断されてしまうリスクがあります。
そうなると、株式取得後は本来の株主に対して招集通知が出されていないという意味で株主総会が正しく開かれていなかったことになり、株主総会で決議される取締役の選任の効力の問題にまで発展してしまう危険があります。
この記事では非上場の企業を念頭に、経営陣が自社株の買い取りを進める手段や、進める際に必ずおさえておかなければならない注意点について解説します。必ず弁護士に事前相談の上、正しい手続きで買い取りを行うようにしてください。
咲くやこの花法律事務所では、会社経営者からのご依頼を受けて、少数株主からの株式の買い取りの交渉を多数担当させていただき、買い取りに成功してきた実績があります。
共同経営者から株式を買い取る場面、事業承継の準備として株式を買い取る場面など様々なケースがあると思いますが、株式の買い取りでお困りの場合はご相談ください。
自社株の買い取りに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績については以下をご参照ください。
▶株式の買い取りに関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,株式を買い取るメリットとは?
中小企業において自社株を買い取るメリットとしては以下の点があげられます。
(1)書面決議による株主総会の省略が可能になる
最も大きいメリットは、自社株を買い取って株主を自分1人にしてしまうか、または身内だけにしてしまえば、株主総会の省略が可能になるということでしょう。
前提として全ての株式会社では、毎年、定時株主総会を開いて、決算の承認を得ることが法律上義務付けられています。株主総会を開かないでいると、法律違反になりますので、その点を不備として他の株主から指摘されかねません。
特に、株式会社では、役員報酬を定款で定めていない場合は、株主総会で役員報酬を決めることになっています。株主総会を開かずに役員報酬を決めていると、後になって、受けとった役員報酬の返還を求める裁判を起こされ、敗訴しているケースも存在します。
他の株主を会社から排除し、株主を自分1人だけ、あるいは自分の意向に賛成してくれる経営陣など身内だけにしてしまえば、合法的に株主総会を省略することが可能になります。
具体的には書面のやりとりだけで済ませることができる書面決議の制度(会社法第319条、第320条)を利用することにより、株主総会を開かなくても株主総会決議があったものとみなすことができます。
中小企業では、毎年の株主総会を開いていないというケースも少なくありませんが、これは大変なリスクです。
特に、株主総会を開かずに役員報酬を決めていると、正しい手続きを経ずに会社から報酬をとっていたことになり、後で役員報酬の返還を求められる危険があります。
前述の書面決議の制度等を利用できない場合は、必ず株主総会を開くことが必要です。
(2)株主代表訴訟のリスクをなくすことができる
会社に、身内以外の株主がいると、例えば会社が大きな損失を出した場合は、取締役が十分注意して仕事をしていなかったからだとして、損害の賠償を求める訴訟を起こされるケースがあります。
これを株主代表訴訟といいます。
株主を自分1人だけあるいは身内だけにしてしまえば、このような訴訟リスクを気にすることなく、自由に経営することができます。
例えば、現経営者が後継者に経営を譲る事業承継の場面で、後継者が少数株主の意向を気にせずに自由な経営ができるように、株式の買い取りを進めるケースも多くなっています。
(3)相続による株の分散を防ぐことができる
株主が多数いると、その株主の死亡時に株式が相続されます。相続により、株式が分散し、株主の数が増えていきます。
中には連絡が取れない株主、面識のない株主が出てきて、対応に苦慮することになるリスクもあります。また、株主総会の招集通知の送り先も増えていくことになります。
こういった問題を回避するためにも、株主を自分1人にしておくか、身内だけにしておくことは検討に値します。
相続による株の分散を防ぐというテーマについては、株式が相続された場合に会社がその株式を強制的に買い取ることを会社の定款で定める方法での対応も可能です。
会社法第174条に基づく「相続人等に対する株式の売渡しの請求」と呼ばれる制度です。
ただし、この制度は、自分が死んでしまった場合に、自分の相続人がこの制度を利用して株式の売渡しの請求を受けてしまい、会社を乗っ取られるリスク(「相続クーデター」と呼ばれます)があることに注意が必要です。
▶参考情報:「相続人等に対する株式の売渡しの請求」の制度については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
2,買い取りをする前の準備事項
株式の買い取りをする前の準備事項として以下の点をおさえておいてください。
(1)株券がない場合は注意が必要
会社法上、会社は「株券発行会社」と「株券不発行会社」にわかれます。
そして、「株券発行会社」については、株式の譲渡の時に株券を売主から買主に渡さなければならず、これをしなければ株式の譲渡が無効になるという重要な注意点があります(会社法第128条1項)。
会社法が施行された2006年5月1日より前に設立された会社については、株券発行会社が大半です。現実に株券を発行しているかどうかにかかわらず、定款に株券を発行しないことが書かれていなければ、法律上、株券発行会社として扱われます。
株券発行会社かどうかの判断基準、確認方法は以下で詳しく書いていますのでご参照ください。
(2)株券発行会社なのに株券がない場合の対応
現実には、株券発行会社なのに株券が発行されていない会社が少なくありません。また、株券を発行していても、買い取ろうとしている相手が株券を紛失しているケースもあります。
この場合、株券の引き渡しを受けることができませんので、株式の買い取りに合意しても、譲渡が無効になってしまう危険があります。
そのため、株式の買い取りを進める前の事前準備として、株券不発行会社への変更ををしておくことが必要です。株券不発行会社への変更には、株主総会を開いて定款を変更することが必要になります。
株券不発行会社にしてしまえば、株式を買い取る際に株券の引き渡しを受ける必要はありませんので、株券のことを気にする必要はありません。
3,株式買い取り交渉の進め方
買い取りのための準備ができたら、まずは、合意による買い取りを目指していきましょう。
買い取り相手に連絡をして、株式の買い取りを提案し、買い取りに応じてもらえるように話をしていくことになります。また、買い取りに応じてもらえる場合は、その金額について話をしていくことになります。
(1)買取価格の決め方
非上場企業の場合は、株式の買取価格は、当事者間の交渉で自由に決めることができます。
税理士や会計士に株式の価値を算定してもらうことが一般的ですが、必ずしも算定された価格にこだわる必要はありません。ただし、買取価格が実際の株式の価値よりも著しく安い場合は、買主が贈与税を負担することになります(みなし贈与課税)。
(2)合意ができた場合は契約書の作成が必要
買い取りについて合意ができた場合は、売主との間で株式譲渡契約書を作成する必要があります。
株式譲渡契約書の注意点については以下の記事で解説していますのご参照ください。
(3)買い取りについて会社の承認が必要
中小企業では大半の場合、株式を買い取る場合に株主総会または取締役会の承認を得なければならないことが、会社の定款で定められています。
定款がどのような記載になっているか確認しておきましょう。特に、株主総会の承認が必要な場合は、招集通知を全株主に送る必要があり、手間がかかります。
株主総会での承認の手間を避けるために、以下のように、承認手続きの省略に関する規定を入れてしまうことも1つの方法です。
買い取りの準備として、前述の株券不発行会社への変更のための定款変更を行う場合は、その際の株主総会で一緒に譲渡承認の規定についても上記のように変更すると、手間が省けるケースもあります。
(4)合意により買い取る場合の手順
合意により買い取る場合の具体的な手順例は以下の通りです。
- Step1:まずは株主と話し合って買い取りについて合意する。
- Step2:株式譲渡契約書を作成する。
- Step3:買主は会社に株式譲渡の承認の申請をする(会社法第137条)
▶参考情報:
株券不発行会社の場合は、買主は売主と共同で会社に譲渡承認の申請をすることが必要です。
一方、株券発行会社の場合は、株券を会社に提示することにより、買主は買主単独で譲渡承認の申請が可能です(会社法施行規則第24条2項)。
- Step4:会社は株主総会または取締役会で譲渡を承認する(会社法第139条1項)。
- Step5:会社は譲渡を承認したことを買主、売主双方に通知する(会社法第139条2項)。
- Step6:買主は承認の通知が届いたら、会社に株主名簿の記載の変更を請求する(会社法第133条)
▶参考情報:株主名簿とは、会社法上すべての株式会社が作成を義務付けられている株主の名簿です。
株主の氏名や株式の数、取得年月日などが記載されます。
▶参考情報:株券不発行会社の場合は、買主は売主と共同で株主名簿の記載の変更を請求することが必要です。
一方、株券発行会社の場合は、株券を会社に提示することにより、買主は買主単独で会社に株主名簿の記載の変更を請求することが可能です(会社法施行規則第22条2項)。
- Step7:会社が株主名簿の記載を変更することで譲渡手続きが完了する
(5)株式買い取りと税金
株式の売主に対しては、株式の譲渡により得た利益について譲渡所得税が課されます。
一方、買主は、買取価格が実際の株式の価値よりも著しく安い場合に、贈与税を負担することになります(みなし贈与課税)。
4,買い取りに応じず拒否された場合に強制的に買い取る手段
買い取ろうとする相手が買い取りに応じない場合は、強制的に買い取ることが必要になります。
少数株主から強制的に株式を買い上げる手法を「スクイーズアウト」といいます。
「スクイーズアウト」には複数の手段があり、以下のように今持っている自社株が多ければ多いほど、強制的な買い取りがしやすくなります。
(1)議決権の90パーセント以上を持っている場合
「特別支配株主の株式等売渡請求」の制度を利用することにより、比較的簡単な手続で株式を強制的に買い取ることができます。
詳細は以下で解説していますのでご参照ください。
「特別支配株主の株式等売渡請求」の制度を利用する場合、買い取り価格について双方で合意ができない場合、買主が売主に対して一方的に決定して通知することができます。
ただし、売主側は買主から通知された買取価格に不満がある場合は、裁判所に価格決定の申立ができ、裁判所で価格を決めてもらうことができます。
(2)議決権の3分の2以上を持っている場合
議決権の3分の2以上を持っている場合は、「株式併合」の手法を利用して強制的な買い取りが可能です。
この方法は株主総会が必要になるため、やや手間がかかります。株式併合を利用したスクイーズアウト(株式の強制的な買い取り)については、以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。
株式併合の制度を利用する場合も、買い取り価格について合意ができない場合、買い取り価格は、裁判所の審理によって決まることになります。
(3)3分の2未満の議決権しかもっていない場合
3分の2未満の場合は強制的な買い取りはできません。
この場合の進め方は以下の2通りです。
1,他の株主と協力して株式併合を目指す
自分が3分の2未満の議決権しか持っていない場合でも、他に協力している株主がいて、それとあわせれば3分の2以上の議決権になる場合は、株式併合によるスクイーズアウトを進めることが可能です。
2,交渉により3分の2の確保を目指す
一部の株主との間で買い取り交渉をして、議決権の3分の2以上を取得できれば、株式併合の手法を利用して強制的な買い取りが可能です。
5,【補足】株式買取請求とは?
ここまで、自社の株式を買い取る方法について、交渉により買い取る方法、強制的に買い取る方法の両方をご説明しました。
最後に補足として、「株式買取請求権」についてご説明しておきたいと思います。
株式買取請求権とは、株主の側から会社に対して自分のもっている株式を買い取ることを請求する権利をいいます。
例えば、株式併合や合併の場面でこのような権利が株主に認められています。つまり、株式買取請求権は、株式を売りたい株主が「株式を買い取ってくれ」と請求する権利です。自分が株式を買い取りたいときは、株式買取請求権の問題ではありませんので、注意して下さい。
6,自社の株式の買い取りに関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所における企業向けのサポート内容についてご説明したいと思います。
(1)株式買取交渉、スクイーズアウトのご相談
咲くやこの花法律事務所では、会社法務に精通した弁護士が、株式買取交渉やスクイーズアウト(株式の強制的な買い取りの手続き)についてのご相談をお受けしています。
弁護士がご相談者の状況に照らしてベストな手段を助言します。
株式の買い取り交渉を弁護士にご依頼いただくことで、買い取りの手続きを正しく進めることが可能です。また、感情的なトラブルがあり、合意による買い取りが難しくなっているケースでは、第三者である弁護士に依頼して交渉すると、感情面のもつれをいったんおいて合理的な交渉が可能になることがあります。
一方、スクイーズアウト(株式の強制的な買い取りの手続き)の検討する場合は、株主総会の招集通知や株主への通知、裁判所への許可申し立てなどの手続を正しく行うことが非常に重要です。
株式の買い取り手続に不備があると、その後に会社で行う株主総会の決議の効力がくつがえされる可能性があり、会社にとって重大なリスクになります。
咲くやこの花法律事務所では、弁護士が買い取りの交渉や、強制的な買い取りの手続きを代理で行うことで、株式の買い取りを確実にサポートします。
咲くやこの花法律事務所の会社法務に精通した弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)M&Aや事業承継についてのご相談
M&Aや事業承継の準備として株式の買い取りを検討されている方もおられると思います。咲くやこの花法律事務所では、企業のM&Aや事業承継についてもご相談をお受けしています。
契約書の作成やリーガルチェック、事業承継のスキーム作りやその実行を弁護士がサポートします。
咲くやこの花法律事務所の会社法務に精通した弁護士へのご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
なお、事業承継に関する弁護士の役割については以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年9月24日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」株式買い取りに役立つ情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587