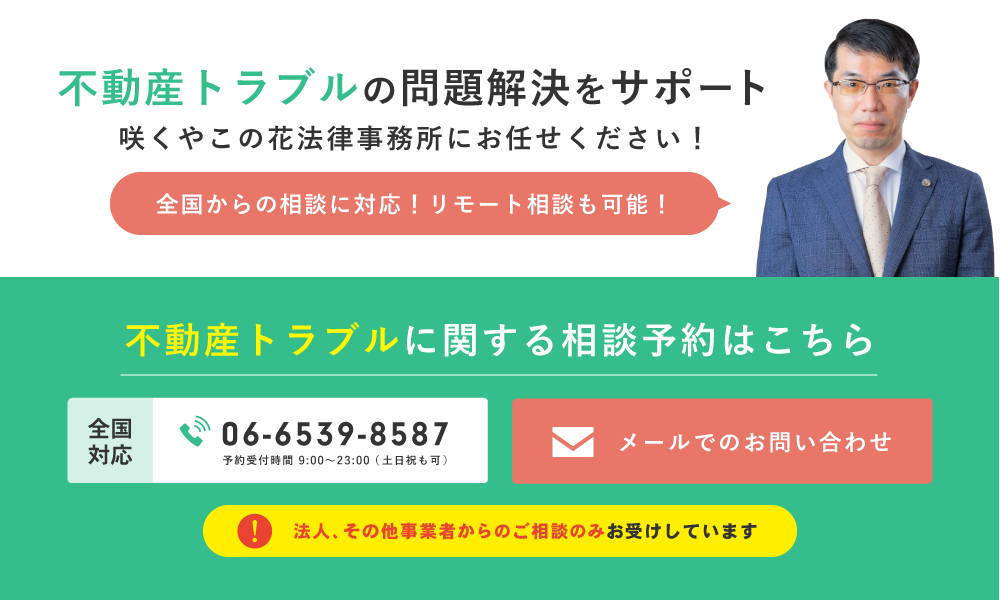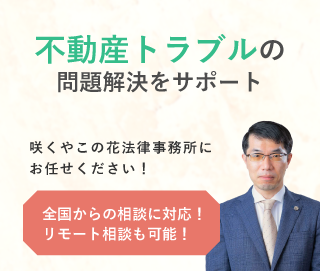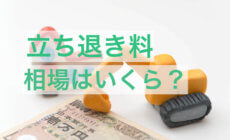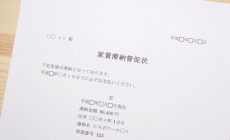こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
賃貸している住宅や店舗、オフィスなどの立ち退き交渉がうまく進まずに悩んでいませんか?
立ち退き交渉を上手に進めるにはおさえておくべきポイントが多数あります。
知らないまま進めると、交渉が進まず立ち退きの実現が難しくなってしまったり、多額の立ち退き料を支払うことになって後で後悔することになってしまいます。
今回は、弁護士である筆者の経験も踏まえ、賃貸人側の立場からみた立ち退き交渉のポイントについてご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、立ち退き交渉の場面で、交渉前の確認ポイントをおさえながら、実際の交渉をスムーズに進めていただけくことが可能になります。
立ち退き交渉を賃貸人自身が行うことで、立ち退き交渉が感情的なやりとりになってしまったり、賃借人側から不合理な要求をされてしまい、収集がつかなくなってしまっているケースが少なくありません。
立ち退き交渉は交渉開始前に弁護士に相談することが重要なポイントです。弁護士に相談することで立ち退き交渉について具体的な進め方のポイントや落としどころを事前に把握して交渉を開始することができます。
この記事では、立ち退き交渉を弁護士に依頼するメリットについても解説します。
咲くやこの花法律事務所では、立ち退きに関してご相談を受け、サポートを行ってきました。咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。
▶立ち退き交渉に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,立ち退き交渉には2つの場面がある
立ち退き交渉とは、賃貸している住宅や店舗、オフィスなどを賃借人に退去してもらうための交渉のことを指します。「賃貸している建物について建て替えの必要がある場合」や「賃貸している建物を賃貸人自身が利用したい場合」あるいは「賃借人に家賃滞納などがある場合 」などに、賃借人との立ち退き交渉が行われます。
立ち退き交渉の場面は大きく分けて以下の2つがあります。
(1)賃借人側に契約違反がなく、賃貸人の都合で立ち退きを求める場合
賃借人側に家賃滞納などの重大な契約違反がなく、賃貸人の都合で立ち退きを求める場合は、立退料の支払が必要になることがほとんどです。
建物を建て替えるために立ち退きを求める場合や、賃貸人が自身で建物を利用するために立ち退きを求める場合が、このケースにあたります。
(2)賃借人側に家賃の滞納などの契約違反がある場合
賃借人側に家賃の滞納や無断転貸などの契約違反がある場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することにより、賃借人に店舗の明け渡しを求めることができます。
この場合、立退料は必要ありません。
家賃滞納の場合の立ち退き交渉については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
この記事では、上記のうち、1つ目の「賃借人側に契約違反がなく、賃貸人の都合で立ち退きを求める場合」(大家都合の立ち退き交渉)についてご説明します。
この記事では、建物からの立ち退き交渉についてご説明します。土地を貸しており、借地の立ち退き交渉が必要な場合は以下をご参照ください。
2,大家都合の立ち退き交渉では原則として立退料が必要
大家都合の立ち退き交渉には、賃借人に対する立退料の支払が必要になることが通常です。
以下では、なぜ立退料が必要になるのかについての法律上のルールを確認しておきたいと思います。
(1)大家都合の立退きには「正当な理由」が必要
住居や店舗、事務所など建物の賃貸借契約には、借地借家法が適用されます(ただし、平成4年7月までに契約された賃貸借契約については借家法が適用されます)
借地借家法でも借家法でも、建物の賃貸借契約について賃貸人の側から、賃貸借契約の解約を申し入れる際は、正当な理由が必要であるとしています。
そして、この「正当な理由」のルールは、賃貸借契約の期間が満了したときに、賃貸人の側から次回の更新を拒否する場面にも適用されます。契約期間が満了した場合でも「正当な理由」がなければ賃貸人の側から更新を拒否することはできません。
(2)「正当な理由」には立退料の支払が必要
前述の「正当な理由」は、「老朽化した賃貸建物を建て替えるため」、「再開発のため」あるいは「賃借している物件を賃貸人自身が利用したいため」などということだけでは、通常は認められません。
建物の老朽化や賃貸人自身の利用の必要性などの事情に加えて、立ち退きを余儀なくされる賃借人に対して一定の金銭的補償をしなければ、「正当な理由」を認めないとする判例が大多数を占めています。
事例1:
居酒屋の立退料算定事例(平成30年7月20日東京地方裁判所判決)
老朽化したビルの居酒屋(賃料8万8457円)の立退料を1156万1000円と算定した事例
事例2:
賃貸アパートの立退料算定事例(平成29年1月17日東京地方裁判所判決)
築44年の賃料7万4000円のアパートの立退料を200万円と算定した事例
このようなルールがあるため、賃貸人側から、「正当な理由」があるとして立退きを求めるためには、賃借人に対する金銭的補償(立退料)の支払が必要になってくるのです。
(3)立退料が不要なケース
立退料が必要な事情についてご説明しましたが、以下のケースでは立退料は不要です。
1,賃借人側に家賃の滞納などの契約違反があり、賃貸借契約を解除できる場合
賃借人側に家賃の滞納や無断転貸などの契約違反がある場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することにより、賃借人に貸室の明け渡しを求めることができ、立退料は不要です。
2,定期建物賃貸借契約の場合
定期建物賃貸借契約では、賃貸借契約の更新をしないことが法律上認められています。
そのため、賃貸人は、契約期間が満了すれば、「正当な理由」があるかどうかにかかわらず、賃借人に明渡しを求めることが可能であり、立退料は必要ありません。
3,建物が極端に老朽化して重大な危険がある場合
建物が極端に老朽化して重大な危険がある場合は、立退料を支払わなくても、立退きを求める「正当な理由」があるとされるケースがあります(平成28年9月6日東京地方裁判所判決等)。
ただし、これはごく例外的な場面に限られます。
立ち退き料については、以下の記事や動画で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
▶参考情報:立ち退き料の相場はどのくらい?4つのケースに分けて詳しく解説
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「立ち退き料とは?3つのケースに分けて相場を弁護士が解説」の動画でも詳しく解説しています。
3,立ち退き交渉を進める前の確認事項5つ
まず、交渉を始める前に、交渉にあたって問題になる重要な点を確認し、交渉の全体像を把握しておくことが重要です。
立ち退き交渉前の確認事項5つは、以下の通りです。
- (1)立退料の相場は「テナント」か「住宅」かで異なる
- (2)賃借人が建物をどのような用途に利用しているのかを把握する
- (3)次回の更新時期を把握する
- (4)近くの同等の物件との賃料差額を把握する
- (5)立ち退きの場合に返還が必要になる敷金があるか?
それぞれ、順番に詳しく解説していきます。
(1)立退料の相場は「テナント」か「住宅」かで異なる
立ち退き交渉で主要なテーマになることが多いのが、立退料です。立退料の相場は、住宅の立ち退きか、テナントの立ち退きかで大きく変わってきます。
1,賃貸住宅の場合
賃料5万円~10万円程度の老朽化した賃貸住宅の立退料は、100万円~200万円程度が相場になることが多いです。
2,テナントの場合
一方、テナントについては、店舗なのか、事務所やオフィスなどかによって違いがあります。
店舗の立ち退きのケース
店舗の立ち退きでは、営業補償や新店舗の内装費が立退料の内容に加わるため、老朽化した建物に入居している小規模(賃料10万円前後)の飲食店や理髪店の立退きの場面でも、1000万円から1500万円程度の立退料が相場です。
店舗の立ち退きについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
事務所やオフィスの立ち退きのケース
これに対し、事務所やオフィスの立退料については、立ち退きによる支障は店舗ほど大きくないことから、店舗と比べると低額になる傾向にあり、立ち退きを求める貸室の賃料の2年分がおよその目安になります。
(2)賃借人が建物をどのような用途に利用しているのかを把握する。
立ち退き交渉の前に賃借人の建物の利用状況を良く把握しておきましょう。
1,居住用の賃貸の場合
例えば、居住用の賃貸の場合は、何人で住んでいるのか、高齢や病気の人がいるのかを事前に確認しておくべきです。
2,営業用の店舗やオフィスの賃貸の場合
一方、営業用の店舗やオフィスの賃貸については、事業内容をよく確認し、移転により賃借人にどの程度、営業上の損害が生じるのかを検討しておくべきです。
▶参考例:
- 飲食店や理髪店など来店型の店舗で近隣に空き店舗がない場合は常連客を失い移転による損害が大きくなる可能性がある
- オフィスや倉庫については移転による支障が小さい
これらの点を良く把握しておくことが、立ち退き交渉の中で賃借人側から出てくる要望を予測し、それに対応するための手掛かりになります。
例えば、賃借人が賃借した店舗で物販の店舗をしている場合、来店での販売が多いか、通信販売が多いかによって、移転による損害の程度が異なります。
通信販売が多い場合は移転による営業上の損失はわずかになるはずです。そのため、通信販売と来店客への販売の割合を確認することが重要になりますが、こういった点を立ち退き交渉をスタートしてから聴くと、賃借人側としても移転の不利益を強調したい意図が働き、正確な回答が得られないことがあります。
交渉がスタートしてからでは正しい答えが返ってくるとは限りませんので、交渉開始前に聴いておくことが必要です。
(3)次回の更新時期を把握する
立退料と並んで交渉の主要テーマとなるのが「立ち退き時期」です。
立ち退き時期については、賃貸人と賃借人の合意により自由に決めることが可能ですが、交渉前の準備の場面では、賃貸借契約の次回の更新時期を把握しておくことが重要です。
なぜなら、交渉がまとまらない場合には、賃貸人から裁判を起こし、賃借人に立ち退きを求めることを検討することになりますが、裁判で立ち退きを求めることができるのは、賃貸借契約の更新のタイミングのみだからです。
裁判では、賃貸借契約の途中での立ち退きを求めることはできないことに十分注意してください。
立ち退き交渉にあたっては、万が一交渉で解決できず裁判に進む場合のことも考えて、あらかじめ更新のタイミングを把握しておくことが非常に重要です。
立ち退きについては、更新の時期を見据えながら、更新の2年くらい前から退去に向けた話し合いをスタートすることをおすすめします。
更新直前になって話をするのでは、更新のタイミングまでに退去の話がまとまらず、次回の更新までタイミングを逃すことになりかねません。
(4)近くの同等の物件との賃料差額を把握する
立ち退きを求められた場合に賃借人が一番気になるのは、立ち退く場合に適切な移転先があるかどうかという点です。
近隣の同等の物件の賃料を調べておくと、移転先について賃借人と具体的な話がしやすいです。
(5)立ち退きの場合に返還が必要になる敷金があるか?
賃貸借契約について敷金を入れてもらっている場合は、立ち退き時に返すことになりますので、確認しておきましょう。
賃借人に立ち退く資金がないという場合は、敷金の返還額を活用することで解決できる可能性があります。未払の賃料がないかどうかについても念のため確認しておきましょう。
4,交渉の進め方の6つのステップ
交渉の進め方はケースバイケースと言わざるを得ませんが、通常は次のような順序をたどります。
以下では交渉の進め方6つのステップでご説明します。
- (1)立ち退きを求める理由を説明する
- (2)賃借人側の事情を聴く
- (3)立ち退き時期、立退料と敷金についての話をする
- (4)譲歩のポイントを考えておく
- (5)口頭ではなく文書で解決案を提示する
- (6)交渉決裂の場合の代替策も考えておく
各ステップごとに順番に解説していきます。
(1)立ち退きを求める理由を説明する
まずは、賃借人のもとを訪問して、立ち退きを求めなければならい理由と、賃貸人側で考えている立ち退きの時期を伝えることが必要です。
立ち退きを求めなければならない理由は、例えば「賃貸人自身が建物を利用するため」とか「老朽化していて建て替えたいため」とか「建物を解体して再開発したいため」など様々なケースがありますが、本当の理由を伝えることが重要です。
立ち退き交渉にあたって、賃貸人側の説明に嘘や隠し事があると、交渉が失敗する原因になりますので注意してください。
例えば、建物が老朽化して建て替えたいという話をする場合、単に築年数が古い、不具合が多いという話をするだけでは、なかなか賃借人の説得に至りません。老朽化していることによる具体的な危険性について耐震診断を受けて把握したうえで、資料をもとに説明することが必要です。
(2)賃借人側の事情を聴く
次に、賃借人に立ち退きに応じることを決断させるための説得活動をする必要があります。
これには、賃借人側の事情をよく聴いて、賃借人において移転を決断するにあたり何が支障になっているかを見極め、その支障を1つずつ解決していくことが必要です。
話を具体的に進めるためには、賃貸人側で移転先の候補や家賃について情報収集し、賃借人にそれを見せて移転を促すことが効果的です。具体的な移転先の候補を提案し、それに対する賃借人の反応を見ることで、どのような点を解決すれば、賃借人が移転を決断できるのかを見極めることができます。
(3)立ち退き時期、立退料と敷金についての話をする
移転にあたっての支障のうち、金銭面については、立退料を賃貸人側から提示することで解決していく必要があります。あわせて敷金の返還見込み額も伝えることにより、賃借人側の金銭的な不安を解消していくことが必要です。
賃貸住宅についての立退料の最初の提示は、移転先家賃の「6ヶ月分+引っ越し代程度」が1つの目安になります。一方、店舗やオフィスの場合は、移転によりどの程度の営業上の損害が生じるかによってケースバイケースです。
移転先の内装費用がいくら、引っ越し代がいくら、移転先の礼金がいくらといった個別の項目ごとに金額を決めていこうとすると、交渉事項が多くなりすぎてなかなかまとまりません。
そのため、個別の項目ごとの金額を1つずつ決めるという考え方ではなく、個別の項目を踏まえたうえで、「総額でいくらにするか」を話し合うという考え方で進めるべきです。
(4)譲歩のポイントを考えておく
どのような交渉にもいえることですが、譲歩できるポイントを予め考えておくことが重要です。
立ち退きの交渉で、ポイントになるのは立退料のことだけではありません。
例えば、通常は立退料は立ち退き後に支払いますが、賃借人が金銭面で困窮している場合は、先に移転費用や移転先との契約に必要な敷金、礼金などの初期費用分として、立退料の一部を前払いすることにより、交渉がまとまるケースもあります。
そのほかにも以下のような点について譲歩ができないかを検討してみましょう。
- 立ち退きの時期について先にする譲歩ができないか
- 建て替え後に現在の賃借人に優先的な入居を提案できないか
- 賃借人に代替の賃貸物件を用意できないか
(5)口頭ではなく文書で解決案を提示する
ある程度賃借人との交渉を重ね、賃借人側の考え方もわかってきた段階で、口頭ではなく、文書による解決案を賃貸人の側から提示することが重要です。
口頭での提示どまりになると、賃借人側からはまだ交渉の余地があるように思え、なかなか解決に至りません。書面で解決案を提示して決断を促すことで、解決に向かう見込みが高くなります。
(6)交渉決裂の場合の代替策も考えておく
どのような交渉にもいえることですが、交渉決裂の場合の代替策を考えておくことは重要です。
交渉をどうしてもまとめなければならないという立場に追い込まれてしまうと、相手のほうが立場が有利になり、高額な立退料を支払わざるを得ないことにもなりかねません。
立ち退き交渉の場合、交渉決裂時の代替策の中で最も有力なものが、裁判により立ち退きを求める方法になります。
一定の立ち退き料の支払と引き換えに賃借人に立ち退きを命じる判決が出されているケースは多数あります。そのため、賃借人側があまりにも高額で不合理な要求をする場合は、裁判により立ち退きを求めるということを選択肢として考えるべきです。
但し、前述の通り、裁判で立ち退きを求めることができるのは、賃貸借契約の更新のタイミングのみであり、賃貸借契約の途中での立ち退きを求めることはできないことに十分注意してください。
また、ケースによっては、裁判以外の選択肢として、「賃貸物件を第三者に売却する」、「賃借人が物件を使用する必要がなくなるタイミングをしばらく待つ」などの代替策をとりうるケースもあります。
5,交渉を弁護士に依頼するメリット

立ち退き交渉を弁護士に依頼することも可能です。
弁護士に依頼するためには費用がかかりますが、以下のようなメリットがあります。
(1)感情面や過去の経緯と切り離して交渉ができる
賃借人の中には、「これまで長い間借りてきたのに家主の都合で立ち退かされるのは納得がいかない」というような感情面や、過去の経緯を持ち出して、交渉が難航するケースも見られます。
そのような場面の交渉を弁護士にまかせることで、感情面や過去の経緯と切り離して法的な交渉ができるようになります。
(2)弁護士が交渉することで賃借人側も訴訟を意識することになる
賃貸人から立ち退きを求めても、賃借人が真剣に検討せず、時間だけがずるずると過ぎてしまうケースがあります。
そのような場面でも弁護士が期限を区切って回答を求めることで交渉をスムーズに進めることができます。
また、弁護士が交渉の場に出ることで、賃借人側としても立ち退きを拒めば訴訟になるということを現実的に意識することになり、賃借人に解決に向けた検討をさせるためのプレッシャーを与えることが可能になります。
(3)立退料についても合理的な金額にすることができる
最も重要な交渉課題になるのが立退料です。
立退料は相場がないということをよくいわれますが、弁護士であれば裁判になった場合およそどの程度の結論になるのか、おおよその見通しを立てることができます。
裁判例をもとに賃借人側の要求が不合理であることを示し、裁判ではそのような主張が通らないことを説明することで、立ち退きに向けて賃借人を理詰めで説得することが可能になります。
6,交渉の代行の弁護士費用
立ち退き交渉を弁護士に依頼するためにかかる弁護士費用は、法律事務所によって異なります。
筆者が代表を務める弁護士法人咲くやこの花法律事務所における弁護士費用例をご紹介すると以下のようなものがあります。
立退き交渉についての弁護士費用例
●着手金(依頼時にいただく弁護士費用です)
30万円+税
●報酬金(立ち退きを実現した場合にいただく弁護士費用です)
50万円+税
不動産オーナーや不動産を所有する会社が、立ち退き交渉の弁護士費用を支出した場合は、その費用を経費にすることが可能です。
7,立ち退き交渉に関する咲くやこの花法律事務所の解決事例
咲くやこの花法律事務所では、賃貸物件の立ち退きをめぐる交渉について、賃貸人側あるいは賃借人側からご相談をいただき、解決を実現してきました。
以下で、咲くやこの花法律事務所の解決事例の一例をご紹介します。
(1)賃借人側で立ち退き交渉に対応して当初提示の立退料の2倍の額を獲得した事例
1,10年経営してきた飲食店の交渉事案
相談者は10年間同じ場所で飲食店を経営していましたが、家主が不動産会社に変わった直後に「老朽化」を理由に年内の退去を求められました。実際には再開発が目的であり、提示された立退料が妥当かどうか不安を抱き、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。
2,弁護士による交渉で立ち退き料の大幅増額に成功
弁護士は相談者と打ち合わせの上、立ち退きを前提に交渉を行う方針を決定しました。そして、補償額を算定して新家主と交渉した結果、当初提示額の2倍を超える立退料を獲得することができました。
補償に含まれた内容
- 移転先の内装費用
- 家賃差額の補填
- 引っ越し費用
- 移転に伴う休業補償
- 顧客案内費用
- 移転先での営業補償
さらに、退去期限についても貸主の一方的な要求によるのではなく、相談者の都合に合わせたスケジュールで実施できました。加えて、退去前3か月間の家賃免除や原状回復義務の免除、不要物を残したままの退去といった有利な条件も獲得しました。
3,弁護士による交渉で有利な条件を引き出したポイント
ご相談をお受けして、弁護士はまず「正当な理由の有無」を検討し、正当な理由は乏しいと判断しました。相談者は退去を望んだため補償条件の最大化に注力し、協力事業者と連携して移転先候補を探し、見積もり資料を準備するなど、交渉に説得力を持たせました。
貸主に対しては「本来立ち退きに応じる必要はない立場」であることを前提に、十分な補償を要求し、粘り強い交渉の結果、金額の大幅増額に加え、複数の有利な条件を引き出しました。
▶参考情報:この事案の詳細については、以下からご覧いただけますのでご参照ください。
(2)賃貸人側で交渉して店舗の立退料を半額以下にすることに成功した事例
1,一等地から立ち退き交渉が必要になった事案
本件は、大阪市内の繁華街にある築70年近い賃貸物件をめぐる立ち退き交渉の事案です。物件所有者(貸主)は隣接建物の所有者と取り壊し計画を進めており、8月中の退去が必要でした。当初テナントのアパレルショップ(借主)は退去に応じる姿勢を示していましたが、後に態度を翻し、弁護士を立てて立ち退きを拒否しました。さらに約1300万円の立退料を請求してきました。
2,厳しいスケジュールでの交渉
貸主側は訴訟に持ち込むと1年以上かかり、約束していた9月の取り壊しに間に合いません。そのため訴訟以外の解決が必須でした。しかも交渉期間はわずか2か月でした。そして、請求された1300万円は一見高額に思えますが、過去の裁判例では店舗立ち退きで1000万円~1500万円が認められるケースが多く、必ずしも不当とは言えない状況でした。
3,短期での立ち退きを実現した交渉の工夫
担当弁護士は、まず「いずれ建物の老朽化で立ち退かざるを得ない」ことを強調し、借主に近隣の空き店舗情報を提供するなどして、移転後の負担が過大にならないことを理解してもらうよう努めました。
さらに減額交渉のポイントとして以下を主張しました。
- 過去に家賃値下げの要望に応じ、累計1500万円程度減額してきた経緯があること
- 借主のアパレルショップは売上の7割が通信販売であり、移転による顧客離れのリスクが小さいこと
また、相手方弁護士に対しても立ち退きの必要性を丁寧に説明し、借主の説得に協力を得ることで交渉を前進させました。
その結果、最終的に立退料を請求額の半額以下の600万円まで減額することに成功し、9月初旬に退去を実現させることができました。長年の賃貸借関係にあった賃借人と最終的に円満な合意による解決ができたことで、依頼者(貸主)にも大変満足していただきました。
▶参考情報:この事案の詳細については、以下からご覧いただけますのでご参照ください。
8,【補足】業者や司法書士など弁護士以外への依頼は弁護士法違反となることがある
不動産業者や司法書士に立ち退き交渉を依頼することは、弁護士法第72条との関係に注意が必要です。
弁護士法第72条は、いわゆる「非弁行為」の禁止を定めた条文です。
この条文により、弁護士以外が報酬を得る目的で他人の法律事務を取り扱うことは、原則として禁止されており、違反には刑罰が科されます。
▶参考情報:弁護士法第72条
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
・参照元:「弁護士法」の条文はこちら
参考判例:
平成22年7月20日最高裁判所判決
過去にはビルの所有者から委託を受けて賃借人らの立ち退き交渉をした不動産業者について、裁判所が、弁護士法第72条違反として、罰金300万円、社長に懲役2年・執行猶予4年、没収・追徴を命じたケースがあり、最高裁判所で判決が確定しています(平成22年7月20日最高裁判所判決)。
行政書士が立ち退き交渉をすることも同様に犯罪になります。司法書士についても、原則として立ち退き交渉を代理で行うことはできません。
ただし、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」については、請求額が140万円までの場合に限り、立ち退き交渉を代理することができます。
借家人からの請求額が140万円を超えることが発覚した場合は、「認定司法書士」であっても、それ以降、交渉の代理をすることはできません。
立退交渉の事件は、賃借人が主張する立退料の額が140万円以上になるケースがほとんどであり、そのようなケースでは司法書士は立ち退き交渉を代理することはできません。
9,立ち退き交渉に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に咲くやこの花法律事務所の、賃貸建物の立退きに関するサポート内容をご案内します。
(1)賃貸人側からの立ち退き交渉に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、建物の老朽化による建て替えなどを目的とする立ち退き交渉について、賃貸人側からのご相談を承っています。
賃貸人側で立ち退き交渉をする場合、建物の耐震性が低いことや、耐震工事よりも建て替えが合理的であることなどについて、資料を示して交渉すること、賃借人に代替の移転先を提案することなど、さまざまな交渉のポイントがあります。
また、遅くとも立退きの2年前には交渉をスタートすることにより、期限ぎりぎりの交渉にならないようにすることも重要なポイントです。
立退料については、その金額の相場感に大きな幅があり、交渉の方法によって、結果も大きく変わってきます。
咲くやこの花法律事務所では、不動産トラブルに強い弁護士がご相談を承りますので、お困りの際はご相談ください。
不動産トラブルに強い咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
(2)オフィスや店舗の賃借人側からの立ち退き交渉に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、オフィスや店舗について立ち退きを求められた賃借人の立場からの交渉についてもご相談を承っています。
特に長期間営業した店舗や長期間利用したオフィスを立ち退く場合、その経済的なデメリットは大きく、それに見合う補償を立退料として受領する必要があります。
ところが、賃貸人側から提示される立退料は、裁判例などの基準と比較すると大幅に低い水準になっていることがほとんどです。
また、立退料について賃貸人からの提示をベースに増額交渉を行うのではなく、賃借人側から自身の計算に基づく立退料を請求して交渉しなければ、正当な立退料を得ることができません。
立退料については、営業補償や借家権価格といった実費以外の部分の交渉も重要です。交渉の方法によって、結果が大きく変わってきます。
咲くやこの花法律事務所では、不動産トラブルに強い弁護士がご相談を承りますので、お困りの際はご相談ください。
不動産トラブルに強い咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年9月26日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」立ち退き料に役立つ情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587