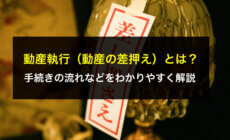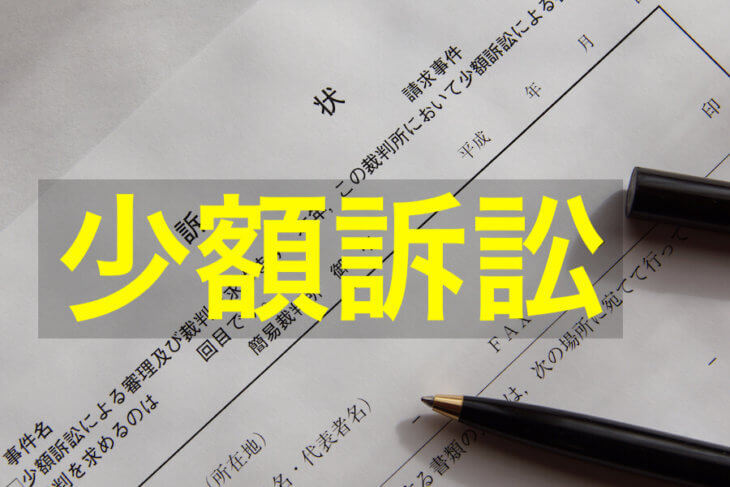
少額訴訟の制度は、60万円以内の金銭の請求について、1回の裁判で解決することを目指す制度です。
一見すると、少額の債権回収に使いやすそうな便利な制度ですが、実は以下のようなデメリットもあることに注意する必要があります。
- 1回で終わることを想定して十分な主張と証拠を準備をして臨まなければ自社に不利な結果になってしまうことがある
- 自社に不利な結果となってしまっても、上級の裁判所での審理を求めることができず、リカバリーが難しい。
この記事では、債権回収に少額訴訟制度を利用することのメリットとデメリットや具体的な手続きなどについてご説明したいと思います。
なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でご説明していますのでご参照ください。
▶【動画で解説】西川弁護士が「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」について詳しく解説中!
▶【関連情報】債権回収の少額訴訟に関する情報は、以下の関連情報もあわせてご覧下さい。
・成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読
・不動産・銀行口座(預金)・債権など仮差押の正しい手続きの進め方
・債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,少額訴訟とは?
少額訴訟とは、簡易裁判所で行われる裁判手続きの1つで、60万円以内の金銭の請求について、1回の裁判期日で解決することを目指す手続です。被告からの希望があれば通常の民事訴訟に移行する点、少額訴訟の判決に対しては不服申し立て(控訴)により上級の裁判所での審理を求めることはできない点に大きな特徴があります。
少額訴訟は簡易裁判所で行われます。簡易裁判所の場所については以下をご参照ください。
・参考情報:裁判所Webサイト「各地の裁判所一覧」
2,債権回収の場面で少額訴訟を利用するメリット
少額訴訟は、60万円以内の少額の債権回収について、手間や労力がかかりすぎないように、1回の裁判期日で終わらせることを目指した制度であり、以下のメリットがあります。
(1)裁判所に1回行くだけで判決までもらえる。
少額訴訟制度については、相手から通常の民事訴訟手続への移行の希望が出なければ、原則として、1回裁判所に出廷するだけで、判決をもらえるということが、大きなメリットといわれています。
しかし、少額訴訟ではない、簡易裁判所で行われる通常の民事訴訟も、その7割以上は、1回の口頭弁論期日で終わっています。
通常の民事訴訟では、判決は別の日に言い渡されますが、判決のために出廷する必要はありません。
そのため、債権回収のための法的手段を検討する場面で、「1回で終わる」ことを通常訴訟と比較した少額訴訟の大きなメリットであると強調することについてはやや疑問があります。
ただし、簡易裁判所で通常の民事訴訟をすれば、2回以上出廷が必要となるケースも3割近くはあるので少額訴訟により「1回で終わる」ことについて全くメリットがないとはいえないでしょう。
債権回収のための手段を検討するうえでは、その迅速性も非常に重要な要素です。この点、少額訴訟の平均的な審理期間は2.2ヶ月程度、簡易裁判所の通常訴訟については2.7ヶ月程度になっています。このように、迅速性の面でも、少額訴訟が通常訴訟と比べて、大きなメリットがあるとは言いにくい状況です。
(2)和解による解決も期待できる
裁判所の統計によれば、少額訴訟の約39%が和解で終わっています。
その多くが、債権者側が少額訴訟を起こして、債務者に対して「本気度」を示したことにより、債務者が裁判所に出頭して支払の約束をする内容の和解をして終了しているケースであると推測されます。
このように、和解による解決が一定の割合で期待できることも、債権回収の場面で少額訴訟を利用するメリットの1つです。和解による解決ができることは、通常の訴訟でも同じですが、1回の期日で和解できるという面ではメリットといえるでしょう。
3,債権回収の場面で少額訴訟を利用するデメリット
一方で、少額訴訟については、デメリットも多くあります。
(1)被告から希望があれば通常訴訟に移行する
被告から少額訴訟ではなく、通常の民事訴訟での審理を希望する旨の申し出があれば、少額訴訟は通常の民事訴訟に移行されます。そして、被告側が通常の訴訟での審理を希望する申し出をするために、特段の理由は必要ありません。
ただ、このこと自体は、最初から通常訴訟を起こしたのと同じ扱いになるだけですから、大きなデメリットとまではいえません。
(2)1回で終わることを想定して事前にすべての準備が必要
少額訴訟のデメリットの大きな部分の1つは、1回の裁判期日で終わることを想定して、完全な準備を事前にしておくことが必要になるという点です。
主張すべき点をもれなく主張したうえで、証拠についても万全にそろえておく必要があります。特に、証拠として、証人の証言がある場合は、原則として、証人を当日裁判所に連れてくる必要があります。
そして、このように万全の準備をして臨んだとしても、相手から通常訴訟への移行を希望する旨の申し出があった場合、通常訴訟に移行します。通常訴訟に移行した場合、普通は証人から事情を聴く手続きは、第1回期日には行われません。
そのため、第1回期日のために万全の準備をしたことが無駄になってしまうことがあります。証人にも再度、別の日に裁判所に来てもらうことをお願いすることが必要になります
▶参考情報:
ただし、証人について電話会議システムという出廷が必要ない手続を利用してもらうことも可能です。
(3)思わぬ不利な判決が出ても控訴できない
少額訴訟について、もう1つの大きなデメリットは、控訴ができない点です。
「控訴」というのは、言い渡された判決に不服がある場合、さらに上の裁判所の判断を求めることです。
▶参考情報:控訴については以下もご参照ください。
もちろん、少額訴訟で相手に請求額全額の支払いを命じる判決が出れば、特に問題はありません。
しかし、相手からも一定の反論があったり、証拠が不十分だったり、あるいは契約書がなかったりした場合は、自分が思っている通りの判決が出ないことがあります。
そのような場面でも、上の裁判所に判断を求めることができません。
統計上、相手が出席した少額訴訟のうち、約2割は棄却判決、つまり、請求が認められずに全面敗訴しています。
このように、敗訴するリスクは現実にあり、その場合も、上の裁判所での審理を求めることができないことは、大きなデメリットになる可能性があります。
そのため、債権回収の場面で少額訴訟を利用するかどうかを検討する際には、少額訴訟で敗訴するリスクがないかを慎重に検討することが必要です。
(4)裁判所の判断で分割払いになったり、遅延損害金がカットされることがある
少額訴訟では、債権者側が勝訴した場合も、裁判所の判断で、分割払いを命じる判決になったり、全額支払った場合の遅延損害金を免除する内容の判決になることがあります。
通常の訴訟であれば、一括払いを命じる判決となり、遅延損害金もつきますので、この点は少額訴訟のデメリットといえます。
特に分割払いを命じる判決になった場合、債権者側としては途中で支払いがされなくなるリスクを負うことになります。
(5)同一の簡易裁判所では年間10回まで
少額訴訟には回数制限があり、1つの会社あるいは1人の人が、同じ簡易裁判所で少額訴訟を起こすことができるのは年に10回までです。
年に10回も少額訴訟を超すことは普通はありませんので、この点は通常は大きなデメリットにはならないでしょう。
(6)勝訴しても相手が支払わない場合は相手の財産調査が必要
少額訴訟で相手に対して支払いを命じる判決が出されても、相手が支払をしない場合は、相手の財産を差し押さえるために、相手の財産を調査することが必要です。
例えば、相手の銀行口座を調べて、相手の預金を差し押さえれば、その預金から債権を回収することが可能です。
これに対して、相手に対して支払いを命じる判決が出されても、相手の財産が把握できないときは、差押えができず、実際に債権を回収することができません。
▶参考情報:銀行預金の差押えについては以下をご参照ください。
このように判決をもらっても支払がされない場合は、相手の財産の把握が必要になるということは、重要な点です。そして、このことは、債権回収全般にあてはまることであり、少額訴訟だけの問題ではなく、通常訴訟でも同じです。
債権回収のために訴訟を起こす前に、判決をもらった後のことを見据え、どのようにしてその金銭を回収するのかということも考えておく必要があります。
その他のポイントして、少額訴訟で1回は簡易裁判所への出廷が必要であることもおさえておいてください。
4,実際に必要な手続の流れ
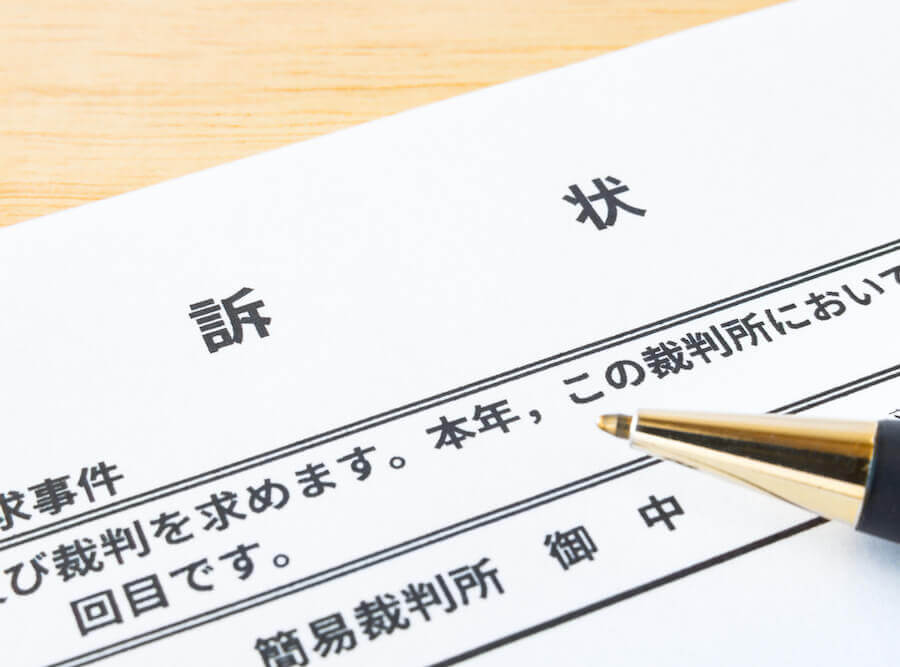
少額訴訟の手続きの流れは下の図のとおりです。
以下で詳細をご説明したいと思います。
▶参考:少額訴訟の流れの図解
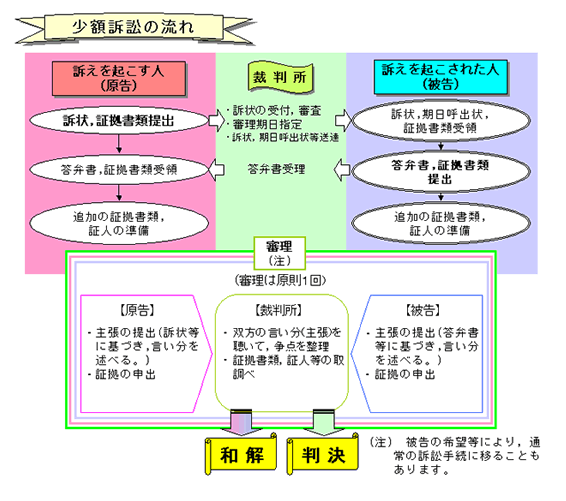
▶引用元:裁判所ウェブサイトより引用
(1)訴状の作成
少額訴訟を起こすためには、訴状を作成する必要があります。訴状には、請求する内容やその法的根拠を記載します。少額訴訟は1回で終わる手続きであるため、必要なすべての内容を訴状に記載しておくことが原則です。
(2)証拠の準備
少額訴訟は1回の期日で終わることを前提とする手続きであるため、証拠についても、期日の前にすべて準備しておくことが必要です。
契約書などの書証(文書になっている証拠)については、訴状と一緒に裁判所に提出することが通常です。
(3)訴訟の提起
訴状と証拠が準備できた段階で、裁判所に郵送して、訴訟を提起します。「訴訟提起」とは訴訟を起こすことを言います。
少額訴訟をはじめとする民事訴訟では、訴える側(債権者側)を「原告」、訴えられた側を「被告」と呼びます。
(4)訴状の送達
訴訟を提起すると、簡易裁判所で訴状が審査され、第1回の裁判期日が指定されます。
そして、被告に対して、裁判所から訴状を送る「送達」の手続が行われます。
(5)答弁書の受領
被告側は、訴状に対する反論文書である「答弁書」を提出することを裁判所から求められます。
原告は被告から答弁書を受け取ることで、被告が訴訟においてどのような反論をするのかを把握することができます。
また、被告側が少額訴訟による審理を希望しないときは、通常手続移行申述書を提出することができ、その場合は、通常の民事訴訟手続に移行します。
通常の民事訴訟手続きによる債権回収の解説は以下をご参照ください。
(6)裁判期日
通常の民事訴訟手続に移行しない場合は、第1回の裁判期日で、原則としてすべての審理が行われます。
証人がいる場合は、証人に対して裁判所で質問する尋問手続が行われることがあります。
(7)和解
被告側も出席している場合は、裁判所から和解の打診があるケースがほとんどです。
和解の進め方は裁判官により様々ですが、裁判所から和解案が示され、その和解案に合意できるかどうかを、原告側、被告側の双方で検討することが一般的です。
原告側、被告側の双方が和解することに合意した場合は、和解調書という裁判所の文書を作成したうえで、訴訟は終了します。
(8)判決
和解ができなければ、第1回の裁判期日で、裁判は終了となります。
原則として、その日に判決が言い渡されます。
(9)異議申し立て
少額訴訟の判決で請求の一部または全部が認められなかったときは、2週間以内に異議申し立てをすることで、通常訴訟の手続きで審理を再開してもらうことが可能です。
この場合、少額訴訟を起こした簡易裁判所と同じ簡易裁判所で審理されることになります。
この異議申し立ては、上の裁判所での審理になるわけではないという点で、通常の民事訴訟における「控訴」とは異なります。
(10)強制執行(差押え)
判決により、債権者側の権利をが認められた場合は、債権者側は、債務者の財産を差し押さえることができます。
これを「強制執行」といいます。
少額訴訟を利用した債権回収の場面では、通常の強制執行よりも簡易的な「少額訴訟債権執行」という手続が設けられています。
▶参考:少額訴訟債権執行の手続き
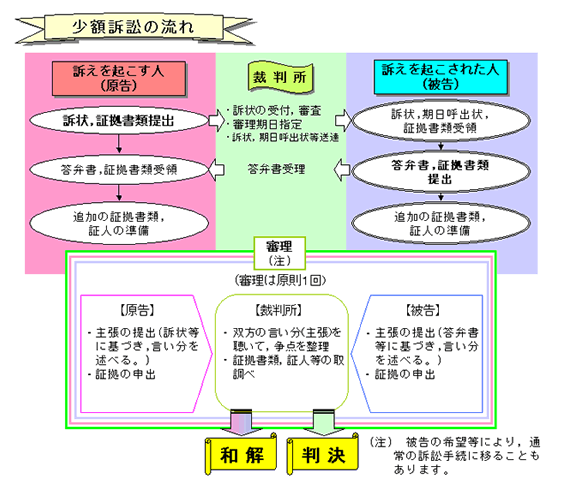
▶引用:裁判所ウェブサイトより引用
以上、少額訴訟の一般的な手続きをご説明しました。
5,弁護士に依頼すべきか?
少額訴訟を起こす場合に、弁護士に依頼しているケースは全体の約7%、司法書士に依頼しているケースは全体の約2%にすぎません。
これは、弁護士や司法書士に依頼するためには一定の費用が必要であり、少額の債権回収の事案では、弁護士や司法書士に依頼しても費用倒れになってしまうことが多いことが理由です。
そのため、少額訴訟について弁護士や司法書士に依頼することはあまり現実的とは言えません。
▶参考情報:できるだけ費用をかけずに弁護士に依頼する方法については、以下のサイトもご参照ください。
6,少額訴訟の費用について
少額訴訟は裁判所を利用する制度であるため、裁判所に費用をおさめることが必要です。裁判所におさめる費用は、主に、「印紙」と「郵便切手」があります。
(1)印紙について
少額訴訟の費用のうち、印紙の額は、通常訴訟と同じです。
以下の表中の「訴えの提起」の欄をご参照ください。
少額訴訟は訴額60万円以内であるため、印紙の額は最大で6000円です。
(2)郵便切手について
郵便切手は、裁判所から被告に訴状等を送達するために必要となるものです。訴訟の提起の段階で必要になる納付額は、東京簡易裁判所の場合は5,200円、大阪簡易裁判所の場合は5,000円です。
いずれも被告が1名の場合であり、連帯保証人も被告とする場合のように、被告が複数名の場合は追加が発生します。
7,まとめ
今回は、簡易裁判所の少額訴訟手続きについて、そのメリットとデメリット、手続の流れなどをご説明しました。
少額訴訟手続きは、デメリットも多い手続きですので、少額訴訟手続を利用するか、それとも、通常訴訟の手続を利用するかは慎重に検討しましょう。
また、少額訴訟と同じように、債権回収に使える手続きとして、「支払督促」の手続きもあります。
支払督促の手続きについては以下を参照してください。
8,少額訴訟など債権回収に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
債権回収に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
以下よりメルマガ登録やチャンネル登録をしてください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年8月5日
 06-6539-8587
06-6539-8587