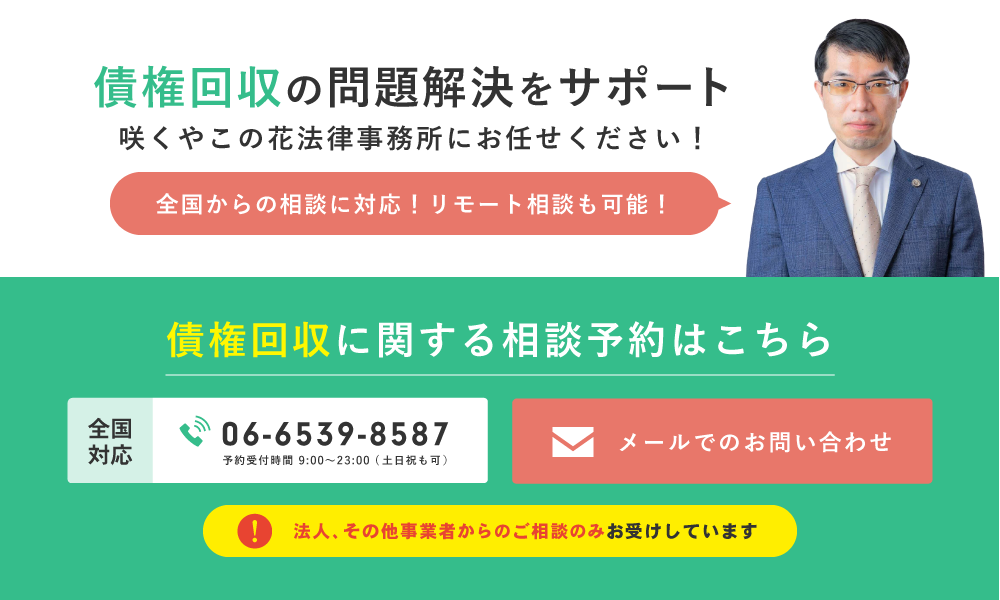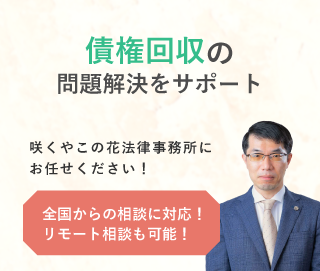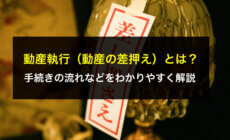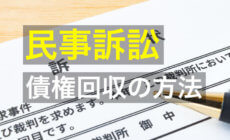こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の代表弁護士西川暢春です。
会社経営や店舗経営をしていると、以下のような債権回収の悩みを経験することがあります。
- 「商品を売ったのに支払いをしてくれない。」
- 「工事をしたのに支払いをしてくれない。」
このような債権回収に関するトラブルは、会社経営にはつきものであり、咲くやこの花法律事務所の企業法務でももっとも相談の多いジャンルの一つです。
債権回収の回収率アップのためには、スピード対応が必要となりますが、最初に「弁護士から債務者宛てに内容証明郵便を送って、支払いを督促する」というような方法が効果的です。
しかし、それでも支払いをしないという場合は、債務者に対して訴訟に進まなければなりません。このようなケースで、訴訟の前に強力な手段の一つとして「仮差押」という手続きがあります。「仮差押」とは、訴訟の前に債務者の財産を凍結してしまい、処分できなくする手続きです。
今回の記事では、全額回収率を少しでもアップさせるための「仮差押の正しい手続きの進め方」についてご説明したいと思います。この記事を最後まで読んでいただくと、仮差押を検討する場面で事前に検討すべき重要ポイントなどがわかり、現在、社内で抱えている債権回収の問題において、仮差押の手続きに向けて動き出すことができるようようになります。
債権回収に関するトラブル対応策として、以下の記事で具体的な対応策をご紹介しておりますので、債権回収にお悩みの方は必ず参考に読んでみてください。
▶参考情報:債権回収に関する基本的な対応について、債権回収の問題が発生した際の動き方として、内容証明郵便の送付から問題解決までの対処法とポイントなどを解説していますので、こちらもあわせてご参照ください。
債権回収に不安がある場合は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。咲くやこの花法律事務所の債権回収に関するサポート内容や解決実績などについては、以下をご覧下さい。
また、実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がサポートした債権回収に関する解決事例は以下をご参照ください。
▶【関連動画】この記事の弁護士 西川暢春が、「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」の動画でも債権回収の重要ポイントについて詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。
▼債権回収の仮差押について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,仮差押の圧倒的な効力について
全額回収率アップさせるための仮差押ですが、この仮差押も正しい手続きで実施しなければなりません。
今回、仮差押の方法についてお話する前に仮差押をすると、「なぜ、全額回収率をアップできるのか?」を知っておくことで、正しい手続きの方法をイメージしやすくなりますのでご説明いたします。
まず、以下のことを理解しておくことが大切です。
(1)訴訟で勝訴=債権回収成功ではない
訴訟で勝訴すれば、裁判所から債務者に判決正本と呼ばれる文書が送られます。
判決正本の内容は、裁判所が債務者に対して支払いを命じる内容になっています。しかし、訴訟で勝訴した場合でも、債務者にその金額を支払うだけの財産がなければ、債務者としても支払いができません。
その結果、支払いが実行されず、勝訴判決は無駄になってしまう可能性もあります。
このようなことを防ぐために、訴訟を起こす前に、債務者がもっている財産を処分できないように凍結してしまう手続きが「仮差押」です。
(2)勝訴後に債務者に「払えない」とは言わせない仮差押の効果
訴訟の前に「仮差押」の手続きをすることで、勝訴した後になって債務者に「財産がないから払えない」と言わせず、完全に支払いをしてもらうことが可能になります。
1,銀行預金(口座)の仮差押
債務者に銀行預金(口座)があれば、これを「仮差押」することで預金を引き出すことができないようになります。
そして、訴訟で勝訴した後に、債権者は、その銀行から直接預金の支払いをうけることで、債権を回収することができます。
2,不動産の仮差押
債務者に不動産があるのであれば、これを「仮差押」することで債務者が不動産の名義を移転したり、新しく担保に入れたりすることができないようになります。
そして、訴訟で勝訴した後に、債権者は不動産を競売にかけて、その代金から債権を回収することができます。
3,債権の仮差押
債務者に取引上の債権があれば、これを「仮差押」することで、債務者はその債権について支払いを受けることができなくなります。
例えば、A社が債務者に売却した商品の売買代金を回収する場合に、債務者も商品を転売して利益をあげている場合には、債務者は転売先に対して売買代金債権をもっています。
この場合に、この債務者の売買代金債権について「仮差押」の手続をすれば、転売先から債務者への代金の支払いを停止させることができます。そして、訴訟で勝訴した後に、債務者の転売先から直接支払いを受けることで、A社の債権を回収することができます。
このように、訴訟で勝訴した時に全額債権を回収するためには、訴訟の前に仮差押の手続きを取っておくことが極めて有効な手段になります。
2,全額回収率を確実にアップさせるための正しい仮差押の手続きの進め方とは?
全額回収率アップさせるための仮差押ですが、この仮差押も正しい手続きの進め方を知っておかなければ実施できません。
最初に仮差押の流れについてのご説明になります。
仮差押の正しい手続きの進め方「5つのステップ」
- ステップ1:裁判所への申立
- ステップ2:裁判所での審理
- ステップ3:担保の供託
- ステップ4:仮差押の決定
- ステップ5:仮差押の執行
「ステップ1:裁判所への申立」〜「ステップ5:仮差押の執行」までの流れは、通常、約1週間程度で行ってしまうことが理想です。
そして、「ステップ5:仮差押の執行」まで終えて、はじめて債務者の預金を凍結したり、債務者に不動産の名義の移転を禁止したりという、仮差押の効力が生じますので、覚えておきましょう。
ステップ1:
裁判所への申立
仮差押の手続きは、裁判所に「仮差押申立書」を郵送することからスタートします。
弁護士に委任する場合は、これらの書類は基本的には弁護士が作成します。
この申立書には、下記のような書類を添付します。
仮差押の申立書に添付する書類
- (1)請求債権目録
- (2)債権の仮差押の場合は、仮差押債権目録、不動産の仮差押の場合は、物件目録
- (3)債権があることを示すための資料(「疎明資料」といいます【以下、補足1】)
- (4)債権者が法人の場合は、債権者の資格証明書
- (5)債務者が法人の場合は、債務者の資格証明書
- (6)債務者の本社所在地の登記簿謄本
- (7)保全の必要性についての債権者の陳述書【以下、補足2】
- (8)弁護士に委任する場合は委任状
▶補足1:債権があることを示すための資料「疎明資料)」について
債権があることを示すための疎明資料については、「回収する債権に関する契約書」と、「債権の金額がわかる書類」を準備する必要があります。
具体的には、以下の通りです。
1.回収する債権に関する契約書
- 売買代金の回収であれば売買契約書
- 請負代金の回収であれば請負契約書
2.債権の額がわかる書類
- 発注書と発注請書
- 債権額が記載された個別契約書
- 債務残高確認書
- 分割払いの合意書
このような書類は、原本を提出するのがベストです。
▶補足2:保全の必要性についての債権者の陳述書について
「保全の必要性についての債権者の陳述書」とは?
裁判所に対して訴訟の前に債務者の財産について仮差押をして、債務者の財産の処分を禁止しておく必要があることを説明する文書です。
下記のような内容を記載します。
- 1.債権の期限がすでに過ぎており、支払いが遅れていること
- 2.債権者から債務者に何度も督促をしていること
- 3.督促に対する債務者の対応状況
- 4.現在も債務者が支払いをしていないこと
- 5.債務者の資金繰りの悪化をうかがわせるような事情があればその事情
- 6.債務者の財産を訴訟の前に仮差押の手続きをしておかなければ、訴訟で勝訴しても支払われない恐れがあること
これらの内容を弁護士が依頼者からヒアリングして、弁護士が下書きを作成し、それを依頼者が確認して署名捺印するという方法で「陳述書」を作成するのがよいでしょう。
ステップ2:
裁判所での審理
裁判所への申し立てをすると、裁判官が仮差押の可否を審理します。
具体的に、審理の対象となるのは以下2点になります。
- (1)請求債権の有無
- (2)保全の必要性
裁判官から「仮差押の決定」をもらうためには、「請求債権」がありそうだと認められ、かつ「保全の必要性」もあるという判断がされる必要があります。
このうち、「請求債権の有無」は、債権者が主張しているような債権が実際にあるかどうかを裁判所が検討します。
また、「保全の必要性」は、裁判所が訴訟の前に債務者の財産を仮差押して、財産の処分を禁止しておく必要があるかどうかを審理します。
▶参考情報:この点は、前述の「保全の必要性についての債権者の陳述書」をもとに判断されます。
裁判官が資料が足りないと判断したときは、資料の追加提出を指示されますので、その場合は追加提出にスムーズに対応することが必要です。
東京地方裁判所や大阪地方裁判所では裁判官が弁護士と裁判所で面談し、資料が足りないときは面談の場で裁判官から資料の追加を指示されるのが通常です。地方の裁判所では面談は行われずに、裁判官から弁護士に電話などで、資料の追加を指示するのが通常です。
ステップ3:
担保の供託
「裁判所での審理」をクリアすれば、裁判官から、仮差押の決定の前に担保として納めなければならない担保金の額が伝えられます。
債権者は決定された担保の額を法務局に供託します。裁判所は法務局の供託証明書で債権者が担保を供託したことを確認します。
裁判所から担保の額が伝えられてから、通常は7日以内に供託しなければなりませんので、資金を事前に確保しておくことが必要です。
ステップ4:
仮差押の決定
「担保の供託」が済めば、裁判所が「仮差押の決定」を出します。
ステップ5:
仮差押の執行
「仮差押の決定」が出れば、これをもとに「仮差押の執行」に移ります。
●不動産の仮差押の場合
この「仮差押の執行」は、仮差押をした財産について、裁判所の決定に基づき、実際にその処分を禁止するための手続きです。
不動産の仮差押の場合は、債務者の不動産に仮差押をしたことを示す登記をします。これにより、債務者はその不動産の名義を移転することができなくなります。
●銀行預金の仮差押の場合
債務者の預金債権を仮差押した場合は、裁判所から銀行に仮差押決定書を送達して、銀行が債務者に対して預金の支払いをすることを禁止します。
これにより、債務者は預金を引き出すことができなくなります。
▶参考情報:銀行口座の預金の差押え方法とポイント
債権回収の解決策のひとつ「預金差押」についておさえておくべき注意点も、以下の記事で詳しく解説しています。必ずチェックしておきましょう。
「仮差押の執行」が終わってから、裁判所が仮差押決定書を債務者に送達します。この段階ではじめて債務者は自分の財産について、仮差押がされたことを知ることになります。
以上が、仮差押の手続きの進め方になります。
仮差押の手続きは、作成する書類の内容が専門的で裁判官の面談などもあるため、実際には弁護士に委任して進めるのがよいでしょう。
但し、弁護士に委任しても、資料を集めたり、担保金を準備することは必要ですので、以下の点に注意しましょう。
- (1)弁護士が裁判所で追加資料を指示されたら、すぐに準備できるように、仮差押の手続中は、弁護士とスムーズに連絡をとれるようにしておきましょう。
- (2)裁判所で追加資料を指示されたら、スムーズに資料を提出できるように、仮差押をする債権についての資料の原本を整理しておきましょう。
- (3)担保の供託を指示されたらすぐに出金できるように資金を事前に確保しておきましょう。
また、仮差押の手続きを進めていることを債務者に知られると、債務者が仮差押の決定が出る前に預金を下ろしてしまったり、不動産の名義を移転してしまう恐れがあります。
そのため、仮差押の手続きが終わるまでは、秘密にしておくことも忘れないで下さい。
3,仮差押の際に事前に検討しておくべき5つの重要ポイントとは?
このように仮差押は、勝訴した場合の債権回収を確実にするために有効な手段ですが、仮差押の手続きを実施するにあたっては、以下の5点を検討しておく必要があります。
- ポイント1:債権を証明できる証拠があるかを確認すること
- ポイント2:裁判所に預ける担保を確保することが必要
- ポイント3:訴訟にかかる期間や費用を検討しておくことが必要
- ポイント4:仮差押の申立をする裁判所を確認することが必要
- ポイント5:債務者の本社が所在する不動産の登記簿謄本を取得することが必要
それぞれについて、順に詳しく解説していきます。
ポイント1:
債権を証明できる証拠があるかを確認すること
仮差押の手続きでは、裁判所に、債権者が主張する金額の債権が、「実際に存在する」ことの証拠を提出することが必要です。
- 売買代金の回収の場合:債権者が主張する額の売買代金債権が、「実際に存在する」ことの証拠を提出することが必要です。
- 請負代金の回収の場合:債権者が主張する額の請負代金債権が、「実際に存在する」ことの証拠を提出することが必要です。
契約書が作られておらず、債権の金額についても証拠がないという場合は、まずは、下記のような資料を揃えることから始めなければなりません。
1,回収する債権に関する契約書
- 売買代金の回収であれば売買契約書
- 請負代金の回収であれば請負契約書
2,債権の額がわかる書類
- 発注書と発注請書
- 債権額が記載された個別契約書
- 債務残高確認書
- 分割払いの合意書
ポイント2:
裁判所に預ける担保を確保することが必要
仮差押の手続きをするには、裁判所に「担保」を預ける必要があります。
これは、裁判所が「仮差押の決定」をしたものの、後で債権者が敗訴した場合に備えて、債務者が「仮差押の決定」により被る損害の賠償にあてるための一定額を、予め「担保」として債権者に預けさせるものです。
「担保」の金額は裁判所が決定しますが、目安として、仮差押をしようとして請求する債権の額の「約10%〜30%」程度になります。
「担保」は、原則として仮差押をした後に、債権者側が債務者に対して訴訟を起こし、訴訟で勝訴したあとに、裁判所から返金されることになります。つまり、訴訟期間中は、ずっと担保を裁判所に預けておかなければならないのです。
訴訟は長い場合には1年以上必要となりますので、その期間、担保として預けたお金は他の用途には使えません。このように、仮差押にあたっては、現金を担保として裁判所に預けることになりますので、そのための資金を確保することが必要です。
ポイント3:
訴訟にかかる期間や費用を検討しておくことが必要
仮差押をした後は、以下のような流れになり、通常は訴訟に進むことが必要になります。
- 1,仮差押
- 2,訴訟
- 3,勝訴判決
- 4,回収
このように、仮差押をした後は、通常は訴訟を起こさなければなりません。
そのため、訴訟までを踏まえて、必要な期間や弁護士費用を予め検討しておく必要があります。
ポイント4:
仮差押の申立をする裁判所を確認することが必要
仮差押の申立をどこの裁判所に出せばよいのかを確認しておくことが必要です。
通常は債権者側の所在地を管轄する裁判所で申し立てが可能ですが、回収する債権に関する契約書で債務者側の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所として規定している場合は、債務者側の所在地を管轄する裁判所で申立をしなければならないこともあります。
ポイント5:
債務者の本社が所在する不動産の登記簿謄本を取得することが必要
仮差押を申し立てると、裁判所から、債務者の本社が所在する建物の登記簿謄本の提出を求められます。
そして、債務者の本社が所在する不動産が債務者の自己所有の場合は、裁判所は債権の仮差押は認めず、不動産の仮差押に切り替えるように指示してくることがほとんどです。
これは、債権の仮差押をすると、債務者は取引先に仮差押をされたことを知られて大きなダメージを受けることがありますので、「債務者所有の不動産があれば、まず不動産を仮差押するように」という裁判所の配慮によるものです。
そのため、もし債権の仮差押を検討している場合は、特に早めに登記簿謄本を取得し、債務者の本社が所在する不動産の所有名義を確認する必要があります。
そして、債務者の本社が所在する不動産が債務者名義の場合は、申立の内容を不動産の仮差押に切り替える必要がありますので、覚えておきましょう。
4,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が債権回収のトラブルをサポートした解決事例
咲くやこの花法律事務所では、債権回収について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、仮差押えも利用して実際に回収を実現してきました。
以下で咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。
(1)未払い設計料や工事代金の回収依頼を受け、施主のショッピングモールに対する預り金債権を仮差押えできた事例
1.事件の概要
本件は、デザイン・設計を営む会社が内装工事を請け負いましたが、相手方は設計料や工事代金を一切支払おうとせず、裁判となる可能性も濃厚でした。紛争の長期化により工事代金回収が困難となることが予想されたため、相手方が入店するショッピングモールに対し、相手方の売上預り金債権を仮差押えが認められ、代金回収の目途を付けることができた事例です。
会社は、大手ショッピングモールのテナントとして入店している飲食店経営会社(相手方)から店舗のデザイン設計や内装工事を請け負いました。しかし、相手方は設計料や工事代金を請求しても話をはぐらかし、一切支払いをしようとはしなかったため、困り果てた会社は咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。
2.問題の解決結果
弁護士は、相手方の不誠実な態度から、当初から裁判を見据えていましたが、裁判中に相手方の財産が無くなれば、裁判で会社の請求が認められても、工事代金を回収できなくなることから、裁判前に相手方の財産の凍結(仮差押えの申立て)を検討しました。
裁判所に仮差押えを行ってもらうには、裁判官に証拠に基づき仮差押えに理由があると認めてもらうこと、会社側で凍結対象となる相手方の財産を特定することが必要でした。
この点、本件工事について会社は契約書を作成していませんでした。しかし、見積書、図面、相手方とのやり取りの内容を元に弁護士による詳細な説明を加えることで、裁判官に仮差押えに理由があると認めてもらうことができました。
次に、相手方の財産の特定ですが、相手方は不動産等目ぼしい財産がありませんでした。しかし、相手方は、大手ショッピングモールに入店しており、ショッピングモールに対する売上預り金債権があると考えられたため、これを仮差押えの対象としたことで仮差押えに成功しました。
▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。
(2)連絡不通の取引先から500万円回収!工場機械の仮差押えが決め手となった実例
1.事件の概要
本件は、会社が自社製品の販売をしていたところ、相手方の入金が止まり、連絡も取れなくなりました。会社は、相手方に逃げられるのではないか、相手方が倒産してしまうのではないかと不安に思い、今後の対応も含めて、咲くやこの花法律事務所に ご相談頂きました。
2.問題の解決結果
弁護士と相手方との交渉で分割払いの合意ができましたが、途中で相手方の支払いが止まり、連絡も取れなくなりました。
相手方からの任意の支払いは期待できないと判断し、訴訟を提起することになりましたが、相手方の資力に不安があり、勝訴できても回収が出来ない事態も考えられました。そこで、裁判所を使ってあらかじめ相手の財産を仮の形で押さえておき、勝訴した場合には押さえておいた財産から強制的に回収できるようにする(仮差押をする)方針をとりました。
依頼者と打ち合わせの上、相手方の預金口座、売掛金債権、工場内にあった機械の仮差押えを行いました。相手方は、銀行との関係で一部支払いと引き換えに預金口座に対する仮差押えの取下げを希望したため、一部支払いを受けて、これを取り下げま した。
残金については、分割払いで合意し、一部については会社の希望もあって商品を受け取って返済に充当(代物弁済)するなどし、最終的には全額を回収することができました。
結果的に、相手方から訴訟を経ずに回収することに成功しましたが、これは仮差押えが相手方に対するプレッシャーになっていたからだと思われます。
▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。
(3)相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例
1.事件の概要
本件は、倉庫を借りていた会社が、貸主である相手方に賃貸借契約の終了による保証金の返還を求めても、相手方が返還に応じなかったため、会社が相手方に訴訟を提起して勝訴し、相手方の銀行預金を差押えたところ、回収に成功した事例です。
会社は、3ヶ月分の保証金を差し入れて相手方から倉庫を借りました。契約上、保証金は明渡し後速やかに返還することになっていましたが、相手方は明渡し完了から約3カ月が経過しても、具体的な理由の説明もなく返還しませんでした。そこで、会社から咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。
2.問題の解決結果
弁護士から相手方に保証金の返還を求める内容証明郵便を送付しても、相手方からの連絡はなく、弁護士から電話をしても、相手方の社長は不在を理由に電話に出ようとすらせず、交渉は全く進みませんでした。
そこで、会社は保証金の返還を求める訴訟を提起しましたが、相手方は裁判所に出頭することもなく、会社の請求全額を認める判決が出ました。
判決確定後、あらためて弁護士が相手方に電話をしても、相手方の社長は不在とのことで、直接、話ができなかったため、判決に基づき相手方の銀行預金を差し押える手続きをとりました。その後、相手方から請求額の支払いを条件に差押えの取下げを求める電話があり、即日、相手方から全額が振り込まれ、全額回収に成功しました。
▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。
・相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例
上記の他にも債権回収トラブル関連の事件についての解決事例をご紹介しています。
5,仮差押など債権回収に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

最後に「咲くやこの花法律事務所」における、仮差押に関するサポート内容をご説明しておきたいと思います。
「咲くやこの花法律事務所」では、商品代金や工事代金の未払いのご相談を数多くお受けしており、その中で、個別の事案の内容を踏まえて、仮差押の手続をおすすめすることがあります。
債権回収に強い弁護士がご相談の中で、未払いになっている債権の内容や債務者の状況を詳細にヒアリングし、またお客様がお持ちの証拠書類を検討したうえで、「仮差押の手続をするのがよいかどうか」や「何を仮差押するのがよいか」を判断します。
そのうえで、ベストな方法で仮差押の手続を行い、債務者の財産を凍結して、確実な債権回収につなげます。
仮差押を行うかどうか、何を仮差押えするかは、債権回収の成功の可否をにぎる重要なポイントです。
未払い債権の回収のために仮差押の手続きをご検討中の方は、咲くやこの花法律事務所の「債権回収に強い弁護士のサポートサービス」までお問い合わせください。
弁護士費用例
- 初回相談料:30分5000円+税
- 仮差押え:20万円+税~
- 訴訟:30万円+税~
▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「債権回収に強い弁護士への相談サービスのご案内」の動画で、実際にサポートした一部の実績紹介、弁護士によるサポート内容、弁護士に相談するメリットなどを解説しています。
また、今回のような債権回収に関するトラブルは、企業経営の中でもっとも多いトラブルのひとつです。そのため、日頃から未払金トラブル発生時の対応など債権回収に関する正しい知識や事前準備を顧問弁護士に相談してしっかり対策しておくことも有効です。
債権回収に強い弁護士による顧問弁護士サービスは以下の情報も合わせてご覧下さい。
▶【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
▶大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
顧問弁護士の主な役割や必要性、費用の相場など基本的な情報をご覧になりたい方は以下の記事をご参照ください。
咲くやこの花法律事務所の弁護士への問い合わせ方法
「商品を売ったのに支払いをしてくれない。」や「工事をしたのに支払いをしてくれない。」など、債権回収でお困りの企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。また、問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
6,まとめ
今回は、全額回収率アップの有力な手段である「仮差押」について、以下のご説明をいたしました。
- なぜ、仮差押が有効な手段なのか?
- 仮差押の正しい手続きの進め方とは?
- 事前に検討しておくべきポイントとは?
訴訟を起こす前に正しい方法で仮差押することで、債権回収の確実性が格段にあがることは、私たち企業法務の専門家である弁護士だからこそわかることです。
仮差押には、担保金の準備、資料の準備、陳述書の作成等、さまざまな準備が必要で面倒な手続きではありますが、その労力に見合うだけの効果はあると考えます。
会社を経営している経営者の皆様、体験してからでは遅いため、予め、債権回収についての知識は深めておきましょう。
7,【関連情報】仮差押など債権回収に関するお役立ち記事
今回の記事では、「不動産・銀行口座(預金)・債権など仮差押の正しい手続きの進め方」についてご説明しました。
仮差押など債権回収については、正しい知識を知っておかなければ「結果的に何も回収できない」ということになりかねません。そのため、他にも必ずおさえておきたい債権回収のお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。
・債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説
・成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読
・売掛金など債権回収の時効は?期間や中断措置・更新措置などを解説
・支払督促とは?債権回収の場面での利用のメリットとデメリットを解説
・民事訴訟による債権回収。メリット・デメリットと手続の流れを解説
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2025年12月9日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」債権回収に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587