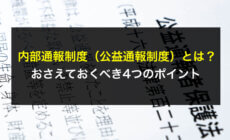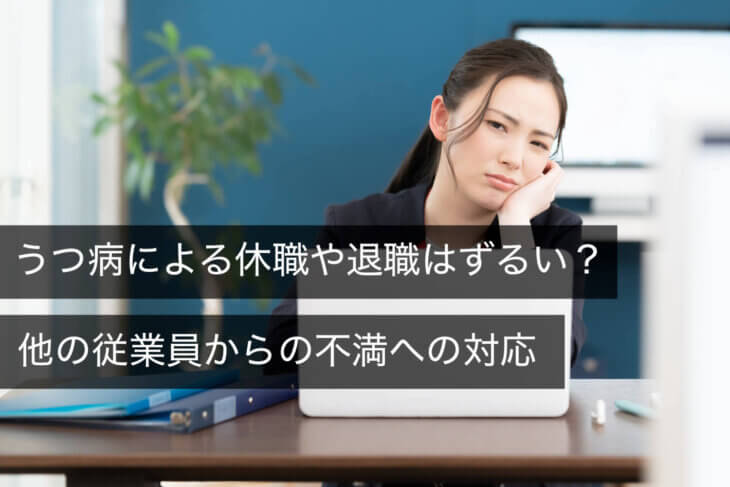
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
うつ病をはじめとした精神疾患で休職や退職をする労働者数は増加傾向にあります。精神疾患を発症した従業員にどのように対応していくかは、企業の経営者や人事担当者として必須の知識です。
一方で見落としがちなのが、休職者や退職者以外の従業員のフォローです。
うつ病での休職者や退職者がでた場合、休職者や退職者が担当していた業務は他の従業員で分担せざるを得ず、他の従業員にしわ寄せが発生することがあります。そのため、休職や退職について、他の従業員から不満の声が上がることも少なくありません。
このような状況を放置すると、従業員の士気が下がってしまったり、新たなメンタルヘルス不調者を発生させたり、休職していた従業員が復職をする際の妨げになったりする可能性があります。
この記事では、うつ病での休職や退職について、周囲の従業員かずるいと感じてしまう理由とその対応策について解説します。
休職者や退職者の対応に追われておろそかになりがちですが、休職者や退職者に対して他の従業員がずるいと思っていたり、不満や負担を感じているというケースは少なくありません。
企業としては、休職者のプライバシーに配慮しながら状況を説明した上で、周囲の従業員の不満を解消するための取り組みを行い、従業員の理解と協力を得る必要があります。
筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でも、従業員の休職や復職について企業側の立場でご相談をお受けしていますので、お困りの際は是非ご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士へのご相談は以下をご参照ください。
▶参考情報:労働問題に強い弁護士への相談サービスはこちら
▼うつ病での休職について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,うつ病による休職や退職をずるいと感じる理由
骨折やがん等の身体疾患で休職したり、退職したりする人をずるいと思う人は少ないのではないかと思います。一方で、うつ病となると、ずるいと感じてしまう人がいるのはなぜでしょうか。
うつ病で休職や退職をする従業員をずるいと感じる理由として、考えられるものを3つあげて解説します。
(1)うつ病に対する理解不足
昨今ではメンタルヘルスの不調に関する理解が広まってきたとはいえ、本人の性格の問題や、甘えだと考えている人が一定数いることも事実です。また、うつ病は、身体疾患とは異なり、不調が明らかな症状として身体に現れないケースもあります。
最悪の場合は自死に至ることもあるほど深刻な病気である一方で、外見からは理解されづらい病気であるため、本当は元気なのではないかといった誤った認識をもってしまう人がいるのです。
このようなうつ病に対する理解不足が、「ずるい」という発想につながっている可能性があります。
(2)業務負担等が増えることへの不満
休職者や退職者に対して不満が生じる原因で、最も多いと考えられるのが、休職や退職によって業務負担が増えることです。
休職や退職があると、休職者や退職者が担当していた業務を、誰かしらが負担する必要があります。さらに、うつ病での休職・退職の場合、本人の体調によっては、十分な引継ぎができないまま、業務を引き継がなければならないケースがあります。
このように業務負担が増えることや、引継ぎが不十分な状況で業務を引き継がなければならないということが、休職者や退職者に対する不満につながっている可能性があります。
(3)傷病手当金の受給に対するやっかみ
私傷病で働くことができなくなった場合、加入している健康保険から、給料の3分の2相当の傷病手当金を受給することができます。
療養中の生活を保障するための制度ですが、中には、働いていないのにお金がもらえてずるいと感じる人がいるようです。
しかし、傷病手当金は、これまでその人が健康保険料を納付してきたから受け取ることができる、当然の権利です。また、休職中でも社会保険料の支払いは免除されず、毎月支払う必要があるため、手元に残るお金は、仕事ができていた頃と比べるとかなり少なくなります。
さらに、一般的には傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月間が上限で、ずっと受給し続けることができるわけではありません。
心身の不調を抱え、社会保険料や医療費の負担があること、傷病手当金の給付は期間限定のものであることを考えれば、やっかむようなものではないと理解ができるのではないでしょうか。
2,従業員の不満への対応策

企業の人事担当者の中には、休職や退職をする本人への対応には注意を払っているけれど、周囲の従業員のことまで気が回らないと感じる方は多いのではないかと思います。
しかし、従業員の不満を放置すると従業員の士気を下げる原因になり、会社の対応次第で休職者や退職者への不満を増幅させてしまう可能性もあります。また、職場の同僚の不満を解消することは、休職者の復帰をスムースにするためにも重要です。
ここからは、うつ病での休職や退職に対して、周囲の従業員から不満がでた場合の対応策を2つ紹介します。
(1)メンタルヘルスに関する研修を行う
前章「1,うつ病による休職や退職をずるいと感じる理由」で説明したとおり、うつ病での休職者や退職者に対する不満は、うつ病をはじめとする精神疾患に対する理解不足から生じている可能性があります。
メンタルヘルスの不調に関する研修を行い、どのような症状があり、どのような配慮が必要なのか、どのように接すればよいのか等、従業員の理解を促すことで、知識不足からくる不満の解消につながります。
また、メンタルヘルスの不調に関する理解を深めることは、新たなメンタルヘルスの不調による休職者や退職者を出さないためにも重要です。
厚生労働省が運営している、職場のメンタルヘルス対策に関する情報提供や研修教材を配布している以下のようなサイトがあります。こういった教材を活用するのも方法の1つです。
(2)人員補充や業務量の調整等を行う
うつ病での休職者や退職者に対する不満につながりやすいのが、休職や退職にともない、休職者や退職者の業務を他の従業員が分担しなければならなくなり、業務負担が増えるという点です。
同僚が休職者に対する不満を感じている状況では、休職者の復職もうまくいかない可能性があります。また、過重な業務負担は、新たなメンタルヘルス不調者を生み出すことにもつながりかねません。
一時的なことであれば、元々いた人員で乗り越えることが出来るかもしれませんが、うつ病は短期間で症状の軽快と増悪を繰り返すこともあり、休職からの復帰の見通しが立たないことも少なくありません。
会社としては、休職者がすぐに復帰できない可能性も見越して、他部署からの人員の補充や、派遣社員の利用、業務の外注等を検討し、他の従業員の負担が大きくならないよう調整することが必要です。
3,病名は公表しない
そもそも、従業員がうつ病等の精神疾患で休職や退職をすることになった場合、病名は公表するべきではありません。
個人の病名は、個人情報保護法第2条3項の「要配慮個人情報」及び労働安全衛生法第104条の「心身の状態に関する情報」に該当し、慎重な取扱いが求められる個人情報です。
本人の同意を得ることなく、勝手に病名を社内で公表してしまったり、漏洩してしまった場合、あとで会社の責任を問われる可能性があります。
仮に、業務上の必要性等から上司や同僚に病名を伝える必要がある場合も、事前に本人の同意を得る必要があります。その際は、「どんな情報」を「誰に」話すのかを具体的に明示して説明をした上で本人から承諾を得ることが重要です。トラブルを避けるためにも、書面で同意をもらっておくとよいでしょう。
▶参考1:個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第2条3項
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
▶参考2:労働安全衛生法 第104条
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
・参照元:「労働安全衛生法」の条文はこちら
4,うつ病で休職する従業員への対応
うつ病で休職する従業員への対応としてまず重要なのは、休職の必要性や休職期間が明記された診断書を提出してもらうことです。休職の要否についての主治医の見解や、どのくらいの期間療養が必要なのかを診断書で確認し、その上で休職の必要性を検討します。
休職手続きは、就業規則の規定に従ってすすめることが重要です。就業規則に休職に関する規定がない会社は、早急に就業規則を整備しましょう。
休職に入る前に、休職期間や休職期間中の給与、休職期間中の会社との連絡方法、復職の手続き等について従業員に十分に説明しておく必要があります。また、社会保険料の負担が必要になることや、傷病手当金等の休職中に受けることができる福祉制度についても説明しておきましょう。
トラブルを避けるために、これらの説明は、口頭だけでなく文書でも交付しておくのがベストです。
さらに、周囲の従業員から「うつ病による休職はずるい」などと不満が出てこないようにするためには、休職者自身に休職中の行動に気を配ってもらうことも必要です。
休職中に休職者が飲み会や旅行に関する投稿をSNS等で発信しているのを同僚らが目にして、これが「休職はずるい」という不満を増幅させるきっかけとなることは少なくありません。
裁判例の中には、うつ病で休職中の従業員がオートバイで頻繁に外出したり、宿泊を伴う旅行をしたりしていた事案について、「うつ病や不安障害といった病気の性質上、健常人と同様の日常生活を送ることは不可能ではないばかりか、これが療養に資することもあると考えられていることは広く知られている」として、これらの行動を療養専念義務違反として問題視するべきではないとしたものがあります(東京地方裁判所判決平成20年3月10日マガジンハウス事件)。
しかし、休職者に対しても、休職中は療養に専念すべきことや、SNS等での発信については同僚からみられている可能性に注意するべきことを伝えておくことがトラブル防止につながるでしょう。
うつ病で休職する従業員への対応方法については、以下の参考記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
5,休職していた従業員が復職するときの注意点
うつ病からの復職にあたっては、必ず診断書を提出させて、主治医の意見を確認することが重要です。
これは、うつ病について本人の病識が足りていなかったり、金銭的な不安等から、体調が十分に回復していないのに無理に復職してしまうケースがあるためです。
また、復職後にどのような配慮が必要か、機械の操作や運転を伴う業務の場合は、服薬との関係で業務に影響がないか等も確認しておくべきです。場合によっては、復職の前に試し出勤等を行い、復職の判断材料としてもよいでしょう。
体調によっては、復職後にすぐに休職前の業務に戻すのではなく、負担の軽い業務につかせる、残業はさせないようにする等の配慮も必要です。無理な勤務はうつ病の症状の再発につながります。
一方で、会社がこのような配慮をすることについて、周囲の従業員が「ずるい」と感じるケースもありますので、復職者のプライバシーに配慮しながらも、周囲の従業員に必要な説明を行い、理解を求めていくいことが必要です。
うつ病で休職していた従業員を復職させるときの注意点については、以下の参考記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
6,従業員の休職や退職について弁護士へ相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、従業員の休職や退職に関するご相談をお受けしております。咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。
(1)従業員の休職や退職に関するご相談
従業員の休職や退職の場面では、休職の必要性の判断や、休職の手続き、復職の可否の判断等のあらゆる判断の場面にリスクが隠れています。
判断を誤ると、従業員から損害賠償を請求されたり、不当解雇として訴えられたりする等のトラブルに発展する可能性があります。
弁護士にご相談いただくことで、弁護士が法的なリスクを事前に指摘したり、適切な進め方について助言を行い、トラブルの発生を防止することができます。
また、何かトラブルが発生してしまった場合も、初期段階で弁護士にご相談いただくことで、問題を小さく収めることができます。問題が大きくなってからご相談いただいても、取れる手段が限られているということも少なくありませんので、早めにご相談いただくことをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士への相談費用
●初回相談料:30分5,000円+税
(2)顧問弁護士サービスのご案内
咲くやこの花法律事務所では、労務トラブルの対応や予防等、企業経営にまつわる法務をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。
休職や退職は思わぬところで法的なトラブルが生じる可能性があります。また、休職や退職手続きにあたっては、就業規則がしっかり整備されていることも重要です。
日頃からこまめに顧問弁護士にご相談いただき、社内の労務管理を整備しておくことで、トラブルの発生を予防することができます。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスでは、顧問契約の範囲内で就業規則のチェックも行っております(一部プランでは別料金となります)。ぜひご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。
7,まとめ
この記事では、うつ病での休職者や退職者に対して、周囲の従業員が「ずるい」と感じる理由やその対応策等について解説しました。
休職者や退職者に対する不満が生じる理由としては、「(1)精神疾患への理解不足、(2)業務負担が増えることへの不満、(3)傷病手当金の受給に対するやっかみ」の3つがあります。
このような不満を解消するためには、うつ病への理解を深めるための研修や、人員補充や業務量の調整等の業務負担の軽減の対応策が有効です。
個人の病名はセンシティブな個人情報であるため、うつ病で休職や退職をする従業員がでた場合、本人の同意なく、休職理由や退職理由(病名)を公表するべきではありません。
また、休職者に休職中の言動に注意してもらうこと、復職の場面では復職にあたり必要な配慮について周囲の従業員に説明して理解を求めることなどが、周囲の従業員の不満防止に役立ちます。
休職や退職については、本人の希望と会社の意向が食い違い、問題がこじれ紛争化てしまうケースもあります。休職や復職をめぐって従業員と訴訟になり、企業側が金銭の支払いを命じられている裁判例も多数存在します。従業員の休職や復職のトラブルでお困りの際は自己判断で対応するのではなく、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
9,うつ病など従業員の休職についてお役立ち情報を配信中(メルマガ&YouTube)
うつ病従業員の休職に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
記事作成日:2023年2月28日
記事作成弁護士:西川 暢春
 06-6539-8587
06-6539-8587