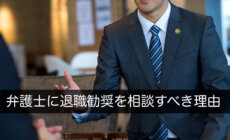こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
「従業員に金銭を横領されて返済がない」、そんな場合にとれる手続きが刑事告訴です。
刑事告訴をすることにより、横領した従業員からの返済を期待することができ、また、刑事裁判により本人に制裁を科すことができます。一方で、刑事告訴を成功させるためには、警察の協力を得ることが欠かせません。このことは、刑事告訴を成功させるために重要な点であり、いくつかのポイントをおさえておくことで、警察の協力を得やすくなります。
今回は、従業員による業務上横領・着服の刑事告訴・刑事告発のメリット、手続きの流れをご説明したうえで、刑事告訴を成功させるためのポイントについてご紹介したいと思います。
▶参考:従業員による横領に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。
▼【動画で解説】西川弁護士が「従業員による横領発覚時の刑事告訴のポイント!」を詳しく解説中
▼【関連情報】業務上横領や着服に関する基礎知識については、以下の関連情報もご覧下さい。
▼業務上横領について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,業務上横領罪の刑事告訴・刑事告発とは?
刑事告訴・刑事告発とは、警察や検察に対して、事件を捜査して犯人を処罰することを求めることをいいます。被害者本人が処罰を求める場合は「刑事告訴」、被害者以外の関係者が処罰を求める場合は「刑事告発」と呼ばれます。
業務上横領罪の刑事告訴・刑事告発の具体例としては以下のようなケースがあります。
事例1:集金業務を担当する従業員による横領の刑事告訴
典型例としては、集金業務を担当する従業員が顧客から集金した現金を着服し、会社には、未収金として報告していたケースがあげられます。
これらのケースについて刑事告訴を行うパターンです。
事例2:店長、支店長クラスによる現金の横領の刑事告訴
典型例としては、店長、支店長が会社に売上額を実際より少なく申告したうえで、差額を着服するケースがあげられます。
これらのケースについて刑事告訴を行うパターンです。
事例3:経理の従業員による横領の刑事告訴
経理を担当する従業員による横領の典型例としては、以下のようなものがあります。
- 会社の預金口座から自分の口座に振り込んで横領するケース
- 第三者と共謀して架空の請求書を出してもらい会社の預金口座から第三者の口座に送金し自身に還流させるケース
これらのケースについて刑事告訴を行うパターンです。
事例4:会社の郵便切手管理者による横領の刑事告訴
会社で購入して保管している郵便切手の管理者が、使用済みと偽って、郵便切手を横領して、換金するケースもあります。
これらのケースについて刑事告訴を行うパターンです。
2,刑事告訴をするメリット
会社が業務上横領の刑事告訴を行うメリットとしては以下の点があげられます。
メリット1:
犯人に処罰を科すことができる。
刑事告訴をすることによって、犯人に処罰を科すことができます。
正式な裁判に進んで犯人が処罰されるかどうかは、刑事告訴後の捜査の結果次第という面がありますが、少なくとも犯人に処罰を科すきっかけを作ることができるのが刑事告訴です。
なお、業務上横領罪の場合の処罰は法律上「10年以下の拘禁刑」とされています。裁判で実際に科される刑罰のおおまかな目安は以下の通りです。
※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。
- 被害金額100万円以下:執行猶予
- 被害金額500万円:2年の実刑
- 被害金額1000万円:2年6か月の実刑
- 被害金額3000万円:3年の実刑
メリット2:
横領金の返済につながりやすい。
刑事告訴は横領金の返済を促す有力な手段の1つでもあります。なぜなら、業務上横領の刑罰は、横領金を返済したかどうかで刑の重さが変わってくるためです。
前述の通り、100万円を超える横領であれば有罪になれば実刑になる可能性が高いです。しかし、刑事裁判が終わるまでに示談して横領金を返済すれば執行猶予になることは珍しくありません。
仮に実刑になるとしても、横領金を返済していれば、1年くらい実刑の期間が短くなることが多いです。そのため、横領した従業員が刑事告訴されて、刑事裁判にかけられれば、自分の刑をできるだけ軽くするために誰かにお金を借りてでも会社に横領金を返済しようという強い動機付けを与えることができます。
ただし、人によっては、刑が長くなっても気にしない人もいますし、横領金を返済しようにも返済資金のあてがない人もいます。そのため、刑事告訴をしたからといって必ず横領金が返済されるわけではありません。
横領した従業員に対する返済請求については以下の動画や記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
▶参考動画:【動画で解説】西川弁護士が「従業員に横領された金銭の返還請求をするときのポイント!」を詳しく解説中!
メリット3:
社内でけじめをつけることができる
刑事告訴は、業務上横領事件について社内でけじめをつけるためにも重要です。
業務上横領があった場合、当然、懲戒解雇するべきですが、その後も返済がない場合に、解雇しただけで事件を終わらせてもいいのかということがあります。
▶参考動画:【動画で解説】西川弁護士が「従業員による横領発覚時の懲戒解雇の注意点を解説」を詳しく解説中!
社内のモラル、秩序を保つためには、刑事告訴をしたうえでそれを社内で発表するということも必要になってきます。
以上の3つが業務上横領罪について刑事告訴を行う主なメリットです。
3,業務上横領罪の刑事告訴手続きの流れ
それでは、次に、業務上横領罪の刑事告訴手続きの流れを見ていきましょう。
業務上横領罪の刑事告訴は通常は以下の流れで進めていきます。
(1)弁護士に相談する
刑事告訴は弁護士に依頼することが一般的です。
自社で刑事告訴をすることもできますが、自社での刑事告訴では警察がなかなか積極的にとりあってくれないことが多いため、実際上は困難です。弁護士に刑事告訴を依頼することで、適切な書類、証拠を準備して刑事告訴を行うことができ、警察の協力を得やすくなります。
(2)告訴状を郵送する
刑事告訴は「告訴状」という文書を警察に提出することから始まります。
告訴状とは、犯人が「いつ」、「どのようにして」、「いくらを」横領したかという業務上横領に該当する事実を記載して、警察に処罰を求める書面です。
告訴状の書き方は専門的な知識が必要ですので弁護士に作成してもらいましょう。
告訴状ができたら警察に郵送することが一般的です。ただし、告訴状を警察に郵送してすぐに告訴を受理してもらえることはほとんどありません。警察は告訴状のコピーをとったうえで、告訴をすぐには受理せず、告訴状を返送してくるのが通例です。
(3)警察との打ち合わせを行う
告訴状を郵送した後は、警察に出向いて、打ち合わせを行います。
特に犯人が複数回にわたって継続的に横領している場合は、「どの横領を処罰の対象にするか」ということが重要な打ち合わせ事項になります。
警察としては、犯人を刑事裁判にかけたが無罪になってしまったということでは困るので、複数回にわたって横領している場合は確実な証拠がある分だけを処罰の対象としたいと伝えてくることが多いです。
警察との打ち合わせをもとに、刑事告訴の対象とする横領行為を確実に証拠のある分のみにしぼる場合は、最初の告訴状の記載内容を修正し、告訴状を出しなおすことが必要になってきます。
(4)告訴状が受理される
警察との打ち合わせを踏まえ、告訴状を正式に受理してもらうことが、刑事告訴の最初の目標になります。告訴状が受理されれば、警察が捜査を開始することになります。
(5)取り調べに協力する
警察の捜査が開始された後も、被害者として警察の捜査に協力していく必要があります。追加で提出できる証拠があれば提出したり、被害者として調書を作成してもらうことに協力しなければなりません。調書作成のために、社長や担当者が警察に出向くことが必要になってきます。
(6)検察庁に送致される
警察で犯人に対しても取り調べが行われた後、事件は検察庁に送致されます。これを「送検」と言います。
(7)検察庁が起訴、不起訴を決定する
事件が送致された検察庁でも、再度、捜査が行われます。
会社側も被害者として調書の作成などに協力していくことが必要になります。そして、捜査が終わった段階で、検察庁が「起訴か不起訴か」を決定します。
「起訴」というのは、刑事裁判にかけるという意味です。一方、「不起訴」というのは、証拠が不十分だとか、被害金額が大きくないなどといった理由で刑事裁判にかけないという判断になります。
(8)刑事裁判が行われる
起訴されれば、裁判所で刑事裁判が行われ、有罪になれば本人の処罰が言い渡されます。
以上が、業務上横領罪の刑事告訴手続きの流れになります。
4,業務上横領罪の刑事告訴の重要ポイント

それでは、前述の刑事告訴手続きの流れも踏まえたうえで、業務上横領罪の刑事告訴のポイントを見ていきましょう。
(1)裏付けの証拠をきっちり集める
刑事告訴の際には、犯人が業務上横領をしたという裏付けの証拠をきっちり集めることが重要です。
警察の立場としては、業務上横領があったとしても十分な証拠がなければ最終的に刑事裁判にかけることができないので、証拠がなければ捜査を始めたくないと考えることが多いです。
そのため、会社側でその犯人が業務上横領を行ったことの裏付け証拠をきっちり集めて刑事告訴することが、警察に刑事告訴を受理して捜査を進めてもらうためのポイントになります。
具体例:例えば、集金業務を担当する従業員が顧客から集金した現金を着服し、会社には、未収金として報告していたケースについては、以下のような証拠が必要になります。
●顧客がその従業員に現金を手渡したことがわかる証拠
例えば、従業員が顧客から現金を集金した際に領収書を顧客に渡しているのであれば、その顧客に協力してもらい、顧客からその領収書を回収して、警察に提出する必要があります。
●その従業員が集金していたにもかかわらず会社に未収金としていたことがわかる証拠
例えば、集金担当者が会社に提出する業務日報や報告書で、横領された顧客の集金分について未収であると報告していることがわかるものを警察に提出する必要があります。
なお、仮に犯人が業務上横領を認めている場合であっても、裏付け証拠はしっかり集める必要があります。
これは、刑事裁判のルールとして、犯人が犯罪をしたことを認めているだけでほかに証拠がない場合は、刑事裁判で有罪にできないというルールがあるためです。
▶参考情報:証拠収集の正しい方法は、以下の参考記事や動画で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
▶【参考動画】「社内で横領が起きたとき!どうやって証拠をおさえる?【裁判例の解説付き】」をこの記事の筆者でもある西川弁護士が解説中
(2)証拠の堅いところだけを告訴の対象とする
横領が複数回行われている場合、「横領が証拠上はっきりとわかるもの」と、「証拠上横領が明確とまでは言えないもの」にわかれることがあります。
具体例:例えば、集金業務を担当する従業員が顧客から集金した現金を着服し、会社には、未収金として報告していたケースについては、顧客がその従業員に現金を手渡したことがわかる証拠が必要です。
従業員が顧客から現金を集金した際に領収書を顧客に渡しているのであれば、その顧客に協力してもらい、顧客からその領収書を回収して、警察に提出する必要があります。
この場合、領収書を回収できなかった顧客からの横領分については、従業員が顧客から現金を集金したことの証拠がないため、前述の「証拠上横領が明確とまでは言えないもの」に該当します。
最初に警察に郵送する告訴状には、証拠上明確かどうかを問わず、会社で把握しているすべての横領を記載してもかまいません。
しかし、その場合、警察から、証拠上明確な横領にしぼった内容で告訴状を再提出してほしいといわれることが多いことが実情です。このような場合は、証拠上明確な横領だけにしぼって告訴する方が警察に告訴を受理し、捜査を進めてもらいやすくなります。
警察としては証拠上はっきりしない部分について労力をかけて捜査することを嫌がることも多いので、証拠の堅いところに告訴の対象をしぼることが告訴を成功させるポイントの1つです。
(3)エクセルで一覧表を作る
業務上横領罪の刑事告訴で、横領が複数回あるときは、警察から、横領事実について、エクセルで一覧表を作って提出してほしいと求められることが多いです。
そのような場合は、各回の横領行為について、以下の項目を整理して提出することが必要です。
- 横領の日時
- 横領行為の内容
- 被害金額
- 横領の裏付け証拠
このようなエクセルの一覧表を早めに準備することが、業務上横領罪の告訴を早く受理してもらうためのポイントになります。
(4)警察への進捗確認を頻繁に行う
警察署の中には、他の事件で多忙であるなどの事情で、告訴された事件の捜査に積極的でないところもあります。そのような場合でも、告訴の受理や告訴後の捜査を迅速に進めてもらうためには、警察への進捗確認を頻繁に行うことが必要です。
告訴が受理される前の段階では、例えば、警察に郵送した資料が届いたかどうか、届いた資料を見てもらえたかどうかなど、逐一確認することがおすすめです。また、告訴が受理された後は、被害者の調書の作成はいつするのか、犯人の呼び出しはいつするのかなど、その都度確認しましょう。時間がたったけれども捜査が進んでいないというようなことにならないようにする必要があります。
(5)民事の話はしない
警察の中には、「民事の話」を嫌がるケースもあります。
業務上横領の告訴の場合、「民事の話」というのは、横領金の返済を求めるために「内容証明郵便」を送って交渉したり、あるいは裁判を起こしたりということを指します。
返済を求めることは、横領された側としては当然のことなのですが、警察としては、「民間のトラブルのために捜査を利用されたくない」と考えるケースも多いのが実状です。そして、刑事告訴は結局のところ警察に協力してもらえなければ話が前に進みません。
そのため、警察では、横領金の返済を求める話についてはなるべく伏せておいたほうが、スムーズに告訴を受理してもらえる可能性が高まります。
以上の点を、業務上横領罪の刑事告訴のポイントとしておさえておきましょう。
5,咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する解決実績
咲くやこの花法律事務所では、企業の発生した横領事件について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、横領された金銭の回収を実現してきました。
以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。
6,従業員の横領による刑事告発・刑事告訴に関して弁護士に相談したい方こちら

咲くやこの花法律事務所では、従業員の業務上横領に関するご相談を企業から承っています。そこで、最後に、咲くやこの花法律事務所における、業務上横領に関する企業向けサポート内容をご紹介したいと思います。
▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「業務上横領に強い弁護士への被害企業向け相談サービス」を動画で解説しています!
サポート内容は以下の通りです。
- (1)従業員による業務上横領事件に関するご相談
- (2)事実関係の調査、本人からの事情聴取
- (3)業務上横領の刑事告訴手続き
- (4)横領についての損害賠償請求、返済請求
- (5)横領を理由とする解雇についての解雇トラブルの対応
- (6)業務上横領を未然に防ぐための予防策
以下で順番に見ていきましょう。
(1)従業員による業務上横領事件に関するご相談
従業員による業務上横領事件が発生してしまった場合は、迅速に、事実関係の調査や刑事告訴、本人に対する返済請求、懲戒解雇などの対処をすることがとても大事です。そのためには、自社だけで対応するのではなく、弁護士のサポートを受けながら進めたほうがよいでしょう。
咲くやこの花法律事務所では、従業員による業務上横領事件に精通し、豊富な経験をもつ弁護士が随時ご相談を承っています。ご相談いただければ、迅速適切に対応策をご提案し、また実行していくことができます。従業員による業務上横領への対応でお悩みの企業様はぜひご相談ください。
業務横領事件に関する相談の弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
(2)事実関係の調査、本人からの事情聴取
業務上横領事件が発生してしまった場合、まずは事実関係を詳細に調査し、その結果を踏まえて本人からの事情聴取をする必要があります。
事実関係の調査が不十分だと刑事告訴をしても警察で受理がされません。また、返済請求も失敗しかねないほか、証拠不十分のまま懲戒解雇などの処分をすれば、不当解雇であるとして訴訟になり会社が敗訴するおそれもあります。調査や事情聴取の段階で、刑事告訴や、後日の返済請求、解雇トラブルに対応することができるだけの証拠を確実に集めてしまうことが重要です。
咲くやこの花法律事務所では、従業員による業務上横領事件に精通し、豊富な経験をもつ弁護士が随時ご相談を承っています。ご相談いただければ、事情をつぶさに聴き取り、弁護士が事案に応じて最適な方法で調査や事情聴取、証拠収集を行います。
調査、事情聴取に関する弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●調査費用:15万円+税~
(3)業務上横領の刑事告訴手続き
横領をした従業員について刑事告訴を行うことは重要です。
刑事告訴をすることによって、従業員にプレッシャーをかけ、返済をうながす効果があります。また、刑事告訴をすることによって、社内に一定のけじめをつけ、他の従業員のモラルの低下を防ぐことができます。
一方、業務上横領事件が起こっているのに、会社が刑事告訴その他の対応をしなければ、他の従業員のモラルも低下して、今後も横領事件が発生してしまう会社になってしまうおそれがあります。
ただし、刑事告訴の手続きは、この記事でもご説明した通り、警察の協力を得ることが必要であり、専門的なノウハウが必要です。
咲くやこの花法律事務所では、従業員の横領に関する刑事告訴についてのご相談も常時承っており、経験も豊富です。従業員による横領について、刑事告訴をご検討中の企業の方は、ぜひとも咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
刑事告訴手続きに関する弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●刑事告訴手続き着手金:40万円+税~
(4)横領についての損害賠償請求、返済請求
従業員による業務上横領事件が発生した場合は、従業員に対し返済や損害賠償を請求することが必要です。
そのためには、会社は事実関係を詳細に把握し、横領の証拠資料を揃える必要があります。また、従業員への請求方法についても、内容証明郵便、仮差押え、訴訟、強制執行などさまざまな方法があり、適切なものを選択して迅速に実行する必要があります。
横領についての損害賠償請求、返済請求については、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。従業員による業務上横領事件について経験豊富な弁護士が、事案を適切に検討し、横領をした従業員とすみやかに交渉を行うなど横領金の返済請求、損害賠償請求をいたします。
損害賠償請求や返済請求に関する弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:15万円+税~
(5)横領を理由とする解雇についての解雇トラブルの対応
咲くやこの花法律事務所では、横領による懲戒解雇後に従業員が不当解雇であると主張してきてトラブルになった場合の交渉や、裁判の対応について多くの実績があります。
裁判所で、横領の証拠が不十分であるなどと判断され、懲戒解雇が不当解雇と判断されてしまうと、会社側が1000万円を超える金銭支払いを命じられる場合もあります。
横領した従業員に対しては懲戒解雇をもって臨むべきですが、懲戒解雇をするにあたっては専門的な知識やノウハウに基づく十分な事前準備が必要なうえ、解雇後にトラブルになった場合にも適切な対処が必要です。
懲戒解雇した従業員とのトラブルでお悩みの場合は、解雇トラブルの解決に精通した咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。
横領に関する解雇トラブルの対応の弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●労働審判対応着手金:45万円+税~
●労働裁判着手金:45万円+税~
(6)業務上横領を未然に防ぐための予防策
従業員による業務上横領は、未然に防ぐに越したことはありません。
従業員により横領がなされた場合、会社が金銭的なダメージを受けるだけでなく、その従業員の懲戒解雇、横領された金銭の返還請求、刑事告訴など人的にも時間的にも非常に大きなコストがかかります。
咲くやこの花法律事務所では、過去に裁判となった事例や実際に取り扱った事例をもとに、従業員による横領を防ぐための実践的なアドバイスをさせていただきます。従業員による業務上横領を未然に防ぐための予防策についてご検討中の企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
業務上横領を未然に防ぐための対策の弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●書類作成:5万円+税~
また、労働問題に強い弁護士による顧問弁護士サービスもございます。以下も参考にご覧下さい。
▶【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
▶大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士による業務上横領に関するサポート内容は、「横領・業務上横領に強い弁護士にへの相談サービス」のページをご覧下さい。
また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
8,業務上横領についてのお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
業務上横領に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
以下よりメルマガ登録やチャンネル登録をしてください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
9,まとめ
今回は、まず、刑事告訴、刑事告発の意味についてご説明したうえで、刑事告訴のメリットと手続き、刑事告訴を成功させるためのポイントをご説明しました。
刑事告訴は、会社側で入手できる限りの証拠を警察に提出し、警察が捜査しやすい環境を作ることが重要なポイントになります。また、中には、告訴事件に積極的でない警察署もありますので、警察に協力してもらえるように、頻繁に進捗を確認しながら、上手に警察と話をしていくことが必要です。
なお、従業員による業務上横領・着服のケースでは、会社側の対応として、刑事告訴のほかに、犯人の懲戒解雇や横領金の返済請求が必要になります。これらの点は以下の参考記事で解説していますのであわせてご確認ください。
▶参考:従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点について
▶参考:従業員に着服、業務上横領された金銭の返金・返済請求の重要ポイント
また、業務上横領の予防策として、不正防止の対策方法や身元保証書の作り方など以下の参考記事で解説しておりますので、こちらもぜひチェックしておいてください。
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2025年8月5日
 06-6539-8587
06-6539-8587