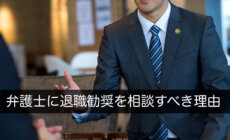「就業規則に異動に関する規定があれば、従業員に対して自由に職種変更を命じることができる」と思っていませんか?
従業員に対する職種変更の命令には一定の制約があり、制約を超えて職種変更を命じてしまうと、裁判で敗訴し、多額の支払いを命じられるケースがあります。
例えば、病院が「事務職員」に対し、「ナースヘルパー職」への職種変更を命じたが従わなかったため解雇した事例では、裁判所は、病院に対し、従業員を復職させたうえで、さらに解雇から判決までの「約4年6か月の期間の給与」を支払うことを命じました。
このように、安易な職種変更命令には、多額の金銭支払いを命じられる裁判トラブルにつながる危険が潜んでいます。
今回は、「企業が従業員に職種変更を命じる際に必ずおさえておくべき3つの注意点」についてご説明したいと思います。
▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。
▼【関連情報】従業員の職種変更については、こちらの関連記事も合わせてご覧ください。
・【転勤や単身赴任を嫌う従業員への対応】転勤命令トラブルを防ぐための4つのポイント
▼従業員の職種変更の対応について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,企業が従業員に職種変更を命じる際に必ずおさえておくべき3つの注意点
「これまで営業職として雇用していた従業員について、営業力がないので、事務職に職種変更したい。」
「社長秘書として雇用していた従業員について、秘書職を廃止するので、販売員に職種変更したい。」
「新規事業のために従業員の職種変更が必要になった。」
このように、企業経営のさまざまな場面で、従業員の職種変更を検討しなければならないことがあります。
しかし、冒頭でご説明した通り、職種変更命令は、思わぬ裁判トラブルにつながることがあり要注意です。
企業が従業員に職種変更を命じる際には、注意点として以下の3点を必ずおさえておいてください。
企業が従業員に職種変更を命じる際に必ずおさえておくべき3つの注意点
注意点1:
職種変更命令の前に職種限定契約かどうかを確認する。
注意点2:
職種限定契約の場合は職種変更を命じることができない。
注意点3:
職種限定契約でない場合も職種変更には制約がある。
以下で順番にご説明してきたいと思います。
1−1,注意点1:
職種変更命令の前に職種限定契約かどうかを確認する。
企業が従業員に職種変更を命じる際におさえておくべき注意点の1つ目は、「職種変更命令の前に職種限定契約かどうかを確認する」という点です。
この点については、まず、最初に、「職種限定契約とは何か」ということをご説明したいと思います。
職種限定契約とは?
「職種限定契約」とは従業員と企業の雇用契約において、その従業員を特定の職種にのみ従事させることを合意していると解釈されるケースをいいます。
従業員との雇用契約が職種限定契約である場合は、企業は従業員に対して職種変更を命じることはできません。
一方で、雇用契約が職種限定契約ではない場合は、一定の制約はありますが、企業は従業員に対して別の職種への職種変更を命じることができます。
では、どのようなケースが「職種限定契約」と判断されるのでしょうか?
裁判例をみると、過去に「職種限定契約」と判断されているケースはおおむね以下の2つのケースです。
過去の裁判例で「職種限定契約」と判断されているケース
ケース1:
高度な資格を要する職種のケース
ケース2:
その職種について他職種よりも高度な能力を求める採用基準が設定されていたケース
具体的な例としては以下のとおりです。
ケース1:
高度な資格を要する職種のケース
例えば、「看護師」のような高度な資格を要する職種については、職種限定契約であり、看護師以外の職種への職種変更命令はできないと判断されています。(仙台地方裁判所昭和48年5月21日判決)
一方で、「タクシー運転手」や「トラック運転手」なども資格を要する職種ですが、裁判所では、高度な資格とまではいえないとして、「職種限定契約ではない」と判断されているケースが多くなっています。
ケース2:
その職種について他職種よりも高度な能力を求める採用基準が設定されていたケース
例えば、「大学教員」については、大学による採用時に、大学事務員等の職種よりも高度な能力を求める採用基準が設定されていたことなどを根拠に、職種限定契約であり、他職種への職種変更命令はできないと判断されています。(福井地方裁判所昭和62年3月27日判決))
また、「英語が堪能であること」などを採用基準として採用した社長秘書についても、職種限定契約であり、他職種への職種変更はできないと判断されています。(大阪地方裁判所平成9年6月10日判決)
このように、高度な資格を要する職種や自社の他職種よりも高度な能力を求める採用基準で採用した従業員については、「職種限定契約にあたる」と判断されていることを、まずおさえておきましょう。
▼従業員の職種変更の対応について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
1−2,注意点2:
職種限定契約の場合は職種変更を命じることができない。
企業が従業員に職種変更を命じる際におさえておくべき注意点の2つ目は、「職種限定契約の場合は職種変更を命じることができない」という点です。
従業員との雇用契約が職種限定契約である場合は、仮に就業規則に「従業員は正当理由なくして異動を拒めない」などの規定があっても、企業はその従業員に対して職種変更を命じることはできません。
以下で、実際の裁判例を見ていきましょう。
雇用契約が職種限定契約であり、職種変更命令は違法であると判断した裁判例
裁判例1:
東北公済病院配転事件
(仙台地方裁判所昭和48年5月21日判決)
事案の概要:
病院が看護師として勤務していた従業員を他の看護師や医師とのトラブルが絶えないことを理由に洗濯場勤務に職種変更した事例
裁判所の判断:
職種変更命令は「違法」と判断しました。
その上で、「看護師としての職務に従事させなければならない」との判決を下し、給与の差額や慰謝料等として「約200万円」の支払いを命じました。
裁判例2:
金井学園福井工大事件
(福井地方裁判所昭和62年3月27日判決)
事案の概要:
大学の方針に批判的な大学助教授に一般事務職員への職種変更を命じた事例
裁判所の判断:
助教授は職種変更を拒否し、大学はこれを理由に助教授を懲戒解雇しましたが、裁判所は職種転換命令は「違法」であり、その拒否を理由とする解雇も不当解雇であると判断しました。
その上で、大学に対し、助教授として大学に復職させることと、助教授に対する「約410万円」の支払いを命じました。
裁判所の判断の理由:
大学の教育職員は大学事務職員と異なる採用基準が設けられ高い能力が要求されていたことなどを理由に、「助教授との雇用契約は職種限定契約であり、職種変更命令は違法である」と判断しました。
裁判例3:
ヤマトセキュリティ事件
(大阪地方裁判所平成9年6月10日判決)
事案の概要:
警備会社が、社長秘書業務に従事していた従業員に警備員への職種変更を命じた事例
裁判所の判断:
従業員は職種変更を拒否し、会社はこれを理由に従業員を解雇しましたが、裁判所は不当解雇であると判断しました。
その上で、従業員を復職させ、解雇により支給されなかった解雇後の期間の給与「約200万円」を支払うことを会社に命じました。
裁判所の判断の理由:
「社長秘書募集」という表題の下に、採用条件として、「英語堪能な方を望みます(仏語もできる方は尚良)」などと記載して、他職種とは異なる採用基準で求人を行っており、社長秘書業務を含む事務系業務に限定されていたと判断しました。
このように、「職種限定契約である」と判断されたケースでは、職種変更命令やそれに従わないことを理由とする解雇は、「違法」、「無効」とされ、企業側が多額の金銭支払いを命じられていることがわかります。
高度な資格を要する職種や他職種よりも高度な能力を求める採用基準で採用した従業員については、職種限定契約と判断されることが多く、その場合、職種変更命令は違法と判断されることをおさえておきましょう。
▼従業員の職種変更の対応について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
1−3,注意点3:
職種限定契約でない場合も職種変更には制約がある。
企業が従業員に職種変更を命じる際におさえておくべき注意点の3つ目は、「職種限定契約でない場合も職種変更には制約がある。」という点です。
職種限定契約でない場合は、就業規則に異動に関する規定があれば、企業は従業員に対して職種変更を命じることが可能です。
ただし、一定の制約があり、その制約を超えて職種変更命令を行うことはやはり違法と判断されます。
職種限定契約でない場合の職種変更に関する制約とは、具体的には、以下のとおりです。
職種限定契約でない場合の職種変更に関する制約
「業務の系統を異にする職種への異動(例えば、事務系の職種から労務系職種への異動)については、特別な事情がない限り、企業が一方的に命ずることはできない」
判例も、「業務の系統を異にする職種への異動、特に事務職系の職種から労務職系の職種への異動については、業務上の特段の必要性及び当該従業員を異動させるべき特段の合理性があり、かつこれらの点についての十分な説明がなされた場合か、あるいは本人が特に同意した場合を除き、企業が一方的に異動を命ずることはできない。」としています。(直源会相模原南病院事件)
そして、このような結論は、就業規則に「従業員は正当な理由なく異動を拒めない」などと規定があったとしても、変わりません。
この点に関する過去の裁判例には以下のようなものがあります。
異なる業務系統間の職種変更であるとして職種変更命令を違法と判断した裁判例
●病院の「事務職員」から「ナースヘルパー職」への職種変更命令(裁判例4)
●高級アパレルブランドの販売会社における「システム専門職」から「倉庫係」への職種変更命令(裁判例5)
同じ業務系統間の職種変更であるとして職種変更命令を合法と判断した裁判例
●ヘルスケア商品の販売会社における「営業事務職」から「検品業務」への職種変更命令(裁判例6)
●児童福祉施設の「児童指導員」から「厨房の調理員」への職種変更命令(裁判例7)
以下で、それぞれの裁判例の概要を見ていきましょう。
まず、異なる業務系統間の職種変更であるとして職種変更命令を違法と判断した2つのケースをご紹介します。
異なる業務系統間の職種変更であるとして職種変更命令を違法と判断したケース
裁判例4:
直源会相模原南病院事件
(東京高等裁判所平成10年12月10日判決)
事案の概要:
病院が事務職員に対し、ナースヘルパー職への職種変更を命じた事例
裁判所の判断:
従業員は職種変更を拒否し、病院はこれを理由に従業員を解雇しましたが、裁判所は職種変更命令は違法であり、命令拒否を理由とする解雇は不当解雇であると判断しました。
その上で、病院に対し、従業員を復職させたうえで、解雇により従業員が給与を受け取れなかった「約4年6か月の期間の給与を支払うこと」を命じました。
裁判所の判断の理由:
裁判所は以下の点を指摘して、職種変更命令を違法と判断しています。
1,就業規則には「正当理由なくして異動は拒めない」とあるが、異なる業務系統間の異動については、特別な事情がある場合を除き、企業が一方的に異動を命ずることはできない。
2,本件では、変更前の職種は事務的作業であり、労務的作業を職務内容とするナースヘルパーへの配置転換は、全く職務内容を異にする職種への配置換えにあたる。
裁判例5:
高級アパレルブランドの販売会社の事件
(東京地方裁判所平成22年2月8日判決)
事案の概要:
高級アパレルブランドの販売会社が、システム専門職の従業員に倉庫係への職種変更を命じた事例
裁判所の判断:
裁判所は職種変更命令を違法と判断しました。
その上で、この従業員が倉庫係として勤務する義務がないことを確認する判決を下し、さらに会社に「50万円」の慰謝料の支払いを命じました。
裁判所の判断の理由:
「倉庫係の業務は、従業員のシステム関連の技術や経験を活かすことができるものではおよそなく、むしろ労務的な側面をかなり有する。」として異なる業務系統間の職種変更命令であると判断しています。
このように、職種限定契約でない場合であっても、事務系職種から労務系職種への職種変更命令は違法と判断される傾向にあります。
次に、同じ業務系統間の職種変更であるとして職種変更命令を合法と判断した裁判例をご紹介します。
同じ業務系統間の職種変更であるとして職種変更命令を合法と判断した裁判例
裁判例6:
コロプラスト事件
(平成24年11月27日東京地方裁判所判決)
事案の概要:
ヘルスケア製品の販売会社が、営業事務職の従業員に検品業務への職種変更を命じた事例
裁判所の判断:
裁判所は職種変更命令を「合法」と判断しました。
裁判所の判断の理由:
営業事務職から検品業務への職種変更は「明らかに異質な業務への配転とまではいえない」と判断しました。
裁判例7:
東京サレジオ学園事件
(平成15年9月24日東京高等裁判所判決)
事案の概要:
児童福祉施設で児童指導員から厨房の調理員への職種変更を命じた事例
裁判所の判断:
裁判所は職種変更命令を「合法」と判断しました。
裁判所の判断の理由:
裁判所は以下の点から、児童指導員の業務と厨房の調理員の業務には共通性があることを指摘して、職種変更命令を合法と判断しました。
1,児童指導員の仕事は、日常の家事的業務も含まれていること。
2,本件学園では調理員も児童指導員と同様に児童の生活や処遇について関わりを持つことが求められていたこと。
このように、職種変更命令が合法とされているケースでは、「変更前の職種と変更後の職種に共通性があり、明らかに異質な業務への配転とはいえないこと」が判断の理由となっています。
以上、職種限定契約でない場合で、しかも就業規則でも「異動を拒めない」旨の規定があったとしても、異なる業務系統間での職種変更を命じる職種変更命令については違法とされる可能性が高いことをおさえておきましょう。
▼従業員の職種変更の対応について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
2,まとめ
今回は、従業員に職種変更を命じる際の注意点について以下の3点をご説明しました。
注意点1:
職種限定契約かどうかをまず確認する。
注意点2:
職種限定契約の場合は職種変更を命じることができない。
注意点3:
職種限定契約でない場合も職種変更には制限がある。
以下でそれぞれの要点を整理すると次の通りです。
注意点1:
職種限定契約かどうかをまず確認する。
「職種限定契約」かどうかで職種変更命令をできるかどうかが異なりますので、まずは職種限定契約かどうかの確認が必要です。
注意点2:
職種限定契約の場合は職種変更を命じることができない。
「職種限定契約」の場合は、仮に就業規則に「従業員は正当理由なくして異動は拒めない」などとあっても、企業は職種変更を一方的に命じることはできません。
注意点3:
職種限定契約でない場合も職種変更には制限がある。
職種限定契約でない場合も、業務の系統を異にする職種への異動については、企業は職種変更を一方的に命じることはできません。
以上の3点を、企業が従業員に職種変更を命じる際の注意点として、おさえておいてください。
また現在、実際に社内で職種変更が必要とされるケースで、今回の記事をご覧いただき不安が生じてきた場合は、できるだけ早い段階で労務相談に強い咲くやこの花法律事務所までご相談下さい。
3,従業員の職種変更の対応について「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせする方法
従業員の職種変更に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士のサポート内容 」のページをご覧下さい。
また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
4,従業員の職種変更についてのお役立ち情報も配信中!無料メルマガ登録
 06-6539-8587
06-6539-8587