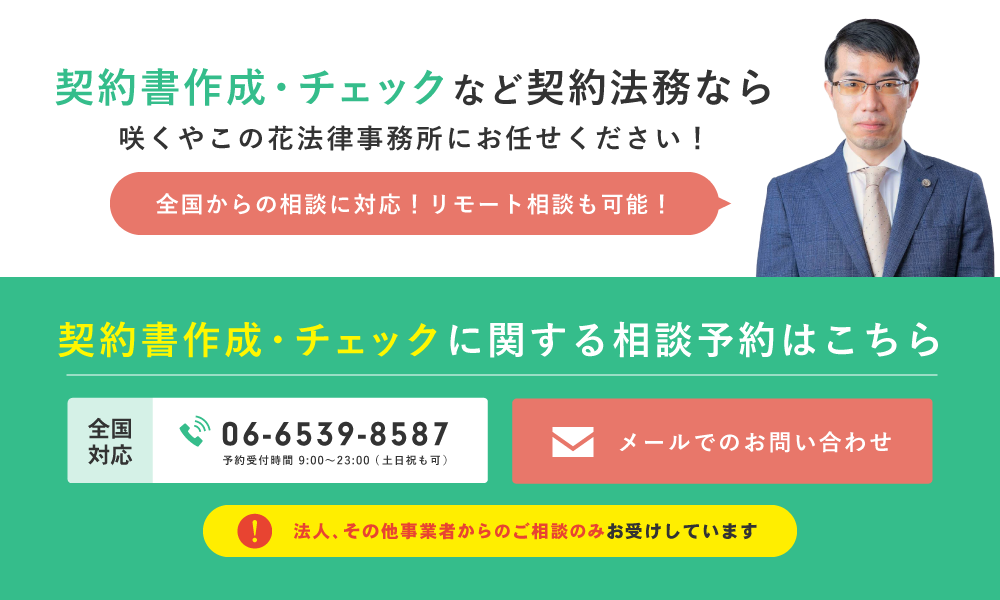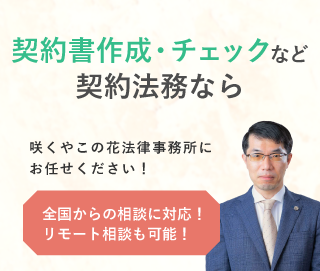こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
契約不適合責任についてわからないことがあり困っていませんか?
2020年4月の民法改正(債権法改正)で、これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが、「契約不適合責任」という名称に変更になりました。
契約不適合責任は様々な契約で問題になる責任であり、契約書の作成や契約書のリーガルチェックの際に必ずおさえておくべき重要ポイントの1つです。この記事では、その中でも基本となる売買契約と請負契約の2種類の契約について、民法改正後の契約不適合責任の内容や、契約書での対応が必要なポイントについてご説明します。
特に、契約不適合責任のルールのうち、従来の瑕疵担保責任のルールが一部変更されている点については、きちんと理解しておかないと、思わぬ損害、損失につながる危険があります。
この記事では、注意点をわかりやすくご説明します。
なお、咲くやこの花法律事務所の契約書に関する実績例を以下で掲載しておりますのであわせてご覧ください。
▶参考情報:契約書に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「契約不適合責任とは?契約書での注意点」について動画で詳しく解説しています。
民法改正(債権法改正)に伴い、企業は契約書のひな形や利用規約を2020年4月以降から民法改正にあった内容に変更しておくことが必要です。契約書を民法改正に対応しないまま放置すると思わぬ損害が生じることも懸念されます。咲くやこの花法律事務所でも契約書のひな形変更や利用規約の改定についてのご相談を承っていますので、早めにご相談ください。
▼契約不適合責任など契約書に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
また契約法務に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様こちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、売買契約で、商品に品質不良や品物違い、数量不足などの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。請負契約でも同様に、請け負った仕事の内容に不備があった場合に、請負人は発注者に対して契約不適合責任を負います。
契約不適合責任の内容は大きく分けて、① 修補や代替品納入の責任、② 買主側に損害が発生した場合の損害賠償責任、③ 売主側が修補等に応じない場合に買主側から代金減額を求められれば応じる責任、④ 売主側が修補等に応じない場合は契約解除の対象となるという4つがあります。
以下では名称の由来や実際に問題となる場面を紹介したうえで、責任の内容などについてより詳しくご説明していきたいと思います。
(1)名称の由来は?
改正民法の条文上、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に発生する責任であることから、「契約不適合責任」と呼ばれています。
この「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」の具体的な内容は以下の通りです。
●種類に関する契約不適合
=購入したものと違う種類の商品を間違って引き渡した場合
●品質に関する契約不適合
=商品が契約で予定されていた品質の基準を満たしていなかった場合
●数量に関する契約不適合:
=引き渡された数量が購入数量に足りなかった場合
(2)契約不適合責任が問題になる場面
契約不適合責任は以下のような場面で問題になります。
- 売買した商品に品質の不良があった場合
- 売買した土地あるいは建物に不具合があった場合
- 工事の契約で工事の内容に不備があった場合
- WEBサイトやシステムの制作の契約で、納品されたシステムに不備があった場合
2,契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
契約不適合責任は2020年3月までは瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、2020年4月の民法改正で、契約不適合責任と呼ばれるようになりました。
改正前の瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵」(=買主側が知らなかった瑕疵)があった場合の売主の責任という位置づけでしたが、改正により、「当事者の合意した契約の内容に適合しているか否か」が責任発生の基準とされ、「隠れた」の要件は外されました。
また、責任の内容の面では、売買契約についての瑕疵担保責任には、買主側から修補や代替品の引渡しを求める追完請求権の規定がありませんでしたが、契約不適合責任では追完請求権の規定がおかれました(民法第562条)。さらに、納品物の品質不良等の場面について、改正前の瑕疵担保責任では代金減額請求権の規定がありませんでしたが、契約不適合責任では代金減額請求権の規定がおかれました(民法第563条)。
そして、改正前の瑕疵担保責任においては、損害賠償や契約解除についてどのようなルールが適用されるのかが不明確でしたが、改正により、契約不適合があった場合の損害賠償責任や契約解除については、他の債務不履行(契約違反)の場合と同じルールが適用されることが明確にされました(民法第564条)。
これらの点を表にまとめると以下の通りです。
▶参考:改正前の瑕疵担保責任と改正後の契約不適合責任の比較表
| 瑕疵担保責任(改正前) | 契約不適合責任(改正後) | |
| 要件 | 「隠れた瑕疵」であることが必要だった | 「隠れた瑕疵」であることは不要 |
| 売買契約における追完請求 (修補や代替品の引渡の請求) |
規定なし | 規定が設けられた(民法第562条) |
| 納品物の品質不良等の場面での代金減額請求 | 規定なし (数量不足の場合の規定のみ) |
規定が設けられた(民法第563条) |
| 損害賠償責任や契約解除のルール | 判例の立場が不明確だった | 他の債務不履行(契約違反)の場合と同じルールが適用されることが明確にされた(民法第564条) |
なお、民法の条文については、「9,契約不適合責任についての条文」に掲載していますので参照してください。
3,民法改正後の契約不適合責任の内容について

以下では商品や不動産などの「売買契約」と、工事やシステム開発などの「請負契約」の場面にわけて、契約不適合責任の内容をご説明します。
(1)売買契約についての契約不適合責任
購入した商品や不動産に不具合があった場合、買主は契約不適合責任の内容として、売主に対し、以下の4つの請求が可能です。
| 改正民法に基づき請求できる内容 | |
| 追完請求 | 引き渡した商品の修理の請求(修補請求)、または不具合がない商品の引渡しの請求(代替品の引渡請求) |
| 損害賠償請求 | 損害が発生した場合は損害賠償請求が可能 |
| 代金減額請求 | 購入代金の減額の請求
※代金減額請求ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。 |
| 契約解除 | 契約を解除して代金の返還を請求することが可能
※契約解除ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。商品は返品することになります。 |
(2)請負契約についての契約不適合責任
建築工事の結果やシステム開発で完成したシステムに不具合があった場合、発注者は契約不適合責任の内容として、請負人に対し、以下の4つの請求が可能です。
| 改正民法に基づき請求できる内容 | |
| 追完請求 | 不具合部分の修理の請求 |
| 損害賠償請求 | 損害が発生した場合は損害賠償請求が可能 |
| 代金減額請求 | 請負代金の減額の請求が可能
※代金減額請求ができるのは、原則として修理を請求したが請負人が応じない場合に限られます。 |
| 契約解除 | 契約を解除して代金の返還を請求することが可能
※契約解除ができるのは、原則として修理を請求したが請負人が応じない場合に限られます。 |
請負契約の解除については以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。
4,契約不適合責任期間と時効について
契約不適合責任には、民法上、行使期限が設けられています。
この行使期限は、厳密には時効ではなく、除斥期間と呼ばれます。
具体的には以下の通りです。
(1)売買契約についての契約不適合責任の時効
買主は「不具合を知ったときから1年以内」に不具合の内容を売主に通知することが必要です(改正民法第566条)。ただし、会社間の売買等は、商法第526条2項が適用され、売主は買主に対し、商品引渡し後6か月以内に不具合の内容を通知することが必要です。
なお、上記の民法や商法の規定はあくまで契約書に行使期限の記載がない場合のルールを定めたものであり、契約書で行使期限をより短く設定することや長く設定することが可能です。
▶参考情報:商法第526条2項については以下の記事をご参照ください。
(2)請負契約についての契約不適合責任の時効
請負人は「不具合を知ったときから1年以内」に不具合の内容を発注者に通知することが必要です(改正民法第637条1項)。
ただし、この民法の規定も、契約書に行使期限の記載がない場合のルールを定めたものであり、契約書で行使期限をより短く設定することや長く設定することが可能です。
5,契約不適合責任と免責について
契約不適合責任について改正民法で定められた内容は前述の通りですが、この規定はいずれも「任意規定」であることに注意していただく必要があります。
任意規定とは、その項目について契約書に記載がない場合には法律の規定を適用するが、契約書に記載があるときは契約書の内容が法律よりも優先して適用される性質の規定をいいます。
そのため、契約書で契約不適合責任の免責を定めたり、期間を民法の規定よりも短く定めることは、民法改正後も可能です。ただし、契約不適合責任を免責したり、期間を短くすることが、民法以外の法律で禁止されている場合は、そのルールには従う必要があります。
(1)民法以外の法律で契約不適合責任の免責や制限が禁止されている例
例1:
BtoCの取引分野では、消費者契約法第8条1項により、事業者と消費者の契約について事業者の契約不適合責任を全部免責とする条項が無効と定められています。
例2:
不動産取引の分野では、宅建業法第40条により、宅建業者が売主となる宅地・建物の売買については契約不適合責任を免責する特約は無効とされています。
6,契約書での対応ポイント

では、民法改正に伴い、契約書のひな形についてはどのような変更が必要になるのでしょうか?
以下で契約書での対応ポイントをご説明していきたいと思います。
(1)民法改正により契約書の用語の変更が必要
まず、契約書で「瑕疵」あるいは「瑕疵担保責任」と記載していた部分は、民法改正に伴い、「契約不適合」あるいは「契約不適合責任」と変更することになります。
用語は変更になりますが、基本的な意味は、従来の「瑕疵担保責任」と同じと考えて問題ありません。
(2)売主側の場合は「買主が知っていた不備」についても責任を負うことに注意
内容面の変更点として、民法改正前は買主が購入時に知っていた不備については、売主は責任を負わない内容になっていました。
つまり、改正前の民法第570条では売主は、「隠れた瑕疵」について責任を負うとされ、買主が知っていた瑕疵については「隠れた瑕疵」にあたらないとされていました。
しかし、民法改正後は、買主が知っていた不備についても「契約不適合責任」の対象になり得る内容に変更されています。
そのため、特に中古品や不動産の売買で、一定の不備があることを買主も承知で売買するようなケースでは、売主として、買主が知っていた不備については責任を負わないことを契約書で明記することが必要になります。
(3)買主側の場合は「買主指定以外の方法による追完を認める規定」の新設に注意
今回の改正で、「売主は買主に不相当な負担にならない範囲で、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる」とされました(改正民法562条1項但書)。
「追完」とは、商品や工事に不備があった場合にそれをなおしたり、不備のない商品と交換することです。
上記の規定は、不備についての修理や代替品の納入について、売主が買主の指定した方法に従わなくても買主は許容しなければならないことを意味しており、買主にとって不利な規定です。
そのため、民法改正後に自社が買主側あるいは発注者側として契約書を作成するときは、この「民法562条1項但書」は適用しないことを契約書に明記しておくという対応が考えられます。
7,IT業界における契約不適合責任への対応
システム開発、Web開発、コンテンツ制作は請負契約あるいは準委任契約にあたるとされ、いずれも契約不適合責任の対象となります。
契約書の注意点として、以下の点をチェックしておきましょう。
(1)民法改正により契約書の用語の変更が必要
これまで契約書で「瑕疵」あるいは「瑕疵担保責任」と記載していた部分は、民法改正に伴い、「契約不適合」あるいは「契約不適合責任」と変更することになります。
用語は変更になりますが、基本的な意味は、従来の「瑕疵担保責任」と同じと考えて問題ありません。
(2)発注者側の場合は「発注者指定以外の方法による追完を認める規定」の新設に注意
自社が請け負ったシステム開発やWeb開発、コンテンツ制作などの一部を外注する場面では、自社が発注者側の立場にたつことになります。
今回の改正で、「売主は買主に不相当な負担にならない範囲で、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる」とされました(改正民法562条1項但書)。
システム開発やWeb開発、コンテンツ制作などの場面でいう「追完」とは、納品物に不備があった場合にそれをなおすことです。
この規定が、民法559条により、請負や準委任にも準用されています。
その結果、「システム開発やWeb開発、コンテンツ制作などを発注した場合に完成物に不備があったとしても、請負人は、必ずしも、発注者が指定する方法で不備をなおす義務を負わない。」ということになります。
つまり、外注先から納品される納品物に不備があっても、必ずしも、自社が指定する方法で修正してもらえないおそれがあります。
そこで、民法改正後に自社が発注者側として契約書を作成するときは、この「民法559条が準用する民法562条1項但書」は適用しないことを契約書に明記しておくという対応が考えられます。
以上、システム開発、Web開発、コンテンツ制作など制作型契約の契約書についての民法改正にともなう注意点をご説明しました。
なお、利用規約については、民法改正で新たに設けられた定型約款のルールとの関係を考慮して、変更が必要な点は変更しておくことが重要です。
利用規約の民法改正への対応のポイントは以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
8,いつから変更になるのか?
契約不適合責任を定めた民法改正は、2020年4月から適用されています。
早めに、契約書のひな形や利用規約を修正する準備を進めておきましょう。対応に不安がある場合は、「契約書に関する弁護士への相談サービス」までご相談ください。
9,契約不適合責任についての条文
最後に、契約不適合責任についての民法改正後の条文をご紹介しておきたいと思います。
(1)売買の契約不適合責任に関する条文
売買契約の契約不適合責任は民法第562条~第564条で以下の通り定められました。
▶参考情報:民法第562条(買主の追完請求権)・563条(買主の代金減額請求権)・564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)の条文
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
改正後の民法の全文は以下をご参照ください。
(2)請負の契約不適合責任に関する条文
請負契約の契約不適合責任は、売買契約の条文を準用する形で定められています。
▶民法第559条(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
この「売買以外の有償契約」に、請負契約も含まれます。
10,契約不適合責任と商法
民法の改正に合わせて、商法第526条2項、3項の規定も、「瑕疵」という用語から「契約の内容に適合しない」、「不適合」という用語に改められました。
改正後の商法の条文は以下の通りです。
(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条
1 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品 質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない 場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、 売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
商法については、用語の変更のみで内容面の変更はありません。
民法改正にともなう商法の一部改正の内容は、以下の「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」でご確認いただくことが可能です。
11,契約不適合責任に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、民法改正(債権法改正)に関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご説明したいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、民法改正に対応した契約書の作成を弁護士に依頼したいという企業様、あるいは契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼したいという企業様のために以下のサポートを行っております。
(1)弁護士による契約書の作成
契約不適合責任に関する契約書の作成のポイントはこの記事でご説明した通りですが、個別の事情を踏まえて盛り込んでおくべき内容は、取引の内容や場面によって当然異なります。
また、民法改正(債権法改正)に関連した契約書の修正点は、契約不適合責任の点のほか、連帯保証に関するルールの変更や契約解除に関するルールの変更など多岐にわたります。
ひながたを安易に利用して契約書を作成すると実際の取引内容に合致しない内容となり、あとでトラブルになることが多々あります。
咲くやこの花法律事務所では、契約書作成に精通した弁護士が企業のお客様の依頼を受けて契約書の作成を行っています。
契約書に関するご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
●契約書作成費用:5万円~10万円程度
(2)弁護士による契約書のリーガルチェック
民法改正(債権法改正)に対応する契約書を自社で作成した場合も弁護士によるリーガルチェックを受けておくことをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所では、契約書作成に精通した弁護士が、契約書を個別の事情を踏まえてリーガルチェックし、追記すべき契約条項や修正すべき点を明確にお伝えします。
契約書に関するご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
●契約書リーガルチェック費用:5万円程度~(顧問契約の場合は無料)
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2025年6月18日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」契約不適合責任に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587