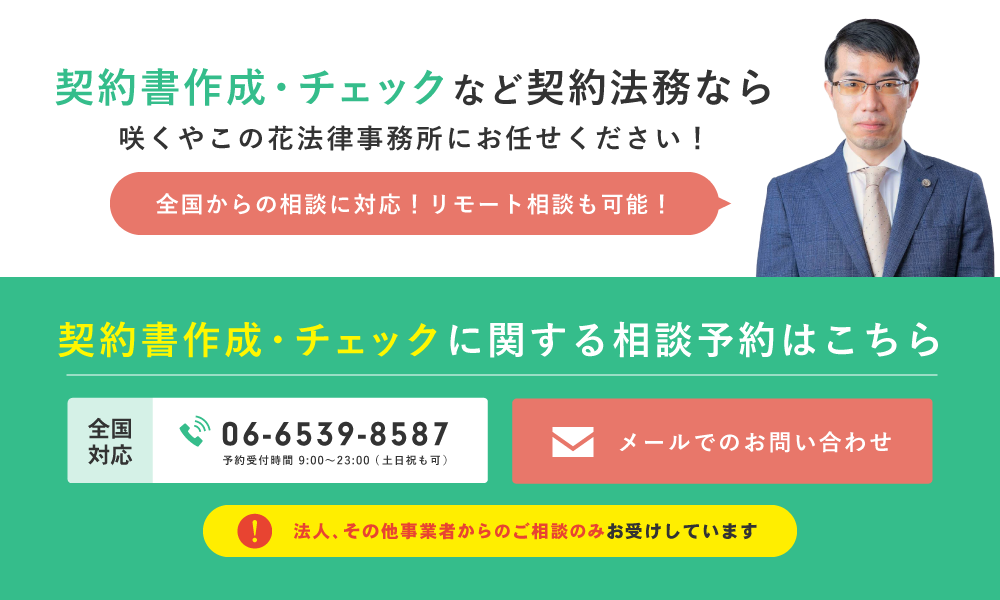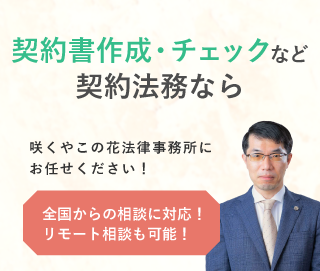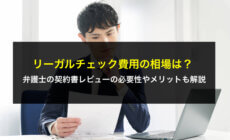こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。
契約書のリーガルチェックやレビューは正しくできていますか?
リーガルチェックの不備は、時によって、会社に重大な損害をもたらします。下記の事例は売買契約書の不備により大きな損害が発生した事例ですが、契約書について正しい知見を持つ弁護士のリーガルチェックを受けていれば、防ぐことができた事案でした。
また、下記の事例は、咲くやこの花法律事務所にリフォーム工事契約書のリーガルチェックの依頼があった事例です。
相談者は民法改正への対応をご希望でしたが、内容を拝見すると特定商取引法など他の重要法令への対応がされていませんでした。
そのままでは、クーリングオフの期間制限も適用されず、工事終了後もいつでも施主からのリフォーム代金の返金要求に応じなければならないという危険な状態であったため、一から契約書を作り直した事例です。
現在は、リーガルチェックを自動でできるとうたうAIツールも開発され、提供されています。
これらのAIツールを利用するときは、その機能として、例えば上記の2つの事例であげたような契約書の重大な問題点を適切に指摘できるのかを検証する必要があります。
また、リーガルチェックを外部専門家に依頼している場合も、リーガルチェックでの指摘がマンネリ化して形式的になっていたり、細部に関する些末な文言の修正の指摘にとどまっているケースでは、本当に指摘するべき重要な問題点が抜け落ちている可能性があります。
今回は、契約書のリーガルチェック(レビュー)の重要性や注意すべき9つのチェックポイント、具体的な進め方等についてご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在、リーガルチェックに関して検討中の法人様は、実際に自社にあった弁護士にリーガルチェックを依頼することができるようになります。
自社のリーガルチェックの体制を確認するためにも、最後までぜひ読んでみてください。
咲くやこの花法律事務所では、約600以上の企業との顧問契約があり、その中で、契約書のリーガルチェック(レビュー)にも対応してきた実績があります。
契約書関係の実績の一部を以下でも公開していますのであわせてご覧ください。
▶参考情報:契約書関係の実績紹介はこちら
また、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるリーガルチェックのサポート内容については、以下をご覧ください。
▶参考情報:契約書に関する弁護士への相談サービスはこちら
▶関連動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「契約書のリーガルチェック!9つのチェックポイント」の動画でも詳しく解説しています。
▼【関連情報】契約書のリーガルチェックに関連する参考情報は、以下もご覧下さい。
・契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】
▼契約書のリーガルチェックに関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,契約書のリーガルチェックとは?
契約書のリーガルチェックとは、取引先から提示された契約書について、法的な問題点がないかどうかや、自社に不利益な条項が含まれていないか、取引内容に合致しているかなどをチェックすることをいいます。「契約書のレビュー」と呼ぶこともあります。
上記の通り、契約書のリーガルチェックは取引先から提示された契約書のチェックをいうことが多いですが、自社で作成した契約書を弁護士や自社の法務部にチェックしてもらうことも含めて、契約書のリーガルチェックと呼ぶこともあります。
2,契約書のリーガルチェックの不備で起こる問題点
契約書のリーガルチェックを怠ったり、精度が低い形式的なチェックしかできていなかったりすると、以下のような問題が発生します。
(1)著しく不利な契約条項を見落として契約してしまう
取引相手から提示される契約書は、程度の差こそあれ、相手に有利な内容にできていることが通常です。
リーガルチェックを怠ると自社に著しく不利な契約をしてしまい、取引が進んだ後にそれに気づいて重大な不利益を受けたり、不利な立場に立たされたりする結果となります。
参考例1:
仕入先から提示された取引基本契約書について
商品に不具合があった場合の対応が、民法や商法の契約不適合責任に関する規定よりも自社に不利になっているにもかかわらず気づかずにそのまま契約してしまう。
その結果、商品を転売した客先で商品の不具合が見つかっても、仕入先にその対応を求めることができず、自社の負担で対応しなければならなくなる。
参考例2:
外注先から提示された業務委託契約書について
自社が外注したい業務内容が契約書に正しく記載されていないため、業務依頼時に追加料金を請求されてしまう。あるいは、業務委託契約の契約期間に関する条項に中途解約の規定がないため、中途解約する際に外注先から損害賠償を請求されてしまう。
参考例3:
派遣会社から提示された労働者派遣基本契約書について
派遣社員が金銭等の取り扱いをする場合の金銭等の紛失、盗難等について派遣会社は一切責任を負わない旨の条項が入っているのに気づかずにそのまま契約してしまう
参考例4:
制作会社から提示されたWebサイトや動画コンテンツの制作に関する契約書について
納品されたコンテンツの著作権が自社に移転されない内容になっているため、制作代金を払っているのに、コンテンツの使用や修正が自由にできなくなってしまう
(2)取引の内容に合わない契約書になってしまう
契約書を作成した取引先の契約書についての知識が乏しかったり、他で利用していたひな形を安易に流用して提示している場合には、実際の取引内容とあわない契約書になってしまっているケースがあります。
これではトラブル発生の際に契約書を基準に解決することができません。
また、実態にあわない契約書に記載されている契約条項から、自社としては思っていなかったような義務が発生し、それを果たせなければ契約違反として責任を問われることになる危険があります。
(3)契約違反の責任を問われる
安易にひな形を流用しているケースでは、実際は果たせないような義務規定が盛り込まれてしまっているケースもあります。
参考例1:
買主側から提示される取引基本契約書について
売主に対して、商品の提供を中止する場合は1年前に買主に通知することを義務付けたり、契約終了後も将来にわたって商品の補修部品の提供を継続することを売主に義務付ける条項が入っていることがあります。
こういった義務規定について、自社が果たせない内容である場合に、安易にそのまま契約すると、あとで、契約違反として損害賠償の請求その他のペナルティをうけることになりかねません。
(4)法律的に問題がある契約書になり制裁や不利益を受ける
契約書をレビューする際は、その契約書に関係する法律を網羅的にチェックする必要があります。
このチェックが不十分になると法律違反としての制裁を受けるケースもあります。
参考例1:リフォーム工事請負契約書
リフォームの契約は顧客の自宅で契約するケースも多いです。そのような場合は特定商取引法の訪問販売の規制の適用があり、契約書に記載するべき項目が法律で決められています。
記載事項が抜けている場合は、顧客側は、期間の限定なくいつでもクーリングオフして、工事代金の返金を求めることができることになってしまい、企業として重大な不利益を被る可能性があります。
▶参考情報:特定商取引法の訪問販売規制については、以下をご参照ください。
参考例2:製造委託契約書やシステム開発契約書、運送委託契約書等
発注者側の資本金が受注者側の資本金と比較して大きい場合は、取適法(旧下請法)の適用があります。
取適法(旧下請法)では、法律上、契約書(発注書面)に記載しなければならない項目が決められています。契約書に記載しなければならない項目が記載されていない場合は、行政による指導の対象となります。
▶参考情報:取適法(旧下請法)について詳しくは、下記の解説記事をご参照ください。
参考例3:エステや学習塾の契約書
一定の場合には、特定商取引法の特定継続的役務提供に関する規制が適用され、契約書に記載するべき項目が法律で決められています。
記載事項が抜けている場合は、サービスを受ける消費者側は、期間の限定なくいつでもクーリングオフして料金の返金を求めることができるため、企業として重大な不利益を被る可能性があります。
▶参考情報:特定商取引法の特定継続的役務提供に関する規制については、以下をご参照ください。
参考例4:
企業と消費者の契約書
消費者契約法で消費者に不利益を与える一定の契約条項が禁止されていることに注意する必要があります。
ゲーム開発大手の株式会社ディー・エヌ・エーが作成した「モバゲー」サービスの利用契約において「当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は一切損害を賠償しません」と定められていたことが消費者契約法に抵触するとされ、裁判所でこの契約条項の使用の差し止めが命じられた事例が報道されています(さいたま地方裁判所令和2年2月5日判決)
以上ご説明した通り、契約書のリーガルチェックに不備があると、「著しく不利な契約条項を見落として契約してしまう」、「取引の内容に合わない契約書になってしまう」、「自社が果たせない義務が盛り込まれた契約になってしまい、契約違反の責任を問われる」、「法律的に問題がある契約書になり制裁や不利益を受ける」などの問題が発生します。
3,契約書のリーガルチェックの9つのポイント

それでは契約書のリーガルチェックはどのような点に注意して行えばよいのでしょうか?
以下で重要なポイントをご説明したいと思います。
(1)まずは契約書をきっちり読みこむ
当然のことではありますが、まずは契約書をきっちり読んで、自社の意図にあわない点がないかどうか、自社が対応できないことが義務付けられていないかを確認することが必要です。
また、「契約不適合責任」とか「表明保証」とか「製造物責任」といった契約書特有の用語はその意味を正しく理解したうえで、そのまま契約するか、相手方に契約条項の修正を求めるかを検討する必要があります。
契約書に相手方特有の用語が使われていたり、相手方が契約書の作成に不慣れだったりすると、契約書を読んでも意味がわからないことがあります。
そのような場合は、相手方に記載の意味を確認したうえで、第三者が読んでも理解できる表現に修正したうえで契約する必要があります。
絶対にわからないまま署名、捺印しないことが重要です。
(2)自社に不当に不利な契約条項がないか確認する
自社に不当に不利な契約条項が含まれている場合は、取引先に対して、その修正を求める必要があります。
問題は、「不当に不利かどうか」をどのように判断するかという点です。これは基本的には民法や商法の規定と比較して不利益過ぎないかどうか、あるいは、業界の慣習やその業界で使用されている標準的な約款などと比較して不利益過ぎないかどうかという観点から判断していく必要があります。
参考例1:
自社が売主となる商品の売買契約を結ぶ場合
買主側が自由に返品できる内容になっている契約条項は通常は自社(売主)に不当に不利な契約条項であるといえます。
なぜなら、民法や商法の規定では商品に不具合があるなど特別な事情がない限り、買主による返品は認められないからです。
ただし、一部の業界では買主側からの自由な返品を認めることが業界の慣習になっていることがあり、そのような場合は、不当に不利な契約条項とはいえません。
このように、民法や商法の規定、業界の慣習などを考慮して、不当に不利かどうかを判断していく必要があります。
(3)契約書の内容が自社の目的に合致しているか確認する
契約書の内容が自社の事業目的や事業計画、契約をする目的に合致しているかどうかという観点からのリーガルチェックも必要です。
参考例1:
ユーザーから依頼を受けて開発するシステムについて、開発を下請先に外注する場合の下請先との契約のリーガルチェック
自社とユーザーとの契約で開発したシステムの著作権をユーザーに移転する内容になっている場合は、自社と下請との契約書において、下請が納品するシステムの著作権が自社に移転する内容にしておく必要があります。
下請との契約書で納品されたシステムの著作権が自社に移転することが書かれていなければ、下請からシステムが納品されてもその著作権をユーザーとの契約に従い、ユーザーに移転することができず、契約の目的を果たすことができません。
例えばシステム開発委託契約書といっても、自社で利用するためのシステムの開発を委託する契約なのか、それとも自社の顧客に納品するためのシステムの開発を委託する契約なのかによって、リーガルチェックのポイントが全く異なります。
決して、「システム開発委託契約書」という契約書のタイトルによって自動的にチェックポイントが導き出されるわけではありません。
そのため、契約書のレビューにあたっては、契約を行う目的や経緯を必ず確認する必要があります。
(4)関連する契約書がある場合はそれとの整合性を確認する
他に関連する契約書がある場合はそれとの整合性の確認が必要です。
参考例1:
他社が提供するクラウドサービスを自社が代理店として自社の顧客に販売する場合
クラウドサービスの利用規約で他社が定めている禁止事項や免責条項が、自社と顧客との間の契約書でも盛り込まれているかどうか、矛盾がないかどうかなどを確認する必要があります。
そのほかにも、例えば、基本契約書に基づいて個別契約書を作成するというパターンでは、基本契約書と個別契約書の整合性を確認する必要があります。
また、既に締結済みの契約書に関連して新しい契約書を作るというパターンの場合は、締結済みの契約書と、新しく作る契約書の整合性を確認する必要があります。
上記の例のように、契約書のリーガルチェックは、他に関連する契約書との整合性を確認しながら行う必要があり、契約書単体をレビューすればよいというものではありません。
(5)自社から要望するべき契約条項がないかを検証する
契約にあたって当然いれるべき条項が抜けている場合は、その点を指摘して、契約条項を追加してもらう必要があります。
参考例1:
契約の相手方が製造する商品を購入するための売買契約書のリーガルチェック
購入する商品が第三者の特許権や著作権その他の知的財産権を侵害しないものであることを、売主に保証させることが一般です。
また、例えば食品や化粧品の購入であれば、日本において適法に販売できる商品であり、かつ法令上必要なすべての表示が適切にされていることを売主に保証させることが一般的です。
このような契約条項が入っていない場合は、買主側から指摘して入れてもらう必要があります。
(6)トラブルを想定し対策を盛り込む
リーガルチェックにあたっては、「もし、その契約でトラブルになる場合、どんなトラブルがありそうか」という観点からも検討し、その対策を契約条項として盛り込むことが必要です。
参考例1:
売主側として自社が製造する製品の売買基本契約書を締結する場合
原材料輸入先での感染症流行により納期が遅れるというトラブルが想定される場合は、そのような納期遅れについて責任を負わない内容の契約条項を盛り込むことが必要です。
参考例2:
買主側として売主が製造する商品の売買基本契約書を締結する場合
大量の商品の中から一部の商品に不具合が見つかった場合に、全て買主側で検査を行うことは負担が大きいため、例えば、一定割合以上の不良品が見つかった場合は売主側の費用負担での検品を義務付ける契約条項を盛り込むことが必要です。
(7)相手の許認可を確認する
契約の相手方が許認可が必要な業種である場合は、その許認可が正しくとられているかどうかを確認することも必要です。
参考例1:
派遣会社と派遣契約書を締結する場合
派遣会社が労働者派遣法上必要な許可を取得しているかどうかを確認することが必要です。
このチェックを怠り、無許可の派遣会社から派遣を受けていた場合には、派遣を受けている側にも法律上のペナルティが科されます。
例えば、不注意で無許可の派遣会社と契約してしまい、その派遣社員から自社での直接の雇用を申し込まれた場合、原則としてそれに応じる義務があることが法律上定められていますので注意してください
その他、例えば、廃棄物処理業者との契約、人材紹介会社との契約、倉庫業者との契約などはいずれも相手方が事業に必要な許可を受けているかどうかを契約書レビューにあたって確認する必要があります。
(8)適用がある法令を網羅的に調査する
契約書のレビューにあたっては、その契約書に関係する法令を網羅的に調査する必要があります。
参考例1:
リフォーム工事請負契約書のリーガルチェック
まずは建設業法の規定に注意する必要がありますが、それだけではなく、以下のような法律もあわせて対応する必要があります。
- 顧客宅で契約することがある場合は、特定商取引法の訪問販売規制への対応が必要です。
- 顧客から分割払いで工事代金の支払いを受ける場合は、割賦販売法の自社割賦規制への対応が必要です。
- 請負契約に関する民法の規定にも注意する必要があります。
このように単に業界の法律だけをチェックすればよいわけではないことに注意してください。
適用される法令を見落としてしまうことは、ケースによっては致命的な問題につながります。
例えば、上記の事例で、特定商取引法への対応を怠ってしまうと、本来であれば契約後8日間の期間に限られる施主からのクーリングオフが、期間の制限なくいつでも行使できることになってしまいます。
クーリングオフされた場合、工事業者は工事後であっても工事代金全額を施主に返金する義務を負います。
(9)過去の判例との整合性について検討する
契約書の契約条項の解釈については、過去に多くの判例がありますので、それを踏まえたリーガルチェックを行うことも必要です。
参考例1:
顧客紹介契約や業務提携契約の入金リンク条項
代理店や業務提携先から、顧客の紹介を受け、紹介料を支払うような契約では、紹介された顧客が自社に対して取引の対価を支払ったことを、紹介者に対する紹介料支払いの条件とすることが通常です。
このように、第三者から支払を受けたことを条件として、相手方への支払をするという契約条項は「入金リンク条項」と呼ばれます。
このような入金リンク条項については、平成22年10月14日最高裁判所判決において、その効力について、限定的に解釈され、入金がなくても支払が義務付けられる場面があると解釈されています。
この場合、このような判例を踏まえたリーガルチェックを行わなければ、顧客から自社への代金の支払いがなくても、紹介者への紹介料の支払を義務付けられることになりかねず、注意が必要です。
参考例2:
従業員との雇用契約における競業避止義務条項
企業が従業員との間で退職後の競業避止義務を定める契約書を取り交わしたり、競業避止義務を定める誓約書を提出させることについては、従業員の職業選択の自由との関係で判例上一定の制限が課されています。
しかし、一方で、いかなる競業避止義務条項も無効とされているというわけではありませんので、過去の判例を分析して、どのような契約条項を設定するか慎重に検討する必要があります。
競業避止義務条項を定めるあたっての参考として、以下の記事もあわせてご参照ください。
4,リーガルチェックの依頼先はどこがよい?
以下ではリーガルチェックのポイントを踏まえて、リーガルチェックを誰に依頼して進めていくべきかについてご説明したいと思います。
(1)弁護士、司法書士、行政書士など誰に頼むべきか?
結論からいうと、リーガルチェックは多くの場合、弁護士に依頼することがベストです。
なぜなら前述したような「適用がある法令の網羅的な調査」や「過去の判例を踏まえたリーガルチェック」という部分については、網羅的に法令や判例を理解し、日々トレーニングを積んでいるのは、弁護士だからです。
また、リーガルチェックについては、取引から予想されるトラブルリスクを想定したうえで、そのトラブルの対策を契約条項としてあらかじめ入れておくという視点が不可欠です。
この「トラブルを想定する」という部分については、日ごろ、企業から、取引のトラブルについて相談を受け、場合によっては裁判で解決している弁護士が、どんなトラブルが起こりやすいか、どういった対策をしておけばよいかという点に最も精通しているからです。
契約書の効力などは最終的には裁判所で判断されます。
その意味でも、裁判所の考え方に日ごろから精通している弁護士に契約書のレビューを依頼することが適切です。
(2)AI(人工知能)を利用したリーガルチェックの注意点
現在は、リーガルチェックを自動でできるとうたうAIツールも開発され、提供されています。
▶参考情報:2020年5月現在提供されている代表的な自動リーガルチェックサービスの例
Googleで「AI リーガルチェック」などで検索していただければ、代表的な自動リーガルチェックサービスのWebサイトをご覧いただけますので参考にご覧下さい。
しかし、契約書のリーガルチェックは形式的な問題点を指摘するだけでは、重要な問題が抜け落ちてしまいます。
AIツールを利用してリーガルチェックを行う場合は、最低限、前述の9つのポイントにそのツールが対応しているのかをよく確認することが必要です。
1,法令について網羅的な調査をする機能があるか
例えばリフォーム工事の契約書であれば、建設業法など、契約書の名称から当然適用がある法令に基づくチェックはAIツールでもされていることが多いです。
しかし、特定商取引法や割賦販売法など、販売方法などに応じて適用があるかどうかがわかれるような法令についてのチェックまでするためには相当高度な機能が必要であると思われます。
しかし、このチェックは重要で必要不可欠のものです。
また、取適法(旧下請法)などの重要法令についてのチェックを行うためには、自社と契約相手の資本金の額がわからなければ、チェックできません。
このように、契約書のレビューにあたっては、少なくとも、販売方法や自社や相手方の資本金の額などを確認しなければ、特定商取引法や取適法(旧下請法)の適用の有無を判断できないため、これらの機能がAIツールにどのように実装されているかを確認する必要があります。
2,判例との整合性を検討する機能があるか
「過去の判例との整合性について検討する」という点については、AIツールが過去の膨大な判例に関する知識を学び、それを踏まえたリーガルチェックを行っているのかという点を確認する必要があります。
3,契約書の内容と自社の目的の合致を確認する機能があるか
さらに、「契約書の内容が自社の目的に合致しているか確認する」という点については、例えば商品を自社で使用するために購入する場合なのか、他社に納品するために購入する場合なのかで、当然、リーガルチェックのポイントが変わってきます。
こういった契約目的の把握という観点について、AIツールでどのように対応されているのかの確認が必要です。
4,他の契約書との整合性などを確認する機能があるか
加えて、他の契約書との整合性の確認、相手方の許認可についての確認や、「トラブルを想定し対策を盛り込む」といった点についても、AIツールでどのような担保がされているのかを確認する必要があるといえるでしょう。
契約書のリーガルチェックは、「自社が契約する目的」や「契約相手との力関係」、「事業内容に関するヒアリングを行ったうえでの適用法令の抽出」、「他の契約書との整合性の検討」、「相手方の許認可の確認」など多岐にわたる情報収集が必須であり、契約書の文言だけでリーガルチェックできるようなものではないことをおさえておく必要があります。
▶参考情報:AIツールによる契約書のリーガルチェックはその適法性についても検討が必要です。令和4年6月6日、法務省はグレーゾーン解消制度を利用した、AIによる契約書等審査サービスの提供の適法性についての事業主からの照会に対し、サービスは「弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があると考えられる。」と回答しています。筆者としては、日本のリーガルテックの進歩をとめないためには、こういったサービスを適法化する法改正が必要であると考えます。
AIによる契約書等審査サービスの提供の適法性についての法務省回答については以下の令和4年6月6日付回答をご参照ください。
5,弁護士にリーガルチェックを依頼する場合の費用の相場
次に弁護士に契約書レビューを依頼する場合の費用について見ていきたいと思います。
なお、費用は、弁護士によって大きく異なることが実情ですので、以下では、筆者が把握している相場を説明させていただくことをご了解ください。
(1)リーガルチェックは顧問契約で対応することが通常
リーガルチェックは企業を続ける限り継続的に発生するニーズであるため、顧問弁護士サービスの中での対応となることが一般的です。
顧問契約でリーガルチェックのサービスを受ける場合、筆者が感じるだいたいの弁護士費用の相場としては、以下のようなイメージです。
ただし、東京の法律事務所は顧問契約が5万円以上からの設定になっているケースが多く、下記よりも割高なところが多いようです。
- 平均して月1~2件程度のリーガルチェック:月額3万円程度
- 平均して週に1件程度のリーガルチェック:月額5万円程度
- 平均して月に5件~10件程度のリーガルチェック:月額10万円程度
- 平均して月20件程度のリーガルチェック:月額15万円~20万円程度
(2)スポットで依頼する場合のリーガルチェックの料金について
顧問契約をしないでスポットでリーガルチェックを依頼したいという場合の費用は、契約書1通につき10万円程度になることが多いようです。
ただし、スポットでの依頼を受けていない法律事務所もあるので、法律事務所に確認が必要です。
なお、スポットで契約書のリーガルチェックを依頼する場合、会社の事業の内容や、契約をする意図や目的、契約に関して会社として感じているリスク要因、契約相手との関係性などについて、弁護士が依頼企業からヒアリングすることが必須になります。
また、取適法(旧下請法)の適用があるかどうかを判断するために資本金の額を確認したり、特定商取引法の適用があるかどうかを判断するために販売の方法や営業の方法を確認したりすることも必要になります。
これらの点は顧問契約をして継続的に相談を受けている顧問先であれば、普段の相談内容から弁護士も把握していることが多い点ですが、スポットでの依頼の場合は、一からヒアリングをしなければ適切なリーガルチェックができません。
スポットでのリーガルチェックが顧問契約を利用したリーガルチェックよりも割高になるのはリーガルチェックの前提となるヒアリングに時間を要することが原因の1つです。
▶参考情報:リーガルチェック費用の相場については、以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
6,契約書に強い弁護士にリーガルチェックの相談をしたい方はこちら

筆者が所属する咲くやこの花法律事務所でも、企業からの依頼を受けて多くの契約書レビュー、リーガルチェックを日々行っています。
以下では、咲くやこの花法律事務所の契約書のリーガルチェックサービスについてご紹介致します。
▶参考動画:咲くやこの花法律事務所によるリーガルチェックなど契約書に関する弁護士のサポート内容については以下もご参照ください。
咲くやこの花法律事務所では、企業の契約書レビュー、リーガルチェックに精通した弁護士がそろっており、また、顧問先企業約600社以上から日々契約書のリーガルチェック、レビューの依頼を受けてきた実績があります。
法律や判例だけでなく、ビジネスの内容や狙い、相手方との力関係なども理解したうえで、実情に即した適切なリーガルチェックを行います。
(1)咲くやこの花法律事務所のリーガルチェック費用例
リーガルチェックの費用は、その契約書の内容や分量などにもよりますが、おおむね以下を目安とさせていただいています。
1,顧問契約した場合の目安費用
| リーガルチェックの依頼頻度 | 顧問契約のプラン | 料金 |
| 月1~2件程度 | ミニマムプラン | 月額3万円 |
| 週1件程度 | スタンダードプラン | 月額5万円 |
| 月5~10件程度 | しっかりサポートプラン | 月額10万円 |
| 月20件程度 | オーダーメイドプラン | 月額15万円~20万円 |
2,スポット依頼した場合の目安費用
| スポットでの依頼 | 内容や分量により1通につき5~10万円程度 |
なお、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスにおけるリーガルチェックのサポート内容については、以下をご参照ください。
ビジネスの実情を理解できる力のある弁護士が、迅速に適切なリーガルチェックを行いますので、気軽に咲くやこの花法律事務所までお問い合わせください。
(2)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所の契約書のリーガルチェックに関するお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
7,契約書のリーガルチェックに役立つ参考ひな形集
契約書のレビューにあたって、該当する契約書のひな形を参照することは、必要な契約条項に抜け落ちがないかなどのチェックに役立ちます。
参考になるひな形を以下にアップしていますで、ご参照ください。
(1)主な契約書のひな形一覧
- 秘密保持契約書のひな形(ダウンロード)
- 業務委託契約書のひな形(ダウンロード)
- コンサルティング契約書のひな形(ダウンロード)
- 正社員の雇用契約書のひな形 (ダウンロード)
- 契約社員の雇用契約書のひな形(ダウンロード)
- パート社員の雇用契約書のひな形(ダウンロード)
- 嘱託社員の雇用契約書のひな形(ダウンロード)
- 労働者派遣契約書のひな形(ダウンロード)
9,【関連情報】ジャンル別の契約書の注意点に関する参考情報
「咲くや企業法務.net」では、ジャンルごとの契約書の注意点についても解説しています。
ジャンルごとの解説記事は以下をご参照いただきますようにお願いいたします。
(1)売買・請負関連の契約書の注意点
(2)IT・知財関連の契約書の注意点
(3)労務関連の契約書の注意点
(4)アライアンスやM&A関連の契約書の注意点
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2026年1月16日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」リーガルチェックに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587