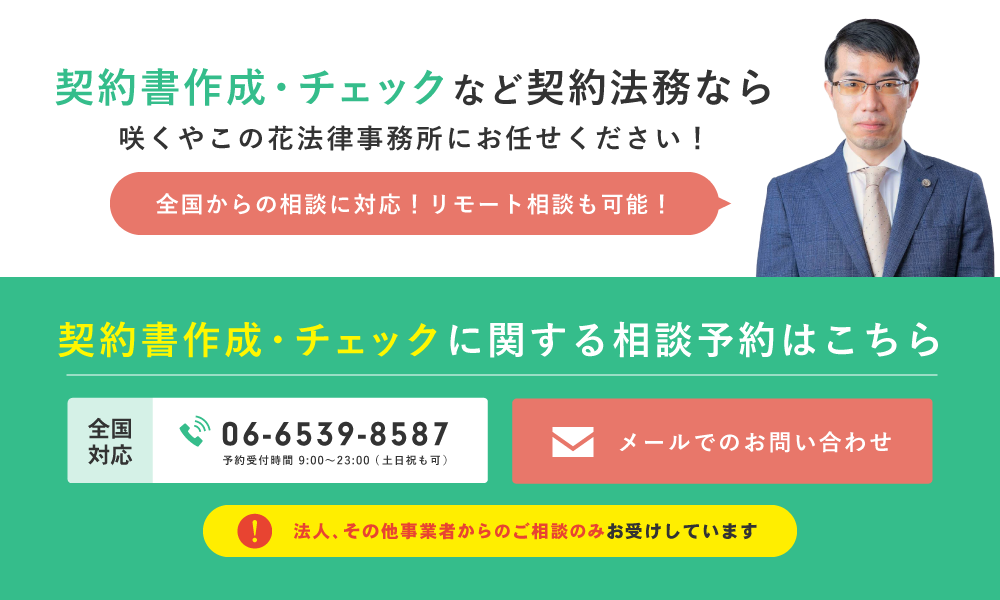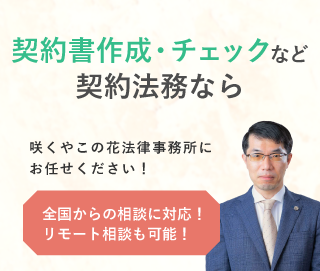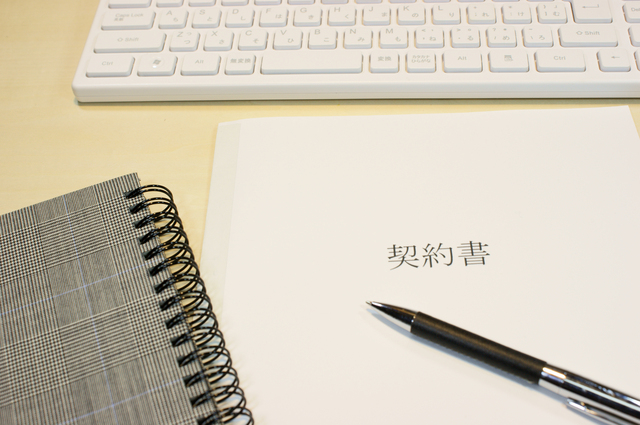
最近のWeb制作(ホームページ制作)会社からのご相談の中で最も多いのが、「Webサイト(ホームページ)制作費の未払いトラブル」です。
Web制作(ホームページ制作)会社がクライアントから発注を受けてWebサイトを制作した後、クライアントが制作費用を支払わずに訴訟になるケースが増えています。
最近の裁判例の中には、以下のようなものがあります。
(1)東京地方裁判所平成23年8月17日判決
工務店からWebサイト制作を請け負ったが、工務店が制作の途中で一方的に制作の中止を要求し、制作費用を支払わなかったケース。
(2)東京地方裁判所平成23年6月3日判決
クリニックからWebサイト制作を請け負ったが、発注者が医師であることから信頼して契約書を作成しなかったため、制作費用が支払われなかったケース。
(3)東京地方裁判所平成22年4月8日判決
マーケティング会社からWebサイト制作を請け負ったが、当初の仕様になかったSSLの導入やリンクバナーの作成について不備を指摘されて、制作費用が支払われなかったケース。
これらの裁判例の他にも、「仕様にない作業を求められたので追加費用をお願いしたら、クライアントが納得せず、制作費を支払わない」など、さまざまな理由でWebサイト(ホームページ)の制作費未払いトラブルが発生しています。
こういったWebサイト(ホームページ)制作費の未払いトラブルが発生した場合、裁判を起こすのにも費用がかかるため、制作費をもらえないまま泣き寝入りになっているケースも多いようです。
そこで、今回はWebサイト(ホームページ)制作費の未払いトラブルをなくすために、Web制作会社が制作にあたりどのような契約書を作成しておくのがよいかについて、「Web制作(ホームページ制作)のための契約書作成の重要ポイント」をご説明したいと思います。
▼【関連情報】Web制作の請負契約書に関連する情報として、以下も参考にご確認ください。
・契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】
▼Web制作の請負契約書に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
また契約書関連に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,Webサイト(ホームページ)制作の契約書を正しく作成しないと「こんなリスクがあります」
- 2,Web制作(ホームページ制作)契約書の7つの重要ポイント
- 3,ポイント1: 「仕様」に関する契約条項の作成のポイント
- 4,ポイント2: 「対応ブラウザ」に関する契約条項の作成のポイント
- 5,ポイント3: 「検収」に関する契約条項の作成のポイント
- 6,ポイント4: 「支払時期」に関する契約条項の作成のポイント
- 7,ポイント5: 「著作権」に関する契約条項の作成のポイント
- 8,ポイント6: 「遅延損害金」に関する契約条項の作成のポイント
- 9,ポイント7: 「クライアントの都合による解約」に関する契約条項の作成のポイント
- 10,Webサイト(ホームページ)制作の契約書に関して弁護士へ相談されたい方はこちら
- 11,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
- 12,Webサイト(ホームページ)制作会社に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
- 13,まとめ
- 14,【関連情報】Webサイト(ホームページ)制作の契約書に関するお役立ち記事一覧
1,Webサイト(ホームページ)制作の契約書を正しく作成しないと「こんなリスクがあります」
契約書については様々な雛形(ひな形)が出回っているところです。
雛形(ひな形)は有用ですが、あくまで参考であり、最終的には事案にあった適切なものをオリジナルで作る必要があります。
きちんと作成しないと以下のようなリスクがあるためです。
(1)契約書の雛形(ひな形)をそのまま使うことのリスク
リスク1:
どこまで仕事をすれば制作代金の支払いを受けることができるのかが不明確になり、クライアントの要望に応じて、何度もやり直しをさせられるリスク
リスク2:
クライアントの都合で契約を解約した場合の扱いが不明確になり、途中で一方的にキャンセルされ、制作代金を支払ってもらえなくなるリスク
リスク3:
クライアントから「思っていたのと違う」などと言われ、制作代金を支払ってもらえなくなるリスク
このようなリスクがありますので、契約書はきちんとオリジナルのものを用意する必要があります。
Webサイト制作費の未払いトラブルなどを防ぐためには、以下の「7つの重要ポイントをおさえてWebサイト(ホームページ)制作の契約書を作ること」が必要です。
2,Web制作(ホームページ制作)契約書の7つの重要ポイント
最初に、「Web制作(ホームページ制作)契約書の7つの重要ポイント」を以下で確認しておきましょう。
ポイント1:
「仕様」に関する契約条項の作成のポイント
ポイント2:
「対応ブラウザ」に関する契約条項の作成のポイント
ポイント3:
「検収」に関する契約条項の作成のポイント
ポイント4:
「支払時期」に関する契約条項の作成のポイント
ポイント5:
「著作権」に関する契約条項の作成のポイント
ポイント6:
「遅延損害金」に関する契約条項の作成のポイント
ポイント7:
「クラアイントの都合による解約」に関する契約条項の作成のポイント
以下、順番にご説明しますので、ぜひ、御社の契約書のひながたと照らし合わせてチェックしてみてください。
3,ポイント1:
「仕様」に関する契約条項の作成のポイント
Webサイト制作(ホームページ制作)の未払いトラブルなどを避けるための契約書の最初のポイントとして、「仕様」に関する契約条項の作成のポイントについてご説明します。
ここでのポイントは、契約書で、制作するWebサイト(ホームページ)の「仕様」をあらかじめ決めておくことです。
「仕様」は、どのようなWebサイトを制作すれば、制作代金の支払いを受けることができるのかの基準となるものです。
「仕様」を契約書に記載していなければ、クライアントと打ち合わせしてFIXした内容で制作を完了しても、クライアントから、「●●●●の機能も当然ついていると思っていたが実装されていない」と言われた際に、反論の方法がありません。
クライアントの機嫌をそこねて制作代金をもらえなくなっても困るので、結局、追加の機能をサービスで構築することにもなりかねず、そうするとWebサイトの制作代金をいただくのが、ずるずると先延ばしになってしまいます。
これに対し、「仕様」を契約書に記載していれば、Webサイト制作完了後にクライアントから、「●●●●の機能も当然ついていると思っていたが実装されていない」と言われても、「契約書に記載している仕様では、そのような機能は予定されていません。
言われているような機能を実装するためには追加で費用をいただかなければなりません。当初のWeb制作代金をまずご入金いただいた後で対応いたします。」と代金の支払いを求めることができます。
このように、「仕様」を契約書で決めておくことは、Webサイト制作費の未払いトラブルを防ぐための非常に重要なポイントです。
では、実際にどのようにして、契約書に「仕様」を記載すればよいでしょうか?
結論から言うと、契約書には、以下のような条項を設けて、「仕様」については別紙として添付することをお勧めします。
▶参考情報:「仕様」に関する契約条項の例
第●条
甲は乙に対して、以下の内容でWebサイトの制作を発注し、乙はこれを請け負った。
仕様:別紙のとおり
制作代金:●●●万円(税別)
納期:平成●●年●●月●●日
※ここでは、「甲」がクライアントで、「乙」が制作会社です。
このような契約条項を設けたうえで、別紙にできる限り詳細かつ具体的に「仕様」を定めるのがベストです。
ただ、実際問題として、「仕様」の作成に労力を割いていられないというケースもあると思います。そのような場合は、別紙の「仕様」として、最低限、「Webサイトに搭載される機能の一覧」と、「Webサイトのワイヤーフレーム」をつけておきましょう。
このように「仕様」を「別紙」にすることで、打ち合わせの際に作成した資料をそのまま契約書に添付することもできますので覚えておきましょう。
4,ポイント2:
「対応ブラウザ」に関する契約条項の作成のポイント
Webサイト制作(ホームページ制作)の未払いトラブルなどを避けるための契約書の2つ目のポイントとして、「対応ブラウザ」に関する契約条項を設けておくことをお勧めします。
ここでのポイントは、「制作するWebサイト(ホームページ)がどのブラウザで適切に表示されれば完成とするか」をあらかじめ契約書で決めておくことです。
Webサイトの制作でよくあるのが、「ブラウザによって表示が崩れるトラブル」です。
世の中にあるブラウザのすべてで適切に表示できるWebサイトを作ることは実際問題として困難です。ところが、クライアントは、「ブラウザによって表示が崩れる」、などということは知らないかもしれません。
そのため、ブラウザによって表示が崩れるトラブルが発生すると、クライアントは、「きちんと表示ができることを確認できるまで、代金の支払いはできません」と主張して、Webサイト制作費の未払いトラブルの原因になります。
そこで、あらかじめ、以下のような点をクライアントに伝えておくことが必要です。
(1)対応ブラウザに関してクライアントに伝えておくべき重要ポイント
- 1,すべてのブラウザで綺麗に表示できるWebサイト(ホームページ)を制作することは現実的に困難であること。
- 2,契約書で取り決めた、「シェアの大きい主要ブラウザ」において、適切に表示されるようにWebサイト(ホームページ)を制作すること。
- 3,「シェアの大きい主要ブラウザ」に対応しておけば、Webサイト(ホームページ)訪問者のほとんどが適切にWebサイト(ホームページ)を閲覧できること。
- 4,契約書で取り決めたブラウザ以外の「特殊なブラウザ」については、別途追加の費用をいただいて対応できること。
その上で、「どのブラウザで適切に表示されれば、そのWebサイトが完成扱いになるのか」を契約書に記載しておきましょう。
たとえば、以下のような条項を作るのが効果的です。
▶参考情報:「対応ブラウザ」に関する契約条項例
第●条
乙は本件ウェブサイトを下記のブラウザにおいて正常に閲覧できるように制作する。
このような条項を入れたうえで、対応できるブラウザを列挙しておきましょう。
このようにしておけば、特殊なブラウザで表示が崩れたとしても代金を支払ってもらい、あとは別途費用での対応とすることができます。
5,ポイント3:
「検収」に関する契約条項の作成のポイント
Webサイト制作(ホームページ制作)の未払いトラブルなどを避けるための契約書の3つ目のポイントとして、「検収」に関する条項の作成のポイントをご説明します。
「検収」とは、Webサイト(ホームページ)を制作した後、それをクライアントに確認してもらう過程を言います。
Webサイト制作費の未払いトラブルを防ぐためには、クライアントが「検収」を引き延ばして代金がもらえないということのないように、「検収」に関するルールを契約条項として定めておくことが必要です。
「検収」の過程で起こるWeb制作費未払いトラブルは、たとえば以下のようなものです。
(1)検収の過程で起こるWeb制作費未払いトラブルの例
- 1,クライアントにWebサイトの検収(確認)をお願いしたけれども、忙しいなど理由をつけて、いつまでも返事をもらえない。
- 2,クライアントにWebサイトの検収(確認)をお願いしたところ、当初の仕様で予定していない機能の追加を言われて、やり直しをさせられる。
上記のような事態が起こると、いつまでたっても検収に合格しないことになり、Web制作費未払いトラブルの原因になります。そこで、「検収」に関する規定を作成する際は、以下3つの点がポイントになります。
(2)「検収」に関する規定を作成する際の3つのポイント
- 1,クライアントの都合で検収の期間が延びないように、「検収の期間」を明記しておくこと。
- 2,クライアントの感覚でやり直しをさせられないように、「検収の基準」を明記しておくこと。
- 3,クライアントから連絡がないまま放置されないように、「クライアントから連絡がなかった時は、検収合格と扱うこと」を明記しておくこと。
具体的には以下のような条項を契約書に設けるのがよいでしょう。
▶参考情報:「検収」に関する契約条項の例
第●条
1,乙は本ウェブサイトの制作を完了したときは、甲にその旨を通知し、甲の検収を受けるものとする。
2,甲は前項による通知の後14日以内に検収を行い、その結果を乙に通知する。
3,検収は、成果物が第●条に定めた仕様に合致するか否かを基準に行う。
4,甲が検収の結果、成果物を不合格と判断した場合は、第2項の検収期間内に書面で不合格とする具体的な理由を乙に通知するものとする。
5, 第2項の検収期間が経過しても、前項の通知がないときは、成果物は検査に合格したものとみなす。
この契約条項の例では、「2項」で検収の期間を14日と明記することで、検収の期間がクライアントの都合で延びることを防いでいます。
そして、「3項」で、検収の基準が契約書に定めた「仕様」であることを明記し、クライアントから仕様にない機能の追加を言われてやり直しをさせられることを防いでいます。
そして、「5項」で、14日以内に不合格通知がないときは合格とみなすことを明記しています。
このようにしておくことで、検収が予定外に長引いたり、不合理な理由で検収不合格とされることを防ぐことができます。
通常のWebサイト(ホームページ)の制作契約書は、Web制作会社がWebサイト(ホームページ)を完成させた後、クライアントが「検収」を行い、「検収」に合格すればWebサイトの制作代金が支払われるという流れになっています。そのため、「検収」はWebサイト(ホームページ)の制作代金が支払われるための条件であり、検収に合格しなければ制作代金はもらえません。
そこで、「検収」についてのルールをきっちり契約書で決めておくことが、Web制作費未払いトラブルを避けるため大切なポイントになりますので、注意しておきましょう。
6,ポイント4:
「支払時期」に関する契約条項の作成のポイント
Webサイト制作(ホームページ制作)の未払いトラブルなどを避けるための契約書の4つ目のポイントとして、「支払時期」に関する条項の作成のポイントをご説明します。
Web制作会社にとって、「Webサイト制作費がいつ支払われるか」は、大変重要なことです。
ところが、Webサイト(ホームページ)の制作契約書を見ると、意外にWeb制作費の「支払時期」に関する契約書の記載が抜けていることがあります。
この「支払時期」に関する契約条項は必ず入れておきましょう。
では、「支払時期」をどのように決めればよいでしょうか?
(1)Webサイト制作費未払いトラブルを避けるための「支払時期」について
Webサイト制作費の未払いトラブルをできる限り回避するためには、Web制作代金のうち一部だけでも、制作開始前あるいは制作開始後の早い段階で入金してもらうことが理想的です。
もちろん他社との競争もありますので、なんでもWeb制作会社の要望通りというわけにはいきませんが、特に、取引実績がない新規の顧客からWebサイト(ホームページ)制作を依頼された時は、制作代金の半分を前金として制作開始前あるいは制作開始後1か月以内に入金してもらうことを社内でルール化しておくことをお勧めします。
取引実績がないのに、「制作代金は全額後払いにしてほしい」と言ってくるようなクライアントは、Webサイト(ホームページ)が完成しても本当にWeb制作代金を支払うかどうか疑わしく、取引自体を避けるべきです。
この点をおさえるためには、Web制作代金の支払時期に関する契約条項例は以下のようになります。
▶参考:Webサイト制作代金の支払時期に関する契約条項例
第●条
甲は乙に対し、以下の通り制作代金の支払をする。
1,平成●年●月●日限り金●●●万円
2,検収完了後30日以内に金●●●万円
「1」の「平成●年●月●」には前金入金の期限を具体的にいれておきましょう。
この前金の入金期限が遅いと、先に代金の一部をもらう意味がなくなってしまいますので、Webサイト制作開始後1か月以内の日を期限に設定しておくことをお勧めします。
Webサイト(ホームページ)の制作の途中で、クライアントが制作に不満をもらすようになったり、あるいはクライアントと連絡がとりにくくなったりして、Web制作を完了してもWebサイト(ホームページ)の制作代金が支払われるか不安な状況になることがあります。
このような状況になった時にも、Webサイト制作開始後、早い段階で「前金」を入金してもらうことを定めておけば、前金の入金がない場合は、いったんWebサイト(ホームページ)の制作をストップし、入金があるまで待つことができます。
ところが、契約書で前金をもらうことを定めていない場合は、Web制作代金が支払われるかどうか不安を抱えながらも、Webサイト(ホームページ)を完成させるほかなくなってしまいます。
このように、前金をもらうことと、その入金期限をきっちり契約条項として記載しておくことは、Web制作費未払いトラブルを避けるための大切なポイントですので覚えておきましょう。
7,ポイント5:
「著作権」に関する契約条項の作成のポイント
Webサイト制作(ホームページ制作)の未払いトラブルなどを避けるための契約書の5つ目のポイントとして、「著作権」に関する条項の作成のポイントをご説明します。
Webサイト制作費の未払いトラブルを避けるために、「著作権」に関して重要なポイントは、「Web制作費がすべて支払われるまで著作権がクライアントに移転しないようにしておく」、という点です。
たとえば、「著作権」に関する条項が、「成果物の著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)は、甲に帰属する。」などとなっている契約書もあります。
このように書かれていると、代金が支払われるかどうかにかかわらず、Webサイト(ホームページ)の著作権はクライアントのものとなります。
その結果、代金を支払わないままクライアントがWebサイト(ホームページ)を利用し続けるということができてしまいます。
Webサイト制作費を確実に回収するためには、Webサイト制作費をすべて支払った段階ではじめて著作権がクライアントに移転するようにしておくことがポイントとなります。
「著作権」に関する契約条項例は以下のようになります。
▶参考情報:「著作権」に関する契約条項例
第●条
成果物の著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)は、 制作代金を甲が乙に対して全額支払ったときに、乙から甲に移転する。
自社のひな形の「著作権」に関する契約条項がどのようになっているか、ぜひ確認してみてください。意外におさえられていない内容ですので、注意しておきましょう。
また、Webサイト(ホームページ)の制作に関わる著作権に関して不安がある場合は、著作権に強い弁護士に必ず相談するようにしましょう。
8,ポイント6:
「遅延損害金」に関する契約条項の作成のポイント
Webサイト制作(ホームページ制作)の未払いトラブルなどを避けるための契約書の6つ目のポイントとして、「遅延損害金」に関する条項の作成のポイントをご説明します。
▶参考:「遅延損害金」とは?
「遅延損害金」というのは、クライアントからの支払いが本来の支払期限から遅れた場合に、制作会社が請求できる賠償金のことです。
ここでは、以下の2点がポイントになります。
(1)「遅延損害金」に関する契約条項の2つのポイント
- 1,クライアントから支払いが遅れた場合に、制作会社がクライアントに対して遅延損害金を請求できることを明記すること。
- 2,遅延損害金の利率を定めておくこと。
遅延損害金は、契約書に「遅延損害金」に関する契約条項がなくても請求することができますが、契約書に遅延損害金の利率が記載されていない場合、遅延損害金の利率は、法律で「年6パーセント」と決まっています。
▶参考:「遅延損害金」のケース例
たとえば、300万円のWeb制作代金の案件について、クライアントが不合理に支払いを拒んだ結果の裁判となった場合を想定してみましょう。
裁判の決着がつくまで1年かかり、本来の支払い期限より「1年」遅れて支払われた場合、「年6パーセント」の遅延損害金であれば、遅延損害金は「18万円」です。これでは、額が小さすぎて、クライアントに対するペナルティ的な意味合いを果たしません。
そこで、「遅延損害金」に関する契約条項を設けて、遅延損害金の利率を定めておくことをお勧めします。
「ポイントは何パーセントにするか」です。
事業者間の契約において遅延損害金の利率について特に法律上の上限規定はありませんが、「利息制限法」の上限にあわせて「21.9%」としておくことをお勧めします。
▶参考:「遅延損害金」に関する契約条項例
第●条
甲が乙に対するウェブ制作代金の支払いを遅延した時は、甲は乙に対して支払い期限の翌日から支払日まで年21.9%の遅延損害金を支払わなければならない。
このような条項を設けておくと、前述の「300万円」のWebサイト制作代金の参考ケース例では、入金が「1年」遅れれば、「65万7000円」の遅延損害金を請求できることになります。
遅延損害金の条項を設けておくことで、クライアントに早く支払いを済ませなければ遅延損害金が増えていくことを意識させることができ、支払いを早く済ませようという動機づけをすることができますので、活用してみてください。
9,ポイント7:
「クライアントの都合による解約」に関する契約条項の作成のポイント
最後に「クライアントの都合による解約」に関する条項の作成のポイントをご説明します。
クライアントから発注を受けてWebサイト(ホームページ)の制作を開始したのに、途中でクライアントの都合で解約されてしまうということがあります。
このような場合でも、Webサイト(ホームページ)の制作代金の支払いをしてもらえるようにしておくためには、クライアントの都合による解約の場合の支払いを契約書に記載しておくことが必要です。
たとえば、次のような契約条項を契約書にいれておきましょう。
▶参考:「クライアントの都合による解約」に関する契約条項例
第●条
甲がウェブサイト完成前に本契約を解約し、または甲の都合によりウェブサイトの制作を中断するときは、乙に対し、解約または中断の時点におけるウェブ制作の進捗に応じたウェブ制作代金を支払わなければならない。また、解約により乙に発生した損害を賠償しなければならない。
このような条項を入れておけば、クライアント都合での解約時に支払いを求める根拠とすることができます。
10,Webサイト(ホームページ)制作の契約書に関して弁護士へ相談されたい方はこちら

最後に、Webサイト(ホームページ)制作の契約書の作成について、「咲くやこの花法律事務所」にご相談いただいた場合のサポート内容についてご説明しておきたいと思います。
サポート内容は以下の2点です。
- (1)弁護士による具体的な事情を踏まえた実効的な「契約書の作成」
- (2)自社または相手方が作成した契約書についての弁護士による「リーガルチェック」
以下で順番に見ていきましょう。
(1)弁護士による具体的な事情を踏まえた実効的な「契約書の作成」
この記事では、Webサイト制作費の未払いトラブルを防ぐための「Webサイト制作(ホームページ制作)請負の契約書の契約条項の作成ポイント」について一般的な内容を説明しましたが、実際の契約書作成にあたっては、契約内容ごとの個別的な事情を踏まえて作成することが必要です。
契約書のひな形やテンプレートをそのまま利用すると、実際の取引内容にあわない契約書になっていしまうことが多く、場合によっては、自社にできないことを約束してしまう契約条項のまま契約してしまっているケースも少なくありません。
このような「ひな形の丸写し」は後日のトラブルのもととなり、大変危険です。
「咲くやこの花法律事務所」では、契約書作成はもちろん今回のケースですと「ITに強い弁護士」が、企業のご依頼に基づき、個別の事情に即した実効的な契約書を作成するサービスを行っております。
この記事では、Webサイト制作(ホームページ)の契約書についてご説明しましたが、そのほかにも「保守契約書」や「リスティング広告運用に関する契約書」、その他にも「IT関連の契約書全般」、「利用規約」などの作成に対応しております。
(2)自社または相手方が作成した契約書についての弁護士による「リーガルチェック」
「咲くやこの花法律事務所」では、ご相談者が自社で作成された契約書について、弁護士によるリーガルチェックのサービスを行っています。
契約書はユーザーとの間で制作費の支払等をめぐるトラブルが発生したときに、確実に制作費を回収するために非常に重要な書類ですので、自社で契約書を作成された場合も、弁護士によるリーガルチェックをうけておかれることをおすすめします。
また、「咲くやこの花法律事務所」では、相談者が契約相手から提案された契約書についての、弁護士によるリーガルチェックのご依頼も承っています。
契約相手から提案された契約書については、自社に不利な内容が含まれていることも多いので、うのみにせずに必ず弁護士のリーガルチェックをうけておきましょう。
11,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
Web関連、IT関連の契約書の作成やリーガルチェックをご希望の企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書関連に強い弁護士への相談サービス」をご覧下さい。
また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
12,Webサイト(ホームページ)制作会社に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
Webサイト(ホームページ)制作の請負契約に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
13,まとめ
今回は、Webサイト制作費の未払いトラブルなどを防ぐためのWebサイト制作(ホームページ制作)契約書の契約条項の作成のポイントについてご説明しました。
Web制作(ホームページ)の受注時の契約書作成における重要な7つのポイントを、もう一度、整理しますと以下の通りになります。
- (1)契約書で「仕様」を定めておくことが大切なポイントになること。
- (2)「対応ブラウザ」についての契約条項を設けておくとよいこと。
- (3)「検収」については、契約書で検収のルールをしっかり決めておく必要があること。
- (4)「支払時期」について、前金の支払時期を契約書に明記しておくことがポイントになること。
- (5)「著作権」については、Web制作代金が支払われるまではクライアントに著作権が移転しない内容にしておく必要があること。
- (6)「遅延損害金」についても、契約条項で遅延損害金の利率を定めておくとよいこと。
- (7)「クライアントの都合による解約」も想定して、解約時に支払いを受けることができるように契約条項を定めておく必要があること。
このようなポイントを必ずおさえておく必要があることを、ご理解いただけたと思います。
Web制作費未払いトラブルが起こってから契約書の不備に気付いて後悔することのないように、この機会にぜひ、自社のWebサイト(ホームページ)制作の請負契約書のひな形を見直してみてください。
14,【関連情報】Webサイト(ホームページ)制作の契約書に関するお役立ち記事一覧
今回の記事では、Web制作会社向けに「Webサイト(ホームページ)制作の請負契約書の作成時の重要ポイント」についてご説明しました。
Webサイト制作費の未払いトラブルなどを防ぐためには、必ずおさえておくべき重要ポイントばかりですが、この他にもWeb制作会社が契約書関連でおさえておくべき情報は多数あります。
以下では、Webサイト制作の契約に関して合わせて確認しておきたいお役立ち情報をまとめておりますので、参考にご覧ください。
契約関連のお役立ち情報
▶秘密保持契約書(NDA)作成方法を弁護士が解説【サンプル雛形付き】
▶契約書の合意管轄条項(専属的合意管轄)の記載方法、交渉方法
▶請負契約の解除のルールと手続きについて解説【民法改正にも対応】
Webサイト制作費の未払いトラブルが発生した際に使えるお役立ち情報
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2022年6月23日
 06-6539-8587
06-6539-8587