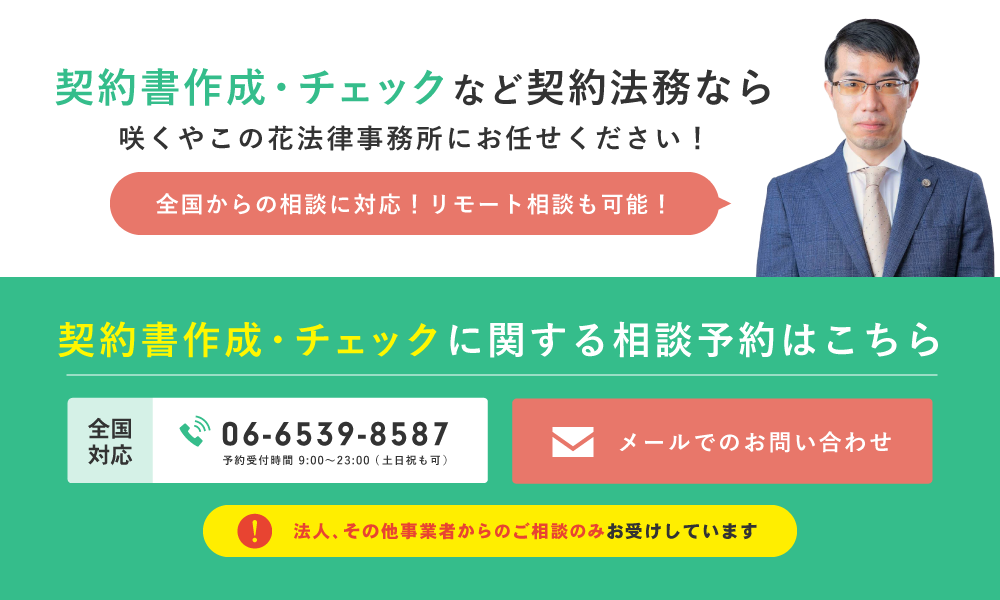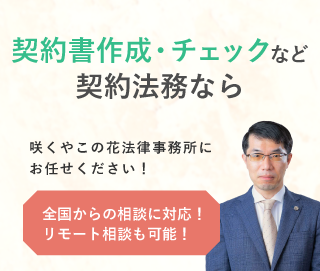2019年の厚生労働省の統計によれば、パート社員を雇用する企業の割合は全体の「78%」を超えており、増加傾向にあります。
一方で、パート社員の増加に伴い、パート社員と企業の雇用トラブルも増えています。
例えば、2013年には、パート社員が正社員との賃金格差を問題にし、正社員との賃金の差額を会社に請求した事件について、裁判所が会社に「160万円」の損害賠償を命じました。(大分地方裁判所平成25年12月10日判決)
また、2018年には、パート社員と正社員との「通勤手当」の格差を違法と判断して、会社に損害賠償を命じた判決も出ています(福岡高等裁判所判決平成30年9月20日)
今回は、企業内においてますます重要性を増しているパート社員について、「雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたい4つのポイント」についてご説明します。
雇用契約書の整備は、雇用トラブル防止の基本ですので、必ず確認しておきましょう。
▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。
▼【動画で解説】西川弁護士が「パート社員の雇用契約書!重要ポイント」について弁護士が詳しく解説中!
▼【関連情報】雇用契約書に関連する情報として、以下も参考にご確認ください。
・雇用契約書がないとどうなる?会社のリスクやデメリットを詳しく解説
・契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】
▼雇用契約書の作り方やチェックについて今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,パート社員の法律上の定義について
パート社員の雇用契約書を作成する際のポイントについてご説明する前に、まず、「パート社員」の法律上の定義を確認しておきましょう。
(1)「パート社員」の法律上の定義
「パート社員」は、法律上は、「短時間労働者」と呼ばれ、「1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことをいいます。
ここでいう「所定労働時間」とは、「定時」のことです。
たとえば、正社員の所定労働時間が、「1週間40時間」の会社において、「週に3日、1日8時間」しか出勤しない従業員は、1週間の所定労働時間が正社員より短いことになりますので、「パート社員」にあたります。
仮に、社内で「アルバイト」あるいは「嘱託社員」などと呼んでいたとしても、1週間の所定労働時間が正社員よりも少なければ、法律上はすべて「パート社員」にあたります。
そして、「パート社員」については、労働基準法だけでなく、「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されます。
▶参考情報:パートタイム・有期雇用労働法について
ここでは、まず、「パート社員」の定義を確認しておきましょう。
2,パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたい4つのポイント
それでは、パート社員の定義を踏まえたうえで、「パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたい4つのポイント」について見ていきましょう。
パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたい4つのポイントは以下の通りです。
- ポイント1:法律上明示が義務付けられている項目をすべて網羅する
- ポイント2:「無期の雇用契約か有期の雇用契約か」を決める
- ポイント3:賃金の決め方については、就業規則、パートタイム・有期雇用労働法、最低賃金法に注意!
- ポイント4:始業時刻・終業時刻の記載についての注意点
以下で詳細を見ていきましょう。
ポイント1:
パート社員の雇用契約書に記載する必要がある項目を網羅する
パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたいポイントの1つ目は「法律上明示が義務付けられている記載項目をすべて網羅する」という点です。
パート社員を雇用する際は、そのパート社員に、雇用条件に関し、法律で決められた項目を明示することが、労働基準法施行規則及びパートタイム・有期雇用労働法施行規則で義務付けられています。
そのうち、「書面で明示すること」が義務付けられている項目は以下の18項目です。
パート社員を雇用する際に、書面で明示することが義務付けられている18項目
- (1)労働契約の期間
- (2)有期の雇用契約の場合は契約更新の有無、及び、契約更新ありの場合は更新するか否かの判断基準
- (3)就業の場所
- (4)従事する業務の内容
- (5)始業時刻・終業時刻
- (6)所定労働時間を超える労働の有無
- (7)交替制勤務をさせる場合は交替期日あるいは交替順序等に関する事項
- (8)休憩時間
- (9)休日
- (10)休暇
- (11)賃金の決定・計算方法
- (12)賃金の支払方法
- (13)賃金の締切り・支払の時期に関する事項
- (14)退職に関する事項 ※解雇事由を含む
- (15)退職金の有無
- (16)昇給の有無
- (17)賞与支給の有無
- (18)短時間有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
このうち、「(1)~(14)」は労働基準法施行規則により記載が義務付けられている項目、「(15)~(18)」はパートタイム・有期雇用労働法施行規則第2条により記載が義務付けられている項目です。
これらの項目については、書面の交付による明示が義務付けられていますが、パート社員がファックスまたは電子メールでの明示を希望する場合は、ファックスまたは電子メールで明示すればよいとされています。
また、これらの項目について、「労働条件通知書」などの書面で明示することも適法ですが、「労働条件通知書」は通常は従業員側の印鑑が捺印されません。従業員が労働条件について承諾したことを明確にするためには、「労働条件通知書」ではなく、「雇用契約書」において上記の18項目を明示することをおすすめします。
以上、法律上明示が義務付けられている項目をすべて網羅した雇用契約書を作成することが、パート社員の雇用契約書を作成するうえでの基本的なポイントになりますのでおさえておきましょう。
雇用契約書の記載事項については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
ポイント2:
「無期の雇用契約か有期の雇用契約か」を決める
パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたいポイントの2つ目は「無期の雇用契約か有期の雇用契約かを決める。」という点です。
パート社員の雇用契約には、大きく分けて「無期の雇用契約」と「有期の雇用契約」があります。
そして、「無期の雇用契約か有期の雇用契約か」は、「ポイント1」で挙げた「パート社員を雇用する際に、書面で明示することが義務付けられている18項目」の(1)の「労働契約の期間」に該当し、雇用契約書に記載することが必要な項目の1つです。
また、契約の内容としても、「無期の雇用契約か有期の雇用契約か」は重要な違いがあります。
そこで、以下では、まず、「無期の雇用契約か有期の雇用契約かの選択の基準」についてご説明し、次に、「有期の雇用契約にする場合の注意点」についてご説明したいと思います。
1,無期の雇用契約か有期の雇用契約かの選択の基準について
1.無期の雇用契約を選択するべきケース
「無期の雇用契約」とは、従業員からの退職の申し出がない限り、原則として定年まで雇用する契約です。
長期間継続する仕事に従事してもらうためにパート社員を雇用する場合は、無期の雇用契約が原則といえるでしょう。
2.有期の雇用契約を選択するべきケース
「有期の雇用契約」とは、あらかじめ契約で決めた期間に限り臨時で雇用する契約です。
臨時で発生した仕事に対応するために期間限定で雇用する場合や、育児休業や介護休業を取得した従業員の代替人員として雇用する場合は、有期の雇用契約とすることが適切です。
以上が選択の基準ですが、「有期の雇用契約」にする場合は、労働者保護の観点から、法律上、一定のルールが設けられている点に注意が必要です。
以下で、「有期の雇用契約にする場合の注意点」を見ていきましょう。
2,パート社員との雇用契約を有期の雇用契約にする場合の注意点
有期の雇用契約にする場合の注意点としては以下の3つをおさえておくことが重要です。
注意点1:
雇用契約の期間は、原則として、3年を超えてはならない
注意点2:
雇用契約の際は、「契約更新の有無」と「更新ありの場合は更新するか否かの判断基準」の明示が必要
注意点3:
3回以上更新し、あるいは雇用の期間が1年を超えている従業員について契約を更新しない場合、30日前までの予告が必要
以下で詳しく見ていきましょう。
注意点1:
雇用契約の期間は、原則として、3年を超えてはならない
労働基準法第14条で、例外的な場合を除き、有期の雇用契約の期間は「3年」を超えてはならないとされています。
これは、長期間の雇用契約をすることで、従業員が意向に反して仕事に従事させられる事態を防止するための制限とされています。
そのため、雇用契約の期間は原則として3年以内に設定しましょう。
注意点2:
雇用契約の際は、「契約更新の有無」と「更新ありの場合は更新するか否かの判断基準」の明示が必要
有期の雇用契約では、雇用契約の際に、「契約更新の有無」と「更新ありの場合は更新するか否かの判断基準」を書面で明示することが労働基準法施行規則第5条で義務付けられています。
これは「ポイント1」でご説明した「パート社員を雇用する際に、書面で明示することが義務付けられている18項目」の(2)の項目にあたります。
有期の雇用契約とする場合は、雇用契約書に「契約の更新の有無」を記載し、「更新あり」の場合は「更新するか否かの判断基準」を記載しておきましょう。
具体的な記載方法は、この記事の最後にある「雇用契約書の雛形」を参照してください。
ひな形の第8条で、「契約更新の有無」と「更新するか否かの判断基準」について記載しています。
注意点3:
3回以上更新し、あるいは雇用の期間が1年を超えている従業員について契約を更新しない場合、30日前までの予告が必要。
3回以上更新し、あるいは雇用の期間が1年を超えている従業員について、会社が雇用契約を更新しない場合は、契約期間満了の30日前までに、更新しないことを従業員に予告することが義務付けられています。
予告を怠ると、契約の継続を巡って、パート社員とトラブルになることがありますので注意が必要です。
以上、「無期の雇用契約か有期の雇用契約かの選択の基準」と「有期の雇用契約にする場合の注意点」をおさえておきましょう。
ポイント3:
賃金の決め方については、就業規則、パートタイム・有期雇用労働法、最低賃金法に注意!
パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたいポイントの3つ目は「賃金の決め方についての注意点」です。
賃金については、「ポイント1」で挙げた「パート社員を雇用する際に、書面で明示することが義務付けられている19項目」の(11)に該当し、雇用契約書に記載することが必要な項目の1つです。
また、「ポイント1」の(15)~(17)に挙げた「退職金の有無」、「昇給の有無」、「賞与支給の有無」についても、賃金に関する項目です。
パート社員との雇用契約書に記載する賃金を決めるにあたっては、以下の3点について注意が必要です。
注意点1:
パート社員に適用される就業規則がある場合は、パート社員の賃金は就業規則に記載されている基準を下回ってはならない
注意点2:
正社員との待遇の格差については、パートタイム・有期雇用労働法に注意が必要
注意点3:
最低賃金法の最低賃金を下回ってはならない
以下で順番に見ていきましょう。
注意点1:
パート社員に適用される就業規則がある場合は、パート社員の賃金は就業規則に記載されている基準を下回ってはならない
就業規則には労働条件の最低基準を決める効力があります(労働契約法第12条)。この効力は「就業規則の最低基準効力」と呼ばれます。
▶参考:パート社員、アルバイトの就業規則について詳しくは以下も参考にご覧ください。
そのため、自社に、パート社員に適用される就業規則が存在する場合は、パート社員の賃金は、就業規則に記載されている労働条件を下回らないように注意しなければなりません。
パート社員に適用される就業規則が存在する場合とは、具体的には以下のようなケースです。
1.パート社員に適用される就業規則が存在する2つのケース
ケース1:
パート社員用の就業規則が通常の就業規則とは別に作成されているケース
ケース2:
パート社員用の就業規則はないが、通常の就業規則に「別途規定がない限り、全従業員に通常の就業規則が適用される」ことが記載されているケース
このように、パート社員に適用される就業規則が存在する場合は、以下の例のように、就業規則に記載されている労働条件を下回る条件を雇用契約書に記載することは、就業規則違反となり、トラブルのもとですので注意しましょう。
2.就業規則の労働条件を下回る条件を雇用契約書に記載してしまうケースの例
ケース1:
就業規則あるいは賃金規程に皆勤手当を支給することが記載されているのに、パート社員に皆勤手当を支給しないケース
ケース2:
就業規則に昇給について記載されているのに、パート社員との雇用契約書で「昇給なし」と記載するケース
ケース3:
就業規則あるいは退職金規定に退職金の支給について記載されているのに、パート社員との雇用契約書で「退職金なし」と記載するケース
このように、パート社員との雇用契約書に記載する賃金を決めるにあたっては、就業規則の規定に注意する必要があることをおさえておきましょう。
注意点2:
正社員との待遇の格差については、パートタイム・有期雇用労働法に注意が必要。
パートタイム・有期雇用労働法第8条、第9条により、パート社員についても、正社員との同一労働同一賃金が法律上義務付けられています。
具体的には、以下の点に注意する必要があります。
1.正社員と職務内容や人事異動の範囲等が同じパート社員について
正社員と比較して差別的な賃金とすることが禁止されます(パートタイム・有期雇用労働法第8条)。
2.正社員と職務内容や人事異動の範囲等が異なるパート社員について
正社員と異なる待遇とすることも許されますが、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることが禁止されます(パートタイム・有期雇用労働法第9条)。
この同一労働同一賃金ルールについては、基本給、賞与、通勤手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当などの各賃金項目ごとに検討する必要がありますが、特に、通勤手当、皆勤手当の格差については、格差が不合理として違法とされる傾向が強く注意が必要です。
九水運輸商事事件では、通勤手当について通勤経路にかかわらず正社員は一律10000円、パート社員は一律5000円を支給していた事案について、このような格差は不合理であるとして企業が賠償を命じられています(福岡高等裁判所判決平成30年9月20日)
同一労働同一賃金ルールについては、以下で詳しく記載しましたので、参照してください。
注意点3:
最低賃金法の最低賃金を下回ってはならない。
最低賃金法は、労働者の賃金の下限を定める法律です。
パート社員の賃金を決めるにあたっては、最低賃金を下回ってはならないことにも注意しておきましょう。最低賃金には、「1,地域別最低賃金」と「2,特定最低賃金」の2つがあり、いずれも下回らないように注意する必要があります。
以下で順番に確認していきましょう。
1.地域別最低賃金について
地域最低賃金は、すべての労働者に適用される最低賃金です。
都道府県ごとに定められており、厚生労働省のホームページに「地域別最低賃金」の情報が掲載されています。
2.特定最低賃金について
特定最低賃金は、特定の事業の労働者にのみ適用される最低賃金です。
こちらは都道府県ごと、業種ごとに定められており、厚生労働省のホームページに「特定最低賃金の全国一覧」の情報が掲載されています。
最低賃金は、毎年10月に改訂されることが通例ですので、常に新しい最低賃金でチェックすることが必要です。
以上、パート社員の賃金の決め方については、「1,就業規則を下回らない」、「2,正社員との同一労働同一賃金ルールに違反しない」、「3,最低賃金を下回らない」の3点をおさえておきましょう。
ポイント4:
始業時刻・終業時刻の記載についての注意点
パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたいポイントの4つ目は「始業時刻・終業時刻の記載についての注意点」です。
始業時刻・終業時刻については、「ポイント1」で挙げた「パート社員を雇用する際に、書面で明示することが義務付けられている18項目」の(5)に該当し、雇用契約書に記載することが必要な項目の1つです。
パート社員の始業時刻、就業時刻、休憩時間に関する基本的な記載例は以下の通りです。
1,始業時刻、就業時刻、休憩時間があらかじめ決まっている場合の記載例
▶参考記載例:
第◯条(始業時刻、終業時刻、休憩時間)
始業時刻 9時 終業時刻 17時 休憩 12時から13時までの1時間
但し、会社は必要があるときは、始業時刻あるいは終業時刻を繰り上げ又は繰り下げることができる。
以上が基本的な記載例ですが、パート社員についてシフト制を採用している場合は、出勤の曜日、始業時刻、就業時刻はシフトで定まることになり、あらかじめ決まっていないことがよくあります。
このような場合の「始業時刻、就業時刻の記載」については、厚生労働省の通達があります。
この通達において、シフト制を採用している場合の始業時刻、就業時刻の記載については、「勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示したうえ、当該労働者に適用される就業規則上の関係項目を網羅的に示すことで足りる」とされています。
つまり、シフト制の場合、始業時刻や終業時刻については日によって異なることもあるので、毎日の始業時刻、終業時刻を雇用契約書に記載する必要はありませんが、「勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方」を示すことは必要です。
シフト制のパート社員についての雇用契約書の記載方法としては以下の例があげられます。
2,シフト制のパート社員についての雇用契約書の始業時刻、終業時刻、休憩時間の記載方法
▶参考記載例:
第◯条(始業時刻、終業時刻および休憩時間)
1 始業時刻、終業時刻、休憩時間については、甲が毎月25日までに翌月分のシフトを定め、社内に掲示して周知する。
甲は、原則として毎週4日を出勤日とし、週の労働時間が30時間を上回らない範囲で、以下の3パターンの中から乙の出勤日のシフトを定める。ただし、甲の都合により、他のパターンのシフトを定めることがある。
【パターン1】 始業 12時 終業 18時 休憩 15時から16時までの1時間
【パターン2】 始業 8時 終業 16時 休憩 12時から13時までの1時間
【パターン3】 始業 12時 終業 20時 休憩 15時から16時までの1時間
2 甲は必要があるときに、乙に対して所定時間外労働を命じることができる。
このように、シフト制であっても、雇用契約書に、主な勤務パターンについて始業時刻及び終業時刻を記載したうえで、シフトの組み方についてのおおまかなルールを記載することが求められています。
ここでは、特にシフト制の場合の始業時刻・終業時刻の記載の方法をおさえておきましょう。
この記事の最後にある雇用契約書のひな形でも、第4条で、シフト制の場合の始業時刻、終業時刻、休憩時間について記載しています。
3,【補足】パート社員の社会保険加入義務に関する法改正について
最後の補足として、「パート社員の社会保険加入義務に関する法改正」についてご説明しておきたいと思います。
従来は、週の所定労働時間及び所定労働日数が、通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上のパート社員にのみ、社会保険加入が義務付けられていました。
しかし、2016年10月から、従業員501名以上の企業については、社会保険の加入が義務付けられるパート社員の範囲が拡大されました。
具体的には、従業員501名以上の企業については、以下の5つの条件を全て満たすパート社員には社会保険加入が義務付けられます。
従業員501名以上の企業について社会保険加入が義務付けられるパート社員の範囲
- 1, 週の所定労働時間(残業時間を含まない労働時間)が20時間以上
- 2,1か月あたりのあらかじめ決まっている給与の額(残業代や賞与など月により異なる賃金を含まない額)が88,000円以上
- 3,現在75歳未満
- 4,1年以上の雇用が予定されている(1年未満の契約だが、更新の可能性がある場合も含みます)
- 5,現在、学生ではない
このうち、「週の所定労働時間が20時間以上」の条件については、シフト制で週の所定労働時間が決められていないケースでは、週当たりの平均の労働時間が20時間以上かどうかで判断するとされています。
また、さらに2022年10月からは、この週の所定労働時間20時間以上のパート社員への社会保険加入義務化が従業員数101名~500名の企業にも拡大されることが決まっています。
あわせて、前述の4で「1年以上の雇用が予定されていること」が週20時間以上のパート社員の社会保険加入義務の要件とされていましたが、この点も「2か月以上の雇用が予定されていること」と変更されることが決まっています。
この点について、詳しくは以下をご参照ください。
以上、補足として、パート社員の社会保険についての変更事項をおさえておきましょう。
4,パート社員の雇用契約書の雛形ダウンロード
以下で、今回の記事でご説明してきたパート社員の雇用契約書のテンプレート書式を掲載しますので、雛形をダウンロードしてご利用ください。
テンプレート書式の雛形ダウンロードはこちら
※1年間の有期雇用でシフト制のパート社員のケースを想定した雇用契約書の雛形です。従業員500名以下の企業で、週の所定労働時間を30時間以内に設定し、社会保険に加入しないケースを想定して作成しています。
5,パート社員の雇用契約書に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、労働問題に強い弁護士が雇用契約書関連のご相談を担当しています。
具体的なサポート内容とおおまかな費用の目安は以下の通りです。
(1)社内事情にあわせた雇用契約書の作成
今回の記事に、雇用契約書の一般的なひながたをアップロードしていますが、実際にはひな形を御社個別の事情を踏まえて修正したうえで使用することが必要です。
ひな形を参考にしながら、御社の具体的な勤務体系や仕事の内容、賃金体系を反映させて、御社の実情にあったオリジナルの雇用契約書を整備することが必要です。
また、「就業規則との整合性」や「正社員とパート社員の待遇の差がある場合、その差を合理的に説明できるようにしておくこと」にも配慮する必要があります。
咲くやこの花法律事務所においては、労務問題に精通した実績豊富な弁護士が、各企業の具体的な事情に適合する雇用契約書の作成を行っております。
弁護士費用例
●初回ご相談料/30分5000円(税別)
●雇用契約書作成費用/3万円(税別)〜
(2)自社で作成した雇用契約書のリーガルチェック
咲くやこの花法律事務所では、すでに自社で雇用契約書を作成されている企業のために、作成された内容について弁護士がリーガルチェックを行うサービスも行っております。
労務トラブル防止のための基本的な書類である雇用契約書について、弁護士のチェックを受けることは、労務に関する法的な整備をすすめるうえで必要不可欠です。
作成した雇用契約書が自社の労働条件を正確に反映しているかどうか、補充すべき点はないか、就業規則との整合性がとれているかなどの点について必ず弁護士のチェックを受けておきましょう。
弁護士費用例
●初回ご相談料/30分5000円(税別)
●雇用契約書のリーガルチェック費用/2万円(税別)~
「正しい雇用契約書になっているか不安」、「今、雇用契約書を作成しようとしている」など、雇用契約書に関するお困りごとがありましたら、トラブルが発生する前に早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。
6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の雇用契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書に強い弁護士への相談サービスについて」をご覧下さい。
また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
7,雇用契約書のお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
雇用契約書に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
8,まとめ
今回は、まず、パート社員の法律上の定義について確認したうえで、パート社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたいポイントとして以下の4つをご説明しました。
- ポイント1:パート社員の雇用契約書に記載する必要がある項目を網羅する
- ポイント2:「無期の雇用契約か有期の雇用契約か」を決める
- ポイント3:賃金の決め方については、就業規則、パートタイム・有期雇用労働法、最低賃金法に注意!
- ポイント4:始業時刻・終業時刻の記載についての注意点
また、補足として、パート社員の社会保険加入義務に関する法改正についてもご説明しました。
パート社員との雇用トラブルを防ぐためにも、雇用契約書の整備は万全にしておきましょう。
またパート社員の増加と合わせて、契約社員の勤務形態も増えてきています。今回の記事の関連情報として、「契約社員の雇用契約書の作成方法」についても以下を参考にしてください。
既存の雇用契約書に不安がある場合、また改善の必要がある場合などは、労務や労働問題に強い弁護士がそろう「咲くやこの花法律事務所」までトラブルが発生する前に早めにご相談ください。
9,【関連情報】パート社員の雇用契約書と合わせて確認しておきたいお役立ち記事
今回の記事では、「パート社員の雇用契約書の作成の際の重要ポイント」をテンプレート(ひな形)ダウンロード付きでご説明しました。
パート社員を雇用する際に雇用契約書を締結しなければなりませんが、その際、この記事でもご説明してきたように他にも「就業規則」など知っておくべき重要なことがあります。
以下では、それらのお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。
・ 雇用契約書とは?正社員用の書き方など作成方法を弁護士が解説【雛形テンプレート付】
・就業規則の作成について!詳しい作り方や作成料金を弁護士が解説
・パート・アルバイト用の就業規則の重要ポイントと注意点【雛形あり】
・在宅勤務やテレワーク・在宅ワーク対応の就業規則の重要ポイント7つ
・就業規則の変更手続きと不利益変更や同意書取得に関する注意点
実際に従業員を雇用されている会社では、自社にあった最適な雇用契約書を作成しておく必要があります。そのため、雇用契約書を整備しておくことはもちろん、万が一「労務トラブル」などが発生した際は、スピード相談が早期解決の重要なポイントです。
雇用契約書の作成や変更については、「労働問題に強い弁護士」に相談するのはもちろん、普段から自社の労務環境の整備を行っておくために「労働問題に強い顧問弁護士」にすぐに相談できる体制にもしておきましょう。
労働問題に強い「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士については、以下をご参照ください。
▶【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
▶大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
また顧問弁護士に関する具体的な役割や必要性、費用の相場などをご覧になりたい方は以下の記事をご参照ください。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年1月5日
 06-6539-8587
06-6539-8587