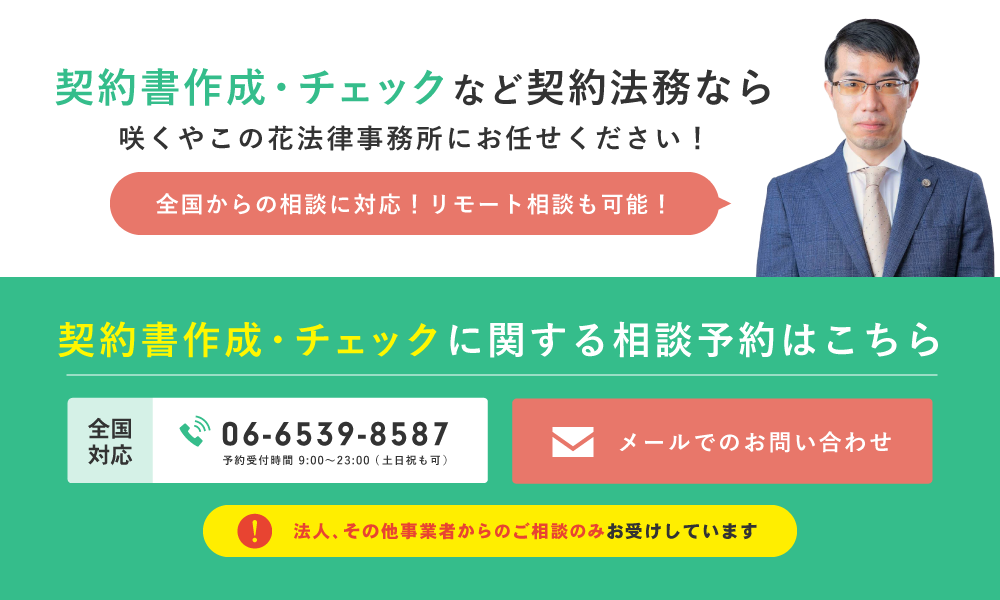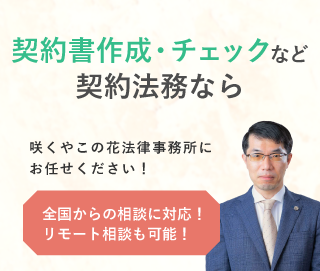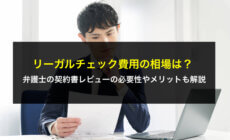こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
事業の迅速な拡大のための強力な手段の1つが「フランチャイズ(FC)」です。一方で、フランチャイズは、本部と加盟店のトラブルが尽きず、以下のような裁判に発展するケースも多いビジネスモデルです。
フランチャイズ(FC)に関する裁判の事例
- カフェのフランチャイズで情報提供等を怠った本部に「1823万円」の賠償を命じた事例(東京地裁平成24年1月25日判決)
- ステーキハウスのフランチャイズで本部に加盟金「600万円」の返還を命じた事例(神戸地裁平成15年7月24日判決)
今回は、トラブル回避のためのもっとも基本的な対策であるフランチャイズ(FC)契約書の整備についてご説明します。
フランチャイズ(FC)契約書については、安易にひな形を修正して利用したために、加盟店に対してできないことを約束する内容になってしまっていたり、加盟店の問題行動に対応できない内容になってしまうなど、トラブルになるケースが尽きません。
このような「ひな形利用の危険性も踏まえ、トラブルにならないフランチャイズ契約書の実際の作成における注意すべきポイント」をご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、トラブルを回避するためのフランチャイズ契約書の整備に向けて動き出すことができるようになります。
はじめてフランチャイズビジネスに取り組む方にもご理解いただけるようにわかりやすくご説明していますので、ぜひ目を通してください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所のフランチャイズ契約書の作成やリーガルチェックなど、弁護士によるサポート内容は以下をご参照ください。
また、実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がサポートしたやる気のないフランチャイズ契約に関するサポート事例は以下をご参照ください。
▼フランチャイズ契約について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
またフランチャイズ関連に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,フランチャイズ契約(FC契約)とは?
- 2,フランチャイズ契約書(FC契約)の一般的な記載事項
- 3,フランチャイズ契約書(FC契約)作成の重要ポイント
- 4,ポイント1: 商標の使用許諾について決める。
- 5,ポイント2: 提供するノウハウの内容、ノウハウ提供の方法を決める。
- 6,ポイント3: テリトリー制を導入するかどうかを決める。
- 7,ポイント4: ロイヤリティの計算方法をどうするかを決める。
- 8,ポイント5: 加盟店の会計の把握をどのように行うかを決める
- 9,ポイント6: 商品や備品、店舗内装を本部指定とするかどうかを決める。
- 10,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がフランチャイズ契約のサポートをした事例
- 11,フランチャイズ契約書に関して弁護士に相談したい方はこちら
- 11,まとめ
- 12,【関連情報】フランチャイズ契約書に関する他のお役立ち情報
1,フランチャイズ契約(FC契約)とは?
フランチャイズ契約書の作成方法の説明に入る前に、まず、「フランチャイズ契約(FC契約)とはなにか」を確認しておきます。
フランチャイズ契約(FC契約)とは、本部が加盟店に対して、特定のマークや名称(「商標」といいます)などを使用する権利を与えるとともに、事業経営について指導・援助を行い、その対価として加盟店が本部に金銭を支払う契約をいいます。本部は「フランチャイザー」、加盟店は「フランチャイジー」と呼ばれます。
そして、加盟店が本部に支払う金銭には、一般、「加盟金」や「ロイヤリティ」、「研修費用」などさまざまな費目があります。これらの金銭は、「本部が加盟店に特定の商標を使用する権利を与えること」あるいは「本部が加盟店の事業経営について指導・援助を行うこと」の対価であり、フランチャイズ契約書の作成においても、その点を常に意識しておく必要があります。
また、フランチャイズビジネスを成功させるためには、「本部が使用を認める商標」と「本部による加盟店に対する指導・援助」が、本部が加盟店から受け取る金銭に見合うだけの価値あるものであることが大前提になりますので、おさえておきましょう。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「絶対に避けたい!フランチャイズのよくあるトラブル5つ【前編】」や、「フランチャイズのよくあるトラブル5つと予防策を弁護士が解説【後編】」の動画で、フランチャイズビジネスでよくあるトラブルについて詳しく解説しています。
2,フランチャイズ契約書(FC契約)の一般的な記載事項

それでは、フランチャイズ契約書(FC契約書)の作成方法をご説明します。
結論からご説明すると、フランチャイズ契約書の作成にあたっては、まず、一般的な記載事項を確認したうえで、自社のフランチャイズビジネスに適合したオリジナルの契約書を作り上げていくことが必要です。
ここでは、まず、「フランチャイズ契約書の一般的な記載事項」をご説明します。
フランチャイズ契約書の一般的な記載事項としておさえておきたいのは以下の30の項目です。
(1)フランチャイズ契約書の記載事項
1,契約の目的
「フランチャイズチェーンの理念」や「世の中に提供する価値」、「本部と加盟店の共存共栄」などフランチャイズ契約の目的を定めます。
2,フランチャイズチェーンの概要
フランチャイズチェーンにおいて提供する商品やサービスの内容、フランチャイズチェーンの名称を定めます。
3,独立事業の原則
加盟店が独立の事業者であり、加盟店の経営責任は加盟店自身にあることを定めます。
4,商標の使用許諾
フランチャイズチェーンにおいて本部が加盟店に使用を認める商標(マークや名称)や商標使用時の制限事項について定めます。
5,営業名・営業場所の指定
本部が加盟店に営業を認める店舗等の名称と営業場所を定めます。
6,ノウハウの提供・権利の帰属
本部が加盟店に対して必要なノウハウを提供すること、またノウハウの権利が本部に帰属することを定めます。
7,マニュアルの遵守義務
加盟店は本部が定めたマニュアルを遵守する義務を負うことを定めます。
8,テリトリー権
加盟店に対して、本部が加盟店の店舗から一定の距離の範囲内に同チェーンの他店舗を出店しないことを約束するなど、「テリトリー権」を認めるか否かについて定めます。
9,店舗の設備
店舗の設備についてフランチャイズチェーンとして統一すべき項目を定めます。
10,開店前指導援助
本部が加盟店に対して行う、開店前の援助や指導の内容について定めます。
11,運営指導援助
本部が加盟店に対して行う、開店後の運営についての援助や指導の内容について定めます。
12,遵守事項
加盟店の営業日や営業時間、個人情報・顧客情報の管理方法など、加盟店が守るべきルールについて定めます。
13,広告宣伝
広告は本部において統一的に行うこと、加盟店による独自の広告は本部の事前の許可を要することなどを定めます。
14,競業の禁止規定
フランチャイズ契約で得たノウハウを利用して、契約外で加盟店が同様の事業を行うことを禁止します。
15,経営委託や契約上の権利の譲渡の禁止
加盟店が経営を第三者に委託したり、フランチャイズ契約上の権利を第三者に譲渡することを禁止します。
16,立ち入り調査
本部が必要に応じて加盟店に立ち入り調査をすることができる権限を定めます。
17,秘密保持義務
本部が加盟店に提供したノウハウの内容、その他秘密とすべき情報について、加盟店が第三者に開示してはならないことや、本来の目的以外に利用してはならないことを定めます。
18,商品供給
本部が加盟店に対して、商品を指定して供給する場合は、商品供給の条件について定めます。また、加盟店に対して、本部指定商品以外の商品を販売することを禁止する場合は、その点についても定めます。
19,加盟金
加盟店がフランチャイズチェーン加入の際に本部に支払う加盟金について、その内容、支払時期、金額を定めます。また、加盟金は理由を問わず、返金されないことを定めます。
20,ロイヤリティ
加盟店が本部に毎月支払うロイヤリティについて、その内容、支払時期、金額を定めます。
21,システム使用料
本部がフランチャイズ契約に伴い、加盟店に対してシステムを供給する場合に、そのシステム使用料について定めます。
22,広告分担金
本部が行う広告について、加盟店に対して広告分担金を負担させる場合は、その金額や支払い方法について定めます。
23,会計帳簿等の記帳、報告
加盟店が会計帳簿を記帳する義務や、本部に会計内容を報告する義務について定めます。
24,契約期間
フランチャイズ契約の契約期間や更新について定めます。
25,中途解約
フランチャイズ契約を契約期間中に中途解約することの可否や条件について定めます。
26,契約解除
加盟店が破産した場合や加盟店が契約に違反した場合などに、本部がフランチャイズ契約を解除できることを定めます。
27,契約終了後の措置
契約終了後に加盟店が本部の商標やフランチャイズチェーンのノウハウを利用することを禁止するなど、契約終了後の措置について定めます。
28,損害賠償
加盟店による契約違反があった場合の損害賠償や違約金の金額について定めます。
29,連帯保証
加盟店に連帯保証人を求める場合は、連帯保証人の責任について定めます。
30,合意管轄
本部と加盟店が裁判になった場合の専属的合意管轄を定めます。
以上、まずは、フランチャイズ契約書の一般的な記載事項として30項目を確認しておきましょう。
3,フランチャイズ契約書(FC契約)作成の重要ポイント
それでは、一般的なフランチャイズ契約書の記載事項のご説明を踏まえたうえで、「契約書作成の重要ポイント」をご説明していきたいと思います。
フランチャイズ契約書(FC契約書)を作成するうえで最も重要となるポイントをピックアップすると以下の通りです。
(1)フランチャイズ契約書(FC契約)作成の重要ポイント
- ポイント1:商標の使用許諾について決める。
- ポイント2:提供するノウハウの内容、ノウハウ提供の方法を決める。
- ポイント3:テリトリー制を導入するかどうかを決める。
- ポイント4:ロイヤリティの計算方法をどうするかを決める。
- ポイント5:加盟店の会計の把握をどのように行うかを決める。
- ポイント6:商品や備品、店舗内装を本部指定とするかどうかを決める。
これらの6つのポイントは、フランチャイズ契約における根幹の部分になりますので、以下で順番にご説明していきます。
(2)補足
なお、フランチャイズ契約書(FC契約書)については、インターネットや各種書籍でひな形が提供されています。
ひな形は、フランチャイズ契約書(FC契約書)を作成する際に、記載事項に漏れがないかチェックしたり、条文の書き方に迷ったときに参考にするために有用なツールです。
ただし、フランチャイズ契約(FC契約)のようなビジネスの肝となる重要な契約書について、一般的なひな形をそのまま利用したり、ひな形を少し修正しただけで利用することは絶対に避けなければなりません。
インターネットや各種書籍のひな形を安易に使用すると、契約書の内容が自社のフランチャイズビジネスに適合しない内容になってしまい、自社ができないことを加盟店に対して約束する内容になってしまったり、加盟店の問題行動に対して対応できないものになってしまうなどして、加盟店とのトラブルに発展し、ビジネス自体が失敗に終わってしまうからです。
フランチャイズビジネスを成功させるためには、ひな形を参考にしながら、以下でご説明する重要なポイントを踏まえてオリジナルの契約書を作り上げることが必要です。
それでは前述の6つのポイントについて順番に見ていきましょう。
4,ポイント1:
商標の使用許諾について決める。
フランチャイズ契約書(FC契約書)において、まず最初におさえておきたい重要なポイントが、「商標の使用許諾の内容について決める」という点です。
フランチャイズビジネスにおいては「商標」は非常に重要なポイントです。
有名フランチャイズチェーン、例えば「セブンイレブン」や「ローソン」は、本部が加盟店に対して、「セブンイレブン」や「ローソン」の名称あるいはマークを使用させること自体が、加盟店の売上に貢献し、加盟店がフランチャイズに加盟する意義になっています。
これは、「セブンイレブン」や「ローソン」の名称で店舗経営することによって、一般の消費者からの信頼が得られ、来店者増に貢献することを、加盟店としても認識しているためです。
そして、「セブンイレブン」や「ローソン」はその名称やマークについて商標権を取得して、自社の了解なく第三者に名称やマークが使用されないように法的な防御を行っています。
このように、フランチャイズ契約では、名称やマークについての「商標」を核としたブランディングを行うことにより、集客力や顧客からの信頼性を高めていくことが、フランチャイズチェーンの発展に直結します。
そのため、フランチャイズ契約の核となる名称やマークについては、必ず、特許庁に商標の出願を行い、商標登録しておくことが必要です。
▶参考情報:商標を登録しなければどのような損害が発生するかについては、以下で詳しくご説明していますのでチェックしておいてください。
また、商標が登録できたら、加盟店が商標を使用する際のルールをフランチャイズ契約書に定めておくことも必要です。
商標を使用する際のルールとしてフランチャイズ契約書に定めておくべき項目は以下の通りです。
(1)商標を使用する際のルールとしてフランチャイズ契約書に定めておくべき項目
- 項目1:加盟店が、フランチャイズ契約書で認められた店舗以外において、商標を使用することの禁止
- 項目2:加盟店が商標を独自に修正することの禁止
- 項目3:本部の商標と同一または類似の商標を加盟店が商標登録することの禁止
- 項目4:第三者が無断で商標を使用していることを発見した場合に、加盟店が本部に対して報告することを義務付けること
- 項目5:フランチャイズ契約終了後に加盟店が商標を使用することの禁止
なお、項目3については、本部が商標権の更新を怠っていた間に加盟店が商標権を本部に無断で取得してしまうという事件(平成27年8月3日知財高裁判決 のらや事件)も発生しています。
以上のポイントを踏まえて、商標の使用許諾の内容について決めて、フランチャイズ契約書に記載することは、フランチャイズ契約書作成において最初の重要なポイントになりますので、おさえておきましょう。
5,ポイント2:
提供するノウハウの内容、ノウハウ提供の方法を決める。
フランチャイズ契約書(FC契約書)において、次におさえておきたい重要なポイントが、「提供するノウハウの内容、ノウハウ提供の方法を決める」という点です。
フランチャイズ契約において、加盟店がロイヤリティを支払ってでも、フランチャイズチェーンに加入する動機となるのは、前述の「商標使用によるブランド力、集客力」のほか、「本部から提供されるノウハウを利用できる」という点があります。
逆に言えば、ロイヤリティを支払っているのに、提供されるノウハウが十分なレベルではないという場合、フランチャイズ契約の解約や加盟店とのトラブルの原因になります。
フランチャイズビジネスを始めるにあたっては、自社が本部として加盟店に提供するノウハウを確立することがまず必要です。
これまで自社で行ってきたビジネスをフランチャイズ化するケースが多いと思いますが、自社ビジネスでつちかったノウハウを文章にまとめたうえで、ノウハウに磨きをかけ、ロイヤリティの対価として十分なものに高めていく努力が必要です。
また、ノウハウの提供の方法についても、検討しておく必要があります。
フランチャイズ契約における、本部の加盟店に対するノウハウ提供の方法としては、以下のようなものがあります。
1,本部の加盟店に対するノウハウ提供方法の例
- 方法1:加盟店に対して成文化したマニュアルを交付する
- 方法2:加盟店の従業員に対して、開店前に本部が研修を行う
- 方法3:加盟店に対して、開店後に経営指導、運営指導を行う
特に、「方法2:加盟店の従業員に対して、開店前に本部が研修を行う」、「方法3:加盟店に対して、開店後に経営指導、運営指導を行う」については、加盟店を指導する人材が必要になり、人材育成が不可欠です。
このように「ノウハウの内容」と「ノウハウ提供の方法」について、十分に検討したうえで、フランチャイズ契約書にノウハウ提供のためのマニュアルの交付や、開店前研修、開店後の指導について記載することが重要なポイントになります。
ノウハウの内容の確立やノウハウ提供の方法の確立が不十分になると、結局、加盟店は本部に対する支払いに見合うノウハウを得られないことになり、フランチャイズ契約が長続きせず、ビジネス自体が失敗に終わります。
この点については、「加盟店が本部からロイヤリティに見合うノウハウ提供がされなかったとして加盟店から損害賠償請求されるケース(大阪地方裁判所平成2年11月28日判決「焼とり居酒屋チェーン大蔵」の事例など)」もありますので、注意が必要です。
6,ポイント3:
テリトリー制を導入するかどうかを決める。
フランチャイズ契約書(FC契約書)において、次におさえておきたい重要なポイントが、「テリトリー制を導入するかどうかを決める」という点です。
まずは、テリトリー制がどのような制度かを確認しておきましょう。
(1)フランチャイズ契約におけるテリトリー制とは?
テリトリー制とは、本部が、加盟店に対して、特定の地域(例えば、加盟店の店舗から半径5キロ以内など)での独占的あるいは優先的な経営権を承認する制度であり、以下のような例があります。
1,クローズド・テリトリー
テリトリー内に他のフランチャイズ店の出店をさせないことを本部が承認するケース
2,オープン・テリトリー
テリトリー内の店舗数に上限を設け、上限を超えてテリトリー内に他のフランチャイズ店の出店をさせないことを本部が承認するケース
3,期間限定テリトリー
開店後一定期間に限って、テリトリー内に他のフランチャイズ店の出店をさせないことを本部が承認するケース
4,優先的テリトリー
テリトリー内に出店を検討する場合は、本部はまず、テリトリー内の加盟店に優先的に声をかけ、出店権を与えるが、加盟店が出店しない場合は、他の加盟店に出店させることも可とするケース
これらのテリトリー制については、本部側から見た場合に以下のようなメリットとデメリットがあります。
(2)本部側から見たテリトリー制採用のメリット
加盟店の商圏内において、他のフランチャイズ店の出店を制限することによって、加盟店の経営を安定させ、本部と加盟店の信頼関係の強化や共存共栄につながりやすいことがメリットになります。
(3)本部側から見たテリトリー制採用のデメリット
加盟店の売上や利益が順調でないケースでも、テリトリー内への出店が制限されるため、そのテリトリー内で同業他社にシェアを奪われる危険があります。
テリトリー制を採用するかどうか、採用するとしてどのような内容のものにするかについては、このようなメリットとデメリットを考慮したうえで、検討し、フランチャイズ契約書に明記することが必要です。
いったんテリトリー制を採用すると後からテリトリーを廃止することは困難ですので、慎重に検討しましょう。
7,ポイント4:
ロイヤリティの計算方法をどうするかを決める。
フランチャイズ契約書(FC契約書)において、次におさえておきたい重要なポイントが、「ロイヤリティの計算方法をどうするかを決める」という点です。
フランチャイズ契約においてロイヤリティとは、フランチャイズ契約締結後に商標の使用及び事業経営についての指導・援助の対価として、加盟店が本部に対して定期的に支払う金銭をいいます。
フランチャイズ契約時に支払われる加盟金と異なり、ロイヤリティは通常、毎月支払われます。このロイヤリティの計算方法については、大きく分けて、「定額制」と「変動制」があります。
「定額制のロイヤリティ」と「変動制のロイヤリティ」の内容についてはそれぞれ次の通りです。
(1)定額制のロイヤリティ
加盟店の売上や利益にかかわらず、毎月定額のロイヤリティを加盟店が本部に支払うスタイルです。
(2)変動制のロイヤリティ
加盟店の売上や利益をベースに一定のパーセントをかけた金額をロイヤリティとして加盟店が本部に支払うスタイルです。
それぞれの場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
(3)定額制のロイヤリティのメリットとデメリット
1,メリット
定額制をとることにより、本部としては安定した収益計画をたてることができます。
2,デメリット
加盟店としては収益があがらなくても定額のロイヤリティを支払わなければならず、加盟店の経営が悪化したときに本部とのトラブルにつながりやすいというデメリットがあります。
また、逆に、加盟店の経営が成功をおさめた場合でも、ロイヤリティの増額が困難となります。
(4)変動制のロイヤリティのメリットとデメリット
1,メリット
売上または利益に連動するロイヤリティの計算制度を採用することにより、本部と加盟店の利害が一致し、本部と加盟店の信頼関係強化につながりやすいというメリットがあります。
2,デメリット
本部から見た場合、加盟店の売上や利益によりロイヤリティ収入が変動するので、安定した収益計画が立てにくいというデメリットがあります。
また、加盟店が本部に対して虚偽の売上や利益を申告してロイヤリティの支払いを免れようとする不正行為が考えられるので、本部において加盟店の売上や利益を把握する仕組みが必要になります。
以上を踏まえて、ロイヤリティの計算方法についてどのように定めるかを検討し、フランチャイズ契約書に明記することが必要です。
8,ポイント5:
加盟店の会計の把握をどのように行うかを決める
フランチャイズ契約書(FC契約書)において、次におさえておきたい重要なポイントが、「加盟店の会計の把握をどのように行うかを決める」という点です。
まず、本部が加盟店の会計を把握することについては、以下の2つの必要性があります。
(1)本部が加盟店の会計を把握しなければならない2つの理由
- 理由1:本部が加盟店に対して、健全な経営を指導することにより、加盟店の経営の失敗を防ぐ必要がある。
- 理由2:ロイヤリティが変動制の場合は、加盟店の売上や利益を正しく把握することで、ロイヤリティを適切に支払わせる。
そして、本部による加盟店の会計の把握については、以下のような方法があります。
(2)本部による加盟店の会計の把握の方法
1,加盟店の会計処理義務についての契約条項を設ける方法
加盟店が、本部が定めた方式や書式、システムに従って会計処理を行う義務があることをフランチャイズ契約書の契約条項として定める方法です。
2,加盟店の会計報告義務についての契約条項を設ける方法
加盟店が、本部に対して会計帳簿、日報、月次報告書等を提出して、経営状態を報告する義務を負うことをフランチャイズ契約書の契約条項として定める方法です。
3,本部の調査権についての契約条項を設ける方法
本部が加盟店に対して、立入調査を行う権限や、会計帳簿を閲覧して調査する権限をもつことを契約条項として定める方法です。
4,会計処理義務違反、会計報告義務違反、調査拒絶についての制裁条項を設ける方法
加盟店が、会計処理義務あるいは会計報告義務に違反したり、あるいは、本部の調査を拒否する場合、本部はフランチャイズ契約を解除したり、加盟店に対して違約金を請求することができる旨をフランチャイズ契約書の契約条項として設ける方法です。
これらの方法を複数組み合わせることによって、本部が加盟店の会計を適切に把握できるようにしておくことが重要です。
なお、コンビニエンスストアのフランチャイズシステムなどでは、加盟店に売上金すべてをいったん本部に送金させ、本部において加盟店の会計処理を行う方式(オープンアカウント方式)が採用されていることが多いです。
この方式は、本部が加盟店の会計を完全に把握できるというメリットがある一方、本部側で加盟店の会計を行うためのリソースを確保することが必要です。
そのため、これからフランチャイズビジネスを始めるという場面で、オープンアカウント方式の導入は現実性が低く、前述の4つの方法を組み合わせて契約書に盛り込むことで対応すべきことが多いと思います。
以上、加盟店の会計把握に関する契約条項作成のポイントをおさえておきましょう。
9,ポイント6:
商品や備品、店舗内装を本部指定とするかどうかを決める。
フランチャイズ契約書(FC契約書)において、次におさえておきたい重要なポイントが、「商品や備品、店舗内装を本部指定とするかどうかを決める」という点です。
商品や備品、店舗内装を本部指定とすることには、以下のメリットがあります。
(1)商品や備品、店舗内装を本部指定とすることのメリット
- メリット1:商品、備品、内装を統一することにより、フランチャイズチェーンとしての統一的なイメージを確保できる。
- メリット2:加盟店独自の商品として廉価品を販売されて、フランチャイズチェーンのブランドが損なわれることを防ぐことができる。
- メリット3:商品や備品、店舗内装を本部指定とすることにより、本部として商品や備品、店舗内装の供給に関しても利益をあげることができる。
このように、商品や備品、店舗内装を本部指定とすることには大きなメリットがあります。
また、裁判所も商品等について本部指定とする契約条項は有効と判断しています(東京地方裁判所平成13年1月25日判決 天丼フランチャイズチェーンの事例など)。
しかし、一方で、商品や備品、店舗内装を本部指定とすることによって、仕入れ先の確保や、仕入れ先の管理、また場合によっては、商品や備品、内装の不具合についてのトラブルの対応が必要になることもあります。
これらの点を踏まえて、商品や備品、店舗内装を本部指定とするかどうかを決め、本部指定とする場合は、フランチャイズ契約書にもその点を明記しましょう。
なお、商品を本部指定とする場合、その運送費用については「フランチャイズ契約書に加盟店負担と明記しなければ運送費用は本部負担となる」と判断した判例(東京地方裁判所平成19年6月4日判決 居酒屋フランチャイズチェーン「つぼ八」の事例)がありますので、運送費用の負担についても、必ず契約書に明記しておきましょう。
▶参考情報:契約書作成における重要なポイントについては、以下の関連記事もあわせてご覧下さい。
10,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がフランチャイズ契約のサポートをした事例
咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズ契約のトラブルについて数多くのご相談をお受けし、会社側の代理人としてトラブルを解決してきました。咲くやこの花法律事務所の解決実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。
(1)フランチャイズ本部からの依頼で弁護士がフランチャイズ契約書のリーガルチェックをした事例
1.事件の概要
外食フランチャイズチェーンの本部である会社から、フランチャイズ契約書のリーガルチェックを依頼され、会社に有利で紛争防止性の高い契約書に改善した事例です。
会社が加盟金・研修費に関するフランチャイズ契約書のリーガルチェックを咲くやこの花法律事務所に依頼したところ、以下のような不備が見つかり、このままでは加盟店から加盟金等の返還を求められるリスクが高いことが判明しました。
- 加盟金・研修費の対価(本部が提供するサービス内容)の記載がない
- 加盟金・研修費を返還しない旨の規定がない
2.問題の解決結果
担当弁護士は、契約書の不備について、以下のとおり変更しました
・加盟金の対価(ノウハウ提供、商標使用許諾、開業支援など)を明記
・加盟金・研修費は返還しない旨を規定
また、加盟金が過大になっていないか等にも配慮し、紛争防止効果の高い契約書へと改善しました。
▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。
11,フランチャイズ契約書に関して弁護士に相談したい方はこちら

ここまでフランチャイズ契約書の作成方法についてご説明してきました。
最後に咲くやこの花法律事務所でフランチャイズ契約書について行うことができるサポートサービスの内容をご紹介します。
咲くやこの花法律事務所でご提供しているサポートの内容は以下の2点です。
(1)個別の事情に応じたフランチャイズ契約書の作成
フランチャイズ契約書の作成にあたっては、「本部が加盟店に対して提供するメリットにどのようなものがあるか」、「加盟店に提供するメリットの対価として、本部はどのような形式でフィーを受領するのが適切か」、「売上をあげられない加盟店や違反行為をする加盟店にどのように対応するか」、「加盟店がフランチャイズ外で、本部のノウハウを無断で利用する行為にどのように対処するか」などについて、個別の事情に応じた対応策を検討したうえで、契約書に盛り込む必要があります。
このように個別のフランチャイズビジネスの内容に適合した契約書を作成することが非常に重要です。
咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズ契約書の作成に精通した弁護士が、お客様のビジネスの事情に適合した万全のフランチャイズ契約書を作成するサポートを行っています。
また、フランチャイズビジネスを開始後にもさまざまな事情の変化が起こることが通常であり、フランチャイズ契約書については定期的なブラッシュアップが必要です。
咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズ契約書作成後の追加、修正についても、サポートしております。
(2)自社で作成したフランチャイズ契約書のリーガルチェック
お客様が自社で作成したフランチャイズ契約書を、咲くやこの花法律事務所の弁護士がリーガルチェックすることについても対応が可能です。
咲くやこの花法律事務所における、これまでのフランチャイズ関連トラブル解決の実績を踏まえたリーガルチェックにより、加盟店とのトラブルを事前に防ぐことができるように万全のチェックを行います。
フランチャイズ契約書は、ビジネスの肝となる大変重要な契約書であり、契約書の作成は弁護士にご依頼いただくか、弁護士のチェックを受けていただくことを強くおすすめします。
咲くやこの花法律事務所の契約書作成サービスあるいはリーガルチェックサービスについても気軽にお問い合わせください。
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士への問い合わせ方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
11,まとめ
今回は、フランチャイズ契約書の作成方法について、一般的な記載項目をご説明したうえで、フランチャイズ契約書(FC契約)作成の重要ポイントとして、以下の6つのポイントをご説明しました。
- ポイント1:商標の使用許諾について決める。
- ポイント2:提供するノウハウの内容、ノウハウ提供の方法を決める。
- ポイント3:テリトリー制を導入するかどうかを決める。
- ポイント4:ロイヤリティの計算方法をどうするかを決める。
- ポイント5:加盟店の会計の把握をどのように行うかを決める。
- ポイント6:商品や備品、店舗内装を本部指定とするかどうかを決める。
いずれもフランチャイズ契約の骨子を決める重要なポイントになりますので、おさえておきましょう。
12,【関連情報】フランチャイズ契約書に関する他のお役立ち情報
この記事では、「フランチャイズ(FC)契約書の作成の重要ポイント」についてわかりやすく解説しました。
フランチャイズ契約を締結する際は、今回ご紹介したフランチャイズ契約書に関してをはじめ、他にもフランチャイズビジネスの仕組みや関連する法律などを正しく理解しておく必要があり、そのため正しい知識を理解しておかなければ契約時や契約後に重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連するフランチャイズ契約のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・フランチャイズ解約時の違約金について。判例を踏まえた注意点とは?
またフランチャイズビジネスにおける継続的なリスク対策や法律に関する相談、トラブル発生時の早期解決サポートは、フランチャイズに精通している顧問弁護士による日常的なサポートをおすすめします。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年12月9日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」フランチャイズ法務に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587