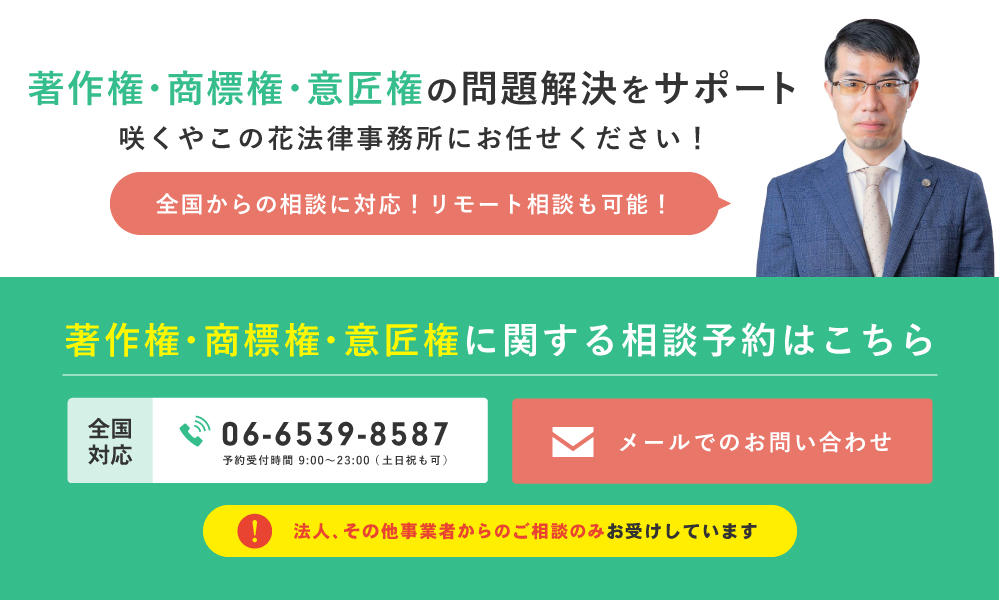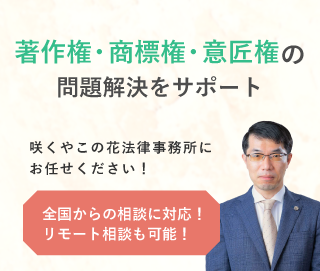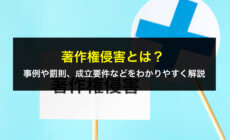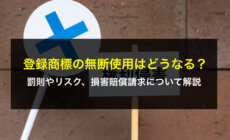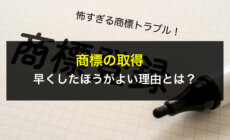「新しい製品を作っても、すぐにコピー商品が出てきてしまう。」
このようなお悩みをお持ちの経営者も多いと思います。
コピー商品、類似商品などの模倣品対策に活用できる知的財産権の1つが、「意匠権」です。
たとえば、本田技研工業株式会社は、オートバイの「スーパーカブ」のデザインについて意匠権を取得し、模倣品の排除に成功しています。同社は、類似のデザインのオートバイを製造・販売した企業に対して、意匠権をもとに訴訟を起こし、裁判所は7億円を超える賠償命令を言い渡しました。
中小企業の中にも、意匠権の活用に取り組む企業は多く、特許庁の資料によると、意匠権の出願者全体の57%を中小企業が占めています。
今回は、模倣品対策に絶大な効果がある「意匠権」について、基本的な内容を具体例をあげながらわかりやすくご説明したいと思います。
▶【関連情報】意匠権に関して、以下の関連情報もあわせてご覧ください。
・商品形態模倣行為とは?不正競争防止法が定める要件や事例を解説
▼意匠権について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,意匠権とは?
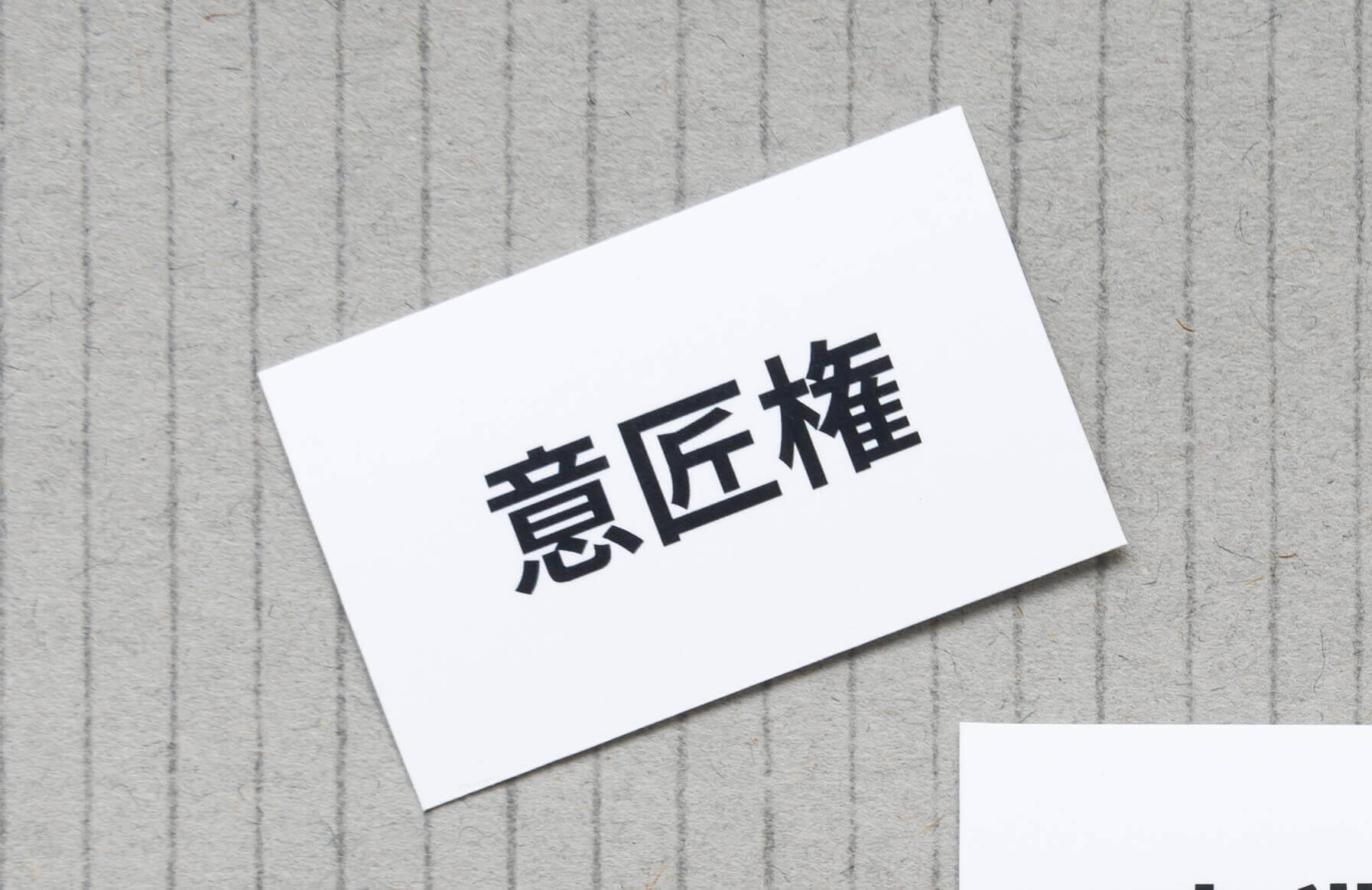
まず、意匠権とは、「製品や商品のデザインについて独占権を認める制度」です。意匠権を取得すれば、意匠権者は、そのデザインを独占的に使用することができます。そのため、自社製品のデザインを意匠登録しておくことは、コピー商品、類似商品などの模倣品対策に絶大な効果を発揮します。
そして、意匠権は、特許庁への登録が必要な登録制の制度になっています。意匠権はデザインを保護するものですので、特許権のように技術的な新規性がなくても、登録は可能です。身近な商品やパッケージについても取得可能な、取得しやすい権利です。
コピー商品、類似商品などの模倣品対策が必要な企業は、模倣品が出ることによる価格競争とブランドの劣化を避けることが長期的な企業戦略として大変重要です。自社の経営に意匠権を活用してみてください。
2,意匠権の具体例
現在、さまざまな物品について意匠権が登録され、権利化されています。「意匠権の具体例」として、以下のようなものがあげられます。
具体例1:
江崎グリコ株式会社「Baton d’or(バトンドール)」の例
江崎グリコ株式会社が、自社商品である高級版ポッキー「Baton d’or(バトンドール)」のパッケージのデザインについて意匠権を取得しています。
▶参考:「Baton d’or(バトンドール)」のパッケージデザイン

具体例2:
オムロンヘルスケア株式会社「体重計」の例
オムロンヘルスケアは自社で販売する体重計(オムロン体重体組成計・体重計)について、体重計のデザインについて意匠権を取得しています。
▶参考:オムロンヘルスケアの体重計

そのほかにも、以下のようなありとあらゆる商品について意匠権が登録されている実例があります。
意匠権が登録されている物の具体例
●日用品:
文房具類、枕、物干しざお、体重計、おもちゃ、調理用品、はぶらし
●住宅関連:
テーブル、机、椅子、照明器具、システムキッチン、浴槽、棚
●衣服類:
衣服、かばん、靴、マフラー、ペット用衣服、アクセサリー、メガネ、布地
●部品関係:
機械部品、ねじ、バルブ類
●機械関係:
携帯電話、デジタル家電、農機具、工作機械、車両、自転車、時計
●容器類:
ペットボトル、包装用容器、スマートフォン用ケース、シャンプー容器、化粧品容器
3,著作権、商標権との違いについて
意匠権の権利の内容は、他の知的財産権である著作権や商標権と比較するとより理解がしやすくなります。
意匠権と著作権や商標権の違いは以下の通りです。
意匠権と著作権や商標権の比較一覧
| 権利の内容 | 登録が必要か | |
| 意匠権 | 商品や製品、部品などの工業用デザインについて独占権を認める。 | 特許庁に登録が必要 |
| 著作権 | 文章や画像、プログラム、音楽などの表現に独占権を認める。商品や製品などの実用品のデザインについては著作権は認められないことが多い。 | 登録不要 |
| 商標権 | 商品名やサービス名、ブランド名、ロゴマークなどに独占権を認める。 | 特許庁に登録が必要 |
▶著作権についての参考:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
▶商標権についての参考:https://www.jpo.go.jp/index.html
このように、意匠権は工業用のデザインを保護対象としています。一方、著作権は、どちらかというと文化面の権利であり、商品や製品などの実用品のデザインについては著作権が認められないとされることが多いため、工業用のデザインは著作権ではなく、意匠権の範囲といえるでしょう。
また、商標権は、例えば「キンチョール」などといった商品名や、「YouTube」などといったサービス名、あるいは「mister Donut」などのブランド名やそのロゴマークに独占権を認める制度であり、商品や製品のデザインを保護するものではありません。
4,意匠権取得の3つのメリット

では、企業が自社製品や自社商品のデザインについて意匠権を取得することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
「意匠権取得のメリット」をご説明します。この点については、主に以下の3つのメリットに整理することができます。
- メリット1:コピー商品、類似商品など、模倣品を法的な強制力をもって排除できる。
- メリット2:自社商品についてデザインを核としたブランド化をすることができる。
- メリット3:発注元に発注先を変更されることについてのリスク対策になる。
以下で順番にこの3つのメリットについてご説明します。
(1)コピー商品、類似商品など、模倣品を法的な強制力をもってを排除できる。
製品のデザインは、目で見てすぐにわかるものであるため、いくら斬新なデザインでも真似されやすいという傾向があります。
そのため、新製品を発売して少し人気が出ると、同じようなデザインのコピー商品、類似商品の模倣品が出てきてしまうという点が問題です。
自社製品のデザインについて意匠権を取得しておけば、意匠権を侵害する模倣品に対して、法律上、以下の権利を行使することができ、模倣品を排除することができます。
意匠権者が行使できる権利の内容
- (1)模倣品の在庫、あるいは製造中の模倣品の強制的に廃棄させることができる。
- (2)模倣品の製造、販売、広告宣伝を中止させることができる。
- (3)模倣品の販売によって自社がこうむった損害の賠償を請求することができる。
意匠権の侵害については、以下の記事でも詳しく解説していますのでおさえておいてください。
(2)自社商品についてデザインを核としたブランド化をすることができる。
意匠権は、偽物やコピー商品など模倣品の排除だけでなく、ブランディングにも活用できます。
ブランディングにはいろいろな手法がありますが、デザインはブランドを支える重要な要素の1つです。自社の優れたデザインについて、意匠権を取得することで、デザインにこだわった商品であることをアピールし、そのデザインを独占することで、自社商品のブランディングを進めることができます。
意匠権を自社商品のブランディングに活用している具体例として、「レクサス」や「メルセデスベンツ」といった高級車のフロントグリルがあります。高級車のフロントグリルには、複数の車種に共通したデザインが使われ、シリーズ化されていますが、これはブランディング戦略の一環といえるでしょう。
(3)発注元に発注先を変更されることについてのリスク対策になる。
自社が、他社から発注を受けて他社製品に使用する部品等を供給する製造業の場合、発注先を同業他社に変更されてしまうことは、経営上重要なリスクです。
そこで、自社が供給する部品の特徴的なデザインについて意匠権を取得しておけば、仮に発注元から発注先を変更されたとしても、その発注先は、同じデザインあるいは類似のデザインの部品を提供できません。
このように意匠権は、発注元に発注先を変更されることについてのリスク対策にも活用することができます。
意匠権にはこのような3つのメリットがありますので、自社で活用できないか、検討してみてください。
5,意匠権を取得するために必要な4つの条件
意匠権を取得するためには、特許庁への登録が必要です。
では、どのような条件を満たせば登録が可能になるのでしょうか?
意匠権を取得するために必要な4つの条件についてみていきましょう。
条件1:
工業上のデザインであること(工業上の利用性)
例えば、農作物の形状や、工業用の利用ができない一品もののデザインについては意匠権を取得できません。
条件2:
誰でも思いつくような簡単なデザインではないこと(創作非容易性)
誰でも思いつくようなデザインや、すでに知られているデザインの一部を別のデザインに置き換えただけのもの、あるいは、すでに知られているデザインを組み合わせただけのものなどは意匠権を取得できません。
条件3:
未発表あるいは発表後1年以内のデザインであること(新規性)
意匠権を取得できるのは未発表のデザインあるいは発表後1年以内のデザインに限られます。
国内で製品として発表したり、販売を開始したり、あるいは新聞や雑誌、インターネットにデザインを掲載してから、1年以上たったときは、意匠権は取得できなくなりますので注意が必要です。
条件4:
類似のデザインについて意匠権が出願されていないこと
意匠権は「早い者勝ち」の制度です。
自社が考案したデザインであっても、他社が、自社よりも早く、同じデザイン、あるいは類似のデザインについて意匠権を出願してしまうと、自社は意匠権を取得することはできなくなります。
意匠権を取得するためにはこのように4つの条件を満たす必要がありますのでおさえておきましょう。
6,意匠権の有効期間
次に、意匠権の有効期限についての説明です。
意匠権の有効期間は、出願の日から25年です(意匠法第21条1項)。
意匠権を出願すれば、25年間はそのデザインを独占的に使用することができます。一方、25年たった後は更新の制度はありません。そのため、25年後は誰でもそのデザインを使用できるようになってしまいます。
7,【補足】意匠権の「国際登録制度」とは?
ここまでご説明してきた意匠権制度ですが、平成27年5月からスタートした「国際登録制度」により、国際的な利用が便利になりました。
以下では補足としてこの意匠権の国際登録制度について触れておきたいと思います。
『意匠権の「国際登録制度」は、本来、国ごとにしなければならない意匠登録の手続きを、複数の国について一括登録することができるようにする制度です。』
この意匠権の国際登録制度を理解していただくうえで、まずご説明しておきたいのが、「意匠権制度は、国ごとの制度である」ということです。
たとえば、自社製品のデザインについて日本で意匠権を取得していても、韓国で意匠権を取得していなければ、韓国での偽物やコピー商品、類似商品など模倣品の製造、販売をやめさせることはできません。
日本で登録した意匠権は、日本国内でしか効力がないのです。
そのため、海外での模倣品の製造・販売を防ぐためには、それぞれの国ごとに意匠権を取得する必要があります。
そして、国際登録制度ができる前までは、海外で意匠権を取得するには、国ごとに意匠登録の手続きをする必要がありました。そのため、大変面倒で費用も高額になっていました。
しかし、国際登録制度がスタートしたことにより、複数の国について一括して意匠権登録が可能になり、しかも、日本での登録手続きが可能となりました。
この国際登録制度により、米国、韓国、EUなど、64の国と地域で、日本での手続きで意匠権の一括登録が可能になり、今後さらに対象国が増える見込みとなっています。
このように、海外での意匠権の取得が以前より、格段に便利になり、コストも低くなっていますので海外での模倣品対策での活用をぜひ検討してみてください。
8,不正競争防止法の商品形態模倣行為について
ここまでご説明したように意匠権については特許庁での登録がないと主張できない権利です。これに対し、意匠権とは別に模倣品対策に利用できる制度として、不正競争防止法の商品形態模倣があります。
この不正競争防止法の商品形態模倣は、登録等がなくても、商品の形態模倣行為に対して差し止めや損害賠償請求を求めることができるという制度ですが、請求が認められるための要件は、意匠権に基づく請求よりも絞られたものになっています。また、商品を日本国内で最初に販売した日から3年以内の行為のみが対象となります。
▶参考情報:不正競争防止法の商品形態模倣行為については以下で詳細を解説していますのでご参照ください。
9,意匠権について弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所における、意匠権に関するサポート内容についてご説明したいと思います。
- (1)意匠権の登録、出願の代理
- (2)意匠権トラブルに関する交渉や訴訟
以下で順番に見ていきましょう。
(1)意匠権の登録、出願の代理
咲くやこの花法律事務所では、意匠権の取得をご検討されている企業様のご依頼受けて、登録・出願の代行を行っております。
登録、出願の費用(いずれも税別)については13万円~14万円程度の費用をいただいています。費用の詳細については以下をご参照ください。
(2)意匠権トラブルに関する交渉や訴訟
咲くやこの花法律事務所では意匠権トラブルに関する相手方との交渉や訴訟についても常時ご相談をお受けしています。
知財分野に精通した咲くやこの花法律事務所の弁護士がトラブルの交渉や訴訟を担当することにより、御社にとってベストな解決を実現します。
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
10,まとめ
今回は、意匠権の基本的な内容や具体例、意匠権活用のメリットなどについてご説明しました。また、補足として、海外での模倣品対策に活用できる国際登録制度についてもご説明しました。
意匠権はデザインを保護するものですので、特許権のように技術的な新規性がなくても、登録は可能です。身近な商品やパッケージについても取得可能な、取得しやすい権利です。
模倣品が出ることによる価格競争とブランドの劣化を避けることは、長期的な企業戦略として大変重要ですので、ぜひ「意匠権」を自社の経営に活用してみてください。
11,意匠権に関連するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
意匠権に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
12,意匠権に関連するお役立ち関連情報
今回の記事では、「意匠権とは?どんな権利?具体例でわかりやすく解説」というテーマについて、具体例を用いてわかりやすくご説明しました。
そもそも「意匠権とは?」の基本的な意味をはじめ、意匠権取得のメリットや取得にために必要な条件など詳しくご説明してきましたが、この意匠権に関しては、「意匠権侵害」などのトラブルに関する情報や、その他、著作権や商標権などの知的財産権に関連するトラブルとも隣り合わせになっていることが多いです。
そのため、以下では今回ご紹介した「意匠権とは?」と合わせて確認しておくべきお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。
商標権について
著作権について
▶著作権侵害とは?事例や罰則、成立要件などをわかりやすく解説
▶記事原稿や画像の無断転載、著作権侵害の損害賠償額の目安と交渉ポイント
▶Web制作やシステム開発の外注の際におさえておくべき著作権の重要ポイント
▶ネットの画像や原稿を引用する場合の方法とルール!著作権侵害に注意
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年12月8日
 06-6539-8587
06-6539-8587