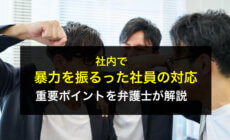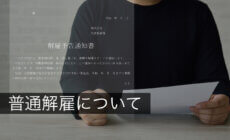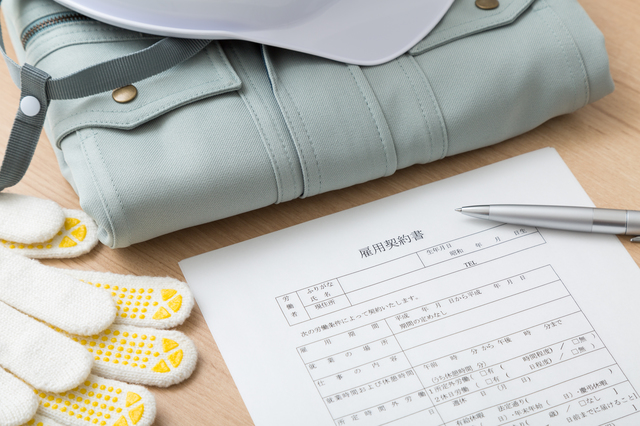
契約社員の雇止め法理というのはどのようなルールでしょうか?
雇止め法理とは、契約社員(有期雇用契約の従業員)の雇用を雇用契約の期間が終わるタイミングで更新せずに打ち切る「雇止め」について、法律上の制限を課すルールです。労働契約法は第19条において「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は雇止めを認めないとして、雇止め法理を定めています。
契約社員の雇止めについては以下のように裁判になる場面が増えており、契約社員を雇用している企業は雇止め法理の意味について正しく理解し対策しておくことが必要です。
事例1:
航空会社による契約社員雇止め事件(平成29年3月6日大阪地方裁判所判決)
→雇止めが無効であるとして約400万円の支払い命令
事例2:
レンタカー会社による契約社員雇止め事件(平成28年10月25日津地方裁判所判決)
→雇止めが無効であるとして約520万円の支払い命令
事例3:
食品加工会社による契約社員雇止め事件(平成28年5月27日京都地方裁判所判決)
→雇止めが無効であるとして約640万円の支払い命令
今回は、契約社員の雇止め法理とその対策について弁護士がわかりやすく解説いたします。
咲くやこの花法律事務所における、契約社員の雇用に関するトラブルの解決実績を以下で紹介していますのでご参照ください。
▼【関連動画】西川弁護士が「契約社員の雇止め法理!会社は次回の契約を更新しないことができる?【前編】」と「令和6年4月労働基準法施行規則改正!契約社員の雇止め法理への影響と対策【後編】」について詳しく解説中!
▼契約社員の雇い止めに関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,そもそも、雇止めとは?
雇止めとは、有期労働契約において、事業者側が契約の更新を拒否し、契約期間満了によって雇用契約を終了させることです。
雇止めについては、今回の記事で解説する「雇止め法理」(労働契約法第19条)により一定の場合は無効とされるなど、労働者保護の観点から様々な規制が設けられています。
雇止めを検討する場合は、労働者と紛争が生じ、訴訟トラブルに発展して、事業者側が敗訴する例も少なくないため、安易に考えず、法的なリスクを慎重に検討することが必要です。
雇止めに関する基本的な説明は、以下の参考記事をご参照ください。
2,労働契約法改正で法定化!契約社員の雇止め法理とは?

前述した通り、契約社員の雇止めとは、契約社員(有期雇用契約の従業員)を契約期間終了のタイミングで契約を更新せずに雇用を打ち切ることを言います。
この雇止めは契約期間終了により新しい契約を締結しないことを意味し、解雇ではありません。解雇というのは契約期間中にやめさせることを指しています。
そして、契約社員の雇止め法理とは、「法律で定める場合は、契約社員の雇止めに合理的な理由が必要とされ、合理的な理由のない雇止めは無効とされる」というルールをいいます。「雇止めは無効とされる」ということは、会社は契約の更新を強制されるという意味です。
ただし、この雇止め法理は、すべての契約社員に適用されるわけではありません。
雇止め法理の適用場面は、以下の「場面1」または「場面2」に該当する場合です。
(1)雇止め法理の適用場面
- 場面1:契約社員の更新手続きがルーズで実質的に見て正社員との雇用契約と同視できる状態にある場合
- 場面2:契約社員が雇用契約の更新を期待することについて無理もないといえるような事情がある場合
そして、この2つのいずれかに該当するときで、契約社員の雇止めが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、従業員が更新を求めれば会社は契約の更新を強制されることが、雇止め法理の具体的な内容です。
ここでいう「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」とは、「世間一般の目から見ても雇止めになってもやむを得ないと考えられるような事情がないとき」という意味と考えていただくとよいでしょう。
この雇止め法理は、平成25年4月の労働契約法の改正により、法律上も明記されました。
労働契約法第19条に定められています。やや複雑な条文ですが、条文の内容は以下の通りです。
▶参考:労働契約法第19条
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
・参照元:「労働契約法」の条文はこちら
3,雇止め法理が適用されるかどうかの判断基準
雇止め法理が適用されるかどうかは、前述の「場面1」あるいは「場面2」のいずれかに該当するかどうかで判断されます。場面1あるいは場面2のいずれにも該当しなければ雇止め法理の適用がなく、更新が強制されることはありません。
場面1あるいは場面2に該当するかどうかの具体的な判断基準は以下の通りです。
(1)雇止め法理が適用されるかの具体的な判断基準
場面1:
「契約社員の更新手続きがルーズで実質的に見て正社員との雇用契約と同視できる状態にある場合」にあたるかどうかについて
更新の際に雇用契約書を作っていないケース、あるいは雇用契約書を作っているが更新後に作っているケースがこれに該当します。
一方、必ず雇用契約期間満了前に新契約締結の手続きをとっているケースで、かつ契約の内容も更新時の状況によりその都度協議して決めているようなケースでは「契約社員の更新手続きがルーズで実質的に見て正社員との雇用契約と同視できる状態にある場合」にはあたらず、雇止め法理は適用されません。
場面2:
「契約社員が雇用契約の更新を期待することについて無理もないといえるような事情がある場合」にあたるかどうかについて
契約社員の仕事の内容が臨時的なものではなく正社員と違いがなかったり、契約社員について長年雇止めをしない運用が社内でされているケースがこの場合にあたります。
また、採用担当者や上司から長期間の雇用を約束するような発言があったケースでも、「契約社員が雇用契約の更新を期待することについて無理もないといえるような事情がある場合」にあたることがあります。
一方、契約社員の仕事の内容が臨時的なものであり、仕事がなくなれば契約終了になることを理解してもらって採用しているケースなどは、契約更新を期待するような事情がなく、雇止め法理は適用されません。
『「場面1:契約社員の更新手続きがルーズで実質的に見て正社員との雇用契約と同視できる状態にある場合」にあたるかどうかについて』または『「場面2:契約社員が雇用契約の更新を期待することについて無理もないといえるような事情がある場合」にあたるかどうかについて』に該当するかどうかの判断にあたっては、個別の事案ごとに以下の要素を総合的に考慮することとされています(平成24年8月10日付基発0810第2号)。
- 雇用の臨時性・常用性
- 更新の回数
- 雇用の通算期間
- 契約期間管理の状況
- 雇用の継続の期待を持たせる使用者の言動の有無 等
4,雇止め法理と更新回数の関係を判例を用いて解説
雇止め法理の適用があれば、契約を更新しないことについて合理的な理由が必要になり、単に契約が終了したからということで雇止めすることはできなくなります。
この点についてよく企業からご相談があるのが、「何回くらい更新していれば雇止めできなくなりますか?」というご質問です。このご質問はより正確に言うと、「何回くらい更新していれば雇止め法理の適用があるか」というご質問になります。
しかし、結論から言うと、何回更新していれば雇止め法理が適用されるというような明確な基準はありません。
以下の判例1のように長期間契約を更新した後の雇止めを合法とした事例がある一方で、判例2のように1回目の更新の際の雇止めを違法とした事例も存在します。
(1)雇止め法理と更新回数の関係する判例
判例1:
東京地方裁判所昭和63年11月30日決定
9年10か月間、契約更新されていた契約社員の雇止めについて雇止め法理を適用しなかった事例です。
裁判所は以下の点を指摘して、雇止め法理の適用を否定しています。
- 理由1:契約社員の業務が一時的な業務であったこと
- 理由2:契約社員の賃金や勤務時間が正社員とは違っていたこと
- 理由3:必ず契約期間満了前に新契約締結手続きをしていたこと
判例2:
大阪高等裁判所平成3年1月16日判決
1年契約のタクシードライバーの最初の更新の際に雇止めしたケースについて雇止め法理を適用した事例です。
裁判所は、以下の点を指摘して、雇止め法理の適用を肯定しました。
- 理由1:契約社員の仕事の内容が正社員と同じであったこと
- 理由2:契約社員について、これまで自己都合退職の場合を除き会社が更新に応じてきたこと
- 理由3:会社の労務管理上、契約社員の雇用契約書が更新の都度作成されているが、作成が前契約終了から数か月も後日にずれ込んだケースもあるなどルーズになっていたこと
このように、判例上、雇止め法理が適用されるかどうかの判断において更新回数が必ずしも重視されているわけではありません。
むしろ、契約更新時の契約書の作成状況や契約社員の仕事の内容など、「会社の労務管理がきちんとできていたかどうか?」が、雇止め法理が適用されるかどうかに最も影響します。
▶参考情報:会社の労務管理について詳しくは、以下の記事で解説していますのでご参照ください。
5,雇い止めが認められる合理的な理由とは?
雇止め法理が適用される場合でも、合理的な理由があれば雇止めが認められます。
では、 雇止めが認められる合理的な理由とはどのようなものでしょうか?
この点については、正社員を解雇する場合に必要な解雇理由とほぼ同じと理解することができます。
「正社員を解雇する場合に必要な解雇理由」については以下の記事で解説していますが、その内容は、雇止め法理が適用される場合に必要な雇止めの理由についてもあてはまりますので参照してください。
6,雇止めを有効とした裁判例
ここからは、裁判で雇止めが有効とされた事例をいくつかご紹介します。
(1)短期大学の助教の再任拒否(雇止め)を有効と判断した事例
1.東京地方裁判所判決 平成30年12月26日(日本大学事件)
3年間の任期(更新は2回限り、最長9年間の条件)で雇用されていた大学の助教が、任期中の助手や学生に対する不適切な行為や、度重なる上司の指示、指導、学科の決定に対する違反行為等を理由に助教として不適格であるとして、一度も雇用契約を更新することなく助教の再任を拒否されたことに対し、雇止めの無効と雇止め以降の賃金の支払いを求めた事例です。
裁判所は、助教の再任の可否は任期満了時点での研究業績や、適性や資質能力等について審査した上で判断するとされていたことから、助教は当然に再任されることが予定されているとはいえず、助教が准教授等へ昇任していくための資質を見極めるためのポストと位置付けられていることや、助教としての任期は3年と明確に設定されていたこと、一度も雇用契約が更新されていないことからすると、契約が更新されると期待を持つことが当然であるということはできないと指摘しています。
その上で、助教の任期中の不適切な行為や、教授から注意を受けていたにもかかわらず改善しなかったこと等を考慮すると、雇止めには客観的に合理的な理由があるとして、雇止めを有効と判断しました。
(2)契約期間満了を理由とする雇止めが有効と判断された事例
1.高知地方裁判所判決 平成30年3月6日(高知県公立大学法人事件)
大学法人において、1年間の雇用契約で雇用され、給与計算等の業務を担当していた契約社員が、2回の更新の後に、契約期間満了を理由に雇止めをされたことに対し、雇止めの無効と雇止め以降の賃金の支払いを求めた事例です。
裁判所は、就業規則で契約職員の雇用期間の上限は3年と明確に定められていたことや、更新にあたり契約期間を明記した労働条件通知書を交付していたこと、契約更新前に管理職による意向確認が行われていたこと、原則として3年間の雇用期間の上限を超えてそのまま契約を更新された例がないこと、契約社員が担当していた業務は代替性が高いものであったこと、準職員採用試験を受けて準職員として内部登用される機会が与えられていたこと等を理由に、雇止め法理は適用されず、雇止めは有効と判断しました。
この事案で、雇止め法理が適用されないと判断されたのは、就業規則で更新上限を3年と定めて就業規則の写しを採用直後に従業員に交付していたという点が大きいと考えられます。そのほか、更新手続が社内の規定に沿って適切に行われていたこと(更新が必要な契約職員に対して更新前に管理職による意向確認が行われ、更新の都度、労働条件通知書と辞令が交付されていた)も、雇止めが有効と判断された理由の1つになっています。
更新手続きが形骸化していたり、社内の規定通りに運用されていない場合、雇止めが無効と判断されてしまう原因になる可能性があります。雇止めトラブルの発生を防止するためには、日頃の労務管理や更新手続きを適切に行うことが大切です。
(3)勤務成績等を理由とする雇止めが有効と判断された事例
1.札幌地方裁判所判決 平成29年3月28日(札幌交通事件)
会社を一度退職した後、嘱託社員として雇用され、6ヶ月間の有期労働契約を2回更新していた従業員が、勤務成績や勤務方法等を理由に雇止めをされたことに対し、雇止めの無効と雇止め以降の賃金の支払いを求めた事例です。
裁判所は、全嘱託社員のうち、更新を拒絶された従業員は2名しかいないことや、会社が嘱託社員の契約は原則として更新すると説明していたこと、雇用契約書には「契約の更新をすることもある」と記載されていたこと等から、契約が更新されると期待することに合理的な理由があり、雇止め法理が適用されると判断しました。
一方で、乗務員が会社からの配車指示に従わなかったことや、走行距離や売上が会社の定める目標に達したことがなく他の乗務員の平均売上の半分に満たないこと、会社が勤務方法を改善するように指導したにもかかわらず勤務方法を変えることなく勤務成績が上がらなかったこと等を考慮すると、雇止めには、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であるとして、雇止めを有効と判断しました。
この事案では、雇止め法理が適用されることを認めた一方で、乗務員の勤務成績や勤務態度等に問題があり、会社の指導にもかかわらず改善の態度をみせなかったことを認め、雇止めをされても仕方がないといえる理由があったとして雇止めを有効と判断しています。この事案で、会社は乗務員に対し、指導の際にこれまでの仕事ぶりを改めなければ雇用を更新しない旨のいわば「最後通告」を行っています。このように、雇止めを検討せざるを得ない事案では、単に指導するだけでなく、改善がなければ雇用を継続できない旨を示して指導することが重要です。
7,雇止めを無効とした裁判例
次に、裁判で雇止めが無効と判断された事例をいくつかご紹介します。
(1)契約更新を繰り返し約7年間雇用されていた契約社員に対する雇止めが無効と判断された事例
1,大分地方裁判所 平成25年12月10日判決(ニヤクコーポレーション事件)
有期労働契約を複数回更新し、約7年間継続して雇用されていた従業員が、会社から雇止めをされたことに対し、雇止めの無効と雇止め以降の賃金の支払いを求めた事例です。
裁判所は、有期労働契約が約7年にわたって継続して更新されていたことや、業務内容が正社員と同じであったこと、就業規則に反して契約更新の際に必ずしも面談が行われていたとは認められないこと、会社全体で有期労働契約の更新を拒絶された者がほとんどいないこと等から、会社と従業員との間の有期労働契約は、実質的に無期雇用契約と変わらないもしくは有期労働契約が更新されると期待することに合理的な理由があるとし、雇止め法理が適用されると判断しました。
その上で、会社の更新拒絶に客観的に合理的な理由があるとは認められず、雇止めは無効と判断しました。
(2)派遣社員に対する雇止めが無効と判断された事例
1,東京地方裁判所判決 令和3年7月6日(スタッフマーケティング事件)
派遣会社との間で有期労働契約をし、家電量販店で業務を行っていた派遣社員が、派遣会社から勤務態度等を理由に雇止めをされたことに対し、雇止めの無効と雇止め以降の賃金の支払いを求めた事例です。
この事案で、裁判所は、有期労働契約が5回更新されていること等を理由に、契約が更新されると期待することに合理的な理由があるとして、雇止め法理が適用されると判断しました。
その上で、雇止めの理由として会社が主張するような、他の従業員への恫喝的な言動や、業務上の指示に対する反抗、協調性の欠如といった問題があったことや、それに対して会社が注意や指導を行ったことを認めるに足る証拠がないため、雇止めに客観的に合理的な理由があるともいえないとして、雇止めを無効と判断しました。
この事案で、派遣社員が雇用されていた期間は約15ヶ月間で、雇用期間としては長くありませんが、裁判所は、契約が5回更新されていることを理由の1つにあげて雇止め法理を適用しています。通算の雇用期間が短くても、短期間の契約を何度も繰り返している場合は注意が必要です。
また、会社は、雇止めは、派遣社員の勤務態度不良が原因であると主張しましたが、それを裏付ける証拠がなかったことも、雇止めが無効と判断された理由の1つになっています。問題行動を理由に雇止めをする場合は、問題が起こるたびに始末書を提出させたり、書面やメール等の記録に残る形で注意や指導をしたり、懲戒処分を行う等、従業員の問題行動の記録や、それに対する会社の指導や注意の記録を残しておくことが重要です。
(3)能力不足や人員整理を理由とする雇い止めが無効と判断された事例
1,横浜地方裁判所判決 平成27年10月15日(エヌ・ティ・ティ・ソルコ事件)
有期労働契約が約17回更新され、勤続年数が15年7ヶ月に及んでいた有期労働労働者が、会社から能力不足や人員整理を理由に雇止めをされたことに対し、雇止めの無効と雇止め以降の賃金の支払いを求めた事例です。
裁判所は、勤務条件が常用労働者とほぼ変わらない内容だったことや、更新が繰り返され15年7ヶ月と長期間にわたって雇用されていたこと、更新手続きが形式的なものであったこと等を考慮すると会社と労働者の間の契約は実質的に無期雇用契約と変わらない状態であるとし、雇止め法理が適用されると判断しました。
そして、本件雇い止めは実質的な整理解雇にあたり、人員削減の必要性の程度が弱く、雇い止めを回避するための努力が不十分であること、会社の成績評価基準には問題があること、雇止めの理由の説明等が不十分であり手続の相当性を欠くことから、雇止めに客観的に合理的な理由があるともいえないとして、雇止めを無効と判断しました。
この事案は、雇止めの法理が適用されることを認めた上で、雇止めが実質的な整理解雇であるとして、整理解雇の有効性が判断されている事案ということができます。
整理解雇については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
▶参考情報:整理解雇とは?企業の弁護士がわかりやすく解説
8,雇止めの予告と雇止めの通知書【雛形ダウンロード付き】
ここまでは雇止め法理の内容についてご説明しましたが、次に、雇止めをする場合の手続きについてご説明しておきたいと思います。
契約社員の雇止めについては、以下の場合には、「雇止めの30日前に予告すること」が義務付けられています。
- ケース1:1年を超えて雇用を継続している場合
- ケース2:3回以上更新した後に雇止めする場合
ただし、あらかじめ更新しないことを契約社員に明示していた場合は、雇止めの予告義務の対象外です。
例えば、3年契約だが更新はないことを雇用契約書に明記したうえで採用したような場合がこれにあたります。
雇止めの予告は口頭でも可能ですが、予告をしたことを明確にするためにも下記のような雇止め通知書を本人に交付することをおすすめします。
▶参考情報:雇止め通知書ひな形は以下よりダウンロードしていただけます。
なお、この雇止めの予告をすれば、必ず雇止めが認められるわけではありません。
雇止めの予告はあくまで最低限の手続きにすぎず、雇止めが認められるかどうかは、予告をしたかどうかとは別に、雇止め法理に基づき判断されます。
雇止めについては、正社員の解雇と違い、解雇予告手当の制度はなく、また、30日前の予告が義務付けられる場合も限定されています。
しかし、予告が義務付けられていない場面でも雇止め法理のもとで雇止めについてトラブルが発生することはあり得ます。
雇止めがトラブルに発展することを避けるためには、予告が義務付けられる場面に該当しないときでも、次回の更新ができないことが分かった時点で契約社員にそのことを伝えておくことが重要です。
9,雇止め法理を踏まえた労務管理上の対策
最後に、ここまでご説明した雇止め法理の内容を踏まえた、契約社員についての労務管理上の対策や注意点を整理しておきたいと思います。
契約社員については会社の仕事量が減ったときは雇止めをしたいと考えておられる会社が多いと思います。つまり、契約社員は雇用の調整弁であるという考え方です。
その場合は、日ごろから、契約社員の労務管理について、以下の点に注意して、雇止め法理が適用されないように対策しておくことが必要です。
(1)契約社員の労務管理についての注意点
対策1:
契約社員との契約更新の際には、必ず更新日より前に次の雇用契約書を作成すること
対策2:
雇用契約の内容は更新時の状況に応じて契約社員と協議して決めるようにし、漫然と更新前と同じ内容で更新しないこと
対策3:
契約社員と正社員の仕事内容の違いを明確にし、契約社員にはできるかぎり臨時的な仕事に従事してもらうようにすること
契約社員が所属する部署の業務が年々縮小されていることなどから、契約社員は臨時的な業務を担当していたのであって、業務として継続性のあるものではなかったとして、雇止めを適法と判断したケースとして、NTT東日本事件(札幌地方裁判所平成24年9月5日判決)があります。
▶参考情報:契約社員の雇用契約書については以下の記事で詳しくご説明していますので参考にしてください。
対策4:
契約社員の契約更新に年数の上限を設けたうえで、正社員への登用試験に合格した優秀者のみ正社員に登用するなどの制度を整備し、試験に合格しない限りは、年数の上限が来たら雇止めになることをあらかじめ明確にしておくこと
最高裁は就業規則で契約職員の更新上限を3年としたうえで、使用者が必要とし職員が希望する場合は無期契約に転換すると定められた事案において、無期契約への移行は使用者が希望した場合に限られることが規定上明確であり、使用者が希望しない場合に、3年の更新限度期間満了により無期契約に移行したとはいえないと判断しています(平成28年12月1日最高裁判所判決)。また、契約社員の契約更新について3年の上限を設けたうえで、正社員への登用試験に合格した優秀者のみ正社員登用するという制度を導入していたケースでは、雇止めは適法と判断されています( 高知県公立大学法人事件 平成30年3月6日高知地裁判決)
また、雇止めの場面でもトラブルにならないようにすためには、以下の点が重要です。
対策5:
次回の契約を更新しないことがわかった段階で契約社員に伝え、契約社員に次の仕事を探す期間的余裕を与えること
対策6:
一方的に雇止めの予告をするのではなく、雇止めになる理由を契約社員に説明し、できる限りの納得を得るように努力すること
以上の対策が自社の労務管理においてできているかチェックしておきましょう。
10,雇止め法理に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、契約社員の雇止めについての咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容をご紹介したいと思います。
咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。
- (1)雇止めに関するご相談
- (2)雇止めに関するトラブルの対応
- (3)契約社員の雇用契約書の整備
- (4)契約社員用就業規則の整備
- (5)契約社員の労務管理に関するご相談
以下で順番にご説明したいと思います。
(1)雇止めに関するご相談
この記事でもご説明したとおり、雇止めに当たっては雇止め法理に照らして問題がないかを十分に検討する必要があります。雇止め法理への対策を怠ると、裁判で雇止めが無効とされてしまい、多額の金銭を支払うことにもなりかねません。
咲くやこの花法律事務所では、雇止めに関する企業からのご相談を随時承っております。労務に精通した弁護士が、御社の事情を踏まえ、雇止め法理への対策や適切な雇止め手続について的確にアドバイスいたします。
咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士への雇止めに関する相談料
●初回相談料:30分あたり5000円
(2)雇止めに関するトラブルの対応
雇止めをした場合、その契約社員は失業することになるため、労務管理の中でもトラブルになりやすい分野のひとつです。トラブルになった場合は適切に対処しなければ、裁判にまで発展し、会社に大きな損害を及ぼすことも起こり得ます。
雇止めに関するトラブルが生じたときは、ぜひ咲くやこの花法律事務所に対応をご依頼ください。労働事件の経験豊富な弁護士が迅速に対応し、適切な解決を実現します。
咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士への雇止めに関するトラブル対応料金
●着手金:15万円~
(3)契約社員の雇用契約書の整備
雇止めを適切に行うには、正しい労務管理が求められます。特に重要となるのが、雇用開始時と契約更新時に雇用契約書をそれぞれしっかりと作成することです。
ここでの「しっかりと作成する」とは、形式的に雇用契約書を作るのではなく、契約社員と協議した内容を反映させて、更新時の状況に応じた雇用契約書を作るという意味です。
形式的な雛型での対応には無理が生じ、自社独自の雇用契約書を作る必要も出てくるでしょう。
その際は、自社のみで対応せず、弁護士に依頼されるのがおすすめです。咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、労務管理に強い弁護士が雇止め法理への対策を踏まえた雇用契約書を整備することができます。
少しでも不安がある方はお気軽にご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士への契約社員の雇用契約書作成の費用
●雇用契約書作成費用:3万円~
(4)契約社員用の就業規則の整備
咲くやこの花法律事務所の労務に精通した弁護士が、企業に個別の事情を踏まえて、契約社員用の就業規則の作成、変更案の作成、労働基準監督署への変更届の提出をサポートします。
就業規則は、裁判の現場でも使用するものですので、実際に労務裁判を経験している弁護士が作らなければ実効性のあるものにしあげることができません。また、就業規則の整備と関連して、雇用契約書の内容は就業規則の労働条件を下回ってはならないという大前提があります。契約社員用の就業規則の整備と並行して、雇用契約書その他各種規定の変更が必要な場合も、弁護士が変更案を作成したうえで、実際の運用面のアドバイスをします。
契約社員用の就業規則を整備しておくことは、労務環境の整備事項の中でも重要なポイントになります。
いざトラブルになったときに就業規則の不備により企業が不利益をうけるケースも多いため、対応に不安がある方は、ぜひ労務管理に強い咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士への契約社員の就業規則作成の費用
●就業規則作成費用:20万円~
(5)契約社員の労務管理に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、企業の経営者の方から、契約社員の労務管理のご相談を常時承っています。
契約社員の労務管理については、今回ご紹介した雇止め法理に関する問題や、雇用契約書・就業規則の整備、雇用期間が5年を超える契約社員について適応される無期転換ルールへの対応など、様々な観点から労務環境の整備を行う必要があります。
労務管理に強い咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談いただくことで、契約社員の労務管理を安心して行っていただけるようサポート致します。
咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士への契約社員の労務管理に関する相談料
●初回相談料:30分あたり5000円
11,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
咲くやこの花法律事務所の雇止めの対応については、「労働問題に強い弁護士サービス」もご覧下さい。
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
12,雇止め法理についてのお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
契約社員の雇止めの対応に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
13,まとめ
今回は、契約社員の雇止め法理について、雇止め法理が適用されるかどうかの判断基準、雇止め法理と更新回数との関係を労務管理に強い弁護士がご説明しました。
また、雇止め法理が適用される場合に、雇止めが認められる合理的な理由についての考え方もご説明しています。
そして、最後に雇止めの予告に関するルールや労務管理上必要な対策について確認しました。
契約社員について、正しい労務管理上の対策ができていないときは、今回ご説明した雇止め法理が契約社員に適用されてしまい、契約社員を契約期間終了で雇止めすることが難しくなります。
そうすると、会社の仕事量が減ったときに契約社員を雇止めして雇用調整することができなくなり、余剰人員をかかえて経営が行き詰まることになります。
一方、無理に雇止めしようとすると冒頭でご紹介したような裁判トラブルに発展し、会社が数百万円もの支払いを命じられるケースが増えています。
このような事態にならないように、この記事でご紹介した6つの対策は必ず行っておきましょう。
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年5月18日
 06-6539-8587
06-6539-8587