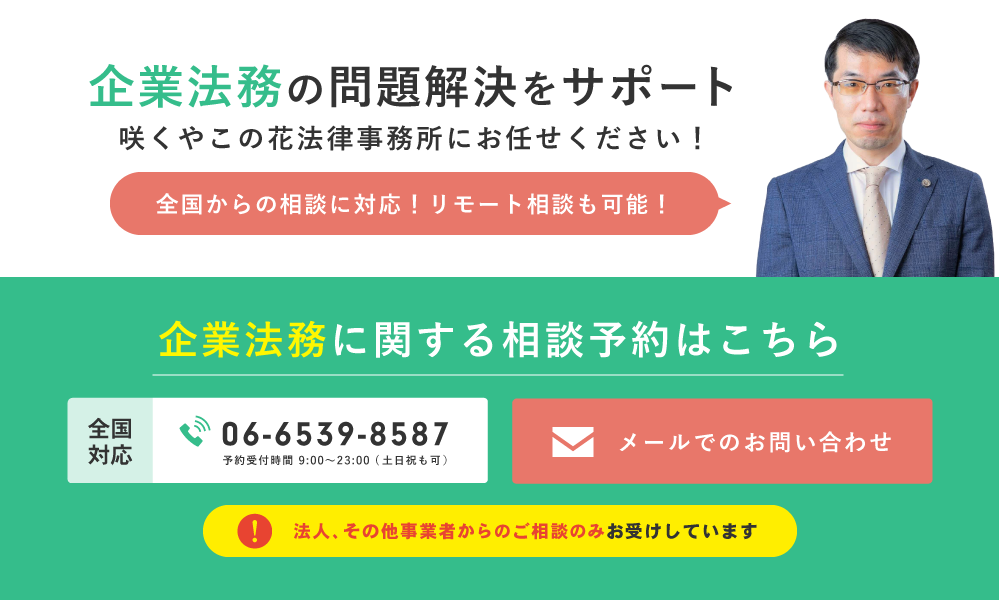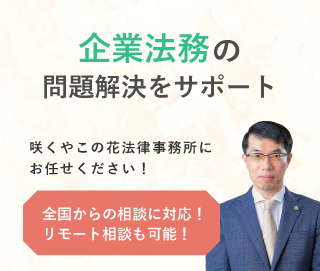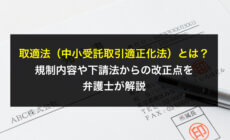みなさん、こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自社の破産を考える場面では、破産のデメリットについて心配になることが多いと思います。
「なんとなく怖い…」と思っていたり、「債権者にどなられるんじゃないか」と心配になって踏み切れないという人もいるのではないでしょうか?
それはあくまでイメージであり、現実とは違っています。
テレビで話題になるような事件がらみの破産では債権者がどなりこんできて混乱することもありますが、通常の会社の破産では債権者集会に債権者が来ることはほとんどありません。
破産は法律上の制度であり、裁判所で行われますので、必要以上に恐れたり不安になる必要はありません。
では、破産のデメリットというのは実際にはどういうものがあるのでしょうか?
この記事では法人破産によるデメリットについてわかりやすく解説します。
破産について弁護士にご依頼いただいた後に以下のようなご感想をよくいただきます。
- 「債権者の督促がきつく、家にも帰れない日が続いたが、弁護士に依頼して通知を出したことにより、督促が止まり、家に帰れるようになった。」
- 「一人で悩んでいないでもっと早く相談すれば、家族にも迷惑をかけなかった。」
悩んでおられる場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
▶参考情報:法人破産(会社破産)に関する弁護士への相談サービスはこちら
【注】財産を隠して破産の手続きをすることは法律上厳罰が科されます。咲くやこの花法律事務所ではご依頼後に財産を隠していたことが判明した場合は、委任契約を解除していますので、ご承知おきください。
▶参考:咲くやこの花法律事務所の法人破産に関する解決実績を以下で紹介していますのでご参照ください。
▶参考動画:この記事の弁護士 西川暢春が、「代表者が会社を破産させる場合の4つのデメリット」を動画で詳しく解説しています。
▼【関連情報】法人破産については、こちらの関連情報も合わせてご覧下さい。
・会社の解散から清算まで。会社の廃業の流れをわかりやすく解説
▼法人破産に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,代表者も破産が必要になることがある

法人破産のデメリットで一番注意しなければならないのが、代表者も破産しなければならなくなる可能性があるという点です。
具体的には、法人に金融機関などからの借入金があり、これを代表者が連帯保証しているケースなどが典型例です。
この場合、法人が破産すると、金融機関は連帯保証人である代表者に請求をしてきます。そのため、代表者個人としても自己破産が必要になるのです。
代表者個人が破産する場合、個人で所有する不動産や預金、生命保険などの資産が債権者への配当にあてられ、失われます。
ただし、完全に全ての資産を失うわけではなく、「自由財産」といって、99万円以下の範囲で現金は手元に残すことができます。
一方、以下のようなケースでは、法人が破産しても代表者個人が破産する必要はありません。
- 代表者個人が連帯保証している法人の債務がない場合
- 代表者個人が連帯保証している法人の債務があっても金額的にわずかで個人で返済できる場合
- 代表者個人が連帯保証している法人の債務があっても、債権者が分割払いに応じて返済を待ってくれる場合
(1)代表者以外への波及にも注意
法人の破産は、代表者以外にも波及する可能性があります。
具体的には以下のようなケースです。
- 法人の債務を代表者以外も連帯保証している場合、その連帯保証人も破産が必要になる可能性があります。
- 法人破産で代表者も破産する場合、代表者個人の住宅ローンなどを連帯保証していた代表者の配偶者や家族も破産が必要になる可能性があります。
法人破産を検討するにあたっては、法人破産と一緒に破産しなければならない人がどの範囲になるかを事前に検討しましょう。
「法人が破産した場合に代表者はどうなるのか?」については、以下の動画や記事で詳しく解説していますので、ご覧下さい。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「法人破産(会社倒産)で代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?」を動画で詳しく解説しています。
2,会社が消滅し、従業員の解雇が必要になる

法人破産のデメリットの2つ目は、会社が消滅し、従業員の解雇が必要になることです。
これまで築きあげた会社の社歴や信用、ブランドが失われますが、ブランドは他社に譲渡したり、新会社を設立して引き継ぐことも可能です。また、従業員全員を解雇する必要があります。
法人破産のための事務処理を代表者1人でこなすことが難しい場合は、解雇後に従業員にアルバイトをしてもらい、事務処理を手伝ってもらうことが可能です。
▶参考情報:法人破産による従業員の解雇の場面ではトラブルになりやすいです。以下の記事や動画では、法人の破産や倒産での解雇の注意点について詳しく解説していますので参考にしてください。
この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「会社の破産・倒産での解雇の注意点!解雇予告手当や給与、進め方」を動画で詳しく解説しています。
3,代表者の信用情報に傷がつく
法人破産のデメリットの3つ目が、代表者の信用情報に傷がつくという点です。
法人を破産させた後に、再度新会社を起こして再起する経営者も多いですが、金融機関は会社を破産させた経営者にはなかなか融資してくれません。
そのため、しばらくは融資を受けなくてすむビジネスを考えたり、あるいは別の人に社長になってもらって会社を再起することが必要になります。
最近は個人的に資金の出資を受けたり、クラウドファンディングなど新しい資金集めの手法により、融資をうけないでビジネスを軌道に乗せる人が増えていますので、融資が受けられなくても再度会社を始めることは十分可能です。
4,破産手続き中は裁判所への出廷が必要

法人破産のデメリットの4つ目が、裁判所への出廷が必要になることです。
法人破産の手続きは1年程度かかることが通常です。
その間、経営者自身が弁護士と一緒に裁判所に出廷しなければならない場面が何度かあります。
2か月に1回程度の頻度で、1回あたりの時間も1時間以内になることがほとんどですので、大きな負担になるわけではありません。
出廷して行われるのは、主に破産管財人が進めていく事務処理の確認といったような内容になることが多く、精神的に負担になるようなものは通常ありません。
ただし、裁判所の手続きは平日行われますので、もし破産申し立て後に会社員として就職する場合は、平日に出廷のために会社を休むことについて就職先に理解を求めておく必要があります。
破産手続きについては、以下の動画で詳しく解説していますので、ご覧下さい。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「法人破産(会社の倒産)の手続きの流れ」を動画で詳しく解説しています。
5,法人破産にはメリットもある
ここまで、法人破産のデメリットを解説しましたが、法人破産についてはメリットのほうが大きいです。
以下で主なメリットを見ていきましょう。
(1)全ての借金から解放される
最大のメリットは全ての借金から解放されることです。
法人破産にかかる費用は最も簡易なケースで80万円以上、一般的な事案では150万円~500万円程度かかることが多いですが、一方で何千万あるいは何億とある債務をゼロにすることが可能です。
これに対して、もし破産ではなく、民事再生やリスケジュールといった手段をとる場合は、これまでの債務の一部または全部を将来にわたって分割して支払っていく必要があります。
つまり、破産のように債務をゼロにするというメリットは得られません。
なお、借金から逃れるために破産ではなく夜逃げをする人もいますが、これは絶対にやめるべきです。夜逃げしても、正式に破産手続きをするまで借金からは解放されません。
場合によっては債権者に夜逃げ先が判明して財産を差し押さえらますし、そうならなくても、財産をもつと債権者に差し押さえられる危険があるため住居などを一切購入せずに生きていかなければならないことになってしまい、生活の様々な面で制約が生じ、家族にも迷惑をかけることになります。
破産申し立てを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対して破産の申し立ての依頼を受けたことを文書で通知します。これを受任通知といいます。受任通知を債権者に送った後は、債権者への支払いを停めることになります。債権者からの取り立てもとまります。これにより、これまで支払いに回っていたお金が会社にプールされるようになりますので、そこから破産の費用を作ることも可能です。また、支払いに追われなくなり、心理的にもゆとりができます。
(2)再度会社を起こすことは可能
裁判所に破産の申し立てをすると破産開始決定がでます。
そして破産開始決定後は破産手続きのためだけに存在する会社となり、この会社で事業を続けることはできません。
しかし、破産手続きと並行して、別の会社を起こして、今と同じ事業を続けることは可能です。
代表者個人がいったん破産していても、再度社長になることは可能です。さらに、破産させた法人のお客さんや従業員がついてきてくれるのなら、新しい会社で再度契約しなおすことも可能です。
【注】ただし、破産させる会社から無償で顧客や取引先を引き継ぐ行為については、本来は価値のある事業を無償で譲り受けることにより破産会社に損害を発生させたとして、損害賠償を命じた判例もありますので注意が必要です(大阪高等裁判所平成30年12月20日判決)。
今の会社を軌道に乗せるのが難しければ、正式に破産の手続きをして、別会社を設立し再スタートを切ることも方法の1つです。
(3)今後稼いだ利益を自由に利用できる
現在破産を検討中の会社において、売上や利益を上げても、後日に破産すれば、稼いだ売上や利益は最終的には債権者に分配されてしまいます。
一方、いまの会社を早期に破産させて、別の会社で事業をする場合、別会社で稼いだ売上や利益はあなたが自由に利用することができます。
このように考えると、法人の破産をするのは早ければ早いほどメリットが大きいです。
破産するまではいくら頑張って稼いでも、それは破産の時に債権者に分配されてしまいます。
6,法人破産に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では会社の破産に関するご相談を常時、会社経営者の方々から承っています。
破産を考える場面では不安が大きいと思いますが、ご相談いただくと不安が解消され、進むべき道が明確になります。
法人の破産に精通した弁護士が対応しますので、会社の破産をお考えの方はぜひ早めにご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の法人の破産に強い弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所の法人破産に関するサポート内容は、「法人破産(会社破産)に強い弁護士」のこちらをご覧下さい。また、お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,まとめ
今回は法人破産のデメリットとして、以下の4点をご説明しました。
- 代表者も破産が必要になることがある
- 会社が消滅し、従業員の解雇が必要になる
- 代表者の信用情報に傷がつく
- 破産手続き中は裁判所への出廷が必要
そのうえで、メリット面もご説明しています。
破産すると借金がゼロになり、また一からやり直したときに、その売上や利益を借金の返済に回さなくて済むという点で、法人破産には大きなメリットがあるといえるでしょう。
法人の破産について弁護士にご依頼いただいた後に以下のようなご感想をいただくことが多いです。悩んでおられる場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
- 債権者の督促がきつく、家にも帰れない日が続いたが、弁護士に依頼して通知を出したことにより、督促が止まり、家に帰れるようになった。
- 労使対立が厳しかったが、破産して、新会社としてやり直すことで事業が落ち着いた。
- 親族の中に破産に反対する人もいたが、弁護士の援助を受けて、取締役会を上手く乗り切り、体力があるうちに破産申立を進めることができた。
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2025年7月8日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」法人破産に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587