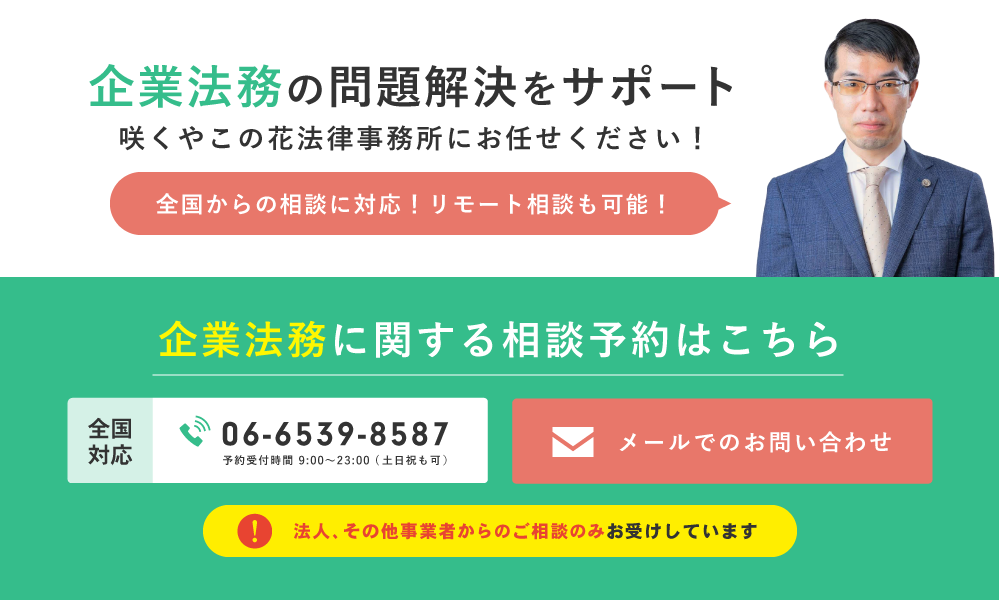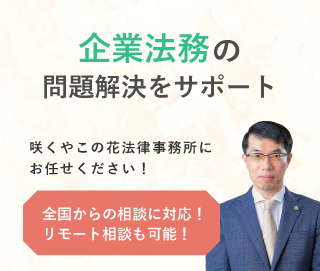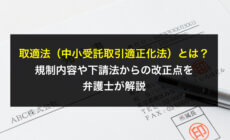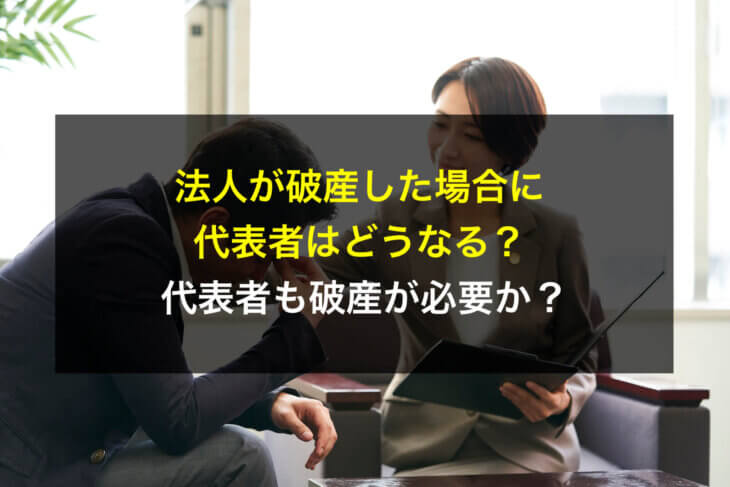
こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自分の経営する会社を破産させた場合、代表者個人はどうなるのでしょうか?
代表者個人についても破産が必要なのかどうか、破産する場合の費用はどうなるのか、生活はどうなるのかなど心配される方も多いと思います。また、会社を破産させたことについて個人責任を問われないか心配されるケースもあると思います。
今回は「法人が破産した場合に代表者はどうなるのか?」について代表者の不安や疑問にわかりやすく回答します。
それでは見ていきましょう。
破産について弁護士にご依頼いただいた後に以下のようなご感想をよくいただきます。
- 「債権者の督促がきつく、家にも帰れない日が続いたが、弁護士に依頼して通知を出したことにより、督促が止まり、家に帰れるようになった。」
- 「一人で悩んでいないでもっと早く相談すれば、家族にも迷惑をかけなかった。」
悩んでおられる場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
▶参考情報:法人破産(会社破産)に関する弁護士への相談サービスはこちら
【注】財産を隠して破産の手続きをすることは法律上厳罰が科されます。咲くやこの花法律事務所ではご依頼後に財産を隠していたことが判明した場合は、委任契約を解除していますので、ご承知おきください。
▶参考:咲くやこの花法律事務所の法人破産に関する解決実績を以下で紹介していますのでご参照ください。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「法人破産で代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?」を動画で詳しく解説しています。
▼法人破産に関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,連帯保証している場合は代表者も破産が必要になることが多い
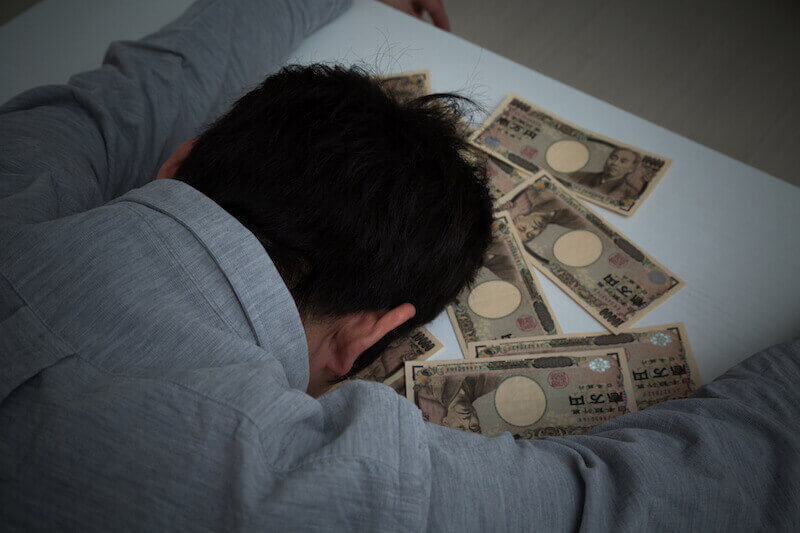
結論から言うと、代表者個人が法人の債務の連帯保証人になっている場合、個人としてその債務の支払いができなければ、代表者個人も破産が必要になります。
(1)代表者個人が破産が必要なケース例
例えば、法人が金融機関から融資を受けている場合は、融資の際に代表者が連帯保証人なっているケースが多いです。その場合、法人を破産させれば、金融機関から代表者に請求が来ることになります。そのため、通常は代表者個人も破産が必要です。
(2)代表者個人が破産する必要はないケース例
一方、以下のようなケースでは、法人を破産させても代表者個人が破産する必要はありません。
- 代表者個人が連帯保証している法人の債務がない場合
- 代表者個人が連帯保証している法人の債務があっても金額的にわずかで個人で返済できる場合
- 代表者個人が連帯保証している法人の債務があっても、債権者が分割払いに応じて返済を待ってくれる場合
(3)代表者が破産するとどうなるか?
代表者個人が破産する場合、個人で所有する不動産や預金、生命保険などの資産が債権者への配当にあてられ失われます。ただし、完全に全ての資産を失うわけではなく、「自由財産」といって、99万円以下の範囲で現金は手元に残すことができます。
▶参考情報:自由財産とは?
自由財産とは個人が破産をした場合でも、生活のために手元に残すことが認められる財産をいいます。原則として、「99万円以下の現金」と「差押禁止財産(衣類や寝具などの生活必需品)」が自由財産とされています。
ただし、手元の現金が99万円よりも少ない場合は、「自由財産の拡張」という手続きをとることによって、自動車や生命保険を手元に残すことが可能です。この場合は、現金と現金以外の財産(自動車や生命保険など)をあわせて99万円以内にすることが原則として必要です。
また、代表者が住宅ローンを組んでいて、その住宅ローンについて、代表者の配偶者が連帯保証しているようなケースでは、代表者の破産後に配偶者に住宅ローンの請求が来ます。そのため、代表者の配偶者も破産が必要になるケースがあります。
2,代表者が破産する場合の手続きの進め方
代表者が破産する場合は、通常は経営している法人と一緒に破産の申し立てをします。このように、法人と代表者が同時に破産申し立てをすることにより、破産にかかる費用を節約することができます。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
手順1:弁護士への相談
まず、弁護士への相談時に、弁護士が代表者個人の債務の内容や資産の内容をヒアリングし、破産手続きの進め方について方針を決定します。
なお、破産申し立てにおける弁護士の役割については以下のページ内の「サポート内容」をご参照ください。
手順2:債権者に破産予定であることを通知
破産の方針が決まったら、債権者に破産予定であることを通知します。通知は弁護士から文書で行います。
手順3:申立書や必要書類を準備する
破産申し立てのための申立書や必要書類を準備します。法人と代表者個人が同時に破産申し立てをする場合は、法人の資料と、代表者個人の資料を段取り良く準備していくことが必要です。
代表者個人の破産に必要な書類については、以下を参考にご覧下さい。
1,代表者個人の破産の必要書類一覧
- 預金通帳(過去2年分を記帳したもの)
- 源泉徴収票
- 不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 自宅や駐車場等の賃貸(賃借)している場合は賃貸借契約書
- 有価証券、ゴルフ会員権がある場合は、その証券のコピー
- 訴訟がある場合は、訴訟関係資料のコピー
- 個人で生命保険に加入している場合は証書と解約返戻金計算書のコピー
- 個人で自動車を所有している場合は、車検証、価格査定書のコピー
- 債権関係資料(金銭消費貸借契約書等)
- 家計収支表(2ヶ月分)
また、法人の破産に必要な書類については以下の「法人破産の手続きの流れを8つのステップで解説します。」の記事内をご覧下さい。
手順4:裁判所に破産の申し立てをする
申立書と必要書類がそろったら、弁護士が裁判所に提出して、破産の申し立てをします。
手順5:破産管財人が代表者の財産を売却し、配当する
破産申し立て後に裁判所は「破産管財人」を選任します。
代表者個人に不動産などの財産がある場合は、破産管財人がその売却を担当します。売却により代表者個人の財産が換金され、債権者への配当が行われます。
手順6:免責許可決定
配当が終わった後に、代表者個人に債務の支払い義務を免除する決定を裁判所が行います。これを「免責許可決定」といいます。
これにより、代表者の債務について支払い義務がなくなります。
以上が、代表者個人の破産手続きのおおまかな流れになります。
一般的には代表者個人の破産手続きは、法人の破産手続きよりも短期間で終わることが多く、早ければ破産申し立て後3か月程度で終了します。
なお、法人の破産手続きについては以下の動画と記事を参照して下さい。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「法人破産(会社の倒産)の手続きの流れ」を動画で詳しく解説しています。
3,代表者が破産する場合の弁護士費用と予納金

法人の代表者が破産する場合、法人と同時に破産申し立てをすることが通常です。これは、法人と代表者が同時に破産を申し立てることにより、破産にかかる費用を少なくすることができるためです。
法人と代表者が同時に破産申し立てをする場合の最も簡易なケースの費用は以下の通り合計約130万円です。
※具体的な金額は、資本金、資産及び負債の額、債権者その他関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて大きく異なります。
法人と代表者が同時に破産申し立てをする場合の費用例(最も簡易なケース)
- 弁護士費用(法人分):50万円+税
- 弁護士費用(代表者個人分):40万円+税
- 裁判所予納金や官報公告費:23万円~24万円程度
- 実費:3万円~5万円程度
4,自社を破産させる場合の代表者の責任
最後に、自社を破産させた代表者の責任についてもご説明しておきたいと思います。
経営に失敗して自社を破産させても、代表者個人の責任を問われることは原則としてありません。これは経営というのは失敗もつきものであり、結果責任ではないという考えによるものです。
例外的に経営者個人の責任が問われるのは以下のようなケースです。
- 法人の事業の中で、顧客や取引先をだますなど詐欺的な行為があった場合
- 資産を隠して破産しようとするなど、破産のルールに違反した場合
- 明らかに不合理な経営判断により、株主に損害を与えた場合
このような例外的なケースを除いて、代表者の責任が問われることはありません。
(1)債権者集会への出席は必要
前述の通り、通常は代表者の個人責任は問われませんが、それでも代表者には裁判所で法人の破産の経緯や資産状況を説明する責任はあります。
具体的には、以下のことが必要です。
- 裁判所が開催する債権者集会などの期日に出席する
- 裁判所が選任する破産管財人からの質問に回答する
法人破産の手続きは1年程度かかることが通常です。その間、債権者集会が何度か開かれます。この債権者集会には代表者が出席しなければなりません。債権者集会で行われるのは、主に破産管財人が進めていく事務処理の確認といったような内容になることが多く、精神的に負担になるようなものは通常ありません。
債権者が来て怒鳴り散らすといったようなこともめったにありません。また、債権者集会には弁護士も一緒に出席しますので、あまり心配する必要はないでしょう。
5,破産後に再度起業することは可能
代表者個人が破産した場合であっても、破産後に再度、社長として起業することは可能です。
ただし、金融機関は、社長に破産歴があると、融資をしてくれない傾向がありますので、融資を受けなくても成立するビジネスを検討する必要があります。あるいは、金融機関以外のところから出資などの方法により資金を得て起業するという選択肢もあります。
今の会社を軌道に乗せるのが難しければ、正式に破産の手続きをして、別会社を設立し再スタートを切ることも方法の1つです。
6,法人破産に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では会社の破産に関するご相談を常時、会社経営者の方々から承っています。
破産を考える場面では不安が大きいと思いますが、ご相談いただくと不安が解消され、進むべき道が明確になります。まずは、弁護士に依頼して債権者に破産の通知を出すことで、債権者への支払いを止めて、金銭的、心理的な余裕を取り戻すことが重要です。
法人の破産に精通した弁護士が対応しますので、会社の破産をお考えの方はぜひ早めにご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の法人の破産に関する弁護士への相談料
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせする方法
咲くやこの花法律事務所の会社破産に関するお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
7,まとめ
今回は、法人を破産させる場合の代表者の責任や代表者も破産する場合の手続きについてご説明しました。
法人を破産させるに伴って代表者個人も破産しなければならないケースでは、代表者個人の資産も失われるため、生活への影響も大きくなります。
しかし、そうだからといって、債務超過の会社で頑張って仕事をして利益をあげても、それは債権者への支払いに消えてしまい、手元に残ることはありません。破産の手続きをして借金を整理し、新しいスタートを切ることは、破産後の稼ぎを自由に利用できるようになるという大きなメリットがあります。
また、最後に触れましたように、破産の手続きをしても、代表者が再度会社を起こし、事業を再スタートするということはもちろん可能です。
8,【関連】法人破産に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「法人が破産した場合に代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?」についてわかりやすく解説しました。会社の破産や倒産については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連する会社の破産や倒産のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・会社の破産とは?手続きや必要な費用についてわかりやすく解説
・会社の破産や倒産での解雇の注意点!解雇予告手当や給与、進め方を解説
・会社の解散から清算まで。会社の廃業の流れをわかりやすく解説
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年7月8日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」会社の破産に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587