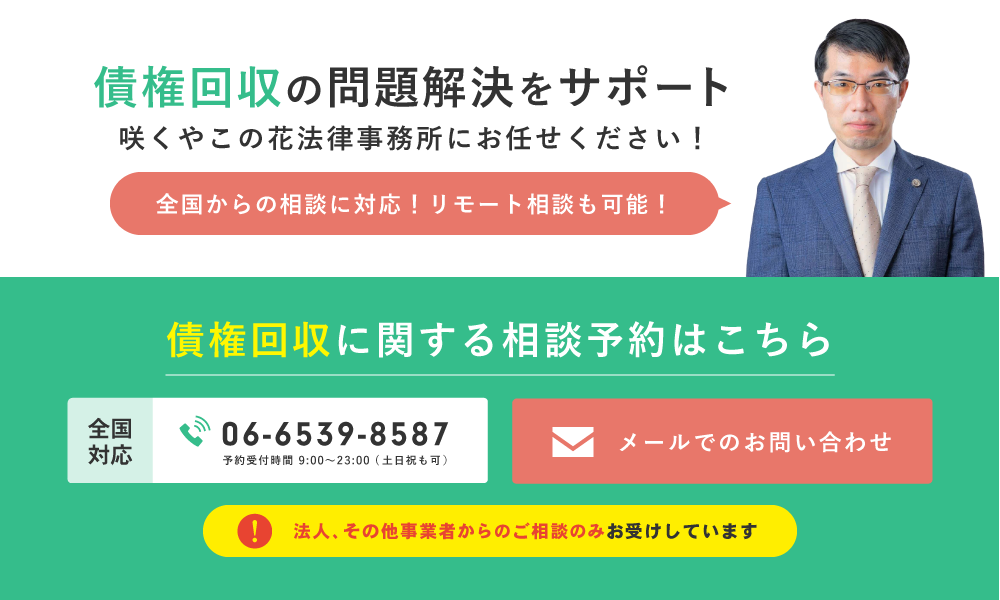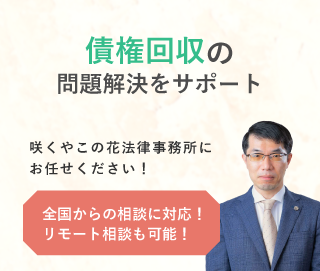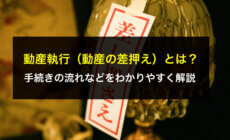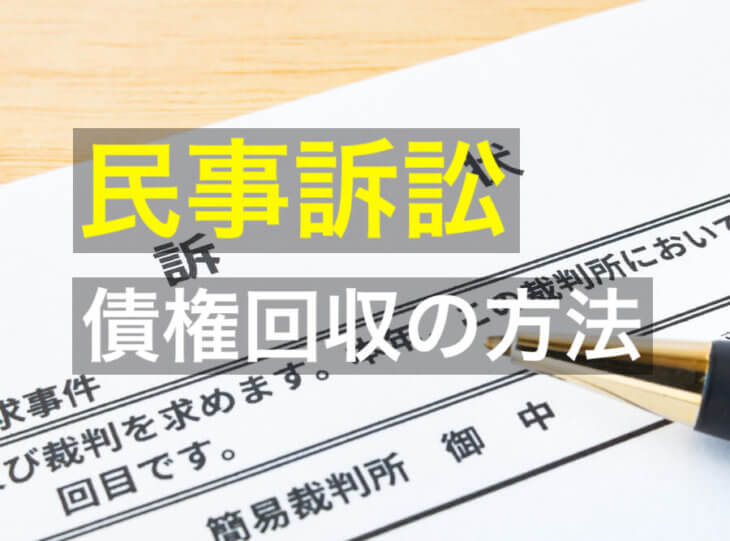
こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の代表弁護士西川暢春です。
支払が遅れている売掛金の回収や工事代金未払いへの対応の場面で、債権回収のために民事訴訟を検討するケースも多いと思います。
民事訴訟は債権回収を実現する強力な手段の1つですが、単に訴訟に勝つことだけでなく「回収」までを見据えた戦略設計をしておくことが重要です。
特に、訴訟で裁判所から支払を命じられても支払をしてこない相手方あるいは支払ができない相手方もいることも踏まえて、訴訟を起こす前の段階から、勝訴後に相手の財産を差し押さえるための戦略をたてておくことが必要です。
この点がおろそかになると、勝訴判決をもらっても、相手の財産を差し押さえるなどして回収することができず、債権回収が失敗に終わってしまいます。
この記事では、債権回収に民事訴訟を利用することのメリット・デメリットをご説明したうえで、訴訟による債権回収の流れ、弁護士への委任のポイント等についてご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在自社でかかえている債権回収のトラブルの問題に対して、訴訟をまじえた回収までの戦略設計のもと、解決に向けて動き出すことができるようになります。
なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でご説明していますのでご参照ください。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」の動画で、法的手段の方法として訴訟など具体的な流れについてを解説しています。
▶債権回収に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,債権回収で民事訴訟を利用するメリットとは?
債権回収で民事訴訟を利用するメリットとしては以下の点があげられます。
- (1)支払を拒否する債務者に対して判決による決着をつけることができる
- (2)判決を得れば差押えが可能
- (3)和解を促す効果もある
それぞれのメリットについて、順番に解説していきます。
(1)支払を拒否する債務者に対して判決による決着をつけることができる
債権回収のご相談をいただくケースの中には、債権の額について相手と意見の食い違いがあったり、相手から何らかのクレームをつけられ支払いを拒否されているケースも少なくありません。
そのような場合でも、裁判所が、相手の主張についての判断を強制的に下し、相手に支払義務があるかどうかを判断してくれる点が、民事訴訟のメリットです。
話し合いでは解決できない相手に対し、裁判所の判決により、決着をつけることが可能です。
(2)判決を得れば差押えが可能
裁判所の判決が出ても、相手が支払いをしない場合、裁判所に強制執行の申し立てをすることで、相手の財産を差し押さえることが可能です。
相手の財産を差し押さえることができることは、「執行力」と呼ばれる判決の重要な効力の1つです。
例えば、相手の預金を差し押さえることにより、相手の銀行預金から直接支払いを受けて、債権を回収することが可能です。
また、相手が不動産を所有している場合はこれを差し押さえて競売にかけることによって支払を得ることが可能です。
(3)和解を促す効果もある
訴訟というと「判決」をイメージしがちですが、令和元年の統計では、地方裁判所で行われる訴訟のうち、約38%が和解により終了しています。
債権回収についての民事訴訟での和解は、基本的に、相手との間で支払義務がある金額について合意したうえで、それを一括または分割で支払うことを相手に約束させる内容になります。
和解に至った場合は、財産の差押えなどをしなくても、相手による支払いが期待できるため、和解を促す効果があることも、債権回収のために民事訴訟を利用する大きなメリットの1つになります。
2,民事訴訟利用のデメリットとは?
一方で、民事訴訟を起こす場合は以下のようなデメリットもおさえておく必要があります。
- (1)勝訴したからといって債権回収が成功するとは限らない
- (2)訴訟に要する期間
- (3)訴訟に要する労力
- (4)訴訟に要する費用
それぞれのデメリットについて、順番に解説していきます。
(1)勝訴したからといって債権回収が成功するとは限らない
勝訴判決をもらっても、実際には支払いが得られないケースは決して珍しくありません。
支払いを命じる判決を受けても相手が支払わないときは、相手の財産を差し押さえて、支払を得ることが必要です。
相手の財産を差し押さえるためには、相手の財産を調査し、裁判所で差押えの手続きをする必要あります。
裁判所で相手の財産を調べてくれるわけではありませんので、差押えの対象財産を見つけるために、弁護士に依頼して、相手の預金残高や預金履歴あるいは所有不動産などの調査を進めていく必要があります。
勝訴しても相手から支払いがされない事態を避けるためには、訴訟の前に、相手の預金等を引き出せなくする「仮差押え」を行うことが効果的です。
この「仮差押え」については以下でご説明していますのでご参照ください。
(2)訴訟に要する期間
訴訟は時間がかかることもデメリットです。
令和元年の統計では、金銭の支払いを求める訴訟についての地方裁判所の第1審の審理期間は以下の通りとなっています。
地方裁判所の第1審の審理期間
- 6ヶ月以内:44%
- 6ヶ月を超えて1年以内:25%
- 1年を超えて2年以内:23%
- 2年を超える:8%
▶参照元:裁判所の司法統計より
この統計を見ると6ヶ月以内に終わっているケースも多いですが、短期間で終わっている訴訟は相手が欠席していることが原因であることが多いことに注意が必要です。
相手が出席して対応する事件では、少なくとも6ヶ月~1年の審理期間が必要であることがほとんどです。
民事訴訟の中でも、以下のようなケースでは、特に審理が長期化する傾向にあります。
- 工事代金の回収の場面で相手が工事の瑕疵を主張して反論してくるケース
- システム開発代金の回収の場面で、相手が納品したシステムの瑕疵を主張して反論するケース
- 債権回収の対象となる代金について契約書あるいは注文書・注文請書が作成されておらず、契約内容の立証に労力を要するケース
(3)訴訟に要する労力
訴訟では、自分の主張を裁判官に理解してもらうための書面の提出、自分の主張を根拠づけるための証拠の整理と提出を進めていくことになりますが、これらは相当程度の労力を要します。
訴訟は弁護士に依頼することが通常ですが、その場合も事実関係を把握しているのは依頼者自身であるため、依頼者自身が負担する労力も小さくありません。
この点を踏まえたうえで、民事訴訟に踏み切るかどうかを決める必要があります。
(4)訴訟に要する費用
訴訟は審理期間も長くなりやすく、また、労力もかかるため、費用も高くなるケースが多いです。
回収が必要な金額が大きければ大きいほど、費用が高額になることが通常です。
標準的な費用例は以下のようになります。
訴訟に要する標準的な費用例
| 裁判所に納める訴訟費用 | 弁護士費用(着手金) | |
| 1000万円の債権回収についての訴訟の場合 | 5万円 | 59万円程度が標準的 |
| 3000万円の債権回収についての訴訟の場合 | 11万円 | 159万円程度が標準的 |
ただし、上記のうち弁護士費用については弁護士によってさまざまである上、回収する債権の額だけで決まるものでもなく、債権回収の難易度や労力も考慮して見積もりがされます。
弁護士に個別に見積もりを依頼して費用を確認することが必要です。
ここまで通常訴訟について説明してきましたが、60万円以下の債権回収については、少額訴訟という制度を利用することも可能です。
この制度では、原則として1回の期日で裁判が終了するため、期間や労力がかかりにくい手続になっています。ただし、少額訴訟を起こした場合でも、相手方が少額訴訟で手続を進めることについて異議を述べた場合は、通常訴訟に移行します。
少額訴訟について詳しい解説は以下の記事をご覧ください。
3,債権回収のための訴訟手続の流れ
債権回収のための訴訟手続の流れは以下の通りです。
- (1)訴状の作成
- (2)証拠の準備
- (3)訴訟の提起
- (4)訴状の送達
- (5)答弁書の受領
- (6)第1回の裁判期日
- (7)準備書面や書証等のやりとり
- (8)尋問手続(人証調べ)
- (9)和解
- (10)結審 (弁論終結)
- (11)判決
- (12)控訴
- (13)強制執行(差押え)
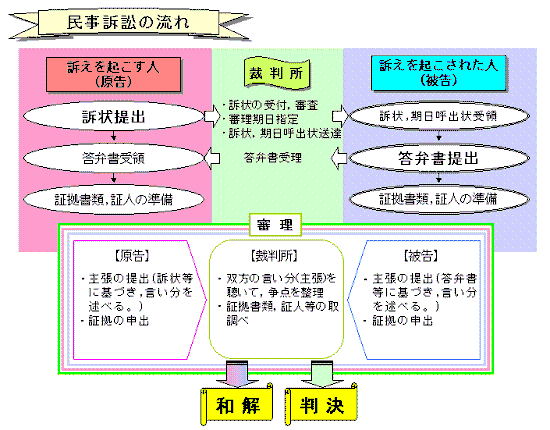
▶引用:裁判所ウェブサイトより引用
以下で、順番に詳しく解説していきます。
(1)訴状の作成
訴訟を起こすためには、訴状を作成する必要があります。
訴状には、請求する内容やその法的根拠を記載します。訴状は、訴訟の骨子を決めるものですので、十分検討したうえで作成する必要があります。
(2)証拠の準備
訴訟を起こす段階で、訴状と一緒に「証拠」も裁判所に提出することが通常です。
ただし、証拠は最初から一度に出す必要はなく、相手からの反論等を踏まえて、追加提出が可能です。
(3)訴訟の提起
訴状と証拠が準備できた段階で、裁判所に郵送して、訴訟を提起します。
「訴訟提起」とは訴訟を起こすことを言います。
民事訴訟では、訴える側(債権者側)を「原告」、訴えられた側を「被告」と呼びます。
(4)訴状の送達
訴訟を提起すると、裁判所で訴状が審査され、第1回の裁判期日が指定されます。
そして、被告に対して、裁判所から訴状を送る「送達」の手続が行われます。
(5)答弁書の受領
被告側は、訴状に対する反論文書である「答弁書」を提出することを裁判所から求められます。
原告は被告から答弁書を受け取ることで、被告が訴訟においてどのような反論をするのかを把握することができます。
(6)第1回の裁判期日
第1回の裁判期日は、被告側は答弁書を出しておけば欠席することが認められています。
そのため、第1回期日には被告が欠席することも多く、その場合は、原告側のみの出席で第1回期日が行われます。
なお、原告側は、会社の代表者が出席することもできますが、弁護士に訴訟を委任している場合は、弁護士のみの出席とすることが通常です。
(7)準備書面や書証等のやりとり
第1回の裁判期日の後、しばらくの間は、原告側が被告の答弁書に反論し、被告側がそれに対して再反論するというような、書面による主張のやりとりを交互に行う期間がしばらく続くことが標準的です。
この期間中、1か月半から2か月くらいの間隔で裁判期日が指定されます。
裁判で自身の主張をし、あるいは相手への反論をする書面を「準備書面」と呼びます。
このような準備書面の提出とあわせて、準備書面での主張を根拠づける証拠(書証等)も提出していくことになります。
(8)尋問手続(人証調べ)
準備書面や書証の提出により、お互いの争点が明確になった段階で、原告側、被告側双方の関係者を呼んで、裁判所で尋問(質問)をする機会が設けられることが通常です。
この尋問手続は、多くの裁判で、いわば「山場」ともいえる場面であり、事前に十分な準備が必要です。
(9)和解
訴訟では、尋問手続の前あるいは後に、裁判所から和解の打診があるケースがほとんどです。
和解の進め方は裁判官により様々ですが、裁判官から和解案が示され、その和解案に合意できるかどうかを、原告側、被告側の双方で検討することが一般的です。
原告側、被告側の双方が和解することに合意した場合は、和解調書という裁判所の文書を作成したうえで、訴訟は終了します。
(10)結審 (弁論終結)
尋問手続の後、特に追加の主張がなければ裁判所が審理を終結します。
これを「弁論終結」あるいは「結審」といいます。
(11)判決
和解ができなかった場合は、弁論終結までに提出された主張や証拠、尋問の結果を踏まえて、裁判所が判決を言い渡します。
(12)控訴
第一審の判決に対して不服がある場合は、より上の裁判所で第一審判決の変更を求めることができます。
第一審判決に不服を申し立てる手続きを「控訴」といいます。
控訴は第一審の裁判所に「控訴状」を提出して行います。
(13)強制執行(差押え)
判決により、債権者側の権利をが認められた場合は、債権者側は、債務者の財産を差し押さえることができます。
これを「強制執行」といいます。
以上、民事訴訟の一般的な手続きをご説明しました。
訴訟を起こした後、しばらくは書面を提出するやりとりが続いたうえで、尋問手続きを行い、判決に至るという流れをおさえておいてください。
4,訴訟手続きを弁護士に依頼する場合のポイント
訴訟手続きを弁護士に依頼する場合は以下の点を確認することが必要です。
(1)債権回収関係の事件の受任実績の有無
弁護士の取り扱い分野には、離婚や相続、破産、企業のコンプライアンス、労働事件など様々な分野があり、債権回収について普段取り扱っていない弁護士も多数存在します。
債権回収に精通し、専門的なノウハウを持つ弁護士に依頼したほうが、よい結果を出すことができます。そのため、依頼を検討する弁護士が、債権回収についてどの程度の実績をもっているかを確認することは非常に重要です。
咲くやこの花法律事務所でも債権回収に関する解決実績は多数ございます。
- 配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例
- 鞄の販売業者の未払い代金の回収について弁護士が依頼を受け公正証書を作成した事例
- 税理士事務所からの依頼を受けて滞納顧問料185万円の回収に成功した事例
- 相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例
- 未払い設計料や工事代金の回収依頼を受け、施主のショッピングモールに対する預り金債権を仮差押えできた成功事例
- 施主と連絡がとれず未払いになっていた内装工事費について工事業者の依頼を受けて全額回収した事例
- 建設会社から債権回収のご相談を受けて、既に時効が完成していた工事代金について、一部回収に成功した事例
- 土地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得て、相手方の銀行預金を差押え、手付金全額を返還させることに成功した事例
上記の事例は一部です。以下より咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する実績紹介をご覧ください。
(2)債権回収に関する弁護士の方針を確認する
この記事でもご説明した通り、単に訴訟に勝てば、債権回収が実現できるわけではありません。
訴訟により、和解での解決を目指すのか、それとも、判決を得て強制執行することにより回収するのかなど、債権回収に関する弁護士の方針をよく確認しましょう。
あわせて、依頼者と弁護士の役割分担として、依頼者側でやるべきことは何なのかも確認しておくとよいでしょう。
(3)弁護士費用
弁護士費用は、弁護士によって違いますので、費用を確認しておくことは重要です。
弁護士は弁護士会の規則で、依頼者と書面で費用について契約をすることが義務付けられています。
費用が不明瞭な弁護士に依頼することは避けるべきです。なお、債権回収については、債権回収に精通した弁護士に依頼することで回収を成功させることが最も重要であり、弁護士費用が高いか安いかだけを基準に弁護士を選ぶことは適切ではありません。
▶参考情報:債権回収の相談や代行を弁護士に依頼すべきかどうかについては、以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
5,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が民事訴訟による債権回収トラブルをサポートした解決事例
咲くやこの花法律事務所では、債権回収トラブルについて数多くのご相談をお受けし、会社側の代理人として、数多くのトラブルを解決してきました。
債権回収のトラブルが弁護士による内容証明郵便の発送や交渉で解決することも多いのですが、債権額について相手方と大きな意見の食い違いがある場合、相手方による任意の支払いが期待できそうもない場合等は、訴訟手続を利用した方が早期解決につながります。。
咲くやこの花法律事務所における民事訴訟を利用した解決実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。
(1)施主と連絡がとれず未払いになっていた内装工事費について工事業者の依頼を受けて全額回収した事例
1.事件の概要
本件は、内装工事業を営む会社が、賃貸マンションの内装工事を請け負ったところ、期限になっても工事費が支払われず、発注者とも連絡が取れなかったため、裁判を起こしたところ、工事費用全額を支払う内容で和解できた事例です。
会社は、数年前から、賃貸マンションの家主から発注を受けてマンションの内装工事を請け負うようになりましたが、取引開始後約1年を経過した頃から、急に支払いが止まりました。会社は、相手方である家主に書面を送付し、自宅訪問を行いましたが、全く応答がなかったため、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきした。
2,問題の解決結果
弁護士から相手方に内容証明を送りましたが、まったく連絡はつかなかったため、裁判を起こしました。しかし、相手方は裁判所から送られた訴状等も任意に受け取ろうとはしませんでした。そこで、「付郵便送達」という相手が書類を受け取らなくても、裁判所から発送した時点で書類を受け取ったと扱う方法で送達を行い、ようやく裁判が開始しました。
相手方は裁判所に出頭し、会社の請求額全額を支払う内容で和解が成立し、会社は工事費用全額の回収に成功しました。
裁判を起こさなければ、回収は困難であったと思われる事案です。
▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。
(2)地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得、相手方の銀行預金を差押え、手付全額を返還させることに成功した事例
1.事件の概要
本件は、不動産の買主が相手方(売主)との合意に基づき不動産売買の手付金の返還を求めたところ、相手方が拒否したため、相手方に対して訴訟を提起して勝訴し、相手方の預金口座を差押えた結果、手付金全額の回収に成功した事例です。
買主は、相手方と約束の期限までに解約すれば手付金を返還する旨の合意をしたうえで、相手方と土地の売買契約を行い、手付金を交付しました。買主は、約束の期限までに解約し、相手方に手付金の返還を求めましたが、相手方は手付金返還の合意を否定したうえで、返還を拒絶しました。そこで、買主から、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。
2,問題の解決結果
相手方は弁護士との交渉に応じず、裁判を起こしても出席しないまま買主勝訴の判決が出されました。相手方が任意に支払うことは期待できないため、事前調査で判明していた相手方の預金口座を差し押さえ、全額を回収することができました。
▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。
・土地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得て、相手方の銀行預金を差押え、手付金全額を返還させることに成功した事例
(3) 配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例
1.事件の概要
本件は、配管工事業を営む会社が、工事代金を請求したところ、相手方は工事代金の一部しか支払わない旨の主張をしましたが、裁判手続きを利用し、400万円で和解することができた事例です。
会社は、材料費相手方負担で、1300万円の本工事と700万円の追加工事を相手方から請け負いました。しかし、相手方は、「本工事の代金は1200万円で追加工事代金は本工事代金に含まれており、材料費を負担する合意はしていない」旨を主張し、工事代金の一部しか支払おうとしませんでした。
そのため、会社は工事代金の回収に不安を覚え、咲くやこの花法律事務所にご相談にいただきました。
2,問題の解決結果
弁護士から相手方に対して未払い工事代金等を請求する内容証明郵便を送りました。しかし、相手方からは、まともな応答がなかったため交渉ができず、訴訟を提起しました。
訴訟では、請負契約書や注文書等の決定的な証拠が無いなか、手持ちの証拠を積み上げることで裁判官に会社の主張が正しい旨の心証を与えることができました。これに対し相手方は、資力が無いとして、当初は、100万円程度しか支払えない旨の回答してきました。しかし、弁護士が粘り強く交渉した結果、400万円まで和解金額を引き上げることに成功しました。
この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。
・配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例
上記の他にも債権回収トラブル関連の事件についての解決事例をご紹介しています。
6,債権回収における訴訟に関して弁護士に相談したい方はこちら

ここまで債権回収について民事訴訟を利用するメリットとデメリット、具体的な手続の流れや弁護士に依頼する場合のポイントなどについてご説明してきました。
最後に「咲くやこの花法律事務所」で債権回収について行うことができるサポート内容をご紹介します。
サポートの内容は以下の2点です。
- (1)債権回収に関する相談、回収のための戦略の立案
- (2)弁護士による債権回収の代行
以下で順番にご説明したいと思います。
▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「債権回収に強い弁護士への相談サービスのご案内」の動画で、実際にサポートした一部の実績紹介、弁護士によるサポート内容、弁護士に相談するメリットなどを解説しています。
(1)債権回収に関する相談、回収のための戦略の立案
咲くやこの花法律事務所では、債権回収の問題でお困りの企業の方のために、債権回収に関するご相談を常時、承っております。
債権回収の手法には、この記事でご紹介した「民事訴訟」のほかに、「内容証明郵便での督促」や「仮差押」や「支払督促」、「債権譲渡担保」、「先取特権に基づく差押え」、「債権者破産を利用する方法」、「動産執行」、「預金差押え」など様々な手段があります。
これらの手段を適切なタイミングで上手に使うことが、回収率を上げるコツです。債権回収の経験豊富な弁護士が、個別の事情を踏まえて、回収のためにベストな戦略を立案します。
咲くやこの花法律事務所の債権回収に関するご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)弁護士による債権回収の代行
債権未払いの問題は弁護士による対応をしなければ回収が困難であるケースがほとんどです。
咲くやこの花法律事務所では、弁護士による債権回収の代行のサポートを行っており、多数のご依頼をいただいております。
弁護士がこれまでの経験も踏まえ、内容証明郵便による督促、仮差押え、訴訟、強制執行、債権譲渡、先取特権の利用など、様々な手法を駆使して債権回収を行うことで、債権回収率のアップが可能になります。
また、債権回収では、他社よりも早く回収行為をスタートし、迅速に回収にかかることがとても重要です。
現在、取引先などと債権回収に関するトラブルを抱えている企業様がいらっしゃいましたら、早めに、債権回収に強い弁護士がそろう咲くやこの花法律事務所にご相談下さい。
咲くやこの花法律事務所の債権回収に関するご相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士によるサポートは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
記事更新日:2025年11月21日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」債権回収に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587