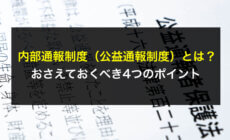こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
会社が「ユニオン」や「合同労働組合」などと呼ばれる外部の労働組合から、未払い残業問題や解雇のトラブルについて、突然、団体交渉を申し入れられるというケースが増えています。
その団体交渉の対応を誤ると、裁判に発展したり、街頭で会社を批判するビラ配りやデモ活動が行われたりするケースも少なくありません。
今回は、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所でご依頼を受けた団体交渉対応の経験も踏まえて、「ユニオン」や「合同労働組合」からの団体交渉の申入れを上手に乗り切るための「団体交渉の進め方について」ご説明したいと思います。
▶参考情報:団体交渉の基礎知識について予め知っておきたい方は、以下で詳しく解説していますので最初にご覧ください。
▶参考情報:団体交渉に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、以下をご覧ください。
・不当解雇を主張する従業員との間で弁護士立ち合いのもと団体交渉を行ない合意退職に至った事例
▶【関連情報】団体交渉については、こちらの関連記事も合わせて確認してください。
・ユニオン・労働組合との団体交渉の注意点と弁護士に相談するメリット、弁護士費用を解説
・団体交渉を拒否したらどうなる?拒否できる正当な理由などを解説
▼団体交渉について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
また労働問題に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの方はこちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,ユニオンや合同労組との団体交渉の流れの概要
「ユニオン」とは、どこの職場に属するかなどとは無関係に、労働者なら誰でも加入することができる個人加盟の労働組合です。「ユニオン」はインターネットなどで労働者の加入を積極的に募集しており、「合同労働組合」、「合同労組」などとも呼ばれます。
団体交渉の進め方についてご説明する前に、まず、最初に「ユニオンや合同労組との団体交渉の流れの概要」をご説明します。ユニオンや合同労組との団体交渉の流れの概要は以下の通りです。
(1)ユニオンや合同労組からの団体交渉の申入れ
社内で残業や有給休暇、いじめ、退職勧奨などに関してトラブルが発生して、従業員がユニオンや合同労組にこれを相談して、ユニオンや合同労組に加入すると、ユニオンや合同労組が会社に対して団体交渉の申入れをしてきます。
(2)団体交渉前の予備折衝
ユニオンや合同労組からの団体交渉の申入れがあったときは、まず、会社とユニオンや合同労組の間で団体交渉の「日時、場所、出席者数」などについての予備折衝を行います。
(3)団体交渉前の準備
予備折衝と並行して、社内において、使用者側出席者の間で、団体交渉における方針について意思統一するなど、団体交渉の前の準備を行います。
(4)団体交渉当日の交渉
実際にユニオンや合同労組と団体交渉を行います。
(5)妥結あるいは決裂で団体交渉が終了
ユニオンや合同労組と交渉事項について合意(「妥結」といいます)に至った場合は団体交渉は終了します。
また、合意に至らず決裂した場合も団体交渉は終了します。
以下では、会社で対応を要する「(2)団体交渉前の予備折衝」から「(5)妥結あるいは決裂で団体交渉が終了」の各場面についてのポイントをご説明します。
2,団体交渉前の予備折衝のポイント
では、「団体交渉前の予備折衝のポイント」から見ていきましょう。
団体交渉前の予備折衝とは、団体交渉の前に、その日時や場所、出席者数についてユニオンと事前に協議を行うことを指します。
団体交渉の日時や場所については、ユニオンや合同労組から団体交渉を申入れられる際に会社に交付される「団体交渉申入書」で一方的に指定されているケースがほとんどです。
しかし、ユニオンや合同労組が指定する日時や場所に従う必要はなく、まずは会社の事情も踏まえて、日時や場所を調整することが必要です。
(1)団体交渉の日時の調整のポイント
団体交渉の日時については、業務に支障が生じないように、業務時間外に行うことが基本です。
所定労働時間中に団体交渉を行うことは、給与の支払いをうけている時間内に団体交渉を行うことを認めることにもなりかねず、望ましくありません。また、団体交渉の時間がエンドレスにならないように、交渉時間は2時間までとするなど、あらかじめ終了時刻をユニオンや合同労組との間で取り決めておきましょう。
(2)団体交渉の場所の調整のポイント
社内で団体交渉を行うことは、他の従業員の目にもつきますので、避けるべきです。社外の会議室等を借りて行うことが望ましいです。
(3)団体交渉の出席者数に関する調整のポイント
団体交渉の出席者数についても、ユニオンや合同労組との間で事前に調整しておくことが必要です。
これは、ユニオンや合同労組が多人数で押し寄せて集団の力で威迫的な交渉を行うケースもあるためです。基本的には、「使用者側3名まで、組合側3名まで」という程度が適切です。
以上、団体交渉前の予備折衝のポイントについておさえておきましょう。
3,団体交渉前の準備の進め方のポイント
予備折衝と並行して、団体交渉前の準備として、社内において、使用者側出席者を決め、出席者の間で、団体交渉における方針を意思統一しておくことが必要です。
団体交渉前の準備の進め方については、以下の点がポイントとなります。
- ポイント1:使用者側出席者のメンバーを決める。
- ポイント2:団体交渉事項についての事実関係の確認を行う。
- ポイント3:団体交渉事項が裁判等に発展した場合の裁判での解決内容の見込みを確認する。
- ポイント4:会社の解決方針や団体交渉の交渉戦略について意思統一する。
以下で順番に見ていきましょう。
ポイント1:
使用者側出席者のメンバーを決める。
まず、団体交渉の使用者側出席者のメンバーを決めることが必要です。
メンバーの選び方については以下の点をおさえておきましょう。
●取締役クラスあるいは部長クラスの出席について
交渉の責任者としてある程度の決裁権を有する取締役クラスあるいは部長クラス以上が参加することが必要です。
●本人の直属の上司の出席について
解雇トラブルなどの団体交渉で、本人の日ごろの業務態度や勤務状態が議論の対象になるケースでは、本人の直属の上司にも団体交渉に同席させることが必要です。
●セクハラやパワハラの調査担当者の出席について
セクハラやパワハラに関する団体交渉では、社内でセクハラやパワハラについての調査を担当した従業員がいる場合は、団体交渉に同席させることが望ましいです。
●弁護士の出席について
団体交渉については独自のルールや注意点がありますので、団体交渉に精通した弁護士にも同席を依頼することが適切です。
以上を参考にしていただき、団体交渉の使用者側出席者のメンバーを決めましょう。
ポイント2:
団体交渉事項についての事実関係の確認を行う。
次に、団体交渉事項について、正確な事実関係の確認を行うことが必要です。
トラブルの内容ごとに例をあげると以下の通りです。
例1:未払い残業代トラブルの場合
未払い残業代トラブルに関連して団体交渉が申し込まれた時は、以下の事実関係を確認しておきましょう。
- 本人の勤務時間の確認(タイムカードなど)
- 残業代の支払い状況の確認(過去2年間分)
- 固定残業代の支払いの有無、額についての確認
- 雇用契約書や就業規則の内容の確認
例2:解雇トラブルの場合
解雇トラブルに関連して団体交渉が申し込まれた時は、以下の事実関係を確認しておきましょう。
- 解雇前の本人の勤務状況の確認
- 解雇理由にあたる事実(成績不良や協調性欠如など)の確認
- 解雇通知書や解雇理由書の記載内容の確認
- 解雇予告手当の支払状況の確認
例3:セクハラ、パワハラトラブルの場合
- 会社においてセクハラ、パワハラについて行った被害者・加害者からのヒアリング内容の確認
- 会社においてセクハラ、パワハラについて行った調査結果の確認(同僚からの目撃内容など)
- 被害者の現在の状況の確認(診断書提出の有無や出勤状況等)
- セクハラ、パワハラ後に会社が行った措置や加害者に対する処分等の内容の確認
これらの項目について、事前に十分な事実確認を行っておけば、団体交渉で出てくるユニオン側からの主張について、事実に照らして間違っているものは使用者側において正すことができ、使用者側が団体交渉の主導権を掌握することができるようになります。
逆に、事実確認が不十分なまま、団体交渉に臨むと、ユニオンや合同労組側から、会社の事実把握の誤りを指摘され、ユニオンや合同労組に団体交渉の主導権を握られることにつながりますので、注意が必要です。
ポイント3:
団体交渉事項が裁判等に発展した場合の裁判での解決内容の見込みを確認する。
正確な事実関係の確認ができたら、次は、労働問題に精通した弁護士に相談して、団体交渉事項が裁判等に発展した場合の裁判での解決内容の見込みを確認することが必要です。
▶参考情報:団体交渉事項が裁判等に発展した場合の解決内容の見込みを弁護士へ相談することについて
上記でご説明してきたように、団体交渉には事前の正確な事実関係の確認が重要で、その準備の精度次第でその後の裁判等に発展した場合の解決内容にも影響してきます。
そのため、団体交渉事項が裁判等に発展した場合の解決内容の見込みに影響を与える「事実関係の確認」の段階から、労働問題に精通した弁護士に相談することが望ましいので、この点も合わせておさえておきましょう。
未払い残業代トラブル、解雇トラブル、セクハラ・パワハラトラブルなどの団体交渉事項について裁判になっても会社が勝訴する見込みが高いと思われる場合は、ユニオンや合同労組との団体交渉においても安易な譲歩はせずに、団体交渉の場で、ユニオンや合同労組に対して、組合員の要求が法的にも認められないことを説明していくことになります。
一方、団体交渉事項について裁判に発展すれば会社が敗訴したり、一定の金銭支払いが必要になる見込みが高いと思われる場合は、ユニオンや合同労組との団体交渉において、一定の譲歩をして団体交渉で問題を解決し、裁判を回避することが適切です。
このように、団体交渉事項が裁判等に発展した場合の裁判での解決内容の見込みを確認しておくことは、団体交渉に臨む方針や、譲歩の程度を決めるための重要なポイントとなります。
ポイント4:
会社の解決方針や団体交渉の交渉戦略について意思統一する。
裁判での解決内容の見込みを確認したら、団体交渉事項についての会社の解決方針や団体交渉の交渉戦略について、使用者側において意思統一をしておきましょう。
以下でケースごとにどのような点について意思統一をしておくのが良いか見ていきましょう。
1,未払い残業代トラブルのケースの例
未払い残業代トラブルの団体交渉で、裁判になれば残業代の支払いを命じられる可能性が高い場合は、団体交渉内で問題を解決してしまうことが得策です。
この場合、いくらくらいの金額を支払うことで合意を目指すのかを検討し、使用者側において意思統一しておきましょう。
一方、従業員の未払い残業代請求が法的に認められる見込みが低く、裁判になっても会社が勝訴する見込みが高い場合は、団体交渉の場で従業員からの請求が法的に見て認められないことを説明していく方針を、使用者側メンバーにおいて確認しておきましょう。
2,解雇トラブルのケースの例
解雇トラブルの団体交渉の場合で、裁判になれば不当解雇と判断されて敗訴することが予想される場合は、解雇を撤回するのか、あるいは、金銭的な補償をして退職してもらうことを目指すのかを検討する必要があります。
そして、金銭的な補償をして退職してもらうことを目指す場合は、裁判になった場合や労働審判になった場合の支払額の見込みを踏まえて、具体的に解雇した従業員の給与の何か月分くらいを金銭解決の目安とするのかについて、使用者側において意思統一しておきましょう。
一方、従業員の請求が法的に認められる見込みが低く、裁判になっても会社が勝訴する見込みが高い場合は、団体交渉の場で従業員からの請求が法的に見て認められないことを説明していく方針を、使用者側メンバーにおいて確認しておきましょう。
以上、団体交渉前の準備の進め方のポイントについておさえておいてください。
4,当日の交渉の進め方のポイント
それでは、続いて、「団体交渉当日の交渉の進め方のポイント」についてご説明します。
以下の4つのポイントをおさえておきましょう。
- ポイント1:まずは、会社の立場を粘り強く説明する。
- ポイント2:団体交渉を理由に解雇や配転を遅らせない。
- ポイント3:組合側の本音や統制力を見極めて譲歩のタイミングや妥結の見込みを探る。
- ポイント4:いったん会社の譲歩案を示した後は、再提案は組合に出させる。
以下で順番に見ていきましょう。
ポイント1:
まずは、会社の立場を粘り強く説明する。
団体交渉の序盤の段階では、会社の立場、主張を粘り強く主張することがまず重要です。
感情的な議論や無意味なケンカは避け、法律的な議論や会社の経営の観点から、冷静で合理的な説明を繰り返し行うことが必要です。また、説明には決して嘘がないようにしなければなりません。
ポイント2:
団体交渉を理由に解雇や配転を遅らせない。
団体交渉の中には、解雇を予定していた従業員から解雇の方針を撤回させる目的で申し入れされる団体交渉や、配転を予定していた従業員から配転の方針を撤回させる目的で申し入れされる団体交渉もあります。
このようなケースでは、団体交渉が申し入れられたからといって、解雇や配転を遅らせるべきではありません。ユニオンや合同労組からの抗議を受けたとしても、必要な解雇や配転は実行しなければなりません。
ポイント3:
組合の本音や統制力を見極めて譲歩のタイミングや妥結の見込みを探る。
例えば、未払い残業代のトラブルや解雇のトラブルについて、裁判になれば会社としても一定の金銭負担を命じられる見込みが高いケースでは、会社として一定の金銭を支払って問題を解決することが合理的であることもあります。
そのようなケースでは、これまでの団体交渉の経緯を踏まえて、組合の本音や、本人に対する統制力の程度を見極めながら、譲歩のタイミングや妥結の見込みを見極めることになります。
ユニオンや合同労組としては、交渉のカードとして、「団体交渉決裂による裁判の可能性」や「ビラ配りなどの抗議活動」をちらつかせて会社側に譲歩を迫ることもありますが、実際には、団体交渉の決裂や抗議活動などの直接行動は避け、団体交渉の中で解決したいということがユニオンや合同労組の本音であることがほとんどです。
そのため、ユニオン側としても、最初の請求額から一定程度の譲歩をすることは予定しており、使用者側出席者においてユニオン側の本音の解決ラインを見極めることが必要です。
一方、ユニオンや合同労組と本人の関係性によっては、会社が譲歩案を提示しても、ユニオンや合同労組が本人を説得して合理的なラインで話をまとめる力がないケースもあります。
このような、ユニオンや合同労組の本人に対する統制力が乏しいケースでは、そもそも妥結が難しいため、会社としても安易な譲歩案は出すべきではありません。
ユニオンや合同労組と本人の力関係についても、交渉の過程の中で見極めていくことが必要です。
ポイント4:
いったん会社の譲歩案を示した後は、再提案は組合に出させる。
団体交渉においては、ユニオンや合同労組から何らかの金銭請求があった場合で、会社としても一定の譲歩をして解決したいという場合は、ユニオンや合同労組からの請求額に対して、会社としてこの範囲なら応じるという譲歩案を出すことになります。
ただし、会社から譲歩案を出すのは「1回のみ」とし、会社から出した譲歩案でユニオンや合同労組が納得しない場合は、ユニオンや合同労組から具体的な再提案を出させることがおすすめです。
会社から出した譲歩案で妥結できないからといって、なし崩し的に会社からさらに譲歩した案を出すなど、譲歩を重ねる交渉方法では、ユニオン側としては粘れば粘るほど譲歩を引き出せるという意識にもなりかねず、問題解決が遠のきやすいので注意が必要です。
以上、団体交渉当日の交渉の進め方のポイントをおさえておきましょう。
5,団体交渉で妥結する場合のポイント
団体交渉でユニオンや従業員との話がまとまり、一定の内容で妥結する場合は、合意内容を明確にするために「協定書」や「合意書」という表題の書面を作成します。
これについては、以下の団体交渉で妥結する場合の3つのポイントをおさえておきましょう。
- ポイント1:従業員にも必ず署名、捺印させる。
- ポイント2:清算条項を必ず入れる。
- ポイント3:必要に応じて口外禁止条項、誹謗中傷禁止条項を入れる。
以下で順番に見ていきましょう。
ポイント1:
従業員にも必ず署名、捺印させる。
会社からの一定の金銭支払いを含む合意内容で妥結する場合、金銭の振込先にはユニオンや合同労組の銀行口座を指定されることがほとんどです。
従業員がユニオンの銀行口座に振り込むことに同意していることを明確にするためにも、「協定書」や「同意書」にはユニオンや合同労組の署名・捺印だけでなく、必ず「従業員の署名・捺印」も求めなければなりません。
ポイント2:
清算条項を必ず入れる。
清算条項とは、「合意書に定めた金銭以外の金銭支払義務が会社にないこと」を確認し、ユニオンや従業員に「合意した金銭以上の請求をしないこと」を約束させる内容の条項です。
清算条項を入れておかなければ、類似の要求が蒸し返されるおそれがありますので、必ず入れておきましょう。
ポイント3:
必要に応じて口外禁止条項、誹謗中傷禁止条項を入れる。
合意の内容によっては、他の従業員への口外を禁止するべきことも多いでしょう。
その場合は、「協定書」や「合意書」を作成するタイミングで、他への口外を禁止する内容の口外禁止条項を入れることを忘れないようにしましょう。
また、ユニオン側による会社批判を封じるためにも、「会社とユニオン・従業員は互いに誹謗中傷しない」という内容の誹謗中傷禁止条項を合意書に入れておくことも検討しましょう。
以上、団体交渉で妥結する場合のポイントをおさえておいてください。
なお、会社がユニオンなどの労働組合と取り交わす書面は、法律上、「労働協約」に該当し、労働組合法でその効力等が定められています。労働協約については、詳しくは以下の記事をご参照ください。
6,団体交渉が決裂した場合のポイント
団体交渉で妥結できず、決裂した場合は、団体交渉を申し入れたユニオン・従業員が次にどのような手段をとってくるか、あらかじめ心づもりしておく必要があります。
以下のような手段がとられることが多いので、あらかじめ心づもりしておきましょう。
団体交渉が決裂した場合にユニオン・従業員がとる手段の例
- (1)街頭宣伝やビラ配り
- (2)労働委員会への不当労働行為の審査申立て
- (3)労働委員会の個別労働紛争のあっせん手続き
- (4)労働局へのあっせん申請
- (5)労働基準監督署への申告
- (6)労働審判の申し立て
- (7)労働裁判の訴訟提起
以下では順番に概要を見ていきたいと思います。
(1)街頭宣伝やビラ配り
ユニオンや合同労組の中には、団体交渉が行き詰まったときに、あくまで団体交渉内で妥結させようと会社に圧力をかける目的で、会社の前で会社を批判するビラを配ったり、街頭でのデモ活動を行うことがあります。
これらの活動の内容によっては、「裁判所に差止めの命令」を出してもらえるケースや、「名誉棄損による損害賠償請求」をすべきケースもあり、弁護士と連携して対応することが必要です。
(2)労働委員会への不当労働行為の審査申立て
不当労働行為の審査申立てとは、団体交渉に関して使用者側に違法、不当な行為があったときに、組合側が都道府県の機関である労働委員会に審査を申し立てることができる制度です。
この制度を利用して、ユニオンや合同労組が団体交渉の中で会社側の違法行為(「不当労働行為」といいます)があったとして、労働委員会に不当労働行為の審査を申し立てるケースもあります。
(3)労働委員会の個別労働紛争のあっせん手続き
未払い残業代トラブルや解雇トラブルなどについては、都道府県の機関である労働委員会で話し合いの手続き(「個別労働紛争のあっせん手続き」といいます)を申し立てることができます。
団体交渉決裂後に従業員がこの労働委員会の個別労働紛争のあっせん手続きを申し立てるケースもあります。
(4)労働局の紛争調整委員会によるあっせん申請
未払い残業代トラブルや解雇トラブルなどについては都道府県の労働局に話し合いの手続き(「あっせん手続き」といいます)を申請することもできます。
このあっせん手続きは、労働局の紛争調整委員会という委員会が担当します。団体交渉決裂後に従業員がこのあっせんを申請するケースもあります。
(5)労働基準監督署への申告
従業員が団体交渉決裂後に、未払い残業などの問題について労働基準監督署に申告し、会社が労働基準監督署から調査を受けるケースもあります。
(6)労働審判の申し立て
団体交渉で決裂した後に、従業員が裁判所に労働審判の申し立てをしてくるケースもあります。
労働審判は従業員と会社とのトラブルを、通常の裁判よりも簡易な手続きで解決する制度です。労働審判については、以下の記事で、労働審判の制度内容の手続の流れや、解決金の相場、会社側弁護士費用の目安についても詳しく確認しておいてください。
(7)労働裁判の訴訟提起
団体交渉が決裂した後に、従業員が裁判所に労働審判ではなく、通常の裁判(労働裁判)を提起するケースもあります。そのため、団体交渉が決裂した場合は、「裁判での会社の守り方」についても弁護士と事前に準備しておくことが必要でしょう。
▶参考として、よくある「解雇のケース」の労働裁判での会社の守り方について
労働裁判の中でももっとも多いケースのひとつが「解雇トラブルの裁判」です。解雇トラブルについてユニオンや合同労組との団体交渉が決裂する見込みとなった場合、労働裁判に発展する可能性も想定して「弁護士が教える不当解雇の損害賠償、慰謝料と裁判での会社の守り方について」の記事も参考にご覧下さい。
ユニオンや合同労組との団体交渉が決裂する見込みとなった場合は、これらの手段がとられた場合の対応について事前に弁護士に相談して検討しておきましょう。
7,弁護士に相談や依頼した時のメリットや弁護士費用について
今回の「ユニオン・労働組合との団体交渉の進め方」でもご説明してきたように、団体交渉の対応には「事前の準備の進め方」から「当日の進め方と対応方法」、「妥結する場合のポイント」や「交渉が決裂した場合のポイント」まで、自社だけで正しく手順で進めていくのは困難です。
対応を少しでも間違うと、結果的に大きな損害が発生してしまうことにもつながります。
そのため、団体交渉の対応については、団体交渉に強い弁護士に相談するようにしましょう。詳しくは、以下の記事を必ずチェックしておきましょう。
8,団体交渉の対応に関して弁護士へ相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では労働問題に強い弁護士がそろっており、企業側からの依頼による団体交渉の対応や同席の実績が豊富です。そのため、団体交渉における進め方のノウハウが蓄積されており、あらゆるケースの団体交渉の場面でベストな解決に向けてお客様をサポートさせていただくこと可能です。
具体的に、咲くやこの花法律事務所に団体交渉に関するご相談をいただいた際には、以下のようなサポートが可能ですので、参考にご覧下さい。
団体交渉に関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容
- (1)団体交渉に関する相談、解決への道筋の提示
- (2)団体交渉における交渉戦略の立案、交渉方法に関する助言
- (3)団体交渉の日程、場所の調整
- (4)団体交渉への弁護士の同席
▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「団体交渉の対応に関する弁護士への法人向け相談サービス」を動画でも解説しています!
「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2025年4月3日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」団体交渉に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587