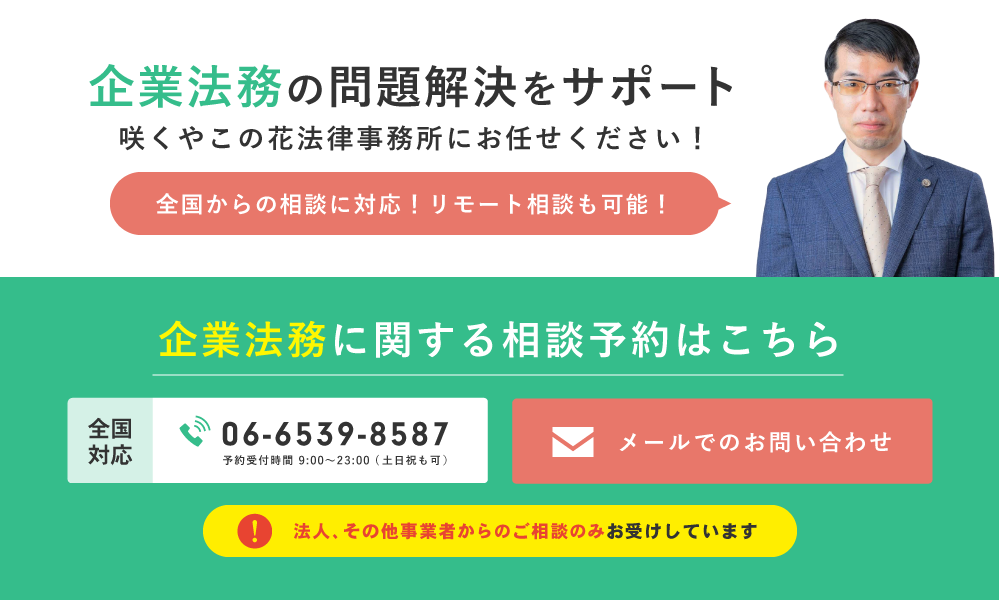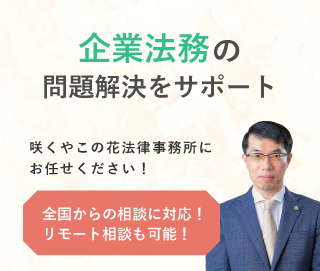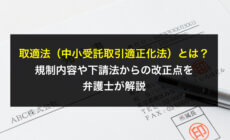神社規則は神社運営の根本原則を定めるものであり、日ごろの神社運営の重要な基準です。
また、神社内部でのトラブルが発生したときにも、神社規則は重要な解決基準となります。神社内部のトラブルは、宮司が意に反して罷免されるなど、深刻な紛争に発展しがちです。
このような紛争を防ぐためには、日ごろから神社規則を整備し、宮司の地位を安定したものにしておくことが必要です。
今回は、神社の顧問弁護士も務める筆者が神社規則の整備と変更手続きについてご説明します。
▼神社規則に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,神社規則とは?
神社規則は神社の組織運営や活動内容を定めた根本規則です。
神社の役員の選び方や事業内容、包括宗教団体に属するかどうかなどの重要な点を神社規則で定めます。
宗教法人法で、すべての宗教法人は、設立時に規則を作成して、都道府県知事の認証を受けることが義務付けられています(宗教法人法第12条1項)。
神社規則はこの宗教法人法の規程に基づき作成される神社の規則です。
長い間、神社規則を変更していない場合は、神社の実際の運営方法と神社規則の間にずれが生じてしまっているケースもあります。
このようなケースでは、神社の実際の運営方法にあわせて神社規則を変更しておく必要があります。
2,宗教法人法で神社規則の記載事項が決められている
神社規則には、宗教法人法により、必ず記載しなければならない事項が決められています。
通常の神社が記載しなければならない一般的な記載事項は以下の通りです。
神社規則で記載しなければならない記載事項
- (1)宗教法人の目的
- (2)宗教法人の名称
- (3)宗教法人の事務所の所在地
- (4)包括する宗教団体がある場合にはその名称等
- (5)役員等の呼称、資格及び任免、任期及び職務権限等に関する事項
- (6)議決機関等がある場合は、その機関に関する事項
- (7)公益事業あるいは収益事業を行う場合は、その種類及び管理運営に関する事項
- (8)基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分等財務に関する事項
- (9)規則の変更に関する事項
- (10)解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
- (11)公告の方法
3,神社規則の変更が必要となる場合
前述の神社規則の記載事項を変更する際は、神社規則の変更手続きが必要になります。
例えば以下のようなケースです。
ケース1:
宮司や責任役員の選任方法や解任方法を変更する場合
この場合、前述の(5)の「役員等の呼称、資格及び任免、任期及び職務権限等に関する事項」のうち、役員の任免に関する項目を変更することになりますので、神社規則の変更が必要です。
ケース2:
駐車場経営などあらたな事業を始める場合
この場合、前述の(7)の「公益事業あるいは収益事業の種類及び管理運営に関する事項」を変更することになりますので、神社規則の変更が必要です。
ケース3:
包括宗教法人から離脱する場合
神社が包括宗教法人に加入している場合、前述の(4)の「包括する宗教団体がある場合にはその名称等」として、包括宗教法人の名称が規則に記載されています。
また、「包括宗教法人の神社明細帳への登録」や「包括宗教法人に協力して神社を運営すること」なども規則に記載されていることが通常です。
そのため、包括宗教法人から離脱する場合は、これらの規程を削除することが必要になり、神社規則の変更が必要です。
4,神社規則の変更の手続きは3つのステップ
神社規則の変更の手続きは以下の3ステップです。
ステップ1:
神社規則に記載された変更手続きを行う。
神社規則には、必ず、神社規則の変更をどのようにして行うかが記載されています。
まず、神社規則に記載された変更手続きを行うことが必要です。
多くの神社規則では、規則の変更には責任役員会での決議が必要と記載されています。この場合、責任役員会を招集して規則変更の決議を行う必要があります。
ステップ2:
包括宗教法人への加入又は脱退の場合は公告が必要
包括宗教法人に新たに加入したり、あるいは今加入している包括宗教法人から離脱する場合は、宗教法人法上、神社規則の変更について公告が必要とされています(宗教法人法第26条2項)。
公告とは、信者らに広く知らせることを指します。
具体的な方法については、神社規則に「公告の方法」として記載されている方法で行う必要があります。一般には、新聞への掲載や事務所での掲示などの方法により、公告することが定められた神社規則が多くなっています。
ステップ3:
都道府県または文部科学大臣の認証を受ける。
神社規則に記載された変更手続きを行ったら、変更について都道府県の認証を受けることが必要です。
ただし、複数の都道府県に境内地がある神社の神社規則の変更については、文部科学大臣の認証を受けることになっています。
変更の認証の申請があった場合に、都道府県や文部科学大臣は不合理な理由で認証をしないことはできません。
変更内容が法令に適合し、かつ、ステップ1、ステップ2でご説明した、法人内部の変更手続きや公告の手続きが正しく行われている場合は、認証しなければならないとされています(宗教法人法第28条1項)。
なお、包括宗教法人から離脱するための神社規則の変更については、もし、神社規則の中で包括関係の廃止について包括宗教法人の承諾などが必要となっている場合であっても、承諾は要しないこととされています(宗教法人法第26条1項)。
5,宮司の地位を安定させるためには神社規則の整備がポイント
宮司の地位が不安定な神社規則は、神社内部の争いの原因になり、ひいては神社運営自体が不安定になります。
特に注意が必要なのが、宮司の解任の手続きが神社規則でどのように定められているかです。
宮司の解任については神社規則の記載事項の1つになっていますが、通常は責任役員会の議決で解任できることが記載されています。
そのため、意に反する解任を防ぎ、宮司の地位を安定させるためには、宮司の神社運営に賛同してくれる人を責任役員にすることが重要なポイントです。
(1)宮司の地位が不安定な神社規則の例
例えば、以下のように定められている神社規則では宮司の地位が不安定なものになります。
- 「責任役員は総代会で選考し、代表役員が委嘱する。」
- 「総代は、氏子または崇敬者から選任する。選任方法は役員会で定める。」
- 「宮司の進退は役員会の議決によるものとする。」
これでは、結局、責任役員は総代会で決まることになり、必ずしも宮司の神社運営に賛同してくれる人が責任役員に就任するとはいえません。
そのため、責任役員会で宮司が解任されるなどのトラブルが起こり得ます。
(2)宮司の地位を安定させる神社規則への変更例
では、宮司の地位を安定させるためにはどのような神社規則にすればよいのでしょうか?
結論からいうと、宮司以外の責任役員の過半数を宮司が指名できるようにしておくことが重要なポイントです。
誰かが宮司の解任を言い出した場合に、通常は、責任役員会で解任するかどうかの議決をすることになります。このときに、解任の対象となる宮司自身は議決に参加できません。
そのため、宮司自身を除く責任役員の過半数を宮司が指名できる仕組みにしておき、もし解任の議案がでても否決してもらえるようにしておくことが宮司の地位を安定させるうえで重要なポイントになります。
責任役員は宮司も含めて3名以上であることが必要です(宗教法人法第18条1項)。
もし、宮司も含めて責任役員が3名の場合、責任役員のうち1名を宮司が指名できるようにしておけば、宮司が意に反して解任されるなどの事態をさけることができるでしょう。
いま、「責任役員は総代会で選考する」などとなっている場合は、神社規則を変更して、責任役員を宮司が指名できるようにしておくことが、宮司の地位を安定させ、安定した神社運営をするための重要なポイントになります。
なお、さらに宮司の地位を安定させるために代表役員の地位を終身制とすることも可能です。ただし、これは、宮司が高齢になった場合や病気になった場合に、代務者に業務をゆだねることになり、不都合が生じることも多く、あまりおすすめできません。
6,神社規則など神社運営に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所における神社向けのサポート内容についてご説明したいと思います。
サポート内容は以下の通りです。
- (1)神社規則の整備、変更のご相談
- (2)神社の労務管理、雇用契約書・就業規則整備のご相談
- (3)神社の内部紛争、労務管理のご相談
- (4)神社が行う事業についてのご相談
- (5)神社向け顧問弁護士サービス
以下で順番に見ていきましょう。
(1)神社規則の整備、変更のご相談
この記事でご説明したように神社規則は神社運営の根本原理であり、非常に重要です。
そして、神社運営にトラブルが生じた後では神社規則の変更を進めることは難しくなります。そのため、平時から神社規則の整備や、必要な変更に取り組むことが重要です。
咲くやこの花法律事務所では神社規則に精通した弁護士が神社規則の整備、変更のご相談をお受けしていますので、ぜひご相談ください。
(2)神社の労務管理、雇用契約書・就業規則整備のご相談
神社を安定して運営するためには神職や巫女の労務管理や雇用契約書・就業規則の整備も重要になります。
問題行動を起こす神職への指導や解雇、病気休職への対応、残業代に関するトラブル、その他さまざまな労務トラブルの場面で、雇用契約書や就業規則は最も重要な基準になります。
雇用契約書や就業規則が作成されていなかったり、実態に合ったものになっていない場合、労務トラブルが深刻化し、神社の運営に重大なダメージになります。
日ごろから雇用契約書・就業規則その他労務管理の整備に努めることが安定した神社運営のポイントです。
咲くやこの花法律事務所では労務管理に精通した弁護士が雇用契約書や就業規則の整備、問題行動を起こす神職への対応、その他労務管理に関する各種のご相談をお受けしていますので、ぜひご相談ください。
なお、労務管理を弁護士に相談するメリットについては以下の記事もあわせてご参照ください。
▶参考情報:労務管理を弁護士に相談するべき理由と弁護士選びの注意点
(3)神社の内部紛争、労務トラブルのご相談
咲くやこの花法律事務所では、神社の内部紛争や労務トラブルについても常時ご相談をお受けしています。
最近は神社でも未払い残業代トラブルやパワハラトラブルが問題になっています。また、神職を解雇して裁判トラブルに発展することも少なくありません。
例えば、福岡地方裁判所平成27年11月11日判決は、神社が神職を解雇したところ、解雇された神職がパワハラや残業代未払い、不当解雇などを理由に神社を訴えた事件です。
神社側が敗訴し、約800万円の支払いを命じられています。
咲くやこの花法律事務所では、労働裁判、労働審判その他の各種労務トラブルについて多くの実績があります。
弁護士が神社の内部紛争、労務トラブルについて、適切に対応し、最大限、神社の意向に沿う解決を実現します。
労務トラブルの対応については以下の記事も併せてご参照ください。
(4)神社が行う事業についてのご相談
咲くやこの花法律事務所では、神社が行う駐車場運営、不動産賃貸、結婚式、宿泊施設の経営など各種事業に関するトラブルについてのご相談も常時承っております。
賃料の回収やクレームなどのトラブルへの対応、契約書のリーガルチェックなどについてもぜひご相談ください。
各種サービスについて詳しい情報は以下もご覧下さい。
(5)神社向け顧問弁護士サービス
神社規則の整備、就業規則や雇用契約書の整備、その他神社の安定した運営に欠かせない整備事項は決して一度にまとめて行えるものではありません。継続的に弁護士と相談し、1つ1つ取り組むことが重要です。
咲くやこの花法律事務所では、顧問契約をしていただくことにより、これらの整備に継続的にとりくみ、神社運営で起こるトラブルの事前予防に貢献します。もし問題が生じたときも法的な整備が十分されていれば迅速に解決することが可能です。
顧問弁護士サービスについて詳しい情報は以下もご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
8,神社運営についてお役立ち情報も配信中(メルマガ&You Tube)
神社運営に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
9,まとめ
今回は、神社運営の根本規範である神社規則について、法律上の記載事項をご説明したうえで、神社規則の変更がどのような場面で必要になるかをご説明しました。
そのうえで、神社規則の具体的な変更手続きについてもご説明しました。さらに、一例として、宮司の地位を安定させるための神社規則変更のポイントについてもご説明しました。
神社内部のトラブルが発生してから神社規則を変更したいと思っても、なかなか変更はできません。平常時から神社規則に注意を向け、必要な整備をしておきましょう。
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年1月26日
 06-6539-8587
06-6539-8587