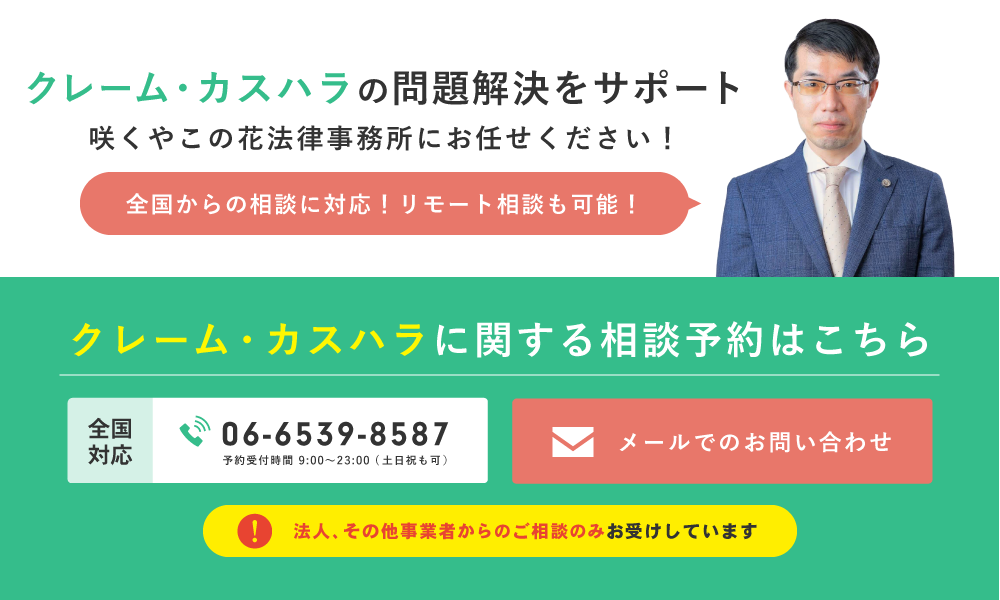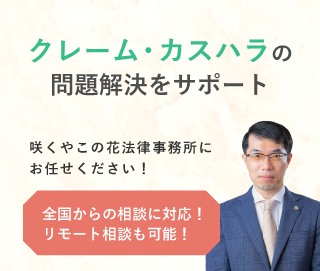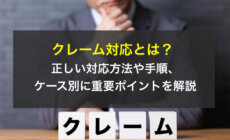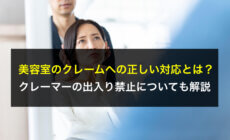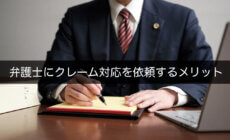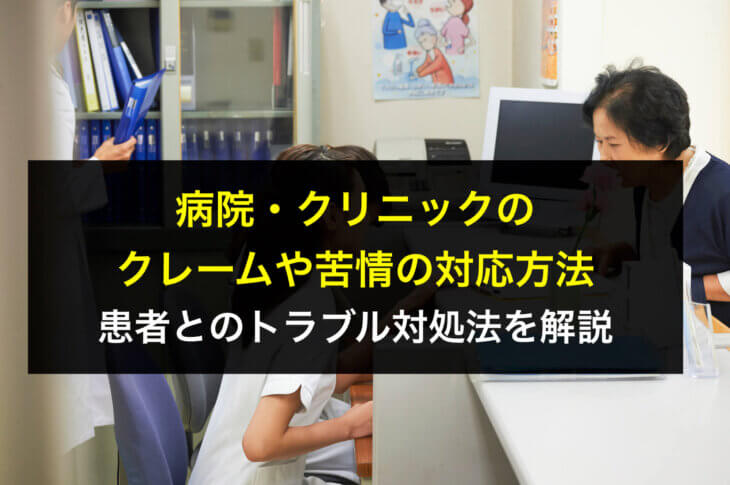
こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
「待ち時間に対するクレームや苦情」や「治療内容の説明に納得ができないというクレームや苦情」、「接遇に関するクレームや苦情」など、医療現場でのクレームや苦情に悩んでいませんか?
病院・クリニックといった医療現場の特性から、高度な対応や体調不良の患者への対応を求められることも多く、結果としてそれが患者クレームや医療苦情につながるケースも少なくありません。病院やクリニック側に落ち度がなかったとしても、対応方法を誤ると、クレームや苦情はエスカレートし、本来の業務に重大な支障を生じさせることがあります。
そのようなトラブルは、直接対応するスタッフはもちろん、それを支えるスタッフまで疲弊させてしまいます。そして、その結果、スタッフの離職が相次げば、全体のサービスレベルが低下し、患者様が他院へ流れてしまう事態を招きかねません。
このような事態を防ぐためには、まず、何が「正しい対応」であるかを理解し、実践できるようになることが必要です。また、問題発生時に早期に弁護士に相談していただくことで、スムーズな解決が可能になります。医療機関において対応困難なクレームは、弁護士に依頼して、弁護士が代わって対応することが適切です。
そこで本記事では、すべての病院・クリニック関係者の方に知っておいていただきたい「医療機関におけるクレーム・苦情対応の基本的な考え方とトラブル対処法」について、弁護士の立場から分かりやすく解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、対応困難な患者クレームや医療苦情が発生した場合でも、落ち着いて適切な対応をするための判断軸を身につけていただくことができ、トラブルをこじらせることなく、スムーズな解決に向けて動き出すことができるはずです。
それでは見ていきましょう。
咲くやこの花法律事務所では、多くの病院やクリニックから、クレームや苦情に関する対応のご相談をお受けし、弁護士が実際に相手に対応するなどして解決に導いてきました。
医療機関では対応困難なクレームも弁護士にご依頼いただくことで、相手も法律に沿った解決を意識することになり、スムーズに解決できることが多いです。患者クレームや医療苦情でお悩みの病院・クリニックの方は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
クレームや苦情の対応に関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しく紹介していますので、あわせてご参照ください。
▶参考情報:クレーム対応や悪質クレーマーに関する弁護士への相談サービスはこちら
※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。
また、咲くやこの花法律事務所のクレーム対応の解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。
▼病院・クリニックのクレームや苦情に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
またクレーム対応に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,病院やクリニックのクレームや苦情の対応の原則を弁護士が解説

病院やクリニックへのクレームや苦情については、各病院で「クレーム対応マニュアル」が作成されていることが多いと思いますが、まず、基本原則として以下の8点をおさえておきましょう。
- 原則1:複数人で対応する
- 原則2:別室に案内する
- 原則3:否定せずに患者の話を聴き、丁寧な説明を繰り返す
- 原則4:正確なメモをとる
- 原則5:クレームや苦情の内容は病院内で共有する
- 原則6:できない約束や特別扱いはしない
- 原則7:困難な事案は文書による対応や弁護士への依頼に切り替える
- 原則8:違法行為に注意
それぞれについて順番に詳しく解説していきます。
原則1:複数人で対応する
クレームや苦情には複数人で対応することが原則です。
複数で対応することにより患者を落ち着かせることができますし、スタッフの負担を減らすことができます。スタッフが一人でクレームや苦情を受けたときは、いったん中に下がって一緒に対処してくれるスタッフを呼ぶなど、複数名で対応するためのルールを設けておきましょう。
原則2:別室に案内する
クレームや苦情が簡単におさまらないときは別室に案内することが原則です。
別室に案内することにより患者を落ち着かせ、また他の患者への迷惑を避けることができます。
原則3:否定せずに患者の話を聴き、丁寧な説明を繰り返す
患者の話は否定せずに聴き、患者の気持ちを落ち着かせたうえで、病院のスタッフが丁寧な説明を行いましょう。
原則4:正確なメモをとる
クレームや苦情が正確に伝わっていないと患者が感じるとき、さらにクレームがエスカレートします。クレームや苦情の内容やそれに対するスタッフからの回答内容については正確なメモを残すことが必要です。
正確なメモは、外部弁護士にクレーム対応を依頼する際や、万が一クレームが裁判に発展した場合の裁判対応においても非常に有益です。
原則5:クレームや苦情の内容は病院内で共有する
クレームや苦情の内容やそれに対するスタッフの対応内容はスタッフ間で共有することが必要です。
特に、複数の診療科や部署がある病院では、一部署でのクレームや苦情の内容を全体に共有することに気を配る必要があります。電子カルテ等どこの部署のスタッフもすぐにアクセスできる媒体にクレームや苦情の内容や対処内容を記載して共有することを徹底しましょう。
また、個人のミスが原因でクレームや苦情になっているときは、本人がミスを隠そうとしてしまいクレームや苦情が共有されにくいケースがあります。自分のミスであっても必ず共有することをルール化することが必要です。
原則6:できない約束や特別扱いはしない
できない約束をしたり、特別扱いをすることは、絶対にしてはなりません。
例えば、待ち時間が長いといってわめきたてる患者に対して、特別に診療の順番を早めることは、次回以降も、同じ対応を求められることにつながります。
原則7:困難な事案は文書による対応や弁護士への依頼に切り替える
困難な事案は文書による対応や弁護士への依頼に切り替えることが必要です。
現場で解決することにこだわり、スタッフが疲弊したり、無理な要求をのむということにならないように、困難なクレームや苦情は上にあげて病院の組織として対応するか、クレーム対応に強い弁護士や顧問弁護士に相談や依頼することができる仕組みが必要です。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の弁護士によるクレーム対応に関するサポート内容、解決実績などは以下をご覧下さい。
・クレーム対応や悪質クレーマーに関する弁護士への相談サービスはこちら
また、クレーム対応を顧問弁護士に相談できる仕組み構築の参考として、病院・クリニック・医療法人の顧問弁護士に関しての役割や選び方などを詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
原則8:違法行為に注意
病院側が違法行為をしてしまうと、クレームや苦情に対応するうえで病院側の弱みになってしまいます。
そして、弱みがあると、本来断るべき無理な要求ものまざるを得なくなってしまうことがあります。
例えば以下のような違法行為に該当しないように日ごろから気を配ることが必要です。
病院で問題となりやすい違法行為の例
- 正当な理由のない診察拒否(医師法19条1項違反)
- 正当な理由のない診断書作成拒否(医師法19条2項違反)
- 看護師やスタッフによるレントゲン撮影(診療放射線技師法24条違反)
以上、病院、クリニックのクレームや苦情の対処方法では、まず上記の8つの原則をおさえておきましょう。
なお、クレーム対応の基礎知識については、以下の記事でわかりやすく解説していますのでご参照ください。
2,【事例】大声でわめく患者への診療義務、説明義務を否定した判例
病院・クリニックのクレームに関する参考として、「大声で不満を述べて執拗に診療や説明を要求し、長時間の相談室に居座るなどした患者について、病院側が裁判を起こして診療義務、説明義務等がないことの確認を求めた裁判事例(平成26年5月12日東京地方裁判所判決)」があります。
以下でこの判例についてご紹介したいと思います。
(1)平成26年5月12日東京地方裁判所判決
1,クレームの内容
病院の院長が4年前に行った手術について、患者からカルテや手術の録画記録の開示を求められて、これに応じました。
ところが、患者から「開示された手術の録画記録が本当に自分の手術のものなのかわからない」などと主張されたため、院長が「説明が信じられないのであればしかるべきところに訴えるしかない。質問事項があれば書面で出してください。」などと伝え、クレームになった事案です。
患者は、その後、何度も来院して大きな声で問答を繰り返し、また執拗に院長による説明や診察を求めました。
2,病院側の対応
- (1)院長は当初は質問事項があれば書面で受け付けるという対応をしていましたが、その後、弁護士同席の上で患者に対面での説明を行いました。
- (2)対面での説明にも患者は納得せず、その後も10回以上来院して院長による説明や診察を求めました。
- (3)患者が来院したときは、病院のスタッフが1時間ないし2時間程度対応しなければならないことが多く、また、患者は病院スタッフから帰るように促されても帰らないなどの態度をとりました。
- (4)このような経緯から、病院は、もはやこの患者に対応できないと考え、この患者に対する診療や説明、損害賠償などの義務がないことなどを確認することを求めて、患者に対する訴訟を起こしました。
3,裁判所の判断
裁判所はこの事例で、病院側の診療義務、問診義務、損害賠償義務を否定しました。
その理由は以下の通りです。
(1)損害賠償義務についての判断
患者は、手術に問題があったかのような態度をとっているが、具体的に手術のどの点が不適切だったという主張をしておらず、病院に損害賠償義務はないと判断しました。
(2)説明義務についての判断
患者は、病院からの説明は理解できるものではなく説明義務が尽くされていないということを主張しましたが、裁判所は、すでに説明は行われており、その後も文書での質問等を病院に行うことまでは拒否していないから、病院に説明義務はないと判断しました。
(3)診療義務についての判断
患者は病院に診療義務があると主張しました。しかし、裁判所は、患者が病院の説明に対して信用できないと発言し、院長に謝罪を求めるなどしていた経緯から、適切な医療行為のために必要な患者との信頼関係が破壊されていると判断し、病院には診療義務はないと結論づけています。
このように裁判所は、本件で、病院が患者に対する損害賠償義務を負わないことはもちろん、説明義務、診療義務もないと判断しました。
3,医師法の応召義務と「正当な理由」とは?
診療を拒否しなければならないような困難なモンスターペイシェントの対応において、注意しなければならいことの1つとして、「医師法19条1項の応召義務」があります。
医師法19条1項には、以下の通り、「正当な事由がなければ医師は診療を拒めない」ことが定められています。
では、どのような場合に、診療拒否についての正当な理由が認められるのでしょうか?
この点について、裁判所は、「医師と患者との信頼関係が適切な医療行為を期待できないほど破壊されている場合」は、医師法19条1項の「正当な事由」にあたるとしています。
そのうえで、前述の平成26年5月12日東京地方裁判所判決の事案では、医師の診察拒否については正当な理由があると判断しました。
このような判例を踏まえると、クレームや苦情が原因で患者との信頼関係を築くことが困難となり、診療を拒む場合は、以下の4点について注意することが必要です。
(1)クレームや苦情が原因で患者との信頼関係を築くことが困難となり診療を拒む場合の注意点
- 1.医師により説明をしなければならない項目については十分な説明を行う(弁護士立ち合いの上で説明することがベスト)。
- 2.診療を拒否しなければならなくなった経緯(患者の暴言や暴力など)について詳細な説明ができるように、「いつどのようなことがあってどのような対応をしたか」について詳細なメモを残す。
- 3.同じ内容のクレームや苦情が繰り返され対応に長時間を要する場合は、「これ以上説明することがないので帰るように」と明確に伝えて、それでも帰らない場合はその点について記録を残す。
- 4.「必要な説明は文書で行います」という内容の文書を患者に送り記録を残しておく。
このように十分な説明を行ったうえで、患者の問題行動の内容や病院側の対応の内容についてしっかり記録を残しておくことが必要になります。
診療を拒否しなければならなくなった経緯について十分な記録が残っておらず、単に「モンスターペイシェントだ」というだけで具体的な経緯を後日説明することができない場合は、診療拒否は違法とされてしまいますので、注意してください。また、医師により説明すべき項目について説明を行っていないケースでも、診療拒否は違法と判断されます。
そして、診療拒否が違法と判断されると、患者との裁判の際に、患者に対する損害賠償を命じられることもありますので、注意してください。
▶参考情報:「応召義務」については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧下さい。
・応召義務とは?クレーマーを拒否できる具体的基準を判例付きで解説
また、診療を拒否しなければならないような困難なモンスターペイシェントの対応については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
4,病院やクリニックのクレーム対策には「マニュアル作成」が必要
病院やクリニックからよくご相談をいただくクレーム事例としては以下のようなものがありますが、これらのクレームについてはあらかじめクレーム対策として「対応マニュアル」を作成しておくことが必要です。
(1)病院やクリニックでよくあるクレーム事例
1,スタッフの接遇態度や対応が悪いと言われるクレーム
- 看護師に対するクレーム
- 事務スタッフに対するクレーム
- ソーシャルワーカーに対するクレーム
2,診察や治療に関するクレーム
- 誤診だといわれるケース
- 検査について
- 手術の内容、結果について
3,病院のサービスや対応についてのクレーム
- 入院患者の食事について
- 待ち時間について
- 予約について
- 時間外の対応について
- クレームに対する回答が遅いことについて
- 患者の家族からのクレームや苦情
- 病院に謝罪文や文書での回答を求めるケース
4,治療費についてのクレーム
- 会計についてのクレーム
- 生活保護受給者の患者が薬剤費の支払いを拒むケース
- 返金を求めるケース
マニュアルがないと職員がクレームについて個別に判断して対応することになり、職員により対応に差が出てしまいますし、職員個人の負担も大きくなってしまいます。上記でとりあげたよくあるクレーム事例については、病院としてのルールを整備し、マニュアル化していきましょう。
マニュアル化を進めることで、全職員が同じ判断をすることができるようになります。また、マニュアルをもとにクレームを対処した時に問題がおきたときは、さらにマニュアルを改善していくことで、病院やクリニックをクレームの対処に強い組織にしていくことが可能です。
5,病院やクリニックのクレーム対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所において提供している病院のクレーム対応についてのサポートメニューのご紹介をしたいと思います。
- (1)病院のクレームに関するご相談
- (2)弁護士による患者への説明の立ち合い
- (3)弁護士によるクレーム対応
以下で順番に見ていきましょう。
(1)病院のクレームに関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、クレームにお困りの病院、クリニックから、クレームの解決方法に関するご相談を承っております。
顧問契約を締結していただくと、日々、スタッフからクレームについての対処方法を顧問弁護士に電話で直接ご相談いただくことが可能です。顧問弁護士への相談によりクレーム対処にあたるスタッフの精神的な負担を大きく軽減することが可能になり、スタッフの定着、離職の防止につながります。
(2)弁護士による患者への説明の立ち合い
病院やクリニックにおけるクレーム対処では、患者に対して十分な説明を行うことも必要です。
咲くやこの花法律事務所では、クレームでお困りの病院やクリニックからのご依頼で、医師による説明の場への弁護士の同席のサービスも行っております。
(3)弁護士によるクレーム対応の代行
咲くやこの花法律事務所では、現場での解決が困難なクレームについて、病院やクリニックに代わり弁護士によるクレーム対応を代行するサービスも行っています。
咲くやこの花法律事務所の弁護士は患者への内容証明郵便や文書送付によるクレーム解決経験も豊富です。クレーム対応に精通した弁護士が直接患者に対応することにより病院やクリニックの負担を軽減し、迅速な解決を実現します。
クレームにお悩みの病院・クリニックの経営者、管理者の方はぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
(4)「咲くやこの花法律事務所」への問い合わせ方法
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
6,【関連情報】病院やクリニックのクレームトラブルに関するお役立ち記事一覧
今回の記事では、「病院・クリニックのクレームや苦情の対応方法!患者とのトラブル対処法を解説」についてご説明しました。病院・クリニックにおけるクレームや苦情に関しては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい対応方法を行わないと「重大なトラブル」につながります。万が一、患者さんとのトラブルが発生した際は、多額の支払いが発生することもあります。
以下では、この記事に関連するクレーム対応のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・自社に非がない場合のクレーム対応の重要ポイントと対応例文について
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年12月30日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」クレーム対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587