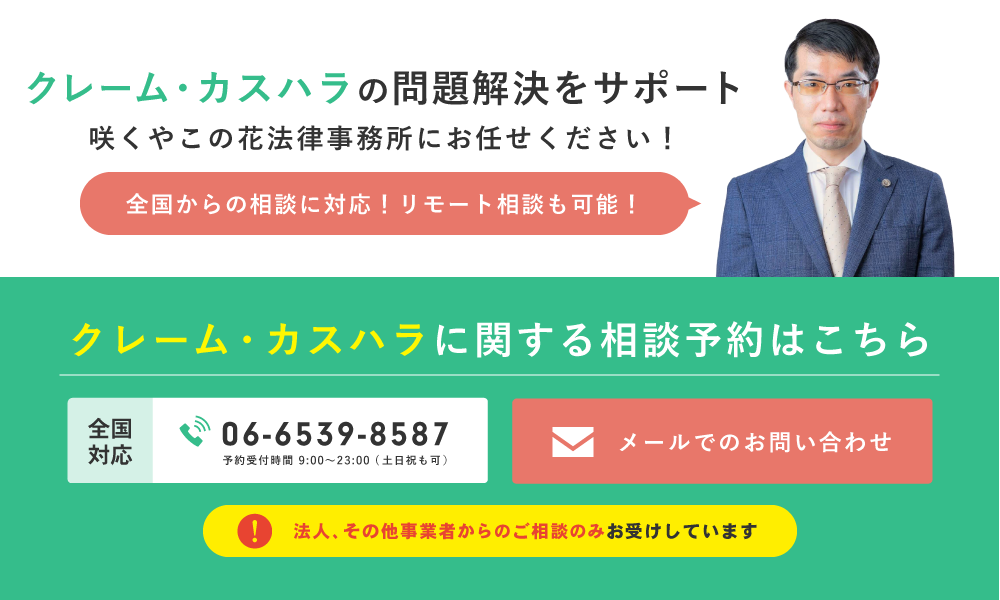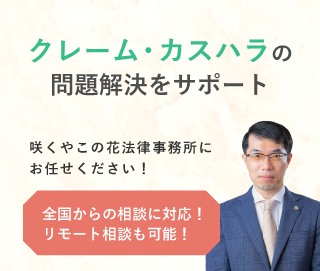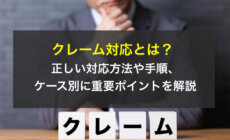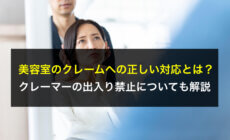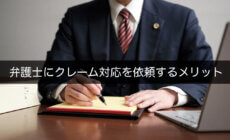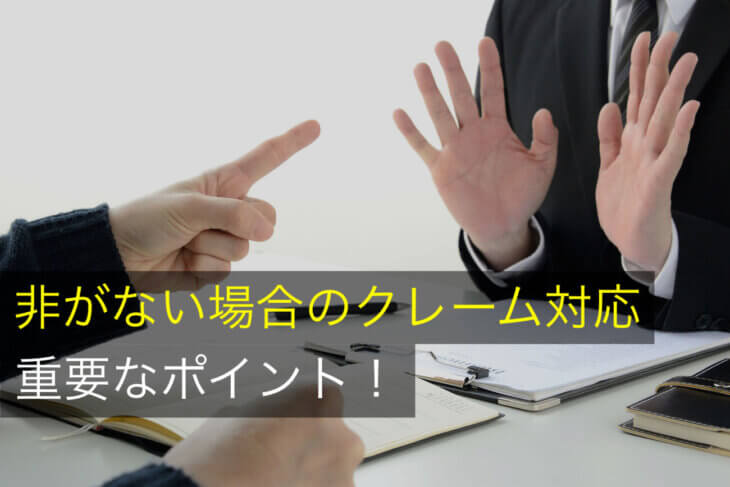
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自社に非がないのに、何度も電話やメールでのクレームを入れてくる顧客への対応に悩んでいませんか?
中には、自社に落ち度がないにもかかわらず、「自宅に謝りに来い」とか「金を返せ」「迷惑料を払え」などと理不尽な要求を受けるケースもあると思います。このようなクレームへの対応を誤ると、対応する側が長時間拘束され、疲弊することになる一方で、いつまでも解決せずに埒があきません。
会社としては一生懸命対応しているつもりでも、誤った自己流の対応をしてしまった結果、逆に解決が遠のき、問題が泥沼化してしまったケースも弁護士として多く見てきました。
そこで、今回の記事では、筆者の経験も踏まえて、自社に落ち度がない場合のクレーム対応についてご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、自社に落ち度がない場面でのクレーム対応の初動を誤らなくて済み、また、解決までの具体的な道筋を見通すことが可能になります。
それでは見ていきましょう。
▶参考情報:なお、クレーム対応の基礎知識については、以下の記事でわかりやすく解説していますのでご参照ください。
会社に落ち度がないのにクレームがいつまでも繰り返されるときは、会社のクレーム対応の方法にも問題があります。
そのような場面で、クレームを解決するためには、弁護士に相談して、これまでの対応方法を改めることが必要です。長く続くクレームに対して間違った対応を続けていると、担当者の疲弊による離職のリスクもでてきます。早めにクレーム対応に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
▶【関連動画】西川弁護士が「理不尽なクレーマーへの対応7つのポイント」を詳しく解説中!
▶【関連情報】クレーム対応に関する情報は、以下も参考にご覧ください。
▼クレーム対応に関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,非がない場合のクレーム対応とは?

非がない場合のクレーム対応とは、自社に落ち度がないにもかかわらず、顧客側の独自の正義感に基づく要求や、過剰な要求・不合理な要求への対応が必要になるケースです。「自宅に謝りに来い」とか「金を返せ」「迷惑料を払え」などと理不尽な要求がされる例が少なくありません。このような要求が金銭を得る目的でされる例もあります。
このようなクレームについては、自社に落ち度があって対応するクレームとは違った対応が必要です。以下で解説したいと思います。
2,クレーム対応は弁護士に頼めば迅速に解決できる

実は、企業がクレーム対応について困っている場合、クレーム客との交渉を弁護士に頼むのが一番早い解決方法です。筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でも、これまで多くの企業からクレーム客との交渉をご依頼いただき実際に解決してきました。
筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所のクレーム対応についての解決実績例をご覧ください。
・設計事務所からの依頼を受け、施主からのクレームを弁護士が窓口となり解決した成功事例
弁護士にクレーム客への対応を依頼することで、「上下の関係ではなく、対等・公平な関係で交渉ができる」、「法的に成り立たない要求は法律上の根拠を示して断ることができる」等大きなメリットがあります。特に、本稿のテーマである、自社に非がないクレームの場合、弁護士が会社の代理人となって、クレーム客に適切な断りの文書を送れば、それ以上、クレーム客から連絡がこなくなることが通常です。
しかし、弁護士に頼むことには費用がかかりますので、全てのクレームについて弁護士に依頼するわけにはいかないと思います。そこで、以下では、弁護士に頼まずにできるだけ自社で解決する方法をご説明します。
ただし、もし、あなたが本当に、クレームでお困りであれば、以下でご説明する方法を自分で実行するのではなく、費用を払ってでも弁護士にクレーム客との交渉を代理してもらうことをおすすめします。
自社で実行することにより対応を誤り、より問題がこじれるケースも多く存在し、弁護士に依頼したほうが、迅速かつ確実にクレームを解決することができるからです。
クレーム対応を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用など、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
3,自社に落ち度がない場合のクレーム対応のゴール
クレーム対応の具体的な進め方をご説明する前に、自社に落ち度がないクレームに対して、どのようなゴールを目標に対応すればよいかをはっきりさせておく必要があります。
多くの企業では、自社に落ち度がない場合でも、クレーム客に納得してもらうことをゴールにクレーム対応を行っています。確かに、クレーム客にもちゃんと納得してもらったほうが、担当者としてもすっきりしますし、会社にもクレームが解決したと報告することができます。インターネットなどで誹謗中傷されるおそれも少なくなるでしょう。
しかし、そもそも会社に非がないのにクレームを言ってくるような客に納得してもらうことは、簡単ではありません。
それにもかかわらず、「クレーム客の納得」というゴールを設定することは、実際上は不可能なゴールを設定していることになり、クレームがいつまでも解決せず、担当者の精神的な疲弊がつのる原因になります。このような場合、そもそもゴールの設定が間違っていることに気づく必要があります。
自社に落ち度がない場合のクレーム対応の正しいゴールは、必ずしも「クレーム客に納得してもらうこと」ではなく、「クレーム客から連絡がこなくなるようにすること」です。
「クレーム客から連絡がこなくなるようにする」ためには、必ずしも納得してもらう必要はなく、クレーム客に「これ以上クレームをつけても対応してもらえない」と理解させ、あきらめさせることによる解決も視野に入れて話をする必要があります。
4,電話、メール、手紙のどれで対応するのが適切か?
多くのクレーム客は、手紙ではなく、電話やメールでクレームをいれてきます。
しかし、「クレーム客から連絡がこなくなるようにする」というゴールを見据えた場合、最も適切なのは手紙による対応です。電話やメールはクレーム客が気軽に連絡しやすいツールであり、会社が電話やメールでクレーム対応すると、すぐにクレーム客から反論がかえってきてしまいます。
これでは、「クレーム客から連絡がこなくなるようにする」というゴールにたどり着きにくいのです。クレーム客から電話やメールでクレームが入る場合、会社も最初のうちは電話やメールで対応するべきですが、それをやっても解決できない場合は、会社は、文書(手紙)による対応に切り替ることが適切です。
5,電話のクレームはまずは話を聴くことが必要
自社が落ち度がない場面でのクレームは、電話から始まることが最も多いです。会社に落ち度がなく、文書やメールで会社に対して要求を出そうとしても、筋の通った内容にならないことをクレーム客自身が理解しているため、電話でクレームを入れているケースもあります。
そして、電話でのクレームは、おおむね「事実を伝える部分」と「クレーム客の感情を伝えている部分 」、「クレーム客の要求を伝える部分」の3つにわかれます。
クレーム客と電話で話をするときは、いまクレーム客がこの3つのうちどの部分の話をしているかを意識して、それによって会社側の対応を変えることが必要です。電話でのクレーム対応については、以下の詳細記事で重要ポイントを解説していますので参考にご覧ください。
(1)クレームのうち「事実を伝える部分」の対応
クレームのうち、「事実を伝える部分」については、クレーム内容を正しく把握するために、メモをしっかりとり、記録を残すことが必要です。
この点があやふやになると、そもそも自社に非がないクレームかどうかも判断できず、会社として明確な対応方針を決めることができません。また、事実関係があいまいなまま対応を進めると、クレーム客に対して不誠実な印象を与え、より感情的なクレームに発展します。
ある程度クレームに対応した後になって、事実関係をクレーム客に質問するということは難しいことが多いので、クレームの最初の段階で事実関係をしっかり確認しておく必要があります。クレーム客の側で整理した話ができないことも多いので、クレーム客が主張する事実について、以下の「5W1H」を、会社担当者からクレーム客に質問し、事実関係を正確に確認してメモを取ることが必要です。
▶参考情報:「5W1H」とは?
・Who(だれが)
・When(いつ)
・Where(どこで)
・What(なにを)
・Why(なぜ)
・How(どのように)
●参考例
クレーム客
「おたくの会社の化粧品を使用したら、まぶたが赤くなった。どうしてくれるんだ。」
企業担当者
まず、いつから、どの部位に、どのくらいの分量、どのような頻度で化粧品を使用したのかを確認。
さらに、まぶたが赤くなる症状が、いつから生じたのか、ほかの部位には症状が出ていないのか、購入者が症状にどのように対処したのかを確認。
正確な事実関係の把握のためには、電話で話しながら常にメモを取る習慣を身に着けることが必要です。電話で話をしているときに手が止まっていないかどうかチェックしてみましょう。
(2)「クレーム客の感情を伝える部分」の対応
クレーム客の話す内容には、「自分がどれだけひどい目にあったか」、「自分がどんなに不快な思いをしたか」という「感情を伝える部分」が含まれています。特に、会社に落ち度がないクレームのケースでは、クレーム客がする話の多くの部分が、この「感情を伝える部分」です。
この「感情を伝える部分」は、ほとんど意味のない主張です。しかし、自社でクレームを解決しようとする場合は、一度は、この部分についてもひととおり話を聞くことが必要です。
ただし、その聴き方としては、「そうなんですね」などと肯定とも否定ともいえない適当な相槌を打ちながら、話を聴くという対応で問題ありません。この「感情を伝える部分」について、クレーム客が言っている話がおかしかったり、不合理な内容であったとしても、この部分は、ほとんど意味のない主張であり、会社側から反論したり、会社側の意見を言ったりすることは必要ありません。
この部分について、会社の立場での主張をすることは、感情面で余計にこじらせることになりますので、控えるべきケースが多いです。
(3)「クレーム客の要求を伝える部分」の対応
クレーム客には、具体的な要求をする人と、具体的な要求をしない人の2パターンがあります。
まず、会社に落ち度がないのに、例えば、「代金を返金しろ」とか「自宅まで謝りに来い」といった具体的な要求をするケースには、はっきりと断ることが原則となります。
端的に「そのようなご要望にはお応えすることはできません。」と断るべきです。
一方、具体的な要求がなく、抽象的に「誠意を見せてほしい」とか「会社のほうで対応を考えろ」と言われるケースもあります。
この場合も「会社としての対応は考えていません。」と断ることが原則です。
(4)クレーム客が怒った後の対応
クレーム客の要求を断ると、クレーム客は怒鳴ったり、罵倒したり、「お前じゃ話にならないから上司を出せ」という反応をすることがあります。
しかし、そのような反応に対しても、「会社としてご要望にお応えすることができないことはお伝えした通りです。」という断り文句を何度も繰り返す必要があります。クレーム客の要求を断る場合に、いろんな側面から言い方を変えて説得したり、いろいろな理由付けを考えて説得したりする必要はありません。
「クレーム客から連絡がこなくなるようにする」というゴールにたどり着くためには、「会社としてご要望にお応えすることができないことはお伝えした通りです。」という同じ断り文句をひたすら繰り返すことで、何度言っても意味がないということを理解させることが効果的です。
また、クレーム客が暴言を吐くときは、礼儀を正すように求めることが必要です。例えば、「今、あなたは、おまえじゃ話にならない、と言われました。そのような言葉遣いはやめてください。礼儀をわきまえない言葉遣いをされる場合は、話をすることはできませんので、電話を切らせていただきます。」などと明確に抗議するべきです。
暴言が出始めた時点で、放置せずに明確に抗議することで、クレーム客に、無茶な要望をしても応じてもらえないのだということをはっきりと理解させることが必要です。
▶参考情報:暴言などのクレームについては、以下の記事で対策なども解説していますので、ご参照ください。
上記の通り、毅然と断ることが原則ですが、自社に落ち度がない場合でもクレーム客の要求に応じたほうがよいケースも存在します。
たとえば、ECサイトで商品を購入する際に、顧客が1個買うつもりが、間違って10個買ってしまったというようなトラブルで、「9個分の代金を返金してくれ、返金しないのはおかしい」という要求がされるケースがあります。
このようなケースは、Webサイトで顧客を誤認させるような記載をしていない限り、特に事業者側に落ち度があるわけではなく、法律上も返金対応の必要はありません。
しかし、クレームが長引くことによる対応の負担や、クレーム解決を弁護士に依頼する場合の費用などを考えると、事業者として返金対応に大きな負担がないのであれば、9個分の商品を返送してもらい、9個分の代金を返金することで解決することが合理的です。
返金要求のクレーム対応については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
6,要求を断った後のしつこい長電話は対応を拒絶し、電話を切る

会社に落ち度がないクレームの場合、そもそも、「会社が電話に出る義務」や「一度出た電話を途中で切ってはいけない義務」があるわけではありません。会社がクレーム客の要求を断った後も、クレーム客がしつこく要求を繰り返す場合は、対応を拒絶し、電話を切る必要があります。
例えば、以下のように告げて電話を切るべきです。
自社に落ち度がない場合のクレーム対応の正しいゴールは、「クレーム客に納得してもらうこと」ではなく、「クレーム客から連絡がこなくなるようにすること」です。上記のように対応することで、クレーム客に、「これ以上クレームの電話をかけても意味がない」と理解させることが必要です。
7,手紙などの文書での対応に切り替える
しつこく電話が続く場合、前述の通り、文書での対応に切り替えることも、1つの方法です。クレーム客の要望を断る内容の手紙を郵便で送るという方法です。
この場合、例えば、クレーム客からの電話を受けたときに、「お話は伺いました。会社としての結論を書面で送付させていただきます。本日は電話を切らせていただきます。」などと言って、文書での対応に切り替えます。
「手紙」は「メール」や「電話」と違い、以下のような特徴があります。
- 「手紙」は会社の最終的な決定であり、反論しても変更されないという印象を与えやすいコミュニケーションツールである。
- 「メール」や「電話」と違い、手紙は、その場で反論ができないため、「クレーム客から連絡がこなくなるようにすること」というゴールにつなげやすい。
「手紙」を送る時のポイントは、「反論が返ってこないような内容のみ書く」、「クレーム客が反論したくなるようなことは書かない」ということです。「クレーム客から連絡がこなくなるようにすること」がゴールですから、反論が返ってこないように書く必要があるのです。
手紙は比較的反論が返ってきにくいツールではありますが、会社からの手紙に対しても、クレーム客が電話やメールで再度反論してくるケースがあります。手紙の内容に工夫をこらして、反論が返ってこないようにすることが重要になります。
8,落ち度がないクレームに対応する場合の例文
反論が返ってこないようにするためには、手紙にクレーム客の要求を断る理由をどこまで書くかがポイントです。
そもそも、クレーム客の要望を断る場合に、必ず理由を書かなければならないわけではありません。弱い理由付けや、クレーム客との間で意見の食い違いがあるような理由付けを記載すると、反論が返ってきて逆効果となります。そのような理由付けを書くくらいなら、理由は書かずに結論だけ書いたほうがよいでしょう。
一方、反論ができないような理由付け、特に法律上の理由付けがある場合は、記載したほうがよいです。
法律上の理由付けを書く場合は、必ず、その条文(例えば、民法第●条)または、根拠となる裁判例(例えば、東京地裁令和●年●月●日判決)を明記しましょう。
以下の例文を参考にしてください。
対応例文1
「●●様は、弊社が設計した住宅に、●●様が購入した家具を搬入できなかったことが、弊社の不手際にあたると主張され、弊社に対して金銭の支払や面談の要望をされています。
しかし、家具は工事完了後に●●様が選定し、購入されたものです。弊社が設計した際には家具の内容は決まっておらず、家具が搬入できなかったとしても弊社の落ち度ではありません。弊社は●●様に対し、金銭の支払いをしたり、面談の要求に応じる義務はなく、その意思もありません。
以上を本件についての弊社の最終の回答とさせていただきます。」
このように、一般論としては、まず「相手の要求内容」を記載すべきでしょう。これは、会社から送った文書がSNSなどに掲載される可能性があることを踏まえて、SNSで文書を目にした第三者から見てもクレーム客の主張内容が不合理であることをわかるようにしておくという意味もあります。
そのうえで「要求に応じる義務がなく、意思もない」と記載し、さらに「最終の回答であること」を記載することで、クレーム客から反論が返ってこないような内容にすることが必要です。
対応例文2(カスタマーハラスメントがある場合)
会社が対応できないことを明確にしているにもかかわらず、電話をしつこくかけてきたり、担当者に対して暴言を吐くなど、カスタマーハラスメントに該当するレベルに至っているケースでは、より踏み込んだ記載をする必要があります。
例えば、以下のようなイメージです。
「あなたは、弊社が設計した住宅に、あなたが購入した家具を搬入できなかったことが、弊社の不手際にあたると主張され、弊社に対して金銭の支払や面談の要求をされています。
しかし、家具は工事完了後にあなたが選定し、購入されたものです。弊社が設計した際には家具の内容は決まっておらず、家具が搬入できなかったとしても弊社の落ち度ではありません。弊社はあなたに対し、金銭の支払いをしたり、面談の要求に応じる義務はなく、その意思も全くありません。いただいたご要望はすべてお断りします。
ところで、あなたは、「きちんと仕事しろや。馬鹿じゃないのか。」「仕事ができないなら金を返せ」などと弊社の担当者に繰り返し発言されました。弊社の担当者がそのような非難をうけるいわれは全くなく、厳重に抗議します。
以上が本件についての弊社の最終の回答となります。
今後もあなたが弊社に対し要求を繰り返される場合は、弊社は本件を弁護士に依頼して対応する予定ですので、申し添えます。」
以下の点がポイントです。
- 「●●様」とは書かずに、「貴殿」もしくは「あなた」と表記することで、対等の話し合いであることを明確にする。
- 失礼な発言や不穏当な発言、しつこい電話などカスタマーハラスメントについて抗議する内容を入れる
- これ以上要求を繰り返す場合は弁護士による対応になることを記載する
カスタマーハラスメントに関する対策については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にご覧ください。
クレーム客に送付する文書の内容は、上記のような例文を参考に、クレーム客の性格、理解能力の程度など、ケースに応じた工夫をこらす必要があります。
例えば、自己保身的な傾向が強いクレーム客には、法律面を意識させる文書が有効です。
「今後もあなたが弊社に対し要求を繰り返される場合は、弊社は本件をカスタマーハラスメント事案として弁護士に依頼して対応する予定ですので、申し添えます。」と明記することも検討に値するでしょう。
一方、精神疾患がうたがわれるクレーム客に対しては、「今後ご連絡いただく場合は弁護士を通じてご連絡ください。」といった内容にすることも検討すべきです。
相手の特性をよく見極めて、返事が返ってこないような文書にすることがポイントになります。クレーム対応の例文についてく詳しい解説は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
9,非がない場合のクレーム対応を弁護士に相談したい方はこちら

最後に咲くやこの花法律事務所のクレーム対応についてのサポート内容をご紹介したいと思います。
冒頭でもご説明した通り、自社に非がないクレームを迅速かつ確実に解決するためには弁護士への依頼がおすすめです。自社で対応すると、対応方法を誤り、問題が余計にこじれて解決が遠のく危険があります。
咲くやこの花法律事務所では、クレーム対応にお困りの企業様から、クレーム対応の進め方についてのご相談をお受けしています。理不尽なクレームや過剰要求のクレームを多数解決した実績のある弁護士にご依頼いただくことで、自社はクレーム対応から解放され、弁護士に解決を任せることができます。
クレーム対応にお困りの時は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
咲くやこの花法律事務所のクレーム問題に強い弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
▶参考動画:クレームや悪質クレーマー対応に強い弁護士への相談サービスの解説動画も参考にご覧ください。
「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
クレーム対応に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
10,【関連記事】クレーム対応に関するお役立ち記事一覧
今回の記事では、「自社に非がない場合のクレーム対応の重要ポイントと対応例文について」について解説しました。クレーム対応については、その他にも確認しておくべき重要な情報があり、「咲くや企業法務.NET」のサイト内でも業種別のクレーム対応に関する解説記事を公開しています。
この記事内でご紹介していない業種別のクレーム対応についてなど、その他のクレーム関連のお役立ち記事は、以下をご覧ください。
【派遣業界】
・【派遣会社向け】派遣先からのクレームや損害賠償請求の対応方法
【医療業界】
・病院・クリニックのクレームや苦情の対応。窓口や受付での患者とのトラブル対処法は?
・モンスターペイシェントとは?対策の基本5つを弁護士が解説!
・応召義務とは?クレーマーを拒否できる具体的基準を判例付きで解説
【製造業・建設業・解体業】
・製造業・建設業・解体業向け!工場や工事の騒音でクレームや苦情を受けたときの対応方法
【化粧品・エステ業界】
・化粧品、エステ・美容業界向け!消費者の肌荒れクレームに対する正しい対応方法
【理美容業界】
・美容室のクレームへの正しい対応とは?クレーマーの出入り禁止についても解説
【接客業】
【学校関係】
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2026年2月5日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」自社に非がない場合のクレームなどクレーム対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587