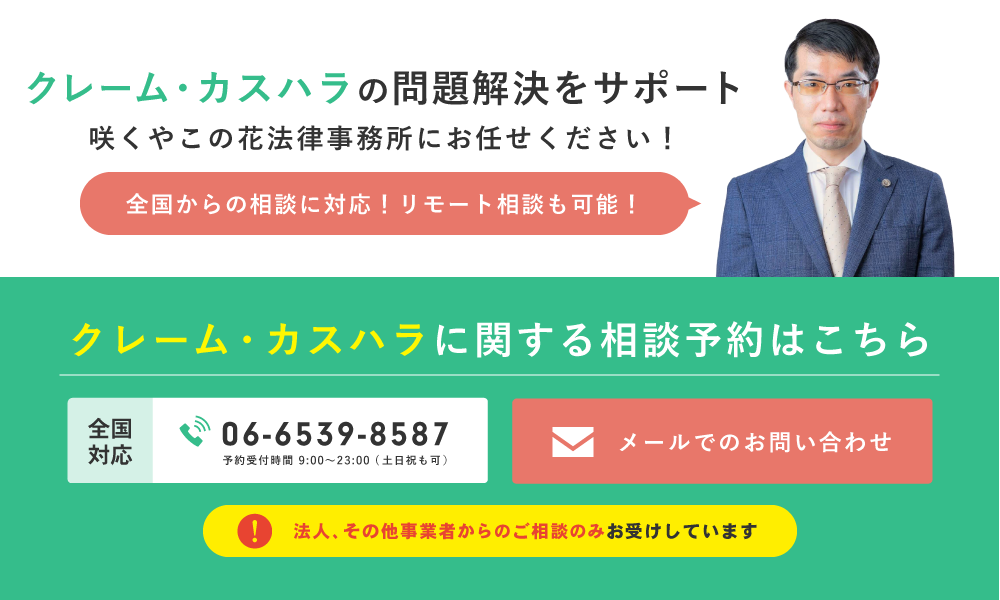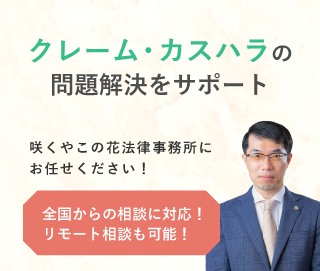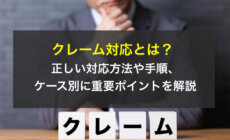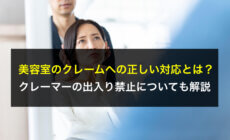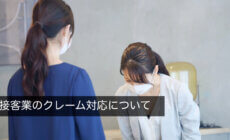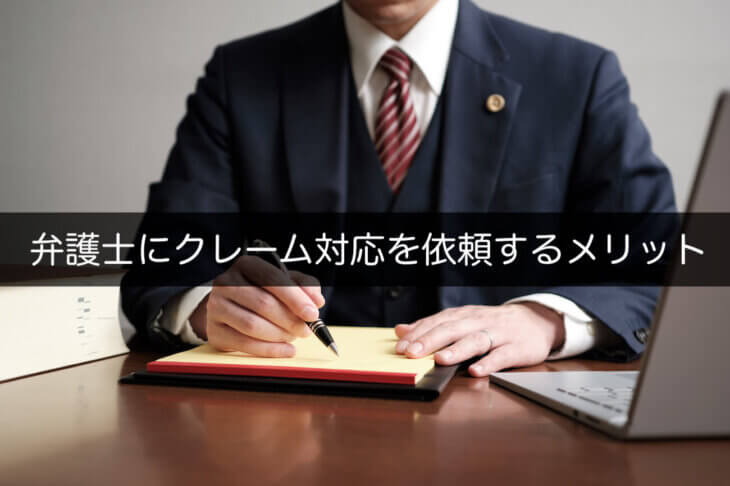
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
クレーム対応やクレーマー対応に時間と手間をとられて悩んでいませんか?
実は、自社では解決できず延々とクレームが続くときも、弁護士に対応を依頼することで迅速に解決できるケースが多いです。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所でも、これまで多くの事業者から、クレーム対応の代行の依頼を受け、解決してきました。その一部を以下でご紹介していますので、あわせてご参照ください。
今回はクレーム対応やクレーマー対応について、事業者が弁護士に依頼するメリットや弁護士費用、頼み方などについて解説します。この記事を読んでいただくことで弁護士への依頼によりクレームを解決する場合の具体的なイメージをもっていただくことができます。きっとクレームの解決に向けて、前向きに取り組んでいけるようになるはずです。
それでは見ていきましょう。
クレーム対応には正しい方法があり、やり方が間違っているといつまでも解決しません。一生懸命対応しても解決できないときは、やり方を見直す必要があり、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所のクレームや悪質なクレーマー対応に強い弁護士への相談サービスについては、以下をご参照ください。
▶参考動画:西川弁護士が「クレームやクレーマー対応を弁護士に依頼する5つのメリット」を詳しく解説中!
▼クレームやクレーマー対応に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,弁護士への依頼を検討するべきクレームとは?
- 2,クレーム対応の代行を弁護士に依頼するメリット5つ
- 3,悪質なクレーマーへの対応は弁護士に依頼して組織として対応する
- 4,弁護士に依頼した後のクレーム解決までの流れ
- 5,弁護士にクレーム対応やクレーマー対応を依頼する方法
- 6,クレーム対応やクレーマー対応の代行を依頼する際の弁護士費用
- 7,弁護士によるクレーム対応やクレーマー対応の解決事例
- 8,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます。」
- 9,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
- 10,クレーム対応に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
- 11,【関連情報】クレームやクレーマー対応に関する関連記事
1,弁護士への依頼を検討するべきクレームとは?

クレーム対応では、お客様の言い分に耳を傾け、謝罪をすることで、お客様の怒りをしずめ、お客様が落ち着いた段階で事実確認をして解決策を提示していくことが基本です。
このような基本的なクレーム対応ができていない場合は、まずは基本をしっかり徹底する必要があります。しかし、このような通常の対応をしても解決が難しいクレームも存在します。
それは以下のようなクレームです。
- 自社がお客様に経済的損害や健康上の被害を与えてしまい、賠償を要求されているケース
- 神経質で次々に要求を変え、延々と電話、メールで要求が続くケース
- 些細なミスにつけこんで過大な要求、対応困難な要求が執拗に繰り返されるケース
- クレーム客独自の感性で「筋をとおす」ことを要求されるケース
これらのクレームに自社で対応することが難しいときは、弁護士に相談すること、あるいは弁護士に対応を依頼することも検討するべきでしょう。
(1)ルールを切り替えることが解決のためのポイント
上で挙げたようなクレームを解決するためのポイントは、「クレーム客が納得するルール」で解決しようとするのではなく、「法律のルール」に基づいて対応していく点にあります。
通常のクレーム対応では、クレーム客の納得を目指して対応しますが、上で挙げたようなクレームで、クレーム客の納得を目指そうとすると、クレーム客の言いなりにならない限り、解決できません。
そこで、クレーム客の要求が、法律上対応すべき限度を超えているときは、クレーム客の納得を目指すのではなく、裁判例等を根拠にクレーム客の要求を断り、納得していなくても要求を断念させることを、解決の基本方針とするべきなのです。
この記事では弁護士に対応の依頼を検討するべきクレームについて解説します。自社で対応すべき日常的なクレームへの対応については以下で解説していますのでご参照ください。
2,クレーム対応の代行を弁護士に依頼するメリット5つ
上記のような場面で、クレーム対応の代行を弁護士に依頼するメリット、逆に言えば自社で対応するデメリットとして、以下の点があげられます。
(1)法律のルールに基づく対応ができる
自社による対応では、どうしても「お客様」としての対応となり、クレーム客も「客としての扱い」を求めます。その結果、「法律のルール」を貫くことが困難です。「法律ではこうなっている」という話を仮に自社からしても、「法律の話をしているわけではない」と返答される恐れがあります。「誠意を見せろ」とか「筋を通してほしい」などと、法律とはかけはなれた観点から、非難を受けることもあります。
しかし、弁護士であれば、クレーム客との間で「事業者とお客様」というような上下の関係性がないため、対等な話し合いができ、 かつ、「法律のルール」に基づく話し合いが可能です。
(2)説得力ある説明ができる
自社による対応では、「法律ではこうなっている」、「裁判例ではこうなっている」という説明をしたとしても、それに説得力を持たせることが困難です。
弁護士が、法律と裁判例のルールをもとにクレーム客と話をすることで、はじめて説得力のある対応が可能になります。
(3)最終的な解決ができる
損害賠償の支払いや商品の交換、返金というように、自社がなんらかの負担をして、クレームを解決しなければならないこともあります。
そのような場面では、それらの負担をすることと引き換えに、それ以上の請求を受けないことを法的に確保しておくことが必要になります。
そして、この点を確保するためには、解決時の合意書の作成について万全を期すことが重要です。合意書の内容が不十分になると、クレームが繰り返され、再度、要求を受け、負担を強いられる危険があります。
弁護士による専門的なノウハウを生かして、クレームが蒸し返されないような合意書を作成する必要があります。
(4)自社は本来業務に集中できる
クレーム対応に多くの労力と時間を割くことで、本来の業務に支障が生じていないでしょうか?
自社で対応できないクレーム客には、いくら労力と時間を割いたとしても、クレームを解決できない可能性があります。むしろ、労力や手間をかければかけるほど、本来の業務にダメージが及んでいきます。それによって、新たなミスや新たなクレームが発生しかねません。負の連鎖が生まれてしまいます。
自社で対応が困難なクレームは、弁護士に依頼することが、この「負の連鎖」を断ち切る近道です。弁護士に依頼することで、クレーム客に対して、「今後は弁護士が対応するので、弁護士宛に連絡してください」と伝えることが可能になります。また、依頼を受けた弁護士からも、今後一切の連絡は弁護士宛てにするように、クレーム客に通知します。
以後は、クレーム客の対応を一切弁護士にまかせることで、自社は本来業務に集中することが可能になります。
(5)ストレスから解放され、職場環境を改善できる
担当者がクレーム対応について、大きなストレスを感じていないでしょうか?
仕事である以上、一定のストレスがあることはやむを得ないことです。しかし、多くのお客さんがいるのに、特定のクレーム客1人が仕事のストレスの大半を占めているということになると、異常な事態です。
そのクレーム客の対応は弁護士にまかせることで、担当者のストレス要因のほとんどを解消することができます。
職場環境の改善にもつながります。
3,悪質なクレーマーへの対応は弁護士に依頼して組織として対応する
担当者の些細なミスや落ち度に付け込んで金品を不当に要求するような悪質なクレーマーについて、現場の担当者に対応をまかせることは、担当者の精神的な負担が大きく、企業の安全配慮義務の観点からも適切ではありません。
悪質クレーマーの問題は、「カスタマーハラスメント」として、担当者まかせにせず、組織として対応することが必要です。
また、社内で、クレーマーに関する情報を共有して、対応しようとしても、対応する人が、その時々によって変わると、人によって対応の違いが発生しがちです。
そして、クレーマは、そこにつけこんできます。そのため、悪質クレーマーへの対応は、「窓口を一本化」することも非常に重要です。
これらの点を踏まえると、悪質クレーマーに対して、組織として毅然とした対応をするためには、対応窓口を弁護士に一本化したうえで、弁護士による内容証明郵便の発送により、クレーマーに対して警告し、クレームをはねのけることが最も効果的です。
(1)悪質なクレーマーへの対応が不適切な場合、企業としての責任を問われることも
悪質なクレーマーにも担当者個人で対応させたり、悪質なクレーマーに対してもクレームを丸くおさめるために担当者にクレーマーに対する不合理な謝罪を指示することは、企業の安全配慮義務違反として、企業の責任を問われることもあります。
裁判例の中にも、小学校長が、悪質クレーマー化して理不尽に謝罪を求める保護者への対応として、現場の教員に保護者の要求に応じて謝罪するように指示した事案について、教員の自尊心を傷つけ、多大な精神的苦痛を与えたと判断して、賠償を命じたものがあります(甲府地方裁判所判決平成30年11月13日)。
一方、NHK視聴者コールセンターでの視聴者からの暴言について、組織として一定のルールを定めて対応していたとして、事業主に安全配慮義務違反はないとした裁判例として、横浜地方裁判所川崎支部判決令和3年11月30日があります。
これらの裁判例で問題にされたような、従業員に対する安全配慮義務違反の問題を起こさないためにも、悪質クレーマーへの対応は弁護士に依頼することが適切です。
なお、安全配慮義務違反については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
また、カスタマーハラスメントについても以下で詳細な解説をしていますので、こちらもあわせてご参照ください。
4,弁護士に依頼した後のクレーム解決までの流れ

では、弁護士に依頼した後のクレーム解決までの流れはどのようなものなのでしょうか?
(1)まずは弁護士から受任の連絡を入れる
弁護士にクレームの解決を依頼すると、弁護士から、クレーム客に受任の連絡を入れることになります。
その中で、弁護士からクレーム客に伝えるメッセージは以下の内容です。
- あなたとのトラブルの解決について、会社から依頼を受けて、私(弁護士)が解決することになりましたというメッセージ
- 今後、一切の連絡は、私(弁護士)宛てにしてくださいというメッセージ
- 本件については、法律や裁判例の基準を踏まえて、正しい解決をしますというメッセージ
(2)クレームの内容を確認するための資料を提出させる
弁護士がクレームについて「法律のルール」に基づいて対応するためには、事実関係の正しい把握が重要です。
そして事実関係を把握するためには、資料を集めることが必要になります。
事実関係を正しく理解するための資料がなければ、事業者がクレーム内容について法的な責任を負うかどうかや、責任を負うとしてもそれがどの程度のものかを判断することができないためです。
例えば、以下のようなイメージです。
●化粧品が肌に合わず、肌荒れ被害が出ているというクレームを受けた場合
→被害の事実を確認するための写真や診断書等の資料を求めることが必要になります。
●賃貸不動産の管理会社が受けるクレームの1つとして、上階からの漏水のクレームがあります。
→この場合、そもそも、漏水の責任が、上階の住人にあるのか、それとも、建物所有者にあるのかという観点からの調査が必要です。そして、それと並行して、漏水被害により汚損した家具類の被害状況写真や家具類の購入価格に関する資料の提出を求めることも必要になるでしょう。
このような資料提出要求は、被害者に対してさらに手間や負担をかけさせることになる面があることは否定できません。
しかし、法律の理屈からすれば、被害を受けたのであればその立証は被害者の責任です。必要な資料の提出は遠慮せずに求める必要があります。
(3)資料をもとに弁護士が解決策を依頼企業と打ち合わせる
クレーム客から提出された資料の内容から、解決のために、事業者が損害の賠償や、返金、商品の交換、工事のやりなおし等の対応をすることが妥当と考えられる場合は、弁護士が法的な観点も踏まえて、クレーム客に提示する解決案を策定します。
そのうえで、まずは、依頼者である事業者との打ち合わせを行い、弁護士が策定した解決案をクレーム客に提示していく方針でよいかどうかを決めていくことになります。
(4)クレーム客に解決策を提示する
クレーム客に提示する内容が決まったら、解決策の提示は、原則として書面で弁護士から行います。
損害の賠償等、事業者として負担を伴う解決を提示する際は、提示額の賠償を受けた後は一切の請求をしないことをクレーム客に確約させる書面を作成し、それにクレーム客が署名、捺印し、返送してから、賠償金の振り込みをするという流れをとることになります。
一方、クレーム客が提示した解決策に納得しないこともあります。
その場合は、主に法的な観点からの説明を弁護士から行うことになります。提出されている資料からは提示した解決策以上の負担には応じられないことを理詰めで説明していくことになります。
そして、それでもクレーム客の納得が得られない場合は、無理にクレーム客の不合理な要求に応じて納得を得ようとするのではなく、「既に適切な対応、適切な解決案の提示をした」として、事業者側からの対応を終了することを検討するべきです。
その場合、クレーム客としては、訴訟等の法的な手段を検討する可能性があります。
しかし、すでに自社から合理的な解決策を提示している場合、訴訟等の手段をとっても、既に提示された解決策を上回る結論が得られる見込みは乏しく、クレーム客は訴訟を断念せざるを得ないことが通常です。
それでも万が一訴訟が起こされた場合は、弁護士が粛々と対応していくことになります。
▶参考動画:弁護士に依頼した後のクレーム解決までの流れについては、この記事の著者 西川暢春が「しつこいクレーマー!弁護士なら撃退できる?」の動画で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
納得しない相手へのクレーム対応のポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
▶参考情報:納得しない相手のクレーム対応はここがポイント!
5,弁護士にクレーム対応やクレーマー対応を依頼する方法
では、弁護士にクレーム対応やクレーマー対応を依頼するためにはどのような手順で進めるのがよいのでしょうか?
(1)クレーム対応やクレーマー対応に強い弁護士の選び方、探し方
現在、クレーム対応やクレーマー対応の分野を扱っておられる顧問弁護士がいる事業者は、まず、その弁護士に相談することになるでしょう。
一方、そのような顧問弁護士がいない場合は、自社のクレーム対応やクレーマー対応を依頼できる弁護士を探すところから始める必要があります。
弁護士の分野もさまざまにわかれており、離婚や交通事故、株主総会対応、労働事件など弁護士の専門性も様々です。
弁護士であれば誰でもよいというわけではなく、クレーム対応やクレーマー対応の分野で経験と実績がある弁護士を探すことが必要です。
(2)近隣の弁護士にこだわらずに探す
近くの弁護士に依頼することは、直接会って相談しやすいというメリットがあります。
しかし、最近では、弁護士の世界でも、電話やZoomでの相談が普通になりました。必ずしも会って相談することにこだわる合理性はないように思います。
また、クレーム対応やクレーマー対応の依頼を受けた弁護士は、通常は、電話や文書で相手に対応することになります。
そういう意味では、近くの弁護士でなくても、ほとんど支障はありません。むしろ、距離にこだわらずに、クレーム対応やクレーマー対応の分野で経験と実績がある弁護士に依頼することを優先するべきです。
(3)初回相談
弁護士への初回相談では、対応を依頼したい問題のクレーム客についての自社での対応経緯をわかりやすく弁護士に伝える必要があります。
クレーム客との整理されていないメールのやりとりをそのまま弁護士に提示しても、初回相談で有益な資料になることは少ないです。
以下の項目を中心に時系列順に整理しておくとよいでしょう。
- クレーム客による購入経緯
- クレーム客の購入内容
- クレームが起きたきっかけ
- 自社でクレーム内容について調査した場合はその調査結果
- クレーム客から資料の提出を受けた場合はその資料
- クレーム客の要望(要望が変遷している場合はその経緯)
- クレーム客から自社が最後に受けとったメッセージ
- 自社がクレーム客に最後に対応した際のメッセージ
初回相談では、弁護士に依頼した場合の弁護士による対応方針を確認し、それが自社の考えと一致するかどうかも確かめることが必要です。
(4)費用の確認
依頼する場合の弁護士費用の確認も重要になります。
すべての弁護士は、弁護士会のルールにより、弁護士費用について書面で契約書を作成することが義務づけられています。
依頼する際は、必ず弁護士に委任契約書を作成してもらい、その内容を確認してください。
6,クレーム対応やクレーマー対応の代行を依頼する際の弁護士費用
クレーム対応、クレーマー対応の代行を依頼する際の弁護士費用は、弁護士によって様々です。
以下では、筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所における費用の考え方をご説明します。
(1)着手金
クレーム対応、クレーマー対応の代行をご依頼いただく際の弁護士費用については、「着手金」と「報酬金」をいただいています。
このうち、「着手金」は、ご依頼いただく段階でお支払いいただく弁護士費用です。
クレーム対応、クレーマー対応の代行の着手金は、事案の難易度や複雑さを踏まえた見積もりをさせていただいています。
クレームの内容が複数にわたっていたり、あるいは複数人を相手方としなければならないケースについては、その点を考慮した見積もりをさせていただいています。
また、クレーム客がなんらかの経済的な被害や健康上の被害を受けたことを主張している場合は、その被害の大きさを着手金の見積もりにおいても考慮しています。
多くの事案で、着手金は15万円(税別)程度からの見積もりをさせていただいています。
(2)報酬金
報酬金は、クレーム対応、クレーマー対応の結果、クレーム客との間で解決の合意に至り、書面を取り交わした場合にいただく費用です。
報酬金についても、着手金と同様に、事案の難易度や複雑さを踏まえた見積もりをさせていただいています。
(3)弁護士費用の例
咲くやこの花法律事務所におけるクレーム対応の弁護士費用例は以下をご参照ください。
ケース1:
通信販売会社が販売している食品について、購入者から異物の混入があったとしてクレームがあった事例
この事例で、弁護士がこの購入者との交渉を担当して、合意書をとりかわして解決した場合の弁護士費用の例は以下の通りです。
- 着手金:15万円+税~
- 報酬金:15万円+税~
ケース2:
整骨院で患者から施術によって骨折したとのクレームを受けた事例
この事例で、弁護士が患者との交渉を担当して、和解により解決した場合の弁護士費用の例は以下の通りです。
- 着手金:15万円+税~
- 報酬金:15万円+税~
ケース3:
工場の騒音に関して周辺住民から慰謝料請求を受けた場合のクレーム対応の事例
この事例で、弁護士が窓口となって周辺住民と交渉し、金銭支払いなしで解決した場合の弁護士費用の例は以下の通りです。
- 着手金:15万円+税~
- 報酬金:発生なし
7,弁護士によるクレーム対応やクレーマー対応の解決事例
弁護士によるクレーム対応、クレーマー対応のイメージについて、より詳しくは、咲くやこの花法律事務所のWebサイトに掲載している解決事例をご参照ください。
(1)化粧品関連のクレーム対応
▶参考事例:化粧品の皮膚トラブルのクレームが発生!慰謝料等「350万円」を請求された事件が「35万円」の支払いで和解に成功した事例
▶参考事例:化粧品販売会社が、購入者から、「まぶたが赤くなった」旨のクレームを受けたところ、弁護士が対応して解決した成功事例
(2)工事騒音のクレーム対応
▶参考事例:水道工事の騒音等に対する近隣店舗からのクレームや金銭要求に対し、弁護士が交渉して要求を断念させた解決事例
(3)設計事務所のクレーム対応
▶参考事例:設計事務所からの依頼を受け、施主からのクレームを弁護士が窓口となり解決した成功事例
(4)通信販売のクレーム対応
▶参考事例:衣類の購入者からの色落ち、色移りに関するクレームトラブルに対して弁護士が対応し、金銭賠償なしで解決した成功事例
(5)リフォーム工事のクレーム対応
▶参考事例:リフォーム会社の顧客がクレームをつけてリフォーム工事代金の減額を要求したケースで、リフォーム代金の全額回収に成功した解決事例
(6)消費者契約法関連のクレーム対応
▶参考事例:消費者契約法に基づく返金請求に対応し、半額返金で解決した事例
8,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます。」

ここまで、弁護士にクレーム対応を依頼するメリットや、依頼後の解決までの流れ、弁護士の選び方などについてご説明しました。
咲くやこの花法律事務所でも、クレーム対応やクレーマー対応についてお困りの事業者から以下のご相談を承っています。
- 解決困難なクレームへの対応方法のご相談
- しつこいクレーム、理不尽なクレーム、繰り返されるクレームについての解決方法のご相談
- 取引先や顧客に大きな被害を与えてしまった場合の解決方法のご相談
- 悪質なクレーマーへの対応のご相談
- クレーム対応、クレーマー対応に関する弁護士による代行のご依頼
- クレーム解決マニュアル作成のご相談
具体的なサポート内容やよくある相談事例、相談するメリット、弁護士費用などについて、以下の動画でも解説していますので、是非、ご覧ください。
クレーム対応は初期対応が重要になります。初期対応を誤ると泥沼化する恐れがありますので、お困りの際は、早めにご相談をおすすめします。
また、日々、現場で起きるクレームについて、その都度、いつでも弁護士に電話やメールで相談できる「顧問弁護士サービス」によるサポートのご依頼も承っています。
クレームを弁護士にスムーズに相談できる環境を整えることで、初期段階での自社での対応の誤りをなくし、クレームがこじれることを防ぐことができます。
また、現場でクレーム対応する従業員に安心感を与え、クレームを個人的に抱え込んでしまったり、クレームを苦に離職してしまうといったことを減らしていくことができます。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスは以下をご参照ください。
9,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
クレームや悪質なクレーマー対応に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
10,クレーム対応に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
クレーム対応に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
11,【関連情報】クレームやクレーマー対応に関する関連記事
この記事では、「弁護士にクレームやクレーマー対応の代行を依頼す5つのメリット」について解説してきましたが、クレーム対応については、クレームの対応の基礎知識をはじめ、納得しない相手のクレーム対応はどうすべきか、理不尽なクレームにはどのように対処すべきか、また業種別のクレーム対応のポイントなど、他のお役立ち情報も多数公開していますので、以下の関連記事もあわせてご覧ください。
【クレーム対応の基礎知識について】
・クレーム対応の例文をポイント解説付きで公開中【メールでの応対編】
・自社に非がない場合のクレーム対応の重要ポイントと対応例文について
【業種別のクレーム対応について】
・通販のクレーム対応方法!ECサイトなどのしつこい苦情はこれで解決!
・住宅業界(新築・中古住宅販売やリフォーム業)のクレーム・苦情の解決方法を弁護士が解説
・【派遣会社向け】派遣先からのクレームや損害賠償請求の対応方法
・病院・クリニックのクレームや苦情の対応。窓口や受付での患者とのトラブル対処法は?
・製造業・建設業・解体業向け!工場や工事の騒音でクレームや苦情を受けたときの対応方法
・化粧品、エステ・美容業界向け!消費者の肌荒れクレームに対する正しい対応方法
・美容室のクレームへの正しい対応とは?クレーマーの出入り禁止についても解説
記事更新日:2026年2月5日
記事作成弁護士:西川暢春
 06-6539-8587
06-6539-8587