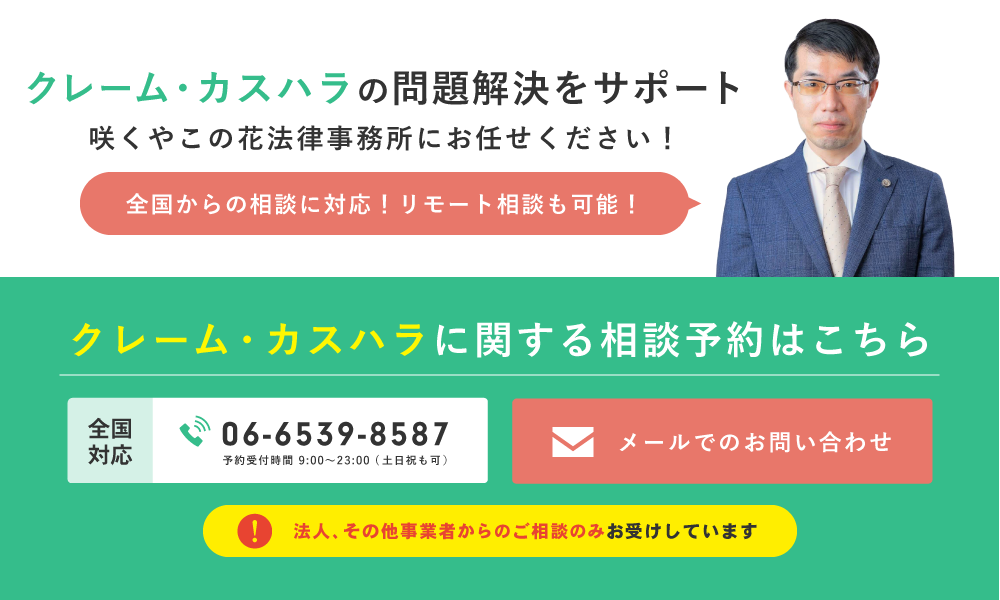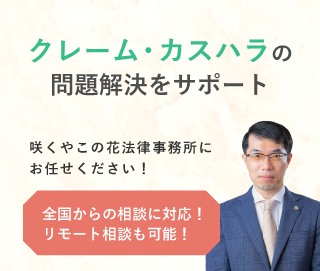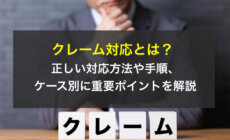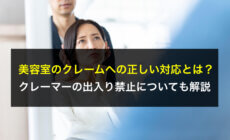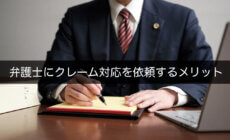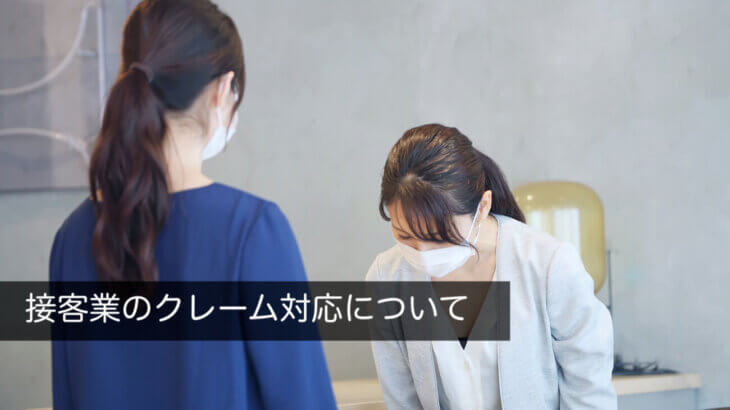
クレームにどう対応していいかわからない、クレームがあると焦ってうまく対応できないと困っている方は多いのではないでしょうか。
接客業はお客様と接する機会が多い分、クレームを受けることが多い業種の1つです。
接客業ではどんなに気を付けていてもクレームの発生を避けることはできないため、クレームが発生した場合の適切な対応方法を知っておくことが重要です。
クレーム対応を自己流で行うと自分でも気づかないところでお客様の気分を損ねて、火に油を注いでしまう結果になりがちです。また、中には、通常の方法で対応すべきではない、悪意のあるクレームや理不尽なクレームも存在します。
ここでは、接客業の方向けに、クレーム対応のポイントやクレーム対応時に使えるフレーズ、シチュエーション別の対応例文もご紹介します。
この記事を読めば、実際にクレームを受けた時にどのように対応すればいいのか、対応のイメージをつかむことができるはずです。
なお、クレーム対応の基礎知識については、以下の記事でわかりやすく解説していますのでご参照ください。
自社では対応が難しいクレームも存在します。その場合は、弁護士に対応を依頼し、弁護士からクレーム対応を行うことが適切です。
クレーム対応を自社で行うのが難しいと感じたときは、問題が複雑化しないうちに、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。また、咲くやこの花法律事務所のクレーム対応についての解決実績は、以下をご参照ください。
▼接客業のクレーム対応に関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,接客業のクレームは予習をすることでスムーズに対応できる
接客業において、クレームを入れるお客様の多くは、自分が受けたサービスや商品に対する不満があり、自身が不利益を被ったことに対して怒っている方です。
怒っている人を前にして、冷静に対応できる人は少ないのではないでしょうか。
クレームに動揺して、しどろもどろになったり、感情的に対応したりすると、かえってクレームをヒートアップさせることにつながりかねません。
誤った対応をしたために、小さなクレームが大きくなり、裁判にまで発展するケースもあります。
クレーム対応において重要なのは、相手の怒りに引きずられることなく、冷静に対応をすることです。
クレーム対応のパターンを予習しておくことで、実際の接客の場面でクレームに直面した時も落ち着いて対応することができ、クレームを解決に導くことにつながります。
2,接客業のクレーム対応4つのステップ

クレームの理由は様々ですが、クレーム対応には基本な流れがあります。
4つのステップを意識して手順を踏んで対応することで、お客様の不満を解消して、クレームを解決に導くことができます。
ステップ1:
はじめは限定的に謝罪をする
クレームを受けた時に、はじめにするべきことは「謝罪」です。
クレームを入れるお客様の多くは怒りで頭に血が上っている状態です。落ち着いて話ができる状態を作るためにも、非があるかないかにかかわらず、まずは謝罪から始めます。
この際に重要なのは、ただ「申し訳ございません」「すみません」と伝えるのではなく、「お客様が不快に思ったこと」「不安を感じたこと」「手間をかけたこと」等に限定して謝罪をすることです。
「相手が何に対して怒っているのか」、「自社に非があるのか」など、詳しい状況がわからない間に全面的に謝罪をしてしまうのは適切ではありません。
相手が悪質なクレーマーだった場合、揚げ足を取られかねないからです。
まずは、ピンポイントに謝罪をして、相手の興奮をしずめ、話ができる土台を作ります。
▶参考情報:伝え方の例
- 「ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません」
- 「ご心配をおかけして申し訳ございません」
- 「お手間をとらせてしまい申し訳ございません」
ステップ2:
「いつ」「どこで」「誰が」等の要点を押さえて事実確認をする
事実関係を正確に把握することは、このあと原因の調査や対応の検討を行う上でも重要です。
確認した内容は必ずメモをとって記録に残しておきます。言った言わないの議論を避けるために録音するのもよいでしょう。
事実確認をする際に、おさえておくべきポイントは主に以下の5点です。
- (1)いつ
- (2)どこで
- (3)誰が
- (4)何をして
- (5)何が起こったか
▶参考情報:飲食店で食中毒ではないかというクレームがあった場合の例
- (1)いつ:いつ来店したか、いつから症状が出ているか
- (2)どこで:どこの店舗で食事をしたか
- (3)誰が:来店人数は何人か、(来店者が複数の場合)そのうちの誰に症状が出ているか
- (4)何をして:当日食べた料理はなにか
- (5)何が起こったか:どんな症状が出ているか
事実確認はこちらから話を聞き出すのではなく、相手に気がすむまで話してもらって、足りない情報を引き出すという意識で行います。
相手が感情的になっていて要領を得ない話をしている場合や、話を聞きだすことが難しい場合は、相手が言いたいことを言いきるまで待つのも1つの方法です。
必ずしも時系列に沿って話を聞きだす必要はないので、お客様の話の中から必要な情報を拾い上げ、足りない情報を聞きだせるように話を誘導することが重要です。
ステップ3:
お客様の要望を明確にする
クレームを入れるお客様は、たいてい「何か」を求めています。
それが、謝罪なのか、返金なのか、交換なのかは人それぞれですが、要望に応えてしまえば気持ちがおさまることがほとんどです。
お客様の気持ちを理解し、要望に応えることがクレーム解決の近道です。
望みどおりの対応ができないとしても、双方の落としどころを見つけるためにもお客様が何を望んでいるのか、要望を明確にすることは重要です。
ステップ4:
再度謝罪をして対応を提案する
事実の確認ができたら、必要に応じて調査を行い、なぜクレームの原因となった物事が起こったのか、店に責任があるのかを明らかにします。
調査の結果を踏まえて、店としてできる提案を検討します。
その上で正式な謝罪を行い、「交換」「返金」「代わりのサービスの提供」「治療費の支払い」等、できる限りの対応を提案します。
対応方法は、できる限り、複数の方法を提案するべきです。
例えば、
- 「今回の代金を返金させていただくか、次回無料でサービスさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか」
- 「商品の交換または代金の返金のいずれかご希望の方法で対応させていただきます」
等、2つ以上の方法を提案し、お客様に選んでいただく形にします。
そうすると、どの方法が自分にメリットがあるかに考えが傾くため、こちらからの提案を受け入れてもらい、クレームの解決につながりやすくなります。
また、店側に非があり、健康被害等が出ているケースでは、症状の程度によっては、治療費や休業損害、慰謝料等の支払いが必要になることもあります。
3,クレームを悪化させる「やってはいけない行為」
ここからは、接客業のクレーム対応の際にやってしまいがちな行為についてご紹介します。
(1)お客様の話を遮る
お客様の中には、不満を吐き出したい、話を聞いてほしいという感情を持っている方も少なくありません。
接客業においては、話を聞くだけでお客様の気持ちが落ち着き、解決することもあります。
逆に、お客様の話を途中で遮ってしまうと、相手が「誠実に対応してもらえていない」「きちんと話を聞く気がない」と感じ、さらなる怒りにつながることもあるので注意が必要です。
理不尽なクレームであっても、まず相手の気がすむまで話してもらうことがクレームの早期解決につながります。
(2)「ですから」「でも」「だから」等の反論ワード
クレームを入れるお客様は、自分が正しいと感じています。
「ですから」や「でも」といった反論の言葉は、上から目線や反抗的な態度ととらえられ、クレームを悪化させる原因になります。
お客様の話を聞くときは、共感を示す言葉を使うことが重要です。
▶参考情報:共感を示すあいづちのフレーズ例
- 「ええ」「はい」
- 「さようでございますか」「おっしゃるとおりです」「ごもっともです」
- 「そのようなことがあったのですね」
- 「私もお客様の立場であれば同じように感じると思います」
何かを伝えるときは、「ですから」「でも」等の直接的な反論ワードではなく、「恐れ入りますが」や「失礼ですが」といった下手に出た言葉で伝えます。
(3)相手の間違いを責めたり不注意を指摘したりする言動
クレームの中には、お客様の勘違い等、店側に非がないものもあります。
お客様の勘違いであっても、「説明不足で大変失礼いたしました」「表現がわかりづらく申し訳ございませんでした」等、客を立てる形で謝罪をすることで、クレームを穏便に収めることができます。
お客様の間違いであったことがわかった場合、相手を責めたり、相手の不注意を指摘するような言動は、新たなクレームの原因になります。
自社に非がない場合のクレーム対応については以下の記事でも解説していますので併せてご参照ください。
(4)対面でのクレーム対応は身だしなみや態度にも注意する
対面でクレーム対応をすることが多い接客業ならではの注意点として、身だしなみや目線、表情等の態度があげられます。
クレームを入れるお客様は、従業員の服装や表情・態度・姿勢等を厳しくみています。
誠実に対応していることを示すために、身だしなみや態度にも注意が必要です。
▶参考情報:クレーム対応時にとるべきではない態度の例
- 腕や足を組む
- 視線を逸らしたり、きょろきょろしたりする
- 貧乏ゆすりをしたり、時計をみたり、あからさまに面倒そうな態度
- にやにやしたり、へらへらした態度
4,接客業のシチュエーション別の対応例文
ここからは、シチュエーション別に接客業でよくあるクレームの対応例文をご紹介します。
「2,接客業のクレーム対応4つのステップ」で説明したステップに沿って対応していきます。
(1)「コンビニやスーパー」接客態度に対するクレームの対応例
接客態度に対するクレームは接客業でよくあるクレームの1つです。
ステップ1:
はじめは限定的に謝罪をする
接客態度に関するクレームが寄せられたら、まずはお客さんが「不快に感じたこと」「不愉快な思いをしたこと」に対して謝罪をします。
▶参考例:
- 「この度は残念な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした」
- 「不愉快な思いをさせてしまい大変失礼いたしました」
ステップ2:
「いつ」「どこで」「誰が」等の要点を押さえて事実確認をする
店員がどんな態度だったのか、いつ起こったことなのか、どのような点に不満があるのか等を確認します。
接客態度に対するクレームで確認するべきことは次のとおりです。
▶参考例:スーパーでの接客態度に対するクレームがあった場合
- (1)いつ:いつ来店したか
- (2)どこで:どこの店舗、売り場で
- (3)誰が:どの店員が
- (4)何をして:どんな状況で(レジ打ち時なのか、品出し時なのか)
- (5)何が起こったか:店員とどのようなやり取りがあったか、店員の態度がどのようなものだったか
ポイント3:
お客様が何を求めているのか明確にする
接客態度に対するクレームの場合、「謝罪」を求めているケースが多いです。
過去に土下座等を強要するクレーマーの存在が話題になりましたが、このような不当な要求には応じる必要はありません。
ポイント4:
再度謝罪をして対応を提案する
確認した内容をもとに調査を行い、必要に応じて店員にも聞き取りを行います。
▶参考例1:再度の謝罪
- 「この度は不適切な対応があり大変申し訳ございませんでした」
- 「ご不快な思いをさせてしまい心よりお詫び申し上げます」
▶参考例2:対応の提案
- 「従業員には厳しく指導をしました」
- 「今後このようなことがないよう指導を徹底いたします」
(2)「アパレル」商品の不具合に対するクレーム
アパレルで多いのが服のほつれや汚れ、装飾品が取れているといった商品の不具合に対するクレームです。
ステップ1:
はじめは限定的に謝罪をする
▶参考例:
- 「お手をわずらわせてしまい大変申し訳ございません。」
- 「(問い合わせの)お手数をおかけして申し訳ございません
ステップ2:
「いつ」「どこで」「誰が」等の要点を押さえて事実確認をする
いつ購入したどの商品なのか、商品にどのような不具合があったのかを確認します。
確認するべきことは次のとおりです。
▶参考例:アパレルショップで商品不良に対するクレームがあった場合
- (1)いつ:いつ来店したか、いつ気が付いたか
- (2)どこで:どこの店舗で購入したか、どこで気が付いたか
- (3)誰が:誰が商品の不具合に気付いたか、販売したスタッフは誰か
- (4)何が起こったか:どのような不具合があるか
また、商品の実物や購入時のレシートやレジの記録も確認しましょう。
ステップ3:
お客様が何を求めているのか明確にする
商品の不具合に対するクレームでは、「返金」または「交換」を求めていることがほとんどです。
お客様が何を求めているのかがわかったら、店側として希望に沿った対応が可能なのか、難しい場合はどのような対応が提案できるかを検討します。
例えば、交換を求めているけれども代わりの商品の在庫がないというケースでは、「商品代金の返金」「同じ価格の他の商品との交換」等の提案が考えられます。
ステップ4:
再度謝罪をして対応を提案する
調査の結果、商品の不具合が店側に非がある場合は、再度しっかりと謝罪をし、返金や交換などの対応を提案します。
▶参考例1:再度謝罪をする
- 「この度は不適切な対応があり大変申し訳ございませんでした」
- 「ご不快な思いをさせてしまい心よりお詫び申し上げます」
▶参考例2:対応を提案する
- 「商品代金の返金か商品を交換させていただきますが、いかがでしょうか」
このように商品の不具合についてのクレームは、謝罪して、返金または交換することで通常は解決できるはずです。
慰謝料を支払ったり、お客様の要求に応じて自宅まで謝罪に行く必要は通常はありません。
謝罪したうえで返金または交換を提案しても、いつまでも納得せずにクレームが続く場合は、納得しない理由を考えたうえで、対応方法を再検討する必要があります。
要求がしつこく、いつまでも納得しないケースのクレーム対応については、以下で解説していますのでご参照ください。
(3)【飲食店】異物混入に対するクレーム
飲食店に対するクレームの中で多いものの1つが、髪やプラスチック等が入っていた等の異物混入のクレームです。
ステップ1:
はじめは限定的に謝罪をする
▶参考例:
- 「ご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません」
- 「ご心配をおかけして大変申し訳ございません」
特にテイクアウト品に関する異物混入のクレームの場合は、「ご体調はいかがですか。」「お体の具合はいかがですか。」等とお客様の状況をお尋ねし、お客様を気遣う言葉をかけることも必要です。
ステップ2:
「いつ」「どこで」「誰が」等の要点を押さえて事実確認をする
店で食事をしているお客様から異物混入の指摘があった場合は、その場ですぐに状況を確認します。
一方、テイクアウトでお客様が自宅に持ち帰った後に、異物混入の連絡があった場合は、どのような料理に、どのような異物が混入していたのか等を確認します。
確認するべきことは次のとおりです。
▶参考例:異物混入に対するクレームがあった場合
- (1)いつ:いつ来店したか、いつ気が付いたか
- (2)どこで:どこの店舗で
- (3)誰が:誰が食べたか、提供したスタッフや調理したのは誰か
- (4)何をして:どんな料理を食べたか
- (5)何が起こったか:どのようなものが入っていたか、体調に変化がないか
ステップ3:
お客様が何を求めているのか明確にする
料理の交換や、代金の返金または代金を請求しないなどの対応が考えられます。
異物の混入について飲食店側に責任がある場合は、料理はすぐに交換し、代金はいただかないことが原則です。
ステップ4:
再度謝罪をして対応を提案する
異物を取り出し、いつ混入したものか、店側で混入したものかを確認します。
そして、飲食店側で混入したものである場合は、再度正式に謝罪をします。
▶参考例1:再度の謝罪
- 「ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。」
- 「ご不快な思いをさせてしまい心よりお詫び申し上げます。」
▶参考例2:対応の提案
- 「料理は交換させていただきます。代金はいただきません。」
- 「(異物の混入によって怪我をした場合は)治療費をお支払いします」
また、飲食店のクレームの解決については以下の記事も併せてご参照ください。
5,接客業のクレームを予防する3つの方法
クレーム対応をしなくていいのであれば、したくないと思う方が大半だと思います。クレームをゼロにすることはできませんが、ちょっとした工夫でクレームを減らすことはできます。
ここからはクレームを予防する方法を3つご紹介します。
(1)クレーム情報を共有しクレームが起こりやすいシチュエーションを改善する
実際に起きたクレームについての情報を社内で共有することで、どのような場面でクレームが起こりやすいのかが見えてきます。
例えば、「店員が挨拶をしない」という接客態度についてのクレームがあった場合、クレームが発生したことを店内で共有することで、スタッフが意識して挨拶をするようになります。
場合によっては、店のシステムやルールを改善します。
例えば、レジの待ち時間が長いというクレームがあった場合は、レジの台数を増やしたり、レジの人員を増やしたりする等の対応が考えられます。
クレームが起こりやすい状況を把握し、意識して対応したり、改善したりすることで、同様のクレームの発生を防ぐことができます。
(2)ダブルチェックを行って不具合やミスの見落としを減らす
クレームの原因となる商品の不具合や異物の混入のなかには、見てすぐに判明するものもあります。
その場で気がついてお客様に提供する前に交換をすれば、クレームが発生することはありません。
1人では見落としてしまうことも、ダブルチェックを行い複数人の目で確認することで、不具合やミスの見落としを減らすことができ、クレームを減らすことにつながります。
(3)クレーム対応のマニュアルを作成する
クレーム対応のマニュアルの作成は、二次クレームを防ぐために重要です。
クレームに対応したスタッフの接客態度や言動が原因で、クレームがクレームを呼び、より大きなトラブルに発展することがあります。
例えば、接客するスタッフがクレーム対応に関する知識が全くない場合、毎回責任者や他のスタッフに確認する必要があり、対応に時間がかかります。すると、お客様を長く待たせることになり、二次クレームにつながる可能性があります。
このような時、店内で対応方法をマニュアル化して共有しておけば、お客様に直接、接客対応するスタッフがその場で判断してすぐに対応することができ、クレームを小さく収めることが可能になります。
6,悪質なクレームの対応は弁護士への依頼も検討する
クレームの中には、一般的な苦情の範囲を超えた「悪質なクレーム」があります。
このようなクレームは通常のクレームとは分けて対応する必要があります。
(1)悪質なクレーマーとは
過剰な金銭や特別な待遇の要求、SNSに書き込むといった脅迫的な言動がみられるような場合は悪質なクレームを警戒するべきです。
悪質なクレームには以下のようなものがあります。
▶参考情報:悪質なクレームの例・自分の要求が通るまで執拗に電話やメールで連絡をしてくる
- 来店して大声で騒ぎ立てたり長時間居座ったりする
- SNSに書き込む等の店の信用を貶めるような脅迫的な発言をする
- 過剰な金銭や特別な待遇を求める
- スタッフに危害を加えることをほのめかすような発言をする
- その場ですぐに要求に応じるように求めてくる
- 反社会的勢力との関わりをうかがわせるような発言をする
(2)悪質なクレームに対応する時のポイント
悪質なクレームに対応する時のポイントは以下の通りです。
1,複数人で対応する
悪質なクレームには複数人で対応することが原則です。
相手の高圧的な態度や暴言に耐えるのは簡単なことではありません。1人で対応した場合、要求をのめば解放されると考え、不当な要求を受け入れてしまうこともあります。
複数人で対応することで、対応するスタッフの精神的な負担を軽減することができ、1対1では強く出ることができるクレーマーも、複数人相手であればトーンダウンすることがあります。
特に対面で対応する際は、身の安全を守るためにも複数人での対応が適切です。
2,やりとりの記録を残す
口頭でのやりとりは言った言わないの話になることが多々あります。
できる限り、書面やメールなどの記録が残る方法でやりとりをして、対面で対応する場合は、防犯カメラのある場所で対応したり、相手との会話をボイスレコーダーで録音したりして、対応の記録を残しておきます。
3,理不尽な要求は毅然とした態度で断る
悪質なクレーマー対応のゴールは、「相手の納得・了解」ではなく、「要求を断りあきらめさせる」ことです。
悪質なクレーマーと判断した時点で、相手が「お客様」であるという意識を捨て、「対等・公平」の関係で対応します。
悪質なクレーマーはあの手この手で自分の要求を通そうとしてきますが、何を言われても譲歩することなく、「そのような要求は法律上通らないこと」を説明してきっぱりと断ります。
悪質なクレーマーの多くは、店から、お金や特別な待遇等、自分に有利な扱いを引き出すことが目的のため、相手に「これ以上何も引き出せない」と思わせることが重要です。
4,クレーマーの名前や連絡先を確認する
自分が不当な要求をしているという自覚があるクレーマーは、自分の個人情報を明かすことを嫌がります。
その場ですぐに対応しようとせず、改めて連絡するので連絡先を教えてほしい等と伝え、クレーマーの名前や連絡先を確認します。
根拠のない要求をしているという自覚があるクレーマーは、これだけで引き下がることもあります。
▶参考情報:伝え方の例
- 「社内で確認して改めてご連絡いたしますので、お名前とご連絡先を教えてください」
- 「お客様の会員情報を確認しますので、お名前をお聞かせいただけないでしょうか」
また、悪質なクレームの対応については以下の記事も併せてご参照ください。
(3)手に負えない場合は弁護士や警察に相談する
1,警察への相談
脅迫や暴力、器物損壊等の違法行為をともなうクレームはすぐに警察に通報をするべきです。
明らかな違法行為がなくても、相手の言動から身の危険を感じる場合には、警察に相談することをおすすめします。
警察がすぐに対応に動いてくれることは少ないですが、事前に相談しておくことで、いざという時に警察に動いてもらいやすくなります。
また、「警察に相談している」と伝えることでクレーマーの言動がエスカレートすることを防ぐ効果もあります。
2,弁護士への相談
店としてできる対応を行っても相手が納得しない場合や、法外な要求を繰り返す場合、営業時間中に何度も電話をかけてきたり、店に怒鳴り込んできたりして、店の営業に支障をきたしているケースでは、弁護士に相談するのも有効な方法です。
弁護士に相談することで、クレーマーの要求に対して、法的な観点からどこまで対応する義務があるのかが明確になります。法外な要求については、「弁護士にも相談しましたが、そのような要求には応じられません」と断りやすくなります。
さらに、クレーム対応を弁護士に依頼し、窓口を弁護士に切り替えれば、スタッフはクレーム対応から解放されるため、店の営業に集中することができます。
そして、弁護士名で通知を送ったり、弁護士から直接「クレーマーの要求が法律上通らないこと」を説明することで、クレームを迅速に解決することができます。
クレーム対応を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用など、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
クレーム対応の分野での弁護士によるサポート内容は以下をご参照ください。
7,接客業のクレーム対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

この記事では接客業のクレーム対応についてご説明しました。
最後に咲くやこの花法律事務所の、接客業のクレーム対応についてのサポート内容をご紹介します。
- (1)接客業のクレーム対応に関するご相談
- (2)弁護士によるクレーム対応
- (3)クレーム対応マニュアル作成のご相談
以下で順番に見ていきましょう。
▶参考動画:クレームや悪質クレーマー対応に強い弁護士への相談サービスの解説動画も参考にご覧ください。
(1)接客業のクレーム対応に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、クレーム対応にお困りの飲食店や美容院、小売業などの接客業の方から、クレーム対応に関するご相談を承っております。
クレーム対応に精通した弁護士がご相談をお受けします。
クレーム対応にお困りの会社からご相談いただくケースは、多くが対応方法を誤っており、自身で対応を続けてもクレームを解決することができないと思われるケースがほとんどです。クレーム対応にお困りの場合は、誤った対応をする前に弁護士にご相談ください。
特に自社に大きな落ち度があり賠償が必要となる見込みの事案や、いつまでも理不尽な要求が続き、解決の見込みが立たない事案については、早急に弁護士に相談していただくことをおすすめします。
こういった事案については、相手の要求をそのまま受け入れることができないことが多く、法的に妥当な部分を超える要求は毅然とした態度で断ることが必要ですが、現場の接客スタッフではそのような対応は簡単ではありません。
弁護士による対応が効果的です。
また、顧問契約を締結していただくと、日々、現場の接客スタッフからクレームの対応について顧問弁護士に電話で直接ご相談いただくことが可能です。
顧問弁護士への相談により、正しい対応をすることができるようになり、スタッフの精神的な負担を大きく軽減し、スタッフの定着、離職の防止につながります。
顧問弁護士サービスに関するサポート内容や顧問料については、以下を参考にご覧ください。
(2)弁護士によるクレーム対応の代行
咲くやこの花法律事務所では、自社での解決が困難なクレームについて、弁護士がクレーム対応を代行するサービスも提供し、実際に多くのクレームを解決してきました。
接客業のクレーム対応に精通した弁護士が直接、クレーム客に対応することにより、現場のスタッフの負担を軽減し、迅速な解決を実現します。
(3)クレーム対応マニュアルの作成
典型的なクレームについてどのように対応するかを予め決めておくことも重要です。
例えば、「謝罪に来い」とか「社長を出せ」とか「誠意を見せろ」といったクレームに対してどのように対応するかについてはあらかじめ決めておくべきです。
咲くやこの花法律事務所では、接客業のクレーム対応に精通した弁護士が、オリジナルのクレーム対応マニュアルの作成をサポートし、実践的なマニュアルを作成します。
(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームより受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
8,【関連情報】接客業のクレーム対応に関する関連記事
この記事では、「接客業のクレーム対応!おさえておくべき4つのステップ」について解説してきましたが、クレーム対応については、クレームの対応の基礎知識をはじめ、納得しない相手のクレーム対応はどうすべきか、理不尽なクレームにはどのように対処すべきか、また業種別のクレーム対応のポイントなど、他のお役立ち情報も多数公開していますので、以下の関連記事もあわせてご覧ください。
【クレーム対応の基礎知識について】
・カスハラとは?カスタマーハラスメントで企業がとるべき6つの対策!
・カスハラ(カスタマーハラスメント)にあたる暴言とは?具体例と対策を解説
【業種別のクレーム対応について】
・住宅業界(新築・中古住宅販売やリフォーム業)のクレーム・苦情の解決方法を弁護士が解説
・【派遣会社向け】派遣先からのクレームや損害賠償請求の対応方法
・病院・クリニックのクレームや苦情の対応。窓口や受付での患者とのトラブル対処法は?
・製造業・建設業・解体業向け!工場や工事の騒音でクレームや苦情を受けたときの対応方法
・化粧品、エステ・美容業界向け!消費者の肌荒れクレームに対する正しい対応方法
・美容室のクレームへの正しい対応とは?クレーマーの出入り禁止についても解説
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2026年2月5日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」クレーム対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587