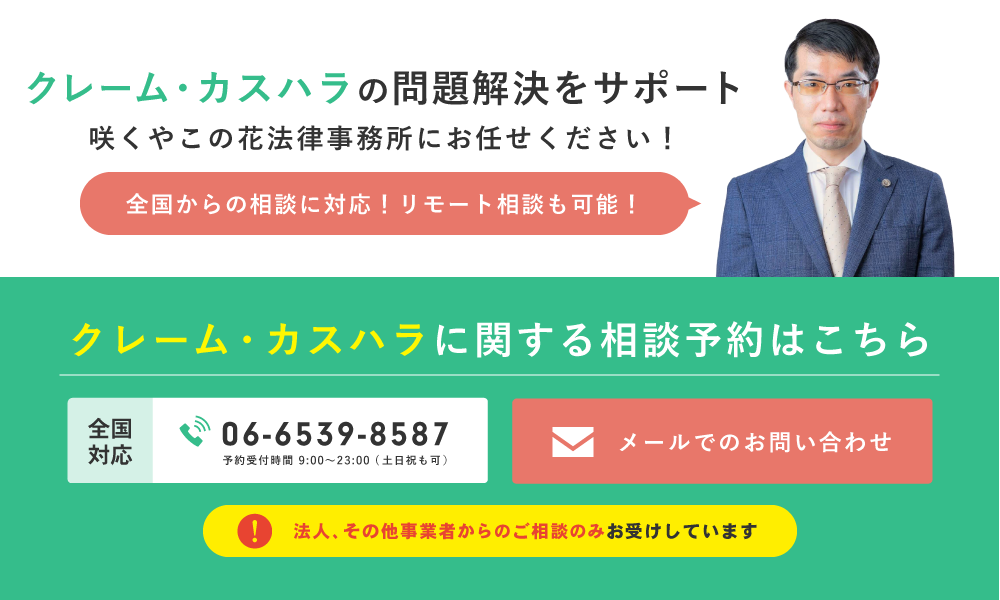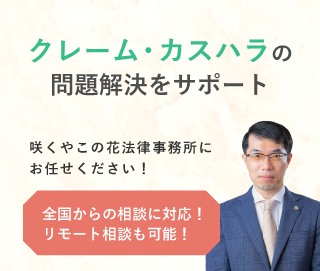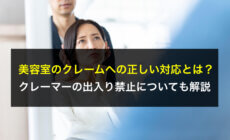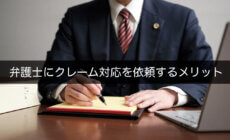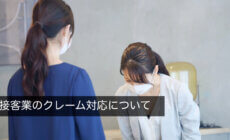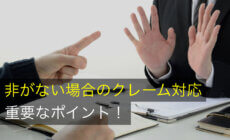こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
電話でのクレーム対応について悩んでいませんか?
クレームへの対応を誤ると、対応する側が長時間拘束され、疲弊することになる一方で、いつまでも解決せずに埒があきません。
会社としては一生懸命対応しているつもりでも、誤った自己流の対応をしてしまった結果、逆に解決が遠のき、問題が泥沼化してしまったケースも弁護士として多く見てきました。
そこで、今回の記事では、筆者の経験も踏まえて、電話でのクレーム対応についてご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、電話でのクレーム対応の重要ポイントを理解していただき、クレーム処理を上手にすませることができるようになるはずです。
なお、クレーム対応の基礎知識については、以下の記事でわかりやすく解説していますのでご参照ください。
それでは見ていきましょう。
クレームがいつまでも続いてしまうときは、会社のクレーム対応の方法にも問題があることが多いです。
そのような場面で、クレームを解決するためには、弁護士に相談して、これまでの対応方法を改めることが必要です。長く続くクレームに対して間違った対応を続けていると、担当者の疲弊による離職のリスクもでてきます。早めにクレーム対応に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
クレーム対応に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下をご参照ください。
▼クレーム対応に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,電話での話し方、聴き方のポイント

まず、電話での話し方、聴き方のポイントからご説明したいと思います。
(1)お客様を落ち着かせる
クレームの電話をかけてきた時点で、お客様は怒っていたり興奮していたりすることがほとんどです。まずはお客様の怒りを受け止めて、落ち着いて話ができる流れにもっていくことが重要です。
電話対応では、大きな声ではっきりと、丁寧な言葉遣いでわかりやすく話すよう心がけましょう。
小声で話したり早口になったりして内容が伝わりづらいと、お客様がより不快感を募らせてしまいます。また、専門用語を使いすぎたり曖昧な言い回しをしすぎたりすると、会話の内容が正しく伝わらないという恐れもあります。
お客様が言葉を荒げるようなことがあっても、それに呼応するようなことがあってはいけません。
クレームの初期段階では、あくまで冷静に、円満に話をできるような態度を崩さないようにすることが必要です。
(2)話の腰を折らない
お客様の話の腰を折らないことも重要です。
お客様の主張が明らかな誤りだとわかる場合でも、まずは途中で遮ったり反論したりせず、相づちを打ちながら話を聞きます。興奮しているときに反論されると、その反論が正しい場合でも、お客様の感情を傷付け、事態が悪化してしまう恐れがあります。
「ですから」、「でも」などの言葉は、上から目線や反抗的な態度だと捉えられる可能性があるので、原則として使うべきではありません。
「さようでございますか」、「はい」などと、相づちを打って、興奮を落ち着かせるようにしましょう。
このようにお客様の言い分に耳を傾けて、クレームの実態を把握するようにします。
クレームの初期段階では、こちらに完全に非がある可能性もあると考えて対応する必要があります。
お客様の言葉遣いが乱暴だからと言って悪質なクレーマーだと決めつけず、しっかり話を聞くことが重要です。
(3)お客様の話についてメモを取る
クレームの電話を受けたときは正確な記録を取ることが重要です。
長々と話を聞いたものの、重要なことについて記録が取れてないと、その後の対応にも影響が出ます。電話を聴きながらメモをとることを習慣にすることが必要です。
また、記録を取ることによって、会社としての対応が適切だったのかどうかや、改善すべき点がなかったのかについて後から検証することができます。
誰がクレーム対応をしても聞き漏らしなく、一定の記録を残せるように、必ず聞き取るべき項目をリストアップして事前にヒアリングシートのようなものを用意しておくと良いでしょう。
2,電話での謝罪の仕方
クレームの電話を受けたときは、早い段階で謝罪をすることで怒りを鎮めていただくことが重要です。
(1)範囲を限定して謝罪する
「謝罪する」といっても、事実関係がよくわからない状況でいきなり全面的に非を認めてしまうことは避けなければなりません。
自社に非があるかどうかがわからない段階で、お客様のクレーム内容そのものを認めて謝罪してしまうと、後々、「謝ったのだから補償しろ」などと責任を追及される恐れがあるからです。
電話を受けた初期段階では、クレームの内容が事実であるかも、責任がどこにあるのかもはっきりわかっていません。
だからと言って、わからないので謝罪拒否という態度を取っているとお客様を余計に怒らせてしまいます。
このような場合は、範囲を限定して謝罪するという方法をとるべきです。
具体的には、以下の通りです。
例1:
お客様が接客対応などについて不快感を訴えている場合
「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません」と謝罪
例2:
商品について不満を述べられている場合
「ご不便な思いをさせてしまいお詫び申し上げます」と謝罪
その他、「本件のためにお手間を取らせてしまい申し訳ございません」などと謝罪するのもよいでしょう。
クレームの内容そのものではなく、お客様に不快感や不満を与えてしまったことや、クレームを入れる手間をかけたことについてのみ謝るようにしましょう。
(2)健康に関するクレームには相手を気遣うことで対応する
飲食店や食品を販売している会社では、「この商品を食べたせいでお腹が痛くなった」といったような健康被害のクレームを受けることがあるかと思います。
このような健康被害を訴えるクレームを受けたとき、本当に自社で提供した食品が原因であるかを検証するためには時間が必要です。
それにもかかわらず、安易に自社の食品が健康被害の原因であると認めてしまうと、後々大きな問題になってしまうリスクが大きいです。
そのため、健康被害についての謝罪は、特に慎重になる必要があります。
健康被害を訴えられた場合は、謝罪よりもまずはお客様の健康を気遣う言葉をおかけするようにしましょう。
痛みが出たことを訴えられたときは、まずは「今のお体の具合はいかがですか」などと、状態を気遣い、お客様の健康状態に最大限の配慮をしていることを強調しつつ、症状の詳細を聞き取るよう話をつなげていくと良いでしょう。
飲食店のクレーム解決方法については以下で詳細を解説していますのでご参照ください。
3,「上司に代われ」と言われた場合の対応
クレーム対応をしていると、お客様から「上司に代われ」、「責任者と話をさせろ」などと要望されることがあります。
この場合、どのように対応すべきでしょうか。
(1)上司にすぐ取り次がない
お客様のご要望どおり、すぐに上司に取り次げばお客様はその瞬間は満足されるかもしれません。
しかしその対応は不適切です。
それまでの経緯を十分に説明せずに急遽交代すると、上司が事態を把握しきれないままに対応することになってしまいます。対応にミスが生じたり、お客様が一度説明したことを再度質問したりして、お客様を余計に怒らせるおそれがあります。
また、電話口の担当者が無責任なので、強く要求すればすぐに責任者を呼び出すことができるという印象を与えてしまうのも適切ではありません。
ただし、だからと言って、「絶対につなげません」と強い調子で拒否するのも適切な対応ではありません。
「社内の規定で」、「私が担当なので」などと理由を示して、お客様の要望を真正面から否定すると、この会社は客の話を聞く気が無く、排除しようとしているという印象を与えてしまいます。
お客様の話を聞いて落ち着かせることが重要な局面で、要望を正面から断固拒否するというのは絶対にしてはいけないことです。
(2)お客様の真の要求に応える
「上司を出せ」という要望には、問題の商品やサービスについて詳しい知識や、事態を収拾するための権限を持っている者と話をして、問題を早く解決したいというお客様の真意があります。
クレームを解決するには、このお客様の真意に応える必要があります。
まずは、これまでの経緯を担当者から上司に報告することと、その上で社内で問題について検討するということを伝えましょう。
そして、検討した上で、改めてこちらからご連絡を差し上げるとお伝えし、一旦終話すると良いでしょう。
頭ごなしに上司にはつなげないと拒否するのではなく、ご要望どおり上司には伝えるが、今すぐに取り次ぐことができないのでお時間をいただく必要があると説明し、ご理解いただくことが大切です。
その後、上司に経緯を報告して対応を検討します。
検討の結果、上司が対応する方が適切な事案であれば上司に引き継ぐと良いですし、引き続き担当者が対応できるケースであれば、上司に説明した結果こうなったと改めてお客様に報告するとよいでしょう。
4,電話によるクレームの基本的な対応手順
クレームの電話がかかってきたときの大まかな対応の手順は以下のとおりです。
- 手順1:不快な気持ちにさせたことを謝罪をする
- 手順2:お客様の説明や主張を聞く
- 手順3:事実の調査と対応策の検討
- 手順4:自社に問題があったときは改めて謝罪をする
- 手順5:解決策を伝える
次の段落では、この手順ごとに電話で使える対応例文を見ていきましょう。
5,電話で使える対応例文
それでは、電話対応の際に使えるフレーズをご紹介します。
(1)謝罪の場面での対応例文
お客様は、自社が提供したサービスや商品について、「何らかの迷惑を受けた」、「不快に感じた」、「不便なことがあった」、という理由があってクレームの電話をかけてきています。
そこで、電話のはじめにまずそれに対して一言謝罪をしましょう。
いきなり事実を認めてしまうのではなく、次のようにお客様の怒り等の心情に対して謝罪をします。
話し方の例文
- 「この度は弊社の商品に関してご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。」
- 「お客様にご不安な思いをさせてしまいまして、誠に申し訳ございません。」
- 「本件のためにお時間を取らせてしまい誠に申し訳ございません。」
(2)お客様の説明や主張を聞く場面の対応例文
次に、クレームの原因となった事実や経緯について、お客様から詳細にお聞きしましょう。
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確にするように、お客様から話を引き出していくことが重要です。
お客様の説明に具体性が欠けるときは、「具体的にはいつ起きたことでしょうか」などと、足りない情報を順に聞いていきましょう。
事実や経緯が把握できれば、次はお客様のご要望を聴き取ります。
「返金を望んでいるのか」、「交換を望んでいるのか」、「ただ不満を聞いてほしかっただけなのか」、お客様の要望によって今後の対応も変わりますので、どうしてほしいのかをはっきり示されない場合には、次のようなフレーズで問いかけて確認します。
話し方の例文
- 「お客様のご要望としましては、〇〇ということでしょうか?」
(3)事実の調査と対応策の検討の場面の対応例文
クレームの詳細が把握できたら、次は事実の調査とどのような対応をするかを検討する必要があります。
すぐに調べて答えられるような案件であれば、電話を保留にしたうえで検討することになります。一方、調査等に時間がかかる場合は、電話を切り、折り返すようにしましょう。
電話を保留にする際は次のようにお伝えします。
話し方の例文
- 「資料を確認いたしますので少々お待ちください」
- 「担当者に確認いたしますので、しばらくお待ちいただけますでしょうか」
電話を保留にした状態で何分もお待たせすると、お客様を怒らせることにつながります。
すぐに調べることが難しいと予想される場合は、一旦終話して折り返しご連絡すると説明した方が良いでしょう。その際には、折り返しにかかる時間の目安も伝えるのがよいです。
- 「いただいた内容を確認いたします。少々お時間がかかりますので、折り返しお電話させていただいてよろしいでしょうか。〇分以内にはご連絡いたします。」
(4)再度の謝罪をする場面の対応例文
クレームの原因を調査した結果、自社に落ち度があった場合は、改めて謝罪をすることになります。
このときは、正面から責任を認めて、誠実な謝罪の意思を示すことが大切です。理由を説明する場合も、まず先に明確に謝罪をした後で簡潔に述べるようにしましょう。
以下のようなフレーズが適切です。
話し方の例文
- 「誠に申し訳ございません」
- 「心よりお詫び申し上げます」
- 「大変なご迷惑をおかけしました」
(5)解決策を伝える場合の対応例文
謝罪の後には、クレームの解決策を提案しましょう。
解決策はできるだけ2案ほど用意して、お客様に選択していただくと良いでしょう。
たとえば、商品に初期不良があったというクレームの場合はこのように提案します。
話し方の例文
- 「当店としては、新品の同商品と交換させていただくか、商品代金を返金させていただきたいと考えておりますがいかがでしょうか。」
提案の際にそれぞれのメリットとデメリットも一緒に伝えることがベストです。お客様が不満に感じられるポイントとしては、金銭や手間が余計にかかることが考えられます。
「たとえば商品を返送する場合の送料はどちらが負担するのか」、「商品を交換するために再度来店する必要があるのか」、「返金にはどのくらいの時間がかかるのか」、など具体的に説明できるよう用意してからお客様に説明するようにしましょう。
6,クレーム対応の電話のかけ方
事実調査のためにお時間を頂戴し、折り返し電話をかけるときの注意点です。
(1)期限を守る
まず、お伝えした折り返しの目安時間内に必ず電話をかけるようにしましょう。
約束していた時間内に連絡がないと、対応が遅い、対応せずに逃げた、などの二次クレームにつながる恐れがあります。
ですので、お伝えした目安時間内に調査が終わらないときも必ず連絡し、事実の確認に時間がかかっていることを説明し、期限を延長していただくようお願いしましょう。
(2)調査結果を伝える
折り返しの電話で事実調査やお客様からの要望についての検討の結果をお伝えするときは以下の点に注意してください。
まず、事実調査の結果、責任が自社にあることが判明した場合は、謝罪して今後の対応策をお伝えします。
しかし、調査をしてもお客様の主張されるようなことが実際にあったのかわからない、あったとしても責任が自社にあるのかわからない、ということもありえます。また、お客様からご要望いただいた対応を自社で検討した結果、どうしても希望どおりには対応できないということもあります。
その場合、「原因はわかりませんでした」、「対応できません」などと、調査や検討の結果だけをあっさり伝えると、お客様の不満につながりやすいので注意しましょう。
「担当者からの聞き取りや記録の精査などをいたしましたが、原因が判明しませんでした」など、しっかり調査活動を行ったことを示すようにしましょう。
また、お客様からのご要望に添えないと伝えるだけでなく、代案を示し、できうる限りの対応をしようとしていることをご理解いただくよう心掛けましょう。
7,折り返しの時間帯はいつが適切か?
折り返しの電話はできるだけ早くかけるべきです。
ただし、早い方が良いと言ってもお客様の都合を考えることも重要です。折り返しのご連絡を約束する際に、お客様の都合の良い時間帯を聞いておくようにしましょう。
お客様から時間帯の指定が特に無い場合も、朝一番、昼前、夕方あたりは一般的に忙しいことが多いので避けるのが無難です。
午後の早めの時間帯(午後1時30分頃~)に連絡してみるのが良いでしょう。
8,クレーム対応の電話の切り方
クレーム対応が終わって電話を切るときには、今後につながるような一言を添えるようにしましょう。
重要なのは、クレームをいただいたことに対して感謝を伝えることです。
「この度は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました」などと丁寧にお礼の言葉を伝えましょう。
自社がお客様からのクレームをありがたく受け止めていることを示し、お客様のことを大切にしていると信頼感の獲得につなげます。たとえお客様の言い分が間違っていたことが判明した場合でも、ご意見をいただいたことに対して謝意を示すようにしましょう。
お客様の顔を立てて、今後も良好な関係を築いていけるようにします。
また、「今回ご指摘いただいた件は、社内でさらに検討し、今後に役立たせるようにいたします。貴重なご指摘をいただき感謝申し上げます。」などと、いただいたクレームを今後の業務の改善のために活かすことをお伝えするのも効果的です。
電話の最後には、「また何かお気づきのことがございましたらご連絡ください」、「再度問題がありましたら担当〇〇までご連絡ください」などと添えると良いでしょう。
今後もお客様に対して真摯に対応するという姿勢を示すことが大切です。
9,クレーム対応の電話は録音する
クレームの電話対応は可能な限り音声を録音するようにしましょう。
お客様からかかってきた電話も、会社から折り返し連絡する場合も、会話の内容を残しておくとよいでしょう。
お客様に伝えずに録音をしても違法ではありませんが、録音のメリットを活かすためには電話の冒頭の自動音声で録音をしていることを伝えるのが望ましいです。
録音を残すことで以下のようなメリットがあります。
(1)クレーム対応の証拠になる
口頭でのクレーム対応は、後から言った・言わないの水掛け論となりがちです。会話を全て録音しておけば、このような不毛な議論を防止することができます。
また、クレームにどのような対応をしたかを社内で正確に共有したり、その対応が適切であったかどうかを後から検証したりすることが容易になります。
(2)クレーム客への牽制になる
クレームの電話をかけるとき、多くのお客様が怒りで感情的になっています。
そのため、電話口で激しい言葉遣いや、脅迫的な発言をされることが多々あります。また、事態を有利に進めるために、あえて強い発言を繰り返す方もいます。
録音をしているとあらかじめ伝えることで、お客様に、「自身のこの発言が残っても問題ないだろうか」という心理が働くので、感情的になりすぎたり、暴言や脅迫発言が飛び出したりすることを抑止する効果があります。
10,アルバイトが対応する場合の注意点
アルバイトの従業員がクレームの電話を受けることもあるでしょう。
アルバイトの従業員でも電話に対応している時点でお客様にとっては会社の窓口にあたります。適切な対応ができるよう、日ごろからクレーム対応について指導しておくようにしましょう。
注意すべき点は次のとおりです。
(1)クレームをたらい回しにしない
お客様からの電話を受けて、「私はアルバイトなのでわかりません」、「担当部署にかけ直してください」などと返答するのは絶対に避けましょう。
話を聞いてもらえないことでお客様の不満や怒りがより大きくなってしまいますし、無責任な対応をする会社だという悪印象を与えてしまいます。
まずはお客様のお話をしっかり聞き取り、その上で担当者や上司に報告しましょう。
(2)言葉遣いなどに気を付ける
お客様の話をお聞きする際には、言葉遣いなどに気をつけましょう。
たとえアルバイトであっても、お客様に対して会社を代表して話すということを意識して、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
また、前述したとおり、お客様の話の腰を折ったり、反論したりしないようにすることも重要です。
(3)責任者や担当者に報告する
お客様からクレームの内容を聞き取ったら、速やかに責任者に報告しましょう。
お客様の主張や、自分がどのように対応したかということを、メモに基づいて、詳細かつ正確に伝えることが大切です。
責任者がクレームのあったことを把握できないままにしていると、後にトラブルが大きくなり、自社に大きな損害を与えることにつながる恐れがあります。
些細なことだと思われるようなクレームであっても、アルバイトだけで勝手に処理をせずに、責任者へ報告することを徹底させてください。
11,悪質で理不尽なクレーマーには毅然とした対応が必要

ここまでは通常のお客様のクレーム対応についてご説明してきましたが、中には理不尽なクレームを延々と繰り返したり、言いがかり的なクレームで現場を困惑させる悪質なクレーマーも存在します。
そのような場面では、ここまでご説明した「お客様に納得してもらい、信頼を取り戻すためのクレーム対応」ではなく、クレーマーの要求を毅然とした態度で断ることが重要になってきます。
自社に非がない場合のクレーム対応の重要ポイントや理不尽なクレーマーへの対応のポイントについては以下の記事や動画で解説していますのでご参照ください。
▶参考動画:理不尽なクレーマーへの対応7つのポイントを弁護士が解説します。
12,自社で手に負えないクレームは弁護士への相談が有効
クレームの内容によっては自社で手に負えないこともあるでしょう。
例えば、以下のようなケースです。
- お客様に大きな迷惑をかけてしまい賠償が必要だがどのように賠償交渉すればよいかわからないケース
- 理不尽な言いがかりのクレームを執拗につけられているケース
- お客様がクレーマー化してしまい、いつまでも納得せず、解決できないケース
このようなケースのクレーム対応を自社でやろうとしても解決できないだけでなく、自社の担当者が疲弊して、職場環境が悪化したり、担当者の離職につながってしまう危険があります。
自社で手に負えないと判断した場合は、早めに弁護士に相談していただくことをおすすめします。クレーム対応を弁護士に依頼し、弁護士がクレーム客との間で話し合いを行い、クレームを解決することがベストです。
弁護士にクレーム対応をご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 相手の要求に対して、法律、判例のルールに基づく話し合いが可能になる。
- 過大な要求については、弁護士から毅然とした対応で断ることができる。
- 第三者である弁護士に依頼することで、お客様と会社という上下の関係から離れて、対等な立場での話し合いが可能になる。
- 金銭を支払って解決する場面では適切な示談書を作成することで、再度の金銭請求を受けることを防ぐことができる。
- クレーム対応を弁護士にまかせることで、自社は事業に専念することができる。
クレーム対応を弁護士に依頼するメリットや弁護士費用など、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
13,マニュアル化や研修がクレーム対応向上の鍵
クレーム対応が上手な会社を目指すためには、自社でクレームに対応する全ての従業員が、この記事でご説明したような対応方法を習得する必要があります。
そのためには、まず、自社でよく起こるクレームを洗い出すことが必要です。クレームの内容は業種や会社によって異なります。
例えば、「待ち時間が長すぎる」、「商品に傷がついていた」、「商品がなかなか届かない」、「対応が横柄」などといったどの業種でも起こりうるクレームもあれば、「洗濯したら色移りした」(アパレル業界)とか「食品に髪の毛が入っていた」(食品販売)といった、業種独自のクレームもあります。
まずは、こういったクレームの内容を洗い出したうえで、それぞれのクレームに対して、この記事でご説明した点を踏まえて、どのように対応すべきかをより具体的にマニュアル化することが重要です。
マニュアル化が終われば、それをもとに、クレームに対応する従業員に対して研修を実施していきましょう。
このようなマニュアル化と研修を進めることで、誰が対応しても同じ対応ができるようになり、会社全体としてクレーム対応を向上させることができます。
14,電話によるクレームに関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業のクレーム対応について、多くの企業からご相談、ご依頼を受け、弁護士が直接、相手方との話し合いによりクレームを解決してきました。
住宅関連、建築関連、自動車関連、化粧品関連、病院・クリニック・整骨院関連、通販事業関連、派遣業関連など様々な業種のクレームについてご依頼をお受けして解決してきた実績があります。
クレーム対応にお困りの際は、自社で誤った対応をして解決が難しくなってしまう前に、クレーム対応に強い弁護士がそろう咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
咲くやこの花法律事務所のクレーム対応に強い弁護士への相談費用
- 30分5000円+税
▶参考動画:クレームや悪質クレーマー対応に強い弁護士への相談サービスの解説動画も参考にご覧ください。
※顧問契約の場合は初回相談料が無料です。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下のページをご覧ください。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの方はこちら
「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
電話でのクレーム対応に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
15,【関連情報】電話でのクレーム対応に関する関連記事
この記事では、「電話でのクレーム対応の重要ポイント」について解説してきましたが、クレーム対応については、納得しない相手のクレーム対応はどうすべきか、また業種別のクレーム対応のポイントなど他のお役立ち情報も公開していますので、以下の関連記事もあわせてご覧ください。
【クレーム対応の基礎知識について】
・カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?企業がとるべき6つの対策!
・クレーム対応の例文をポイント解説付きで公開中【メールでの応対編】
【業種別のクレーム対応について】
・通販のクレーム対応方法!ECサイトなどのしつこい苦情はこれで解決!
・住宅業界(新築・中古住宅販売やリフォーム業)のクレーム・苦情の解決方法を弁護士が解説
・【派遣会社向け】派遣先からのクレームや損害賠償請求の対応方法
・飲食店のクレーム解決方法!異物混入・食中毒・腹痛等の対応事例も解説
・病院・クリニックのクレームや苦情の対応。窓口や受付での患者とのトラブル対処法は?
・製造業・建設業・解体業向け!工場や工事の騒音でクレームや苦情を受けたときの対応方法
・化粧品、エステ・美容業界向け!消費者の肌荒れクレームに対する正しい対応方法
・美容室のクレームへの正しい対応とは?クレーマーの出入り禁止についても解説
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2026年2月5日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」クレームに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587