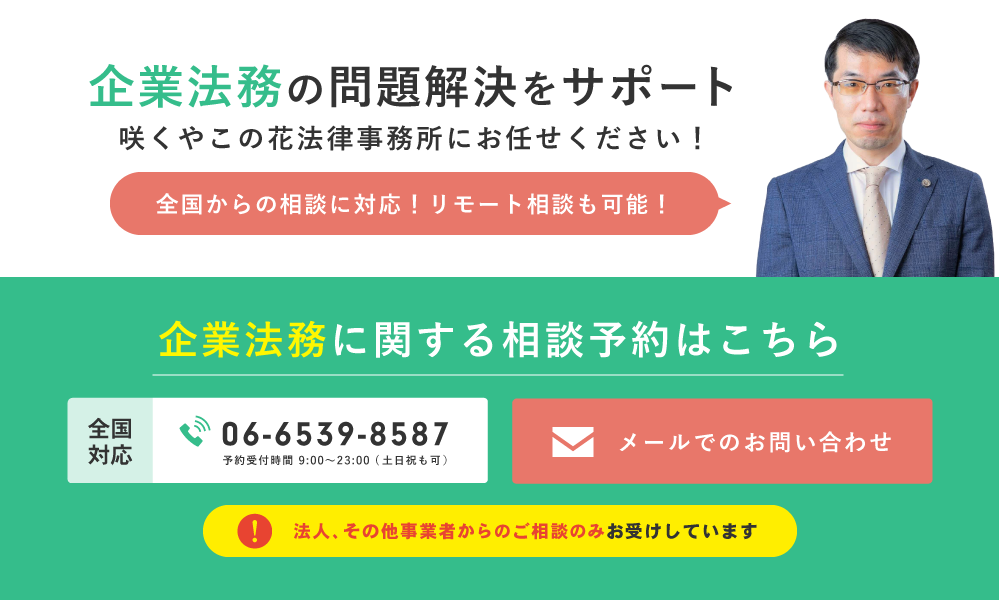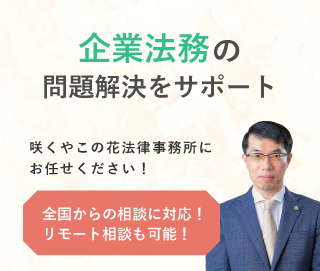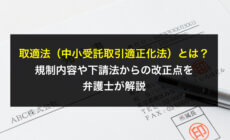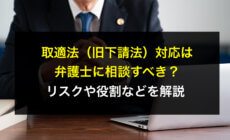こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自社にあった弁護士の選び方がわからず困っていませんか?
ベンチャーやスタートアップ企業の法務は、既存の老舗企業や大企業の企業法務とは大きく性質が異なります。そのため、実際にベンチャーやスタートアップ企業で求められる業務に精通した弁護士を選ぶことが非常に重要です。良い弁護士に巡り会えないと、弁護士とうまくコミュニケーションがとれず、法務の面で足元をすくわれ、企業の成長が挫折することすらあります。
一方、自社にあった弁護士に巡り会えば、自社にとってかけがえのないパートナーとなり、大きな安心を得ることができます。
今回は、ベンチャーやスタートアップ企業を成功に導く法務体制と弁護士の選び方についてご説明します。
きっと自社にあった弁護士の選び方をご理解いただけると思います。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所でも多くのベンチャーやスタートアップ企業の顧問弁護士として、企業の成長をサポートさせていただいています。
具体的なサポート内容のイメージがわかる顧問先企業と弁護士のインタビュー形式の動画をアップしていますので、もしよろしければご参照ください。
▼ベンチャーやスタートアップの法務に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
ベンチャーやスタートアップに強い顧問弁護士をお探しの方は、以下も参考にご覧下さい。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,ベンチャーやスタートアップ企業の法務で重要なこととは?
弁護士の選び方についてご説明する前に、まず、ベンチャーやスタートアップ企業の法務で重要なことはなにか、老舗企業や大企業の法務とは何が違うのかを確認しておきましょう。
(1)事業やビジネスモデルの適法性の調査
ベンチャーやスタートアップ企業の法務では、事業内容やビジネスモデルの適法性の調査がまず重要になります。
企業が提供しようとするサービスや商品が適法であることは、事業の大前提です。事業が成長軌道にのった後に、その事業の適法性に疑義が生じると、また最初からビジネスモデルを構築しなおすことになり、大きな痛手になります。従業員や取引先にも多大な迷惑をかけることになるうえ、違法な事業を行っていたとして制裁を受ければ、社会的に非難をうけることすらあります。
自社の商品やサービスが、各種の法令や、他社の知的財産権その他、他社の権利、あるいは一般消費者の権利と抵触しないかどうかについて、早めに弁護士に相談し、確認しておきましょう。
なお、新しい事業について、行政機関に対して事業の合法性を書面で確認する制度である、法令適用事前確認手続き(ノーアクションレター制度)もよく利用されています。また、法規制の適用の有無を確認するための、グレーゾーン解消制度という制度も設けられています。
合法性や法規制の適用の有無の確認が難しい分野では、こういった制度を利用した確認を弁護士に依頼することも選択肢の1つです。各制度については下記もご参照ください。
▶参考情報:法令適用事前確認手続き(ノーアクションレター制度)について
▶参考情報:グレーゾーン解消制度について
ベンチャー企業のビジネスモデル自体の適法性が問題になったケースの有名な例の1つとして、ソーシャルゲーム業界で問題になった「コンプガチャ」のケースがあげられます。「コンプガチャ」は当時、ソーシャルメディア業界の高い利益率の源泉となっていましたが、消費者庁の違法判断が示され、事業モデルの大きな転換を強いられました。
新しい事業やビジネスモデルについては初期段階でその適法性を確認しておくことが重要です。
(2)事業の基本となる契約書や利用規約の作成
ベンチャーやスタートアップの法務では、早い段階で、事業の基本となるサービスについて、自社オリジナルの契約書や利用規約を作成することが重要です。
特にこれまであまり例がなかった新しいサービス等を提供する場合、どのようなリスクや問題点があるかをよく分析したうえで、契約書や利用規約に落とし込むことが必要になります。新しい商談の際にも、自社サービスについての契約書や利用規約を提示して説明できなければ、成約に至ることは難しくなってしまいます。
ビジネスのチャンスを逃さないためにも、できるだけ早くからきちんとした契約書や利用規約の整備に取り組むことが重要です。また、ユーザーの情報を利用して収益をあげるビジネスモデルでは、プライバシーポリシーの作成も重要になりますので、あわせて整備が必要です。
利用規約やプライバシーポリシーの作成については、以下の記事も併せてご参照ください。
▶参考情報:利用規約の作成について
▶参考情報:プライバシーポリシーの作り方について
利用規約やプライバシーポリシーに対するサービス利用者の意識は年々高まっています。例えば過去にも以下のような事例がありました。
- 2016年:クラウドサービスEvernoteの利用規約変更について炎上事件が発生
- 2019年:Tカードの個人情報が捜査機関に任意に提供されていたことが大きく報道される
利用規約はプライバシーポリシーは思った以上に見られていることを意識して作成していくことが必要です。
(3)労務環境の整備
従業員との信頼関係を正しく築くことも、ベンチャー企業やスタートアップ企業の成功のために非常に重要な要素です。
その中でも、基本となるのが労務関連の法律をしっかり守ることです。法律を守ることができていないと、従業員との信頼を築くことができず、ビジネスが成長しません。
また、IPOでも労務関連の法律を守ることができているかが重要なカギを握ります。特に、残業代の支払いなど賃金関係にかかわる部分について違法なまま放置すると、事業が大きくなってからでは改善が難しいことが多いのが実情です。
会社が成長軌道にあるときは、できる限り早い段階で、労務について弁護士に相談する体制を整備しておくことが重要です。企業の労務管理を弁護士に相談することの重要性については以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
▶参考情報:労務管理とは?重要な15のポイントを解説!
(4)インセンティブを付与する仕組みづくり
資金余力が大きくないベンチャー企業やスタートアップ企業では、従業員に最初から高い給与を支払うことは難しいこともあります。
それでも優秀な従業員を集めるために、将来、上場したあかつきには、多額の利益が得られるストックオプションなどのインセンティブを従業員に付与することが増えています。
最近では、IPOを目指すベンチャー企業やスタートアップ企業においてはストックオプションを導入することが一般的になりました。
例えば、2017年新規上場の27社はすべてストックオプションを発行しています。
こういったインセンティブ付与のための制度設計も、ベンチャーやスタートアップにおける弁護士の重要な役割といえるでしょう。
ストックオプションについては以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(5)ベンチャーキャピタル等の出資者との契約関係
ベンチャーキャピタル等や事業会社から出資を受ける場合は、出資者との契約関係が非常に重要になります。
投資契約書や株主間契約書を締結することが多いですが、その内容を十分理解し、必要に応じて契約書の修正交渉を行うことが必要です。
十分に契約書を検討せずにこれらの契約を締結してしまうと、将来不本意な形で自社株を売却しなければならなくなったり、IPOができなかったときに出資者から株式の買取を要求されて会社が資金的に行き詰まるなどのリスクがあります。
出資者との契約書のリーガルチェックを行い、創業株主や会社にとって不利益な内容になっていないかを確認することもベンチャーやスタートアップにおける弁護士の重要な役割になります。
投資契約書や株主間契約書については以下の記事で詳しく解説していますので参照してください。
(6)取締役会議事録、株主総会議事録などの作成、リーガルチェック
ベンチャー企業やスタートアップ企業を正しく発展させるためには、取締役会を毎月開いて経営方針の策定や重要な業務執行についての意思決定のための議論を行い、同時に経営者を監督していくガバナンスの観点が非常に重要です。
取締役会や株主総会の運営についてサポートし、また、取締役会の招集通知や取締役会議事録、株主総会の招集通知や株主総会議事録などについてリーガルチェックによるサポートを行うことも、ベンチャー企業やスタートアップ企業における弁護士の重要な役割です。
(7)日ごろの事業運営に関する相談
ここまでご説明した分野以外に、日ごろの事業運営について弁護士のサポートを受けることも重要です。
例えば、「売掛金の回収」や「風評被害対策」、「クレーマー対応」、「問題社員対応」、「従業員向けコンプライアンス研修」、「株主総会や取締役会の運営」などの分野で弁護士のサポートを受けることで、トラブルを減らし、スムーズに事業を発展させていくことができます。
▶参考情報:各分野については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
・成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読
(8)継続的に弁護士に相談する体制が必要
ここまで、ベンチャー企業やスタートアップ企業における弁護士の役割についてみてきました。
重要なことは、困ったときに単発で弁護士に相談に行くのではなく、日ごろから継続的に弁護士に相談して、問題が起こる前に予防する体制を確保することが重要になるということです。
例えば、「事業やビジネスモデルの適法性の調査」についても、事業の内容が変化したり、新しいサービスが加わるごとに確認が必要になりますし、事業の内容に変化がなくても、法律や判例など外部環境が変わることによる確認も必要になります。
そのため、一度相談に行って終わりという話ではなく、継続的に相談する体制づくりが必要です。
また、「事業の基本となる契約書や利用規約の作成」についても、一度作ったらそれでよいというものではありません。
事業を進めていくうえで新たなトラブルが出てくることは避けられませんので、それらのトラブルの内容を踏まえて、契約書や利用規約を常にブラッシュアップしていくことが重要になります。
「労務環境の整備」では、毎年のように行われる労務関係の法改正を確認し、対応していくことが必要です。
このように、いずれの分野においても、継続的に弁護士に相談する体制を作ることが重要です。
問題が起こった時に相談するのではなく、日ごろから弁護士に相談して問題を予防するという予防法務の重要性を理解することは、ベンチャー企業やスタートアップ企業を安定的に成長させるうえで大きなポイントになります。
予防法務の役割や重要性については以下の記事でもあわせて解説していますのでご参照ください。
2,ベンチャーやスタートアップ企業を成功に導く弁護士の選び方
それではここまでご説明した点を踏まえ、ベンチャーやスタートアップ企業を成功に導く弁護士の選び方について見ていきましょう。
(1)ビジネスを理解してもらえる弁護士を選ぶ
まず、当然のことですが、自社のビジネスを理解してもえる弁護士であることは重要です。
ベンチャー企業やスタートアップ企業を成功に導くにあたって、法務に携わる弁護士の役割は重要であり、自社のパートナーとして自社の発展を意欲的にサポートしてくれる弁護士を選ぶ必要はあります。
新しいビジネスモデルである場合は、特にこの点に注意して、ビジネスモデルを理解し、趣旨に賛同してくれる弁護士を選ぶようにしてください。
(2)できれば業界に詳しい弁護士を選ぶ
一部の事業分野では、その業界にのみ適用される特殊な法律に精通していることが必要になります。
例えば、医療やヘルスケアの分野では、薬機法や個人情報保護法に精通した弁護士を選ぶのがよいですし、金融商品に関する分野では、金融商品取引法に精通した弁護士を選ぶべきです。
このように、その業界に詳しい弁護士、その業界の企業の顧問経験のある弁護士を選ぶことをおすすめします。
(3)コミュニケーションが取りやすい弁護士を選ぶ
さらに、重要なことは、コミュニケーションがとりやすく、少し気になったことや不安に思ったことでも気軽に相談しやすい弁護士を選ぶことが大切です。
できれば法律に関する部分だけでなく、経営事項や事業戦略についても気軽に意見を聴ける関係を弁護士と築くことが望ましいといえます。
また、コミュニケーションの手段についても確認しておきましょう。
電話で相談するということがオーソドックスですが、例えば、チャットワークやZoomなどのITツールのほうが連絡しやすい場合は、そういったツールに対応してくれる弁護士を選ぶことが必要です。
携帯電話の番号も教えてくれるフランクな弁護士のほうが、気軽に相談しやすいでしょう。
(4)レスポンスの早い弁護士を選ぶ
弁護士への不満としてよく上がるのがレスポンスが遅いということです。
弁護士を選ぶ際はすぐに連絡が取れるか、すぐに返事をくれるかという視点も重要です。
また、契約書のリーガルチェックを多く依頼する予定があるときは、チェックの完了までに標準的にどの程度の時間をがかかるのか尋ねておくとよいでしょう。
3,具体的な弁護士の探し方は2通り
ここまで見てきた通り、ビジネスを理解してもらえる弁護士かどうか、業界に詳しい弁護士かどうか、コミュニケーションが取りやすい弁護士かどうか、レスポンスの早い弁護士かどうかという点が重要です。
そして、これらの点を確かめためには、直接、弁護士と話をして、自社の事業を説明し、また、弁護士の経験や対応できる範囲を尋ねることが必要になります。
具体的な弁護士の探し方としては、主に以下の2通りがあります。
- 「インターネットなどで情報収集して候補となる弁護士を自分で探す方法」
- 「知り合いの社長や自社の税理士に弁護士の候補者を紹介してもらう方法」
インターネットで探す場合は、ウェブサイトなどで自社の業種や業界に対応してくれそうかどうかを確認したうえで、法律事務所に連絡を入れて、実際に弁護士と話する機会を設定してもらうことが一般的です。
一方、知り合いの社長や税理士に紹介してもらう場合は、紹介者同席で弁護士と面会するというケースも多いでしょう。
その場合でも、紹介者の推薦をうのみにせずに、本当に自社の弁護士として適切かどうかを前述の4つの視点で確認することが必要です。
知り合いに弁護士を紹介してもらい、契約をした場合、あとでミスマッチだったと感じても、断りにくいという声が良く聴かれますので、慎重に吟味されることをおすすめします。
自分の会社にピッタリあった弁護士の選び方については、以下の記事も参考にご覧下さい。
4,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます」

最後に咲くやこの花法律事務所のサービス内容についても簡単にご紹介したいと思います。
咲くやこの花法律事務所でも、多くのベンチャー企業の顧問弁護士として、企業の成長をサポートさせていただいています。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの中で最も多くの方に多く選択していただいているのが以下のプランです。
(1)スタンダードプラン(月額顧問料5万円:週に1~2回程度のご相談をご希望の方)
主なサポート内容
- ベンチャー企業やスタートアップ企業法務に精通した弁護士が対応します。
- 週に1~2回の相談頻度を目安に弁護士への相談をご希望の会社向けのプランです。
- 弁護士にいつでもメールや電話、チャットワーク、Zoom、スカイプなどでご相談いただくことが可能です。もちろん事務所に来所いただいての相談も可能です。
- 契約前に担当弁護士との無料面談で相性をご確認いただくことができます(電話・テレビ電話でのご説明or来所面談)
- 来所していただかなくても、電話あるいはテレビ電話でお申込みいただけます。
また、より手厚いサービスをご希望のベンチャー企業やスタートアップ企業の方には、以下のオーダーメイドプランをご利用いただいています。
(2)オーダーメイドプラン(月額顧問料20万円:相談時間制限なし:月1回訪問)
このプランでは、月1回弁護士が企業を訪問し、従業員や役員向けの研修を行ったり、取締役会に参加するなどして、より企業に密着して支援を行い、企業の成長をバックアップいたします。
顧問弁護士サービスの開始までの詳しい流れは以下をご参照ください。
また、咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細や実績については以下のページをご参照ください。
5,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法
ベンチャーやスタートアップ企業に詳しい弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
6,ベンチャーやスタートアップ企業に関連するお役立ち情報も配信中!(メルマガ&YouTube)
顧問弁護士に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2024年5月9日
 06-6539-8587
06-6539-8587