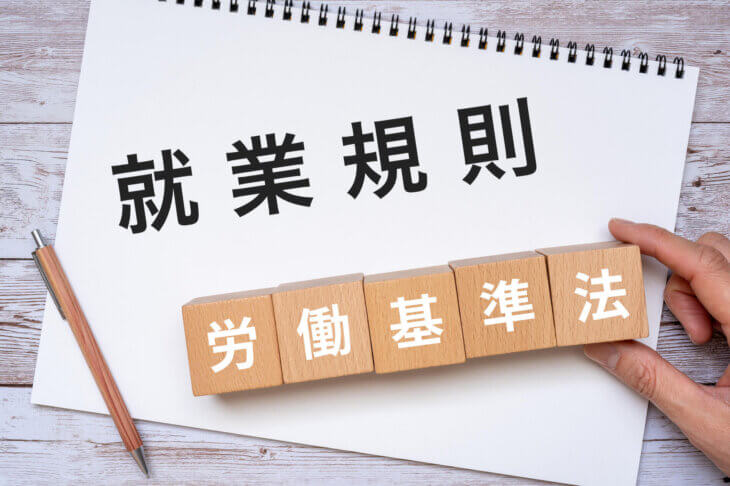
こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
常時10人以上の従業員を雇用している企業は、就業規則の作成が義務付けられています。就業規則は、労働時間や賃金などの労働条件や、服務規律や懲戒など会社におけるルールをあらかじめ定めておくもので、企業と労働者の双方にとって非常に重要なものです。
そして、このような就業規則は、その内容が法律に違反しないように定める必要があり、就業規則で定めている内容が労働基準法などに違反しているような場合には、無効となってしまいます。
せっかく就業規則を作成していても、内容が法律に違反している場合、そのことが労務トラブルのきっかけになってしまったり、就業規則の効力が裁判所で否定されて就業規則がルールとして機能しない事態におちいるおそれがあります。
この記事では、就業規則と法律の優先関係についてご説明した後、就業規則に定める、特に誤りがちな項目について、注意点などを解説いたします。
▶参考:なお、そもそも就業規則とは?など就業規則に関する基本的な解説は、以下をご参照ください。
就業規則に記載しなければならない内容は労働基準法によって定められていますが、ただそれらを記載すればよいのではなく、内容が法律で定められる基準を下回らないようにする必要があります。
また、ひな形をそのまま利用するのではなく、自社の事情を踏まえたオリジナルの就業規則を作成しなければ、自社の実態にあわない就業規則になってしまい、そのこと自体がトラブルの原因になってしまいます。
実際に労働問題、労働裁判の現場を担当してきた労務に強い弁護士に相談しながら、いざとなったときもしっかりルールとして機能し、会社を守れるような内容で作成しておくことが大切です。筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でもご相談を承っていますのでご相談ください。
▼【関連動画】西川弁護士が「こんな就業規則は労働基準法違反!問題のある規定例7選(休職・自宅待機・退職金など)【前編】」「【後編】「こんな就業規則は労働基準法違反」問題のある規定例7選(管理職・有給休暇・賃金減額など)」を詳しく解説中!
▼就業規則について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,就業規則と労働基準法の関係とは?
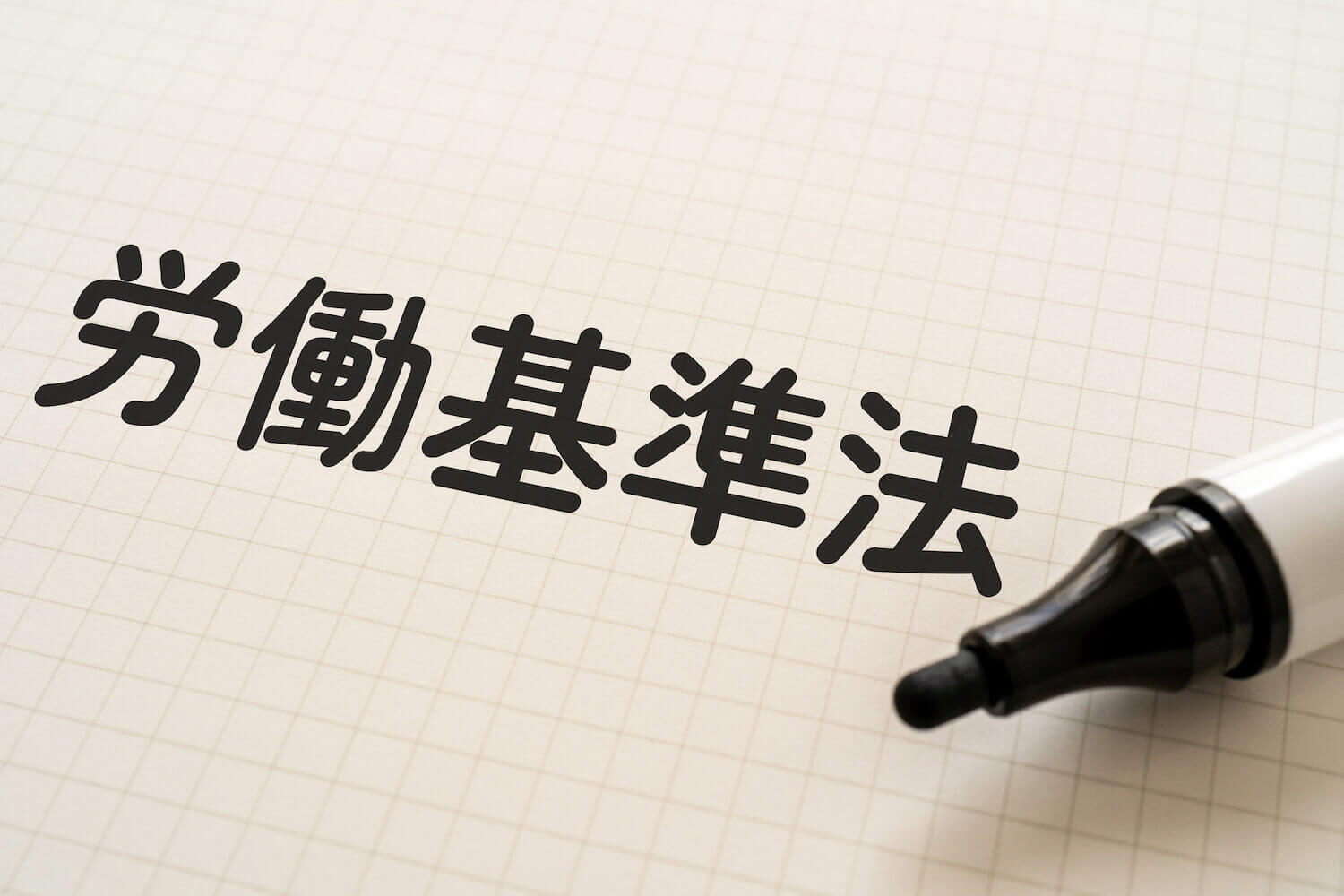
就業規則と労働基準法の関係として重要なことは、まず、就業規則に必ず定めなければならない項目が労働基準法で定められていることです(労働基準法第89条)。次に、就業規則の内容が労働基準法に違反してはならないという点です(労働基準法第92条1項)。さらに、就業規則の周知や届出についても就業規則に定められています(労働基準法第89条、第106条1項)。
これらの点についてこの記事でご説明していきたいと思います。
2,労働基準法に定められた必要的記載事項とは?
就業規則と労働基準法の関係で、まず重要な点は、就業規則に必ず記載すべき項目が労働基準法で定められているという点です。
この点は労働基準法第89条によって定められており、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、その項目について定める場合は必ず就業規則に記載をしなければならない「相対的必要記載事項」があります。そのほか、記載するかどうかが自由である「任意的記載事項」もあります。
特に、絶対的必要記載事項については、就業規則を作成する義務がある全ての事業者が就業規則において定める必要があり、これが抜けていると労働基準法違反(就業規則作成義務違反)として罰則の対象となるため注意が必要です。
就業規則の絶対的必要記載事項は以下の通りです。
- (1)始業時刻
- (2)終業時刻
- (3)休憩時間
- (4)休日
- (5)休暇
- (6)労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- (7)賃金の決定、計算の方法
- (8)賃金の支払の方法
- (9)賃金の締切り及び支払の時期
- (10)昇給に関する事項
- (11)退職に関する事項、解雇事由
▶参考:就業規則の記載事項については、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
なお、就業規則の記載事項について定める労働基準法第89条の内容は以下の通りです。
▶参考:労働基準法第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
3,就業規則の内容に労働基準法違反や法律違反がないか確認する
労働基準法で記載が義務付けられる事項が、就業規則で定められているかをチェックすることとは別に、就業規則で定められた内容が労働基準法その他の法律に違反しないかも確認が必要です。
この点については、まず、「4,就業規則と法律の優先関係」についてご説明した後、特に誤りが発生しやすい以下の規定について解説します。
- (1)退職の規定
- (2)休憩時間の規定
- (3)有給休暇の規定
- (4)賞与の規定
- (5)定年の規定
- (6)解雇事由の規定
- (7)休日の規定
▶参考情報:労働基準法違反については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
4,就業規則と法律の優先関係
まず、就業規則と労働基準法などの法律との優先関係についてご説明します。
(1)就業規則と法律の優先関係は?
就業規則は、法令に反してはならないことが定められています(労働基準法第92条1項)。
就業規則で定める労働条件が法律の規定を下回る場合、法律で定められる基準が優先して適用されます。就業規則の内容が法律で定められている基準より下回っている部分については無効となります(労働基準法13条)。
また、労働者と使用者間のルールとして、法律や就業規則の他に、労働契約(雇用契約書や労働条件通知書等)や労働組合と使用者の間の労働協約が挙げられます。これらの優先関係は、上から以下の通りになります。
- 1.法令(労働基準法や民法など)
- 2.労働協約
- 3.就業規則
- 4.労働契約
▶参考:労働協約とは、労働組合と使用者との間で定める、労働条件や、労使関係全般に関する取り決めのことです。労働協約については以下をご参照ください。
なお、これらの優先関係を定める法律は以下のとおりです。
| 法律 | 優先関係 (優先度高>優先度低) |
条文 |
| 労働基準法13条 | 労働基準法>労働契約 | (この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 |
| 労働基準法92条1項 | 労働協約>就業規則 | (法令及び労働協約との関係)
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 |
| 労働契約法12条 | 就業規則>労働契約 | (就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 |
・参照元1:「労働基準法」はこちら
・参照元2:「労働契約法」はこちら
例えば、就業規則に有給休暇をとる際は会社の承認が必要であると定めたとしても、労働基準法上、有給休暇は会社の承認がなくても取得することができるとされているため、就業規則のうち、承認が必要であると定めた部分については効力が認められません。
(2)就業規則において労働基準法を上回る労働条件を定めている場合
では、例えば、就業規則において労働基準法を上回る労働条件を定めている場合はどうなるのでしょうか。
結論から言えば、この場合は、就業規則の定めが適用されることになります。
例えば、労働基準法第39条1項では入社後6か月の時点で10日の有給休暇を付与しなければならないとされています。この点について、就業規則では入社後6か月の時点で15日の付与を規定しているような場合は、就業規則の規定により、15日の有給休暇が付与されます。
このように、就業規則で定める内容が労働基準法などの法律の基準を下回る場合はその部分は無効となる一方、労働基準法などの法律の基準を上回る部分については、就業規則が適用されます。つまり、労働基準法の規定は、「下回ってはいけない最低限の労働条件」を定めるものです。
5,就業規則の退職の規定と法律の優先関係
就業規則と法律の優先関係について、問題になりやすい項目の1つが「退職」に関する規定です。
退職に関する規定は労働基準法よりも民法との関係が問題になります。
民法第627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」としています。
これは、従業員が一方的な意思表示により事業主の承諾を得ずに雇用契約を終了する「辞職」の場合について規定した条文です。
そして、この民法627条1項は、使用者による不当な人身拘束を防ぐ趣旨のものであり、強行的な性質をもち、2週間を超える予告期間を定めても無効であると解釈されています(東京地方裁判所判決昭和51年10月29日高野メリヤス事件、横浜地方裁判所判決平成29年3月30日プロシード事件等)。
そのため、例えば、「従業員が自己の都合により退職しようとする時は1か月前までに退職願を人事部長に提出し承諾を得なければならない。」と就業規則に定めたとしても、民法627条1項により、従業員は承諾を得ずに2週間前に会社に通知することにより退職することが可能です。
▶参考情報:退職についてのルールは、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
6,休憩時間の規定
休憩時間については、労働基準法により「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とされています(労働基準法第34条1項)。
通常、会社では、正社員の就業は残業も含めると1日の就業時間が8時間を超えることが多いでしょう。その場合は、1時間以上の休憩時間を定めておかなければならず、これより短い休憩時間を定めることは労働基準法違反となります。
また、労働基準法により使用者は、「休憩時間を自由に利用させなければならない。」とされています(労働基準法34条3項)。
この点については、休憩時間中の外出につき会社の許可を得ることを義務付けることも、事業場内で自由に休息できるのであれば、必ずしも違法とはならないとした通達があります(昭23.10.30 基発1575号)
▶参考情報:休憩時間の基本的なルールについては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
7,有給休暇の規定
有給休暇の取得の規定についても誤りが発生しやすく、注意が必要です。
以下でご説明いたします。
(1)付与の日数や付与の時期について
有給休暇の付与日数や付与の時期は労働基準法第39条1項及び2項に定められています。
有給休暇の付与の日数を労働基準法の規定よりも減らしたり、あるいは付与の時期を労働基準法の定めよりも遅らせるような就業規則は労働基準法違反です。
▶参考情報:有給休暇の基本的なルールについては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(2)有給休暇の届出を一定日数以上前に義務付ける規定について
では、就業規則で、有給休暇取得について一定日数以上前に届け出るべきことを義務付けることは労働基準法に違反しないのでしょうか?
この点については、5営業日前までの届出を義務付ける規定について、労働基準法とは別に有給休暇を与えない場合を創設するものであるから、労働基準法違反であり無効と判示した例もあります(大阪地方裁判所 令和4年9月29日 大尊製薬事件)。
しかし、一般的には、一定日数以上前に届け出るべきことを義務付けることも適法とされています。
最高裁判所判決 昭和57年3月18日(電電公社此花電報電話局事件)も、就業規則において年次有給休暇について前々日までの請求を義務付けた事案について、「就業規則の定めは、年次有給休暇の時季を指定すべき時期につき原則的な制限を定めたものとして合理性を有する」としています(但し、シフト制勤務で、組合との間で勤務シフトの変更は前々日までという協約規定があった事案です)。
また、就業規則において年次有給休暇の14日前までの届出を義務付けた規定について、これが有効であることを前提とする判示をした裁判例として、大阪地方裁判所判決 令和4年7月22日(カワサキテクノリサーチ事件)があります。
ただし、このような規定をおいても、例えば前日に年次有給休暇の届出があった場合に、休暇取得を認めないことができるわけではありません。
労働基準法は第39条5項で「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」としています。
就業規則に違反して直前に届出られた有給休暇の取得であっても、事業者は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ、有給休暇の取得日を別の日に変更するように求める権利(時季変更権)を行使できるにすぎないことに注意が必要です。
届出を期限までにしなかった点は、就業規則違反として扱い、今後遵守すべきことを指導できるにすぎません。
▶参考:時季変更権についての解説は以下をご参照ください。
▶参考:就業規則違反への対応についての解説は以下をご参照ください。
8,賞与の規定
賞与を支給するか否かについては、会社と従業員の雇用契約において自由に決めることができます。
ただし、賞与を支給する旨を定める場合には、賞与に関する項目は「2,労働基準法に定められた必要的記載事項とは?」でご説明した「相対的必要記載事項」に該当するため、就業規則に賞与に関する事項を定める義務があることに注意してください。
(1)支給日在籍要件について
賞与について規定する上で注意が必要な点として、「支給日在籍要件」が挙げられます。これは「賞与の支給日に在籍している従業員にのみ賞与を支給する」というルールです。
例えば、従業員が賞与の支給日より前に退職することとなった場合、「せめてこれまで頑張った分の賞与はもらっておきたい」と考える人も多いのではないでしょうか。そのため、支給日前に退職した従業員に賞与を支給しない場合、従業員との間で、賞与の支給をめぐって紛争になるケースも少なくありません。
この点については、最高裁判所判決 昭和60年11月28日 京都新聞社事件の裁判例があります。判決は、この事案で、賞与を支給日に在籍する従業員にのみ支給することは不合理とはいえないとしています。
ただし、賞与について支給日在籍要件のルールを採用するときは、必ず就業規則にその旨を定めておく必要があります。
9,定年の規定
定年についての就業規則の規定は、労働基準法よりも、高年齢者雇用安定法との関係が問題になります。
高年齢者雇用安定法により、定年は原則として、60歳を下回ることができないとされています(高年齢者雇用安定法第8条)。
▶参考:高年齢者雇用安定法第8条
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
・参照元:「高年齢者雇用安定法」の条文はこちら
また、65歳未満の定年を設けている事業主には、定年の引き上げ、定年の廃止、65歳まで希望者を継続雇用する制度の導入のうちいずれかの措置を講じることが求められています(高年齢者雇用安定法第9条1項。高年齢者雇用確保措置と呼ばれます)。
▶参考:高年齢者雇用安定法第9条1項
定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
・参照元:「高年齢者雇用安定法」の条文はこちら
就業規則の定年の規定も、これらのルールを踏まえて定めることが必要です。
上記に加え、令和3年4月の高年齢者雇用安定法改正で、70歳までの就業機会確保のための措置を講じることが努力義務とされていることにも留意が必要です(高年齢者雇用安定法第10条の2)。
高齢者雇用については以下で解説していますのでご参照ください。
▶参考情報:高齢者雇用についてわかりやすく解説
10,解雇事由の規定
解雇は、使用者が一方的に雇用を終了するものであることから、深刻なトラブルに発展するケースも多い場面です。解雇トラブルを防ぐ意味でも、就業規則における解雇についての規定の仕方を十分検討する必要があります。
また、解雇事由について定める就業規則の規定が労働基準法に違反しないようにするためには法律上の解雇制限規定を確認する必要があります。
例えば、業務上の怪我や病気の治療のために休業する期間とその後30日間、及び女性社員の産前産後の休業期間とその後30日間について法律上原則として解雇が禁止されています(労働基準法第19条1項)。就業規則にもこれらの点を反映しておくことが適切です。
▶参考:解雇制限については以下で解説していますのでご参照ください。
さらに、派遣会社では、派遣元指針において、以下の解雇が禁止されていることに注意してください(派遣元指針第2の2(4))。
就業規則にもこれらの点を反映しておくことが適切です。
▶参考:派遣元指針第2の2(4)
- 無期雇用派遣労働者を派遣先との契約終了のみを理由に解雇すること
- 有期雇用派遣労働者を派遣先との契約終了のみを理由に、有期雇用契約の期間内に解雇すること
11,休日の規定
休日については、労働基準法第35条により、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間で4日以上の休日を与えることが義務付けられています。就業規則で休日について定める場合もこのルールを下回らないようにする必要があります。
▶参考:労働基準法第35条
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
・参照元:「労働基準法」の条文はこちら
ここでいう「週」とは、就業規則等で別段の定めがないときは、日曜から土曜までを差します(昭和63年1月1日基発第1号)。
そして、4週間で4日以上の休日を与える方法で対応する場合は、就業規則において、単位となる4週間の起算日を定めておく必要があります(菅野和夫著「労働法 第十二版」)。
就業規則では休日の振替についての規定がおかれることも多いですが、その場合、振り替え後の休日が4週間を通じ4日以上でなければ労働基準法違反となることにも注意してください。
▶参考情報:労働基準法における休日のルールについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
12,周知・届出の義務にも注意
ここまで、就業規則と法律の関係や、就業規則の記載内容についての法律上の規定についてご説明致しました。
就業規則について、もう1つ労働基準法に定められている重要な点が、周知と届出の義務です。
事業者が就業規則を作成・変更したときは、労働基準監督署長に届け出なければならず、また、就業規則の内容を従業員に周知しなければなりません。
13,就業規則の変更と労働基準法
就業規則の変更の場面での労働基準法の規律としては、まず、労働基準法第89条及び第90条により、従業員代表から意見を聴取した上で労働基準監督署長に届けなければならない旨の規定が置かれています。そして、労働基準法第106条1項により、変更後の就業規則の周知も義務付けられています。
一方、就業規則の変更が従業員にとって不利益な内容を含むときに、従業員に変更後の就業規則を適用することができるかどうかという「不利益変更」の問題については、労働基準法ではなく、労働契約法に規定が置かれています。
労働契約法は、第9条において、就業規則の変更による労働条件の不利益変更は原則としてできないことを定めたうえで、第10条で例外として、変更が合理的なものである場合は、変更後の就業規則を周知することを条件に、就業規則の変更による労働条件の不利益変更を認めています。
▶参考:就業規則の不利益変更については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
▶参考:労働契約法第9条・第10条
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
・参照元:「労働契約法」の条文はこちら
14,「咲くやこの花法律事務所」ならこんなサポートができます!

最後に、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介いたします。
(1)就業規則のリーガルチェック
咲くやこの花法律事務所では、すでに作成済みの就業規則について、企業からのご相談により、リーガルチェックのご依頼を承っています。
数々の労働紛争を企業側の立場で解決してきた労務に強い弁護士がリーガルチェックを行うことで、労務トラブルが発生するようないざという場面で、会社を守れるような就業規則を作成することができます。
就業規則のリーガルチェックについては、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
(2)就業規則の作成
咲くやこの花法律事務所では、就業規則の作成のご依頼も承っています。
咲くやこの花法律事務所では労務トラブルに関するご相談やご依頼を多数いただいており、労務トラブルについて豊富な経験と実績を有している弁護士が多く在籍しています。そういった経験を生かし、万が一の労務トラブルに備えた就業規則を作成することで、労務トラブルに強い企業づくりのお手伝いをさせていただきます。
労務トラブルに強い弁護士への就業規則作成のご依頼は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にお任せください。
咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●就業規則の作成費用:20万円+税~
(3)顧問弁護士サービス
咲くやこの花法律事務所では、企業の労務管理全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しております。
就業規則の整備のほかにも、雇用契約書の整備、問題社員対応、ハラスメント対策、労使トラブル対応、法改正対応など、労務のトラブルを予防し、あるいは解決するために必要な取り組みは非常に幅広いです。そして、これらはいずれも、日頃からの予防法務の取り組みができているかどうか、そしてトラブル発生時の早期の対応ができるかどうかが、重要なポイントになります。
咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で数多くの事案に対応してきた経験豊富な弁護士が、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。
(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
15,まとめ
この記事では、就業規則と法律、特に労働基準法との関係についてご説明致しました。
労使間のルールを定めるものとしては、就業規則以外に、法律・労働協約・労働契約が挙げられます。これらの優先関係は以下の通りとなり、法律で定める基準は、あくまで最低限の基準を定めるものです。
- 1.法令(民法や労働基準法など)
- 2.労働協約
- 3.就業規則
- 4.労働契約
また、誤って規定しがちな以下の項目について定める際の注意点などをご説明しました。
- (1)退職の規定
- (2)休憩時間の規定
- (3)有給休暇の規定
- (4)賞与の規定
- (5)定年の規定
- (6)解雇事由の規定
- (7)休日の規定
そして、就業規則の作成後は、労働基準監督署長への届出や、社内の従業員への周知が必要です。
このように、就業規則は作成から周知までのプロセスを経てやっと、ルールとして機能するものとなります。自社の就業規則が本当に法律に適合しているかなどご不安な点がある場合は、労務に強い弁護士へ相談することをおすすめします。
16,【関連情報】就業規則に関する他のお役立ち記事一覧
この記事では、「就業規則と労働基準法の関係とは?違反する場合などを詳しく解説」についてご紹介しました。就業規則に関しては、法律に関して以外にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
そのため、以下ではこの記事に関連する就業規則のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・モデル就業規則とは?厚生労働省作成の無料テンプレートの使い方
・就業規則の閲覧を求められたら?会社は応じる義務がある?対処法を解説
・就業規則の意見書とは?記入例や意見聴取手続きの注意点を解説
・就業規則がない場合どうなる?違法になる?リスクや対処法を解説
・パート・アルバイトの就業規則の重要ポイントと注意点【雛形あり】
・在宅勤務やテレワーク・在宅ワークの就業規則の重要ポイント7つ
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年6月26日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」就業規則に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587












































