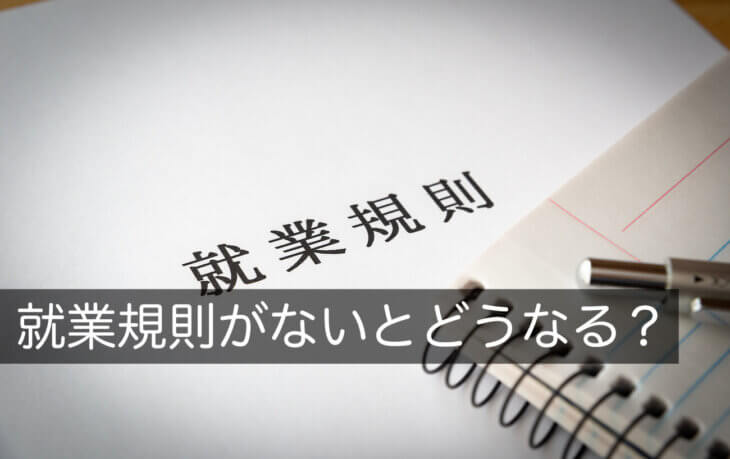
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。
就業規則がない会社(常時10人以上の従業員を使用する事業場がある会社)は、労働基準法第89条の「就業規則の作成及び届出の義務」に対する違反となり、30万円以下の罰金が科されます。また、問題のある従業員に対しても懲戒解雇できなくなる、定年退職の制度がない状態となり高齢になっても従業員の雇用を継続する義務を負うなど様々な不都合がでてきます。
この記事では、就業規則がない場合の会社のリスクや、就業規則がない場合に従業員から受けやすい質問についてご説明したうえで、その必要性や実際に就業規則を整備していくための進め方についてもご説明します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、就業規則がない会社の問題点をよく理解していただき、整備を進めていく方法も理解していただくことができます。
それでは見ていきましょう。
就業規則は従業員が就業するうえで守るべきルールを定める重要なものであり、労務管理のかなめともいえます。労務管理がきちんとできていないと、従業員が問題行動を起こしたときにおさまりがつかず、会社運営に重大な支障を生じさせることにもなりかねません。
この記事で、就業規則がない場合の大きなデメリットを理解いただき、就業規則の整備をすすめてください。咲くやこの花法律事務所では就業規則の整備についてのご相談を、企業の労務管理に強い弁護士が承りますので、ご相談ください。
▼【関連動画】西川弁護士が「就業規則がない会社!そのまま放置は厳禁です!」を詳しく解説中!
▼就業規則がない場合に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,就業規則がない会社は違法なのか?

常時10人以上の従業員を使用する事業場がある会社は、労働基準法第89条(※1)で「就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ること」が義務付けられています。作成しないことや届出をしないことは違法であり、義務違反には、30万円以下の罰金が科されます。
(1)常時10人以上数え方
常時10人以上の数え方として以下のルールがあります。
1,事業場ごとに数える
事業場とは、工場や事務所、店舗等を指します。
このような工場、事務所、店舗ごとに人数を数えて、10人以上の事業場についてのみ、就業規則の作成と届出の義務が課されます。
例えば、10店舗を経営している会社で、従業員が全部で50人いるけれども、従業員が10人以上配属されている店舗はないという場合は、就業規則の作成と届出の義務は課されません。
2,非正規の労働者も含める
正社員だけでなく、パート社員やアルバイトなども含めて10人以上であれば、就業規則の作成と届出の義務の対象となります。
ただし、繁忙期のみ10人以上となるといった場合は、「常時10人以上」には該当せず、作成と届出の義務は課されません。
(2)10人未満でも作ったほうが良い
10人未満の事業場のみの会社は、法律上、就業規則の作成の義務はありません。
ただし、その場合でも、自発的に就業規則を作成することは可能です。
後でご説明する通り、就業規則がないことによるデメリットは大きいので、10人未満の事業場のみの会社も就業規則は作成しておいたほうが良いことは間違いありません。
筆者が法律事務所を創業した当初は、従業員1名のみでしたが、それでも就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ました。
2,就業規則がない場合の会社のデメリット
就業規則がない場合、前述の罰則の対象となるだけでなく、様々なデメリットがあります。
(1)問題社員がいても懲戒解雇はできなくなる
就業規則がない場合、従業員の問題行動があっても、懲戒解雇をはじめとする懲戒処分を科すことができません。
これは、判例上、企業が従業員に懲戒処分を科すためには、あらかじめ就業規則に懲戒の種別(どんな懲戒処分があるか)や懲戒事由(どんな場合に懲戒処分の対象になるか)を事前に定めておくことが必要であるとされているためです(フジ興産懲戒解雇事件 最高裁判所判決平成15年10月10日)。
フジ興産懲戒解雇事件 最高裁判所判決平成15年10月10日の判決については以下をご参照ください。
懲戒解雇をはじめとする懲戒処分は、問題社員の問題行動にけじめをつけさせ、また、社内に向けても会社が問題行動を放置しないことを示して、社内の規律を維持するために重要なものです。
このような懲戒処分をできないことになることは、会社の労務管理のうえで、大きなデメリットになる可能性があります。
ここで説明した懲戒処分や懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
(2)服務規律を明確にできない
就業規則がない場合の問題点として、「服務規律を明確にできない」ということもあげられます。「服務規律」とは、従業員が勤務するうえで守るべき会社のルールのことをいいます。
「服務規律」の内容は企業によって様々ですが、例えば以下のような内容を定めることが多いです。
- セクハラ、パワハラをしてはならないということ
- 営業秘密や個人情報について正しく取り扱うべきこと
- タイムカードを正しく打刻すべきこと、他人に打刻してもらってはならないこと
- 取引先からリベートを受け取ることの禁止
- 通勤時に車両を使用する場合は会社の許可を得なければならないこと
- 就業するうえでの身だしなみについて
こういったことは一見当たり前のことのようですが、ルールとして明確にしておかなければ、違反行為があったとしても、その従業員をとがめることはできません。
社内のルールとして従業員全員の共通認識にするためには、就業規則でこれらの服務規律について明確に定める必要があるのです。
(3)副業に関するルールを明確にできない
会社に勤めながら副業をする人は非常に増えています。しかし、従業員が副業に長時間従事した結果、本業の勤務がおろそかになったり、競合他社で副業することにより競合に情報が漏えいするといったリスクがあります。
そのため、副業を許可制にして、副業に割く時間や副業の内容を確認したうえで、許可、不許可の判断をする仕組みを就業規則で定める必要があります。
就業規則がなければ、副業に関するルールがなく、副業は従業員の自由に委ねられている状態となります。その結果、無許可で副業されても会社として副業をやめなさいということはできなくなるおそれがあります。
副業に関するルールについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
(4)定年制を適用できない
就業規則では定年についても定めることが通常です。
定年を雇用契約書で定めることもできますが、雇用契約書では定年について言及されていないことも多く、その場合に、就業規則がなければ、定年のない雇用契約になってしまいます。
その結果、従業員が高齢になり、就業が難しくなってきても、従業員から退職の申し出がない限り、原則として雇用を継続しなければならないことになってしまいます。
(5)病気休職者への対応ができない
多くの会社では病気休職者への対応について就業規則で定めています。
休職をどのくらいのの期間認めるのか、どのような条件で復職を認めるのかを定めたうえで、休職期間中に復職ができない場合は退職になることを定めていることが多いです。
就業規則がなければ病気休職する場合のルールが不明確になってしまい、従業員が病気になった時の対応をめぐってトラブルになる危険があります。
病気休職をめぐるトラブルについては、以下でも解説していますのであわせてご参照ください。
(6)助成金をもらえない
助成金の制度は頻繁に変更されますが、例えば中途採用の拡大について支給される中途採用等支援助成金「中途採用拡大コース」、契約社員やパート社員を正社員雇用に転換し賃金を増額させたときに利用できる「キャリアアップ助成金」など豊富なラインナップが用意されています。
これらの助成金の活用には事実上、就業規則の整備が必須であり、就業規則が整備されていない会社でこれらの助成金を活用することは困難になっています。
雇用関係の助成金については以下をご参照ください。
就業規則の整備が必須でない助成金もあります。コロナ禍で多く活用された雇用調整助成金などは就業規則がない場合でも受給が可能です。
(7)成績不良者に対しても減給が困難
成績不良などを理由に従業員を降格させて給与を減額することは、就業規則に規程を設けていなければできません(東京地方裁判所判決平成30年9月25日等)。
そのため、給与に見合う成果をあげられない従業員に対しても、就業規則がなければ、給与の減額などの対応ができません。
給与の減額は重大な不利益変更であり、就業規則がある場合でも簡単にできるわけではありません。客観的な理由がある場合に、就業規則のルールに従って行う場合にのみ適法となる余地があります。
労働条件の不利益変更については以下をご参照ください。
3,賃金規程やパート社員用就業規則がない場合
正社員用就業規則はあるけれど、賃金規程やパート社員用就業規則がないという会社もあります。
この点について解説したいと思います。
(1)賃金規程について
賃金規程は、就業規則を構成する一部分です。就業規則の中に賃金に関する項目を記載するか、それとも、賃金に関する項目については賃金規程を作り、就業規則と賃金規程の2本立てにするかは、企業の自由な判断です。
そのため、就業規則に賃金に関する項目が記載されていれば、別途、賃金規程を作る必要はありません。
一方、就業規則に賃金に関する項目が記載されていない場合は、労働基準法上、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」は、就業規則に必ず記載しなければならないことになっていますので、賃金規程を作らなければ、労働基準法違反になってしまいます(労働基準法第89条2号 ※1)。
(2)パート社員用就業規則について
常時10人以上の従業員を使用する事業場では、その全従業員について、適用される就業規則を作成することが法律上の義務です。
例えば、就業規則で、「この就業規則は正社員に適用する。」と定めた場合、パート社員用就業規則がなければパート社員に適用される就業規則がなくなってしまいます。そのようなケースでは、パート社員用就業規則を作成して届け出なければ、労働基準法違反になります。
なお、パート・アルバイト用の就業規則の重要ポイントについて以下の記事で解説していますのでご参照ください。
(3)テレワーク就業規則がない場合
コロナ禍では政府の要請を受けて多くの企業でテレワークが行われました。
従業員にテレワークを認める際は、テレワーク就業規則を作成することが通常です。テレワーク就業規則がなければ、テレワーク中の労働時間の管理方法や、テレワークに伴う費用負担について明確性を欠く事態になりかねません。
ただし、会社と従業員の合意でテレワークが行われる限りにおいては、テレワーク就業規則がなくても、それが法令違反ということにはなりません。
これに対し、会社が感染防止などの目的で従業員の個別の同意を得ることなく、会社からテレワークを命じる場合は、多くの会社で就業規則の変更が必須となります。
これは、多くの会社において雇用契約書で就業場所が会社であることが明記されており、これを従業員の個別の同意を得ずに変更するためには、就業規則の変更が必要になるからです(労働契約法第9条 ※2)。
また、厚生労働省の「テレワークガイドライン」にも以下のように記載されています。
「労働契約や就業規則において定められている勤務場所や業務遂行方法の 範囲を超えて使用者が労働者にテレワークを行わせる場合には、労働者本人 の合意を得た上での労働契約の変更が必要であること(労働者本人の合意を 得ずに労働条件の変更を行う場合には、労働者の受ける不利益の程度等に照 らして合理的なものと認められる就業規則の変更及び周知によることが必 要であること)に留意する必要がある(労働契約法(平成19年法律第128 号)第8条~第11条)。」
テレワークガイドラインをはじめリーフレットなどについては、厚生労働省の以下のページをご参照ください。
テレワーク就業規則の作成については以下の記事で重要ポイントを解説していますのであわせてご参照ください。
4,作成したのに届出していない場合
常時10人以上の従業員を使用する事業場について就業規則を作成したけれども、労働基準監督署に届け出ていないという場合も、労働基準法違反になります。
労働基準法では、就業規則を作成することだけでなく、労働基準監督署に届け出ることも義務付けられているからです(労働基準法第89条 ※1)。
ただし、労働基準監督署に届け出ていない就業規則も、社内で周知されていれば、届出の不備については法令違反ではあるものの、就業規則としての効力を認めるとした裁判例が多くなっています(NTT・NTT西日本事件 京都地方裁判所判決平成13年3月30日等)。
5,従業員からよくある質問
就業規則がないということは、従業員から見た場合、会社のルールが不明であるということになり、従業員から信用を失うことになりかねません。
従業員の立場からよく出てくる質問等に以下のものがあります。
(1)就業規則をもらっていないのは違法か?
常時10人以上の従業員を使用する事業場については、会社は就業規則を作成して届け出るだけでなく、その就業規則を従業員に周知する義務があります(労働基準法第106条1項 ※1)。
就業規則の写し(コピー)を全従業員に配布することも周知の方法の1つではありますが、ほかにも周知方法としては「常時各作業場の見やすい場所へ掲示」などの方法もあります(労働基準法施行規則第52条の2 ※1)。
そのため、このような方法で就業規則を周知していれば、必ずしもコピーを配布しなくても違法とまではいえません。
過去の裁判例の中には、日本語が読めない英語講師に就業規則の筆写のみを認め、コピーや撮影を認めないことがパワハラであるかどうかが問題となった事案について、就業規則の謄写の権利を定めた法令はないことを指摘して、パワハラにはならないと判断したものがあります(東京地方裁判所判決平成30年11月2日)。
ただし、就業規則を従業員に守らせて、労務管理に生かすためには、就業規則の内容をしっかり従業員に理解させることが必要です。
就業規則のコピーを求められて、それを許可しないというのは違法でなくても、適切な対応とはいえないことに注意する必要があります。
(2)退職の手続
退職に関する事項は、就業規則に必ず定めなければならない項目です(労働基準法第89条3号 ※1。絶対的必要記載事項と呼ばれます)。
そのため、就業規則がない場合に、退職の手続をどうすればよいのかということについて従業員から質問を受けることがあります。
この点については、就業規則がない場合、民法上のルールに従い、正社員についてはいつでも退職の申し出が可能であり、会社が退職を承諾したとき、あるいは退職申し出から2週間後が経過したときに退職になると考えることになります(民法第627条1項 ※3)。
▶参考情報:退職についてのルールは、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(3)有給休暇の取得について
休暇についても、就業規則に必ず定めなければならない項目です(労働基準法第89条1号 ※1)。
ただし、法律上の有給休暇を与えることは、企業の義務であり、就業規則がない場合もこのことは同じです(労働基準法第39条 ※1)。
通常は有給休暇について、何日前に申請するべきかといった有給休暇申請手続きを就業規則で定めますが、就業規則がない場合、前日までに申請されれば、会社は有給休暇を与えなければならないことが原則となります。
▶参考情報:有給休暇の基本的なルールについては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(4)退職金について
会社は退職金を支給しないことも可能ですが、退職金について規定を設ける場合は就業規則に必ず定めなければならないとされています(労働基準法第89条3の2号 ※1。相対的必要記載事項といいます)。
就業規則がない場合に従業員から退職金について質問をうけることがありますが、会社で退職金を支払う慣行がなければ、退職金の支払いの義務があるわけではありません。
▶参考情報:退職金制度についての解説は、以下の記事を参考にしてください。
(5)時差出勤について
始業及び終業の時刻も、就業規則に必ず定めなければならない項目です(労働基準法第89条1号 ※1)。
就業規則がない場合、時差出勤が可能かどうかについて、従業員から質問を受けることがあります。
これについて、従業員の希望を認めるかどうかは、会社の判断であり、必ず認めなければならないわけではありません。
(6)法定休日について
休日には法定休日と法外休日があります。
労働基準法第35条(※1)で「毎週少くとも一回の休日」または「四週間を通じ四日以上の休日」を与えることが義務付けられており、この休日を法定休日といいます。
週休2日制の場合は、法定休日のほかにもう1日休日があることになりますが、これは法定休日ではない休日という意味で「法外休日」と呼ばれます。
法定休日に従業員を就業させた場合は、休日割増賃金(35%以上)の対象になるのに対し、法外休日に従業員を就業させた場合は時間外割増賃金(25%以上)の対象になるという違いがあります。
そのため、週休2日制の場合、就業規則で法定休日をどちらの日にするかを定めておくことが望ましいです。就業規則がない場合は、この点が明確でないため、休日に従業員を就業させた場合に、休日割増賃金(35%以上)の対象になるのか、時間外割増賃金(25%以上)の対象になるのかが不明確になってしまうという問題があります。
▶参考情報:法定休日や割増賃金について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。
未払い残業代請求の裁判例の中には、土日休みの週休2日制の会社において、社会慣行を考慮して、日曜日を法定休日として割増賃金を算出したものがあります(東京地方裁判所判決平成24年1月11日)。
6,就業規則がない会社が就業規則を作る方法
就業規則に定めるべき項目は膨大です。また、正社員用の就業規則だけでなく、パート社員用の就業規則等、非正社員用の就業規則も場合によっては必要になることは前述したとおりです。
そのため、現在就業規則がない会社が、一気に問題を解決しようとしても、やるべきことが多くなりすぎるため、1つ1つ解決していかざるを得ないでしょう。
まずは、正社員用の就業規則を作ることからはじめていくとよいです。
(1)始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日を決める
正社員用の就業規則を作る際にまず最初に決めるべき点は、「始業時刻」「終業時刻」「休憩時間」などの労働時間、そして「休日」です。これらの点はどれも、就業規則に必ず記載しなければならない項目です。
これらの項目は自由に決めることができるわけではなく、重要なルールが存在します。それは、所定労働時間は1日8時間、週40時間を超えてはならないというルールです(労働基準法第32条 ※1)。
所定労働時間というのは、始業時刻から終業時刻までの時間のうち、休憩時間を除いた時間です。これが、1日8時間、週40時間を超えないように決めるということからまず始めてください。
正社員用の雇用契約書を作成している場合は、そこに記載があるはずです。
例えば、始業時刻が午前9時、終業時刻が午後6時、休憩時間1時間の場合、所定労働時間は8時間となり、1日8時間を超えてはならないというルールに沿っています。
そして、土日は休日と定めれば、月曜日から金曜日まで5日間出勤しても、週で合計40時間です。そのため、所定労働時間が週40時間を超えてはならないというルールも満たしています。
一方、例えば、始業時刻が午前9時、終業時刻が午後6時、休憩時間1時間でも、休日が月に6日と定められている場合、休日が1日しかない週が発生します。そして、その週は所定労働時間が48時間になってしまいます。これは、所定労働時間が週40時間を超えてはならないというルールに反しており、違法です。
このように、労働基準法のルールに沿う形で、始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日を決めるところから、まず、始めてください。
労働時間や休憩時間に関する労働基準法上のルールについては以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
(2)ひな形を入手する
始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日を決めたら、就業規則のひな形をもとに、自社の労務環境に合致するように修正を加えて、オリジナルの就業規則案に仕上げていくことが必要です。
厚生労働省が公表しているモデル就業規則をひな形として使用し、これをベースに修正を加えるという選択肢もあります。
ただ、厚生労働省のモデル就業規則は、割増賃金の率が法律上必要な割増率よりも高く設定されていたり、試用期間の短縮はできるが延長はできない内容になっていること、法律上は必ずしも与える必要のない休暇に関する規定が設けられていることなど、注意が必要な点も多いです。
厚生労働省のモデル就業規則については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
そのため、モデル就業規則を使うのではなく、中小企業の労務管理の実務に精通した弁護士や社会保険労務士からひな形の提供を受けることが望ましいです。
(3)オリジナルの案に仕上げる
ひな形については修正を加え、追記すべき点は追記して、自社の労務環境にあったものに作り上げる必要があります。
ひな形を修正する際は、「修正してよい部分」と「修正してはいけない部分」があることに注意が必要です。
就業規則の中には、法律上義務付けられていることを記載した部分(例えば有給休暇や労災補償、解雇予告などの規定)も多く、その部分についてまで修正を加えてしまうと、違法な内容の就業規則になりかねないので注意してください。
実際に修正を加えていく作業は、中小企業の労務管理の実務に精通した弁護士や社会保険労務士のサポートを受けながら行うべきでしょう。
就業規則の作成や記載事項、法律上義務付けられていること等については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
ひな形をそのまま安易に使うことは、自社の労務環境と一致しない就業規則を作ることになり、就業規則が形骸化したり、正しい労務管理ができない原因になりますので絶対に避けるべきです。
(4)案ができたら過半数代表の意見を聴取する
就業規則については従業員の過半数代表からの意見聴取が義務付けられています(労働基準法第90条 ※1)。
過半数代表からの意見聴取結果も踏まえて、従業員と話し合いを持ち、場合によっては就業規則案を過半数代表からの意見を踏まえて修正することも検討しましょう。
就業規則の意見聴取に関する注意点を以下の記事で記載していますので、参考にご覧ください。
(5)労働基準監督署に届け出て、社内で周知します
意見聴取が終わった後に、就業規則を「労働基準監督署」に届け出て、社内で周知することが必要です(労働基準法第106条 ※1)。
就業規則の届出については以下をご参照ください。
7,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます」

ここまで、就業規則のない場合の問題点、従業員からよくある質問などについて解説し、最後に就業規則のない会社が就業規則の整備を進める方法についてご紹介しました。
実際に就業規則の整備を進めていくためには、弁護士や社会保険労務士への相談が必要です。
咲くやこの花法律事務所では、企業の労務管理に精通した弁護士が就業規則作成のご相談に対応します。咲くやこの花法律事務所では、最近の裁判例の分析や過去の裁判対応の経験、最新の法改正の内容を踏まえたオリジナルの就業規則のひな形を準備しています。
それをベースに会社独自の点について、弁護士からヒアリングを行い、自社にマッチした就業規則に仕上げていくことが可能です。
現在、就業規則が十分に整備されておらず、お困りの企業様はぜひご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士へのご相談料
30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
この記事の本文中で紹介した参考情報
※1:労働基準法第32条・第35条・第39条・第52条・第89条・第90条・第106条の参考として「労働基準法」の条文はこちら
※2:労働契約法第9条の参考として「労働契約法」の条文はこちら
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2025年1月12日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」就業規則に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587












































