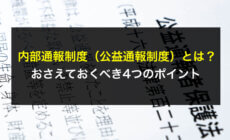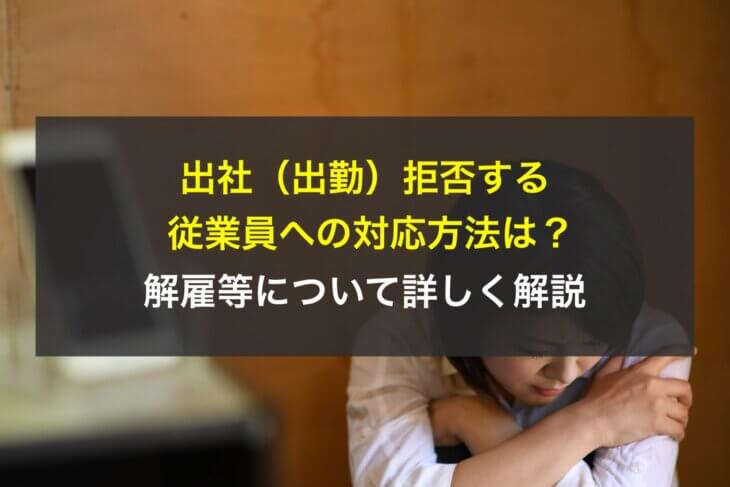
こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
出社を拒否する従業員への対応に悩んでいませんか?
出社拒否や出勤拒否には以下のようにさまざまなケースがあります。
- うつ症状など体調不良を理由とする出社拒否
- ハラスメントの訴えなど職場環境を理由とする出社拒否
- 新型コロナウィルス感染症の危険などを理由とする出社拒否
- テレワーク希望を理由とする従業員の出社拒否
過去の判例では、「雇用契約によって定められた勤務時間および勤務場所に確実に出勤して労務の提供をすることは、従業員の最も基本的な義務であり、…」(東京地方裁判所昭和51年3月24日判決)として、出社は従業員の基本的な義務であるとしています。
しかし、一方で、過去には、精神疾患が疑われる従業員の不出社を無断欠勤として扱い解雇したことが、不当解雇にあたるとして、会社に約1600万円もの支払を命じたケースも存在します(平成23年 1月26日東京高等裁判所判決。日本ヒューレッドパッカード事件)。
今回は、過去の判例も踏まえて、出社(出勤)拒否の場面における企業の対応方法について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在、自社で抱えている出社しない従業員のトラブルについて、リスクを回避しながら問題解決に向けて動き出すことができるようになります。
▶この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「出社拒否する従業員への対応方法を弁護士が解説」の動画でも詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
▶出社拒否の従業員の対応に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,出社拒否の理由に応じた対応が必要
出社拒否についてはその理由によって会社で取るべき対応がことなります。
この記事では以下の4つのケースについて、会社の正しい対応をご説明します。
- (1)うつ症状など体調不良を理由とする出社拒否の場合
- (2)病気からの復帰時のトラブルを契機とする出社拒否の場合
- (3)パワハラやセクハラの訴えなど職場環境を理由とする出社拒否の場合
- (4)新型コロナウィルス感染症の危険などを理由とする出社拒否の場合
2,うつ症状など体調不良を理由とする出社拒否の場合の対応
まず、うつ症状などの体調不良を理由に仕事を休みたいという申し出があった場合の対応について解説します。
うつ症状などの体調不良を理由に仕事を休みたいという申し出があった場合、会社としては原則としてこれに応じる義務があります。
引継ぎの必要や多忙を理由に休ませるのを遅らせることは、安全配慮義務違反に該当する可能性が高いので注意してください(福岡高等裁判所平成28年10月14日判決等)。
(1)診断書の提出を求める
ただし、会社としては従業員に対して診断書の提出を求めて、従業員が真実、体調不良なのかどうかについて確認することが可能です。
病名だけではなく、「就業が可能かどうか」ということも重要なポイントですので、就業の可否を記載した診断書の提出を従業員に求めることが必要になります。
そして、診断書で長期的な自宅療養が必要とされている場合は、従業員に対して休職を命じることが正しい対応です。
なお、万が一、診断書の提出を求めてもこれに応じない場合は、出社拒否を認める必要はありません。
説得しても不合理な理由で出社せず、診断書の提出にも応じない場合は、従業員を解雇することも含めて検討する必要があります。
この場合の具体的な対応手順は、「6,出勤を拒否する従業員に対する正しい対応手順」を参照してください。
▶参考情報:従業員に精神疾患の兆候が出たときの会社の正しい対応については、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。
古い判例ですが、急性胃腸炎により入院した後、会社の再三の指示にもかかわらず診断書を提出することなく一か月以上欠勤した労働者に対する懲戒解雇を有効とした事例として、昭和63年9月26日大阪地方裁判所判決(安威川生コンクリート事件)があります。
3,病気からの復帰時のトラブルを契機とする出社拒否の場合
病気で休んでいた従業員が体調が改善して就労できるようになったとの診断書を提出した後に、復職の条件をめぐって会社とトラブルになり、出社拒否に至るケースも少なくありません。
以下ではその場合の対応方法についてご説明します。
(1)復職にあたって会社としての配慮義務を果たしているかを確認
従業員が病気から復帰する場面では、会社が、病気の内容に応じて復職にあたり一定の配慮をする義務があります。
例えば、復職にあたり「復職後3か月程度の間、業務量、業務時間を半分程度に減らして配慮し、4か月目以降も当分の間残業なしとするという程度の配慮」をすれば休職前と同程度に働けることが見込まれる場合は、企業はそのような配慮をして、一定期間就業時間を減らしたうえで復職させることが求められます。
そのため、従業員の主治医に対して、復職にあたって、従業員の就業時間を減らすなどなんらかの配慮が必要かどうかを確認する必要があります。
そして、配慮が必要な場合は、その手立てを講じたうえで従業員を復帰させることが必要です。
(2)必要な配慮をしても出勤を拒否する場合の対応
一方で上記のような配慮をしても、出勤を拒否する場合は、会社として必要な配慮はしており、出社拒否は認められないことを従業員に説明して、説得することが正しい対応です。
従業員が説得に応じず、出社拒否を続ける場合は、従業員を解雇することも検討する必要があります。
この場合の具体的な対応手順は、「6,出勤を拒否する従業員に対する正しい対応手順」を参照してください。
なお、病気からの復帰条件をめぐる出社拒否について、会社が行った解雇について判断した判例として、以下の2つのケースが参考になります。
1,復職後の配属先が希望にあわず出社拒否に至ったケースの判例【東京地方裁判所平成28年1月26日判決(三菱重工事件)】
事案の概要:
三菱重工業株式会社の愛知県内の事業所に勤務していた従業員が、自律神経失調症や適応障害で休職後に、同居の家族による支援が不可欠だと主張して、家族のいる埼玉県内から通勤可能な事業所での復職を求めて、出勤を拒否したため、解雇した事案です。
裁判所の判断:
裁判所は、「業務内容や勤務時間等の就業上の配慮はともかくとして,原告の食事,洗濯,金銭管理等の生活全般の支援をどうするかは本来的に家族内部で検討・解決すべき課題である。」として、出社拒否は不当であると判断し、解雇を有効と認めました。
2,復職に伴う面談に応じず解雇したケースの判例【大阪地方裁判所平成20年3月7日判決(ハイクリップス事件)】
事案の概要:
治験施設支援などを事業とする会社が、うつ症状により欠勤していた従業員から就労可能との診断書が提出されたため、出勤して面談に応じることを求めたのに対し、面談に応じなかったことなどを理由に懲戒解雇した事案です。
本件では、従業員が付添人の付添を許可することが会社との面談に応じる条件になるなどと主張したのに対し、会社が付添等を拒否し、面談がされなかったという経緯がありました。
裁判所の判断:
裁判所は、「度重なる業務上の正当な指示命令にも従わず,出勤して業務に従事する見込みが立たなかったこと」などをあげて、「原告を懲戒解雇に付したことは,やむを得ない」として解雇の正当性を認めました。
なお、会社からの出勤して面談に応じるようにという業務命令に対して、従業員が付添人の同席の許可を求めた点について、裁判所は「使用者から命じられた業務上の面談について,付添人が同席しない限りこれを拒否する合理的理由は見いだしがたい」としています。
病気で休んでいた従業員の復職の場面は、復職時の条件などをめぐって、トラブルになりやすい場面の1つです。
注意点を以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。
4,パワハラやセクハラの訴えなど職場環境を理由とする出社拒否の場合の対応
パワハラやセクハラなど、職場でのハラスメントを理由として、従業員が出勤を拒否しているケースでは、会社はまずハラスメントの有無を調査し、ハラスメントがある場合は、その問題を解消することが求められます。
▶参考例:
名古屋地方裁判所平成16年4月27日判決は、セクハラに関する事案ですが「セクハラの事実が存在し,職場での就労に性的な危険性を伴うと客観的に判断される場合には,労働者は,同職場での就労を拒絶することができ,これにつき懲戒解雇等の理由となることもないと解するのが相当である」としています。
(1)会社が必要な対策をとった後は出社拒否は認められない
一方で、会社が必要なハラスメント対策をとった後は、従業員の出社拒否は認められません。
そのため、必要な対策をとった後も、従業員が出勤を拒否する場合は、出社拒否は認められないことを従業員に説明して、説得することが必要です。
従業員が合理的な理由なく説得に応じず、出社拒否を続ける場合は、従業員を懲戒し、あるいは解雇することも検討する必要があります。この場合の具体的な対応手順は、「6,出勤を拒否する従業員に対する正しい対応手順」を参照してください。
前述の名古屋地方裁判所平成16年4月27日も、「使用者が,当該セクハラ被害に相応する回復措置を取っていると評価できる場合には,特段の事情がない限り,労働者は,同被害を理由に,性的危険性の存在を主張することができない」としました。
この判例の事案は、会社主催の送別会で酩酊した女性従業員を男性社員が介抱したことについて、後日、女性従業員がセクハラであると主張して出勤の拒否に至り、会社が出社拒否を理由に解雇したというものです。
裁判所は、セクハラと評価できるかどうかも極めて疑問であり、会社が社内で注意喚起を行うなどの対応をした後も、女性従業員が出社拒否を続けたことは解雇理由に該当するとして、解雇を正当と判断しています。
▶参考情報:なお、ハラスメント発生時に企業がとるべき対応については、以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
5,新型コロナウィルス感染症の危険などを理由とする出社拒否の場合の対応
新型コロナウィルス感染症の危険などを理由とする出社拒否については、緊急事態宣言期間中とそれ以外の期間にわけて考えることが必要です。
(1)緊急事態宣言期間中の出社拒否と参考判例
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言の期間中は、会社としてもできる限りテレワークによる対応をすることが求められています。
そのため、テレワークが可能な業務について、従業員が出勤を拒否しているからといって、懲戒処分や解雇をすることはできないと考えるべきです。
また、テレワークによる対応ができず出社の必要性が高い業種についても、緊急事態宣言の期間中は、従業員が出勤を拒否しているからといって、懲戒処分や解雇をすることはできないと考えるべきです。
日本放送協会事件(東京地方裁判所平成27年11月16日判決)の判決
この点については、福島第一原発事故の際の日本放送協会事件(東京地方裁判所平成27年11月16日判決)の判決が参考になります。
事案の概要:
この事例はNHKが、フランス人のラジオ放送担当者が、原発事故やその後のフランス大使館による避難勧告を受けて、業務開始の約2時間前に、業務を放棄して、国外に避難したことなどを理由に、この担当者との契約を解除した事案です。
裁判所の判断:
裁判所は、この事件で、「東日本大震災及び福島第一原発事故発生当時の状況に照らすと,生命・身体の安全を危惧して国外等への避難を決断した者について,結果的に危険が生じなかったとしても,その態度を無責任であるとして非難することなど到底できない。」としてNHKによる契約解除を無効と判断しました。
裁判で、NHKは、「東日本大震災が発生したような緊急時における公共放送の役割は大きく、長年、NHKの業務を続け、その重要性を認識しているにもかかわらず、突然職務を放棄したのは無責任である」と主張しましたが、裁判所は、「国際放送の重要性に思いを致し不安の中で職務を全うした者は大きな賞賛をもって報いられるべきであるが,そうした職務に対する過度の忠誠を契約上義務付けることはできないというべきである。」としています。
この判例からは、仮に、医療機関のように、コロナ禍における社会的使命として、従業員の出社を促して事業を継続する必要性が極めて高い業種であっても、出勤を拒否する従業員に対して懲戒処分や解雇を科すことはできないと考えなければなりません。
出勤を拒否する従業員に対しては、有給休暇消化後は無給とする一方で、出社してくれる従業員に対して、慰労金を出すなどして、バランスをとることが現実的な路線といえるでしょう。
(2)緊急事態宣言期間終了後の出社拒否の対応について
緊急事態宣言期間終了後の出社拒否については、宣言期間中とは事情が異なります。
ここまで述べてきた通り、裁判所は、従業員の出勤は従業員の最も基本的な義務であるとしており、会社が出社に必要な配慮をしたうえでそれでも出社を拒否するケースでは解雇も正当としています。
この点を踏まえると、緊急事態宣言の期間が終わった後に、会社が可能な限りの感染防止に必要な配慮をしている場合は、社内で感染者が発生したなどの具体的な感染の危険性が生じた場合や、本人の持病や高齢により感染症り患によるリスクが高い場合を除き、出社拒否は許されないと考えることができます。
社会的にテレワークが推奨されていますが、テレワークを認めるかどうかは会社の判断であり、感染の危険がゼロにならないことを理由とする出社拒否を認める必要はありません。
会社からの説得にも応じずに出社拒否を続ける場合は、懲戒処分や解雇も許容されると考えられます。
なお、新型コロナウィルス感染症への感染予防のために企業がとるべき措置については以下を参照してください。
6,出勤を拒否する従業員に対する正しい対応手順は?
従業員が正当な理由なく出社に応じない場合の基本的な対応手順は以下の通りです。
- (1)まずは説得の機会を持つ
- (2)説得に応じないときは明確に出社命令を出す
- (3)出社命令に従わないときは懲戒処分を検討
- (4)懲戒処分をしても出社に応じないときは退職勧奨を検討
- (5)やむを得ないときは解雇を検討
それぞれについて順番に詳しく見ていきましょう。
(1)まずは説得の機会を持つ
正当な理由なく出社に応じない従業員に対しても、まずは話し合いの機会を持つことが必要です。
例えば、病気休職をしていた従業員が復帰する場面では、復職にあたり会社として必要な配慮をすることを説明し、出社に向けて説得することが必要です。
また、職場内でパワハラの問題があった場合には、ハラスメントの調査と加害者の懲戒処分を行い、適切なパワハラ防止措置を講じたうえで、出社に向けて説得することが必要です。
コロナウィルス感染症の危険などを理由に出社を拒否しているケースでは、適切な感染防止措置を講じたうえで、出社に向けて説得することが必要です。
▶参考例:
業務命令違反を理由とする解雇に関する裁判例の中には、「まずは本件業務命令の趣旨を説明するなどして、原告の誤りを指摘・指導し、その理解が得られるよう努めるべきであったといえる。」として、十分な説明をしないまま従業員を解雇した会社を敗訴させているものがあります(平成27年10月28日東京地方裁判所判決)。
この点は、出社の命令にもあてはまります。
会社として出社ができる環境を整えたことを従業員に説明し、従業員の理解を得る努力をすることが重要です。
(2)説得に応じないときは明確に出社命令を出す
それでも従わない場合は、文書やメールでの記録が残る形で、明確に出社を指示する命令をだすことが必要です。口頭での指示ではなく、文書やメールで命令を出すことで、記録に残る形にすることが重要です。
(3)出社命令に従わないときは懲戒処分を検討
従業員が出社命令にも従わないときは、懲戒処分を検討することになります。
一般的には、懲戒処分は、軽い順から、戒告またはけん責処分、減給、出勤停止処分、降格処分という順番に重くなります。まずは、戒告やけん責といった軽い懲戒処分により、反省と態度の改善を求め、それでも態度を改めないときは、より重い、減給処分を行う必要があります。
▶参考情報:懲戒処分の種類、判断基準、進め方などについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
(4)懲戒処分をしても出社に応じないときは退職勧奨を検討
懲戒処分をしても、出社に応じないときは、退職勧奨を検討することになります。
解雇により対応することは、不当解雇として訴えられるリスクがありますので、解雇は最後の手段と考え、まずは、合意による退職を説得する退職勧奨を行うべきです。
「退職勧奨」とは、従業員を一方的にやめさせるのではなく、退職に向けて説得し、従業員の意思に基づいて退職してもらうことをいいます。
▶参考情報:退職勧奨については以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
また、問題社員トラブルを解雇ではなく、退職勧奨で円満に解決するための具体的な手順がわかるおすすめ書籍(著者:弁護士西川暢春)も以下でご紹介しておきますので、こちらも参考にご覧ください。書籍の内容やあらすじ、目次紹介、読者の声、Amazonや楽天ブックスでの購入方法などをご案内しています。
(5)やむを得ないときは解雇を検討
退職勧奨にも応じず、他に手段がないときは、解雇を検討することになります。
▶参考情報:解雇の具体的な手順については以下で解説していますので参照してください。
7,出社しない社員の解雇は認められる?
企業側に特に落ち度がないのに出社しない社員に対しては解雇することも法的に認められます。ただし、解雇に至るまでに適切な手順を踏むことが必要です。
(1)出勤命令と懲戒処分を経る
出社しない場合もいきなり解雇するのではなく、まずは、書面で出勤を命じ、応じない場合は、正当な理由なく出勤しないことについて懲戒処分をするプロセスを経たうえで、初めて解雇に進むべきです。
(2)在宅勤務している場合は許可を取り消す
在宅勤務している従業員については、在宅勤務許可を取り消したうえで、書面で出勤を命じ、それでも出勤しない場合は懲戒処分をするプロセスを経たうえで、初めて解雇に進むべきです。在宅勤務許可を取り消すことができるかは、在宅勤務規程で許可の取り消しについてどのように定められているかを確認する必要があります。
(3)体調不良だとして診断書が提出された場合
体調不良だとして診断書が提出された場合は、主治医と面談したり、主治医に対して医療照会を行い、長期間就業ができない状態かどうかを確認することが必要です。長期間就業できない状態である場合、私傷病休職制度がある場合は私傷病休職を認める必要があり、休職を経ないで解雇することは原則として認められません。
▶参考情報:私傷病休職制度については以下をご参照ください。
なお、いずれの場面でも適切なプロセスを経なければ、解雇トラブルになった場合に、不当解雇であるとして企業側が敗訴するリスクがあります。必ず弁護士に相談したうえで対応してください。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。
▶参考情報:また、従業員がパワハラやメンタルヘルス不調を主張して出社しない事例における解雇の可否の判断については、この記事の著者 西川 暢春が、以下の動画で解説していますので、あわせてご参照ください。
8,出社拒否する従業員の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら
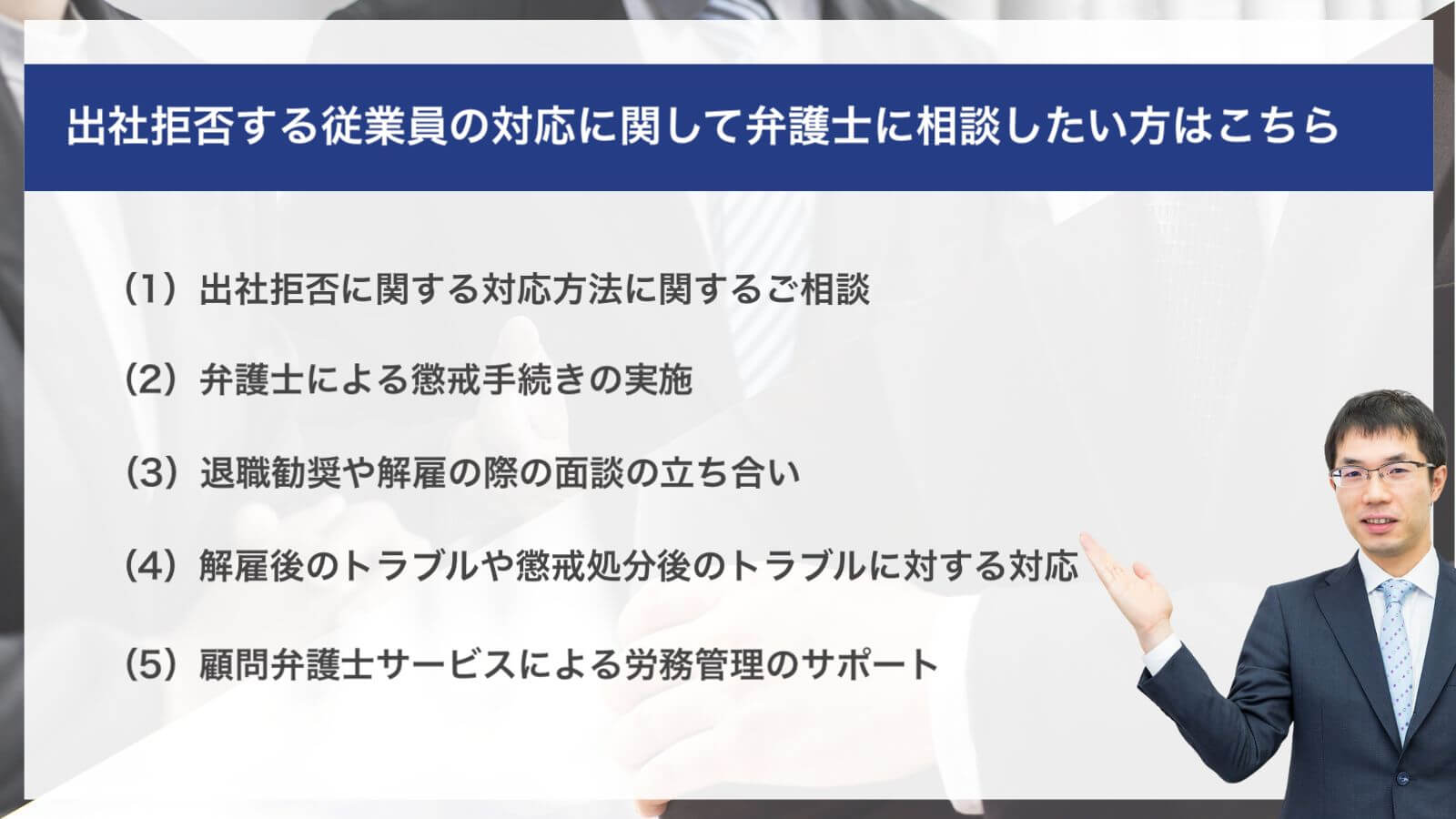
最後に、出社を拒否する従業員への対応方法についてお困りの企業の方に向けて、咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容をご説明したいと思います。
サポート内容は以下の通りです。
- (1)出社拒否に関する対応方法に関するご相談
- (2)弁護士による懲戒手続きの実施
- (3)退職勧奨や解雇の際の面談の立ち合い
- (4)解雇後のトラブルや懲戒処分後のトラブルに対する対応
- (5)顧問弁護士サービスによる労務管理のサポート
以下で順番にご説明します。
(1)出社拒否に関する対応方法に関するご相談
咲くやこの花法律事務所には、出社命令に従わない社員など、問題社員の指導方法や問題社員への対応方法に精通した弁護士が多数在籍しています。
ご相談の際は、まず個別の事情を詳細にヒアリングしたうえで、事案ごとに、過去の事務所での対応経験も踏まえて、出社命令、指導や懲戒、あるいは解雇など、実効性のある対応策をご提案します。
あわせて、職場として配慮するべき点があればその点についても解決策をご提案します。
出社を拒否する従業員の具体的な対応方法にお悩みの企業経営者、管理者の方はご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士による相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
なお、問題社員対応全般については以下の記事でご説明していますのであわせてご参照ください。
(2)弁護士による懲戒処分手続きの実施
咲くやこの花法律事務所では、問題社員に対する懲戒処分手続きについてもサポートを行っています。
正当な理由のない出社拒否に対しても、解雇を最初から検討するのではなく、まずは懲戒処分を行い、それでも改まらない場合に、解雇を検討する必要があります。
咲くやこの花法律事務所では、懲戒処分の種類の選択や、懲戒するべき事情があるかどうかの検討、懲戒処分通知書の作成などについて弁護士にご相談いただくことが可能です。
また、懲戒処分の言い渡しの場面では、従業員がその場で不満を述べたり反論をしてきたりすることがあります。
無用なトラブルを防止するためには、懲戒処分の言い渡しの場に専門家である弁護士も同席することが効果的です。
咲くやこの花法律事務所では、労務トラブルに強い弁護士が懲戒処分の言い渡しの場に同席し、会社側の立場で適切な応答をするなどして、懲戒処分の言い渡しをサポートしています。
懲戒処分の言い渡しに不安があるときは、咲くやこの花法律事務所のサポートサービスをご利用ください。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士によるサポート費用
●初回相談料:30分5000円+税
●面談費用:時間や面談場所への距離に応じて、10万円~20万円+税程度
※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。
(3)退職勧奨や解雇の際の面談の立ち合い
咲くやこの花法律事務所では、企業のご要望に応じて、退職勧奨や解雇の際の面談への立ち合いも行っております。
退職勧奨や解雇の問題に精通した弁護士が立ち会うことで自信をもって、退職勧奨あるいは解雇を進めることが可能になります。
また、解雇の場面で重要な書面になる解雇理由書や解雇予告通知書の作成と発送についてもご依頼を受けています。
解雇の問題に精通した弁護士が書面作成に携わることによって、万が一、裁判等に発展した時のことも見越した書面作成が可能になります。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士によるサポート費用
●初回相談料:30分5000円+税
●面談費用:時間や面談場所への距離に応じて、10万円~20万円+税程度
※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。
(4)解雇後のトラブルや懲戒処分後のトラブルに対する対応
咲くやこの花法律事務所では、解雇した従業員あるいは懲戒処分をした従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も常時承っています。
解雇した従業員が不当解雇であると主張したり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。
また、懲戒処分をした従業員が不当な懲戒解雇であると主張して、懲戒処分の撤回を求めてくるような場面でも、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。
懲戒処分後のトラブルや解雇後のトラブルでお困りの方は、早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士による対応費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:20万円~30万円+税程度~
●裁判時の対応着手金:45万円+税程度~
(5)顧問弁護士サービスによる労務管理のサポート
咲くやこの花法律事務所では、問題社員への対応にお困りの企業を継続的にサポートするために、顧問弁護士サービスによるサポートも行っています。
顧問弁護士サービスによるサポートのメリット
・指導方法や従業員対応についての疑問点をその都度電話やメールで弁護士に相談できる
・業務命令の出し方や、懲戒処分についてもいつでも弁護士に電話で相談できる
問題社員の指導は継続的な取り組みが必要であり、弁護士にいつでも相談できる体制を作ることで、正しい対応を進めていくことが可能です。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用
●スタンダードプラン(月額顧問料5万円/相談時間制限なし)
※契約前に担当弁護士との無料面談で相性をご確認いただくことができます
(電話・テレビ電話・Web会議【ZoomやSkype】でのご説明 or 来所面談)
※来所していただかなくても、電話あるいはテレビ電話でお申込みいただけます。
顧問弁護士サービスご検討の方のための弁護士との無料面談のご案内やお申込みについて、また、顧問弁護士プランの詳細や顧問弁護士サービスの実績については以下のページをご参照ください。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの方はこちら
(6)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2026年2月19日
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」出社拒否など問題社員対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587