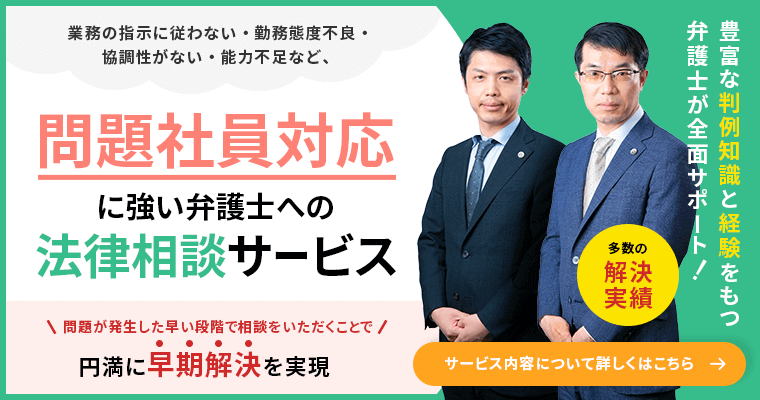こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
業務命令に従わない従業員への対応に困っていませんか?
会社の正当な指示に従わず、無視や拒否を続ける従業員を放置すると、他の従業員に示しがつきません。しんどい仕事、やりたくない仕事を拒否する従業員が他にも出てきて、会社の経営が成り立たなくなります。会社の規律を維持するためにも、正当な業務命令に従わない従業員に対しては、懲戒処分や懲戒解雇などしかるべき対応が必要です。
しかし、一方で、業務命令違反を理由とする解雇については、解雇後に会社が従業員から訴えられて、裁判所で不当解雇と判断されて多額の金銭の支払いを命じられているケースも存在します。
判例1:平成30年4月13日東京地方裁判所判決
業務命令違反を理由とする解雇が不当解雇とされ、会社が約3700万円の支払を命じられた事例
判例2:平成28年2月4日東京地方裁判所判決
業務命令違反を理由とする解雇が不当解雇とされ、会社が約2000万円の支払を命じられた事例
この記事では、業務命令違反を理由とする解雇や懲戒処分について、会社がおさえておくべき重要な注意点5つをご説明します。この記事を最後まで読めば、現在、業務命令に違反する従業員の対応でお困りの事業者の方は、自信をもって問題解決に向けて正しい対応を進めることができるはずです。
従業員が業務命令に従わない場合にも正しい手順で対応しなければ、パワハラであるとか不当解雇であるなどと言われて、逆に会社が訴えられることになりかねません。
弁護士に相談せずに自己流で対応してしまうと、対応を誤って、後日大きな不利益につながるケースが少なくありません。業務命令に従わない従業員への対応は、解雇や懲戒処分をする前に、必ず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性や弁護士費用などについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
▶参考情報:従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関する解決実績は以下をご参照ください。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「業務命令違反を繰り返す従業員の解雇は可能?」の動画でも詳しく解説しています。
▶業務命令違反に関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,業務命令違反とは?
業務命令違反とは、従業員が会社や上司の指示に対して、正当な理由なく従わないことをいいます。業務命令違反は一般的に就業規則で解雇事由として定められています。
▶参考情報:例えば、厚生労働省のモデル就業規則では、第12章第66条2項で「正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。」を懲戒解雇事由として定めています。
労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停 止とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、〇回にわた って注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
(以下略)
2,業務命令違反で解雇する場合の5つの重要な注意点
冒頭でご説明した通り、業務命令違反を理由とする解雇が不当解雇と判断されている事例も多く存在するため、解雇には注意が必要です。
以下でご説明する重要な5つの注意点をおさえておいてください。
(1)業務命令が文書で出されているか
注意点の1つ目は、「業務命令に違反したことについて証拠が残っているか」という点です。
従業員を解雇した場合、会社は後日、その従業員から不当解雇であるとして訴えられることがあります。その場合、会社は解雇の正当性を裁判所で証拠によって説明することができなければ、不当解雇であるとして敗訴してしまいます。
業務命令違反を理由に従業員を解雇した場合は、裁判になれば、まずは「会社が業務命令を出したこと」を証拠に基づいて証明することが要求されます。
業務命令違反での解雇が正当かどうかを判断するうえで、会社が業務命令を出していたことは大前提の事実になるからです。
参考判例:
平成30年4月13日東京地方裁判所判決
例えば、冒頭でもご紹介した平成30年4月13日東京地方裁判所判決は、口頭や電話での業務命令に違反したことを理由に会社が従業員を懲戒解雇した事例です。
この事件では、業務命令が記録上残っていなかったため、 裁判所では「業務命令が存在したものとは認められない。」などとして、不当解雇であると判断され、会社が敗訴しています。
少なくとも、解雇を検討しなければならないような問題の大きい従業員については、業務命令は、文書やメールなど記録に残る形で行わなければならないことを重要な注意点としておさえておいてください。
業務命令は、業務命令であることが明確な形で行わなければならないことにも注意しておいてください。
例えば、「~をお願いできませんか?」というような書き方は、依頼あるいは相談であり、業務命令とはいえません。
(2)業務命令の拒否について正当な理由がないか
注意点の2つ目は、業務命令の拒否について正当な理由がある場合は、解雇や懲戒処分をしてはならないという点です。
参考判例:
平成28年2月4日東京地方裁判所判決
例えば、平成28年2月4日東京地方裁判所判決は、従業員が会社から担当を指示されていたプロジェクトについて、会社に無断で担当を降りる旨を述べたことなどの業務命令違反を理由に、従業員を解雇した事例です。
この事例では、裁判所は、従業員が月100時間近い残業をして体調不良を訴えていたことを指摘して、従業員が正当な業務負担軽減の要望を繰り返す中で行った担当を降りる旨の発言を捉えて、業務命令違反として解雇することは許されないと判断しています。
業務命令を拒否したことを理由に解雇や懲戒処分ができないケースの例
例えば、以下のようなケースでは業務命令の拒否について正当な理由が認められ、業務命令を拒否したことを理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。
- 過重労働や体調不良で業務を軽減するべき事情があるのに、軽減しないまま業務を命じている場合
- 職場にハラスメントの問題があり、業務に支障が生じているのに、ハラスメントについて適切な対応をしないまま、業務を命じている場合
- 妊娠中の女性従業員や、育児中の従業員等に対して、法律上、配慮が義務付けられている場面であるのに、必要な配慮をしないまま業務を命じている場合
- 残業代の不払いの問題があるのに、残業しなければできないような業務を命じている場合
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「業務命令に従わない社員!拒否は認められる?弁護士が解説」の動画でも、業務命令の拒否に正当な理由が認められる場合について詳しく解説しています。
(3)業務命令の趣旨を説明し理解を得る努力を十分行ったか
注意点の3つ目は、業務命令違反で解雇する前に「業務命令の趣旨を説明し理解を得る努力を十分行ったか」という点です。
参考判例:
平成27年10月28日東京地方裁判所判決
平成27年10月28日東京地方裁判所判決は、従業員が、「納得してない仕事は出来ないし,モチベーションが維持出来ません。」などと上司にメールをしたうえで、会社が指示した業務について十分な教育指導を受けていないことを理由に「お断りをしたく考えております。」「上司の指示に対して、反抗している訳ですから、会社さんからのどの様な評価も甘んじて受けいれるつもりでお伝えしています。」などと書いたメールを送ったという事例です。
会社は業務命令違反を理由にこの従業員(原告)を解雇しましたが、裁判所は、「まずは本件業務命令の趣旨を説明するなどして、原告の誤りを指摘・指導し、その理解が得られるよう努めるべきであったといえる。」「少なくとも文面上は、原告の本件業務命令を拒否する意向が強固で話し合う余地すらないものとは認められない。」などとして、会社が行った解雇を不当解雇と判断しています。
従業員が業務命令に従うことを拒否する場合でも、まず、従業員に対してその業務が必要な理由を説明し、理解させるための話し合いの機会をもつことが必要です。
(4)業務命令自体がパワハラになると判断される危険がないか
注意点の4つ目として、会社の業務命令自体が不合理であったり、あるいは業務命令自体がパワハラに該当するような場合は、解雇や懲戒は不当と判断されてしまいます。
必要性のない草むしりや丸刈りの業務命令は業務命令がパワハラである、ないしは不合理であるとされるケースの典型例です。このような業務命令に違反したからといって、従業員を解雇や懲戒の処分の対象とすることは違法です。
さらに、注意すべきものとして、以下のような事例があります。
参考判例:
平成24年10月3日東京地方裁判所立川支部判決
平成24年10月3日東京地方裁判所立川支部判決は、学校法人が、入学式や入試などの行事の際に、教員に対して、通学路に立つことを命じた事例について、肉体的負担と精神的苦痛を課してまで実施すべき理由に乏しい上、他の教員との均衡を欠いて集中的に特定の教員に割り当てた点を指摘して、業務命令は違法であるとして、学校法人に対して損害賠償を命じています。
このようにパワハラにまでは当たらなくても、裁判所で業務命令が不合理あるいは不当と判断されるケースがあります。このようなケースでは、業務命令違反を理由とする従業員の解雇あるいは懲戒処分も、不当な解雇あるいは不当な懲戒処分と判断されることになります。
業務命令の内容について、必要性や合理性を十分裁判所で説明できるかどうかについても事前に検証が必要です。
(5)懲戒処分が行われているか
注意点の5つ目は、業命令違反を理由に解雇する前に、必ず懲戒処分を行うべきであるという点です。
業務命令に従わないからといって従業員をいきなり解雇することは、不当解雇と判断される危険が高いです。まずは、戒告処分、けん責処分といったより軽い処分をしてから、それでも改まらない場合にはじめて解雇を検討するべきです。
参考判例:
平成28年7月20日東京地方裁判所判決
例えば、平成28年7月20日東京地方裁判所判決は、会社が土曜日勤務を命じたのに対しこれを拒否した契約社員を雇止めした事案です。
裁判所は、「正式に業務命令を発令し、これに違反した場合には、注意・指導を行い、ときには懲戒処分に処するなどの手続を検討するべき」とし、注意・指導や懲戒処分を経ずに雇止めした会社の対応を違法であると判断しています。
上記の事例とは逆に、業務命令違反に対してけん責処分をしても態度が改まらなかったことを理由に解雇を正当と認めた判例として、平成29年12月1日東京地方裁判所判決などがあります。
3,業務命令違反があった場合の対応
以下では従業員に重大な業務命令違反があった場合の具体的な対応についてご説明します。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「業務命令を拒否する社員!放置は危険!正しい対処法を弁護士が解説」の動画でも、業務命令を拒否する社員の対応方法について詳しく解説しています。
(1)戒告、減給などの懲戒処分の進め方
業務命令違反を理由とする解雇の前に、懲戒処分が行われていることが必要であることをご説明しました。
以下では懲戒処分の進め方についてご説明したいと思います。
1,弁明の機会を与える
懲戒処分を検討する場合は、本人に懲戒処分を検討していることを伝え、弁明の機会を与えることが必要です。
弁明の機会とは、懲戒処分を検討するにあたり、本人の言い分を聴く機会のことです。
2,懲戒処分の種類を選択する
本人の言い分を聴いた後は、就業規則の懲戒処分に関する規定を確認して、どのような処分をするかを検討することになります。
通常、会社の懲戒処分は、軽い順から以下のような処分が定められていることが一般的です。
本人の弁明の内容も踏まえたうえで、事案の内容に応じて適切な処分を選択する必要があります。
軽微な業務命令違反に対して出勤停止処分などの比較的重い懲戒処分を科すことは、不当な処分として違法になりますので注意してください。
3,懲戒処分を通知する
どの懲戒処分をするかが決まったら、懲戒処分通知書を作成したうえで、処分を本人に伝えることになります。
懲戒処分通知書については、以下の記事をご参照ください。
また、懲戒処分の注意点を進めるにあたっての注意点については以下の記事や動画で詳しく説明していますのであわせてご参照ください。
▶参考情報:懲戒処分とは?種類や選択の基準など詳しく解説
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「問題社員に対する懲戒処分!法律上のルールを弁護士が解説」の動画でも、懲戒処分の進め方や注意点について詳しく解説しています。
(2)始末書の取り方
多くの会社の就業規則では、戒告処分や減給処分の際は、従業員から始末書を提出させることが定められています。
この場合の始末書の取り方についても、注意点があります。
それは、会社が従業員に対して始末書の提出を命じる際は、その従業員に対して、文例やテンプレートを会社側から提示するべきではないということです。
そもそも、始末書は、従業員に業務命令に違反したことを謝罪させ、同様のことを繰り返さないことを誓約させる文書です。
従業員自身の意思で文面を考えて書かせることに意味があり、会社から文例を提示して記載させても意味がありません。
始末書における重要ポイント
- なぜ、業務命令に従う必要があったのか
- 業務命令に従わなかった理由は何か
- 業務命令に従わなかったことによって会社にどのような支障が生じたのか
- 今後はどうするのか
上記のような点を、従業員自身に考えさせ、記載させることが必要です。
自分の頭で考えさせて記載させることによって、従業員が本当に業務命令の意味を理解しているのかどうかや、本当に改善する意思があるのかどうかを確認することが重要です。
始末書については、以下の記事で詳しく解説してますので、あわせてご参照ください。
東京高等裁判所令和元年10月2日判決は、業務命令に従わない従業員を解雇したことを正当と判断した事例の1つです。
この事件で、裁判所は、従業員が業務命令に従わなかったことについて会社から反省文の提出を命じても、会社に対する不満をにじませた反省文を提出してきたことなどを理由に、会社がこの従業員を担当業務から外し、単純業務に就けたことも正当であると判断しています。
このような裁判所の判断からもわかるように、始末書や反省文を従業員自身の意思で文面を考えて書かせることは、問題社員に対して適切な対応をするために非常に重要です。
・参考情報:モンスター社員、問題社員への具体的な対応方法を弁護士が解説
・参考情報:問題社員を指導する方法をわかりやすく解説
(3)解雇ではなく合意による退職を目指す
会社の合理的な業務命令に対して、会社からの十分な説明、説得をしたにもかかわらず、業務命令に違反する態度を続け、懲戒処分をしても態度を改めないときは、従業員を懲戒解雇することも正当です。
ただし、会社のリスクを最小限にし、また、トラブルを長引かせないようにするためには、解雇は最後の手段ととらえ、まずは退職勧奨により、合意による退職を目指すことをおすすめします。
従業員を解雇してしまうと、後で不当解雇として訴えられるリスクがあり、その場合、万一敗訴すれば多額の金銭支払いを命じられます。
また、勝訴したとしても、長期間にわたり、裁判に費用や労力を割くことは企業経営にとってプラスではありません。
退職勧奨という形で、従業員に対して退職を促し、それでも合意に至らない場合に、最後の手段として懲戒解雇を検討するべきです。
退職勧奨については以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。
また、問題社員トラブルを解雇ではなく、問題社員トラブルを解雇ではなく、退職勧奨で円満に解決するための具体的な手順がわかるおすすめ書籍(著者:弁護士西川暢春)も以下でご紹介しておきますので、こちらも参考にご覧ください。書籍の内容やあらすじ、目次紹介、読者の声、Amazonや楽天ブックスでの購入方法などをご案内しています。
(4)合意による解決ができない場合は解雇を検討する
従業員が合意による退職に応じない場合は、解雇を検討します。
解雇にあたっては、「懲戒解雇にするか普通解雇にするか」の判断をすることがまず必要です。
業務命令違反の場合はどちらの方法でも解雇は可能ですが、後で不当解雇であるとして訴えられたときに、裁判所で正当な解雇と認められるためのハードルは、懲戒解雇のほうが普通解雇よりも高くなっています。
懲戒解雇と普通解雇の違いなど、それぞれの解説については、以下の記事を参照してください。
▶参考情報:普通解雇についてわかりやすく徹底解説
また、解雇にあたっては、「予告解雇か、即日解雇か」ということも事前に決めておく必要があります。
予告解雇というのは、30日前に解雇を予告したうえで30日後に実際に雇用を終了させる解雇方法になります。
これに対して、即日解雇というのは、解雇を伝える当日に雇用を終了させる方法です。即日解雇の場合は原則として30日分の解雇予告手当の支払が必要です。
予告解雇や解雇予告手当については以下の記事を参照してください。
▶参考情報:解雇予告とは?わかりやすく徹底解説
このような点を検討したうえで解雇を進めていくことになります。
具体的な解雇の進め方については、以下の記事や動画で詳しく解説していますのでご参照ください。
▶参考情報:問題社員の円満な解雇方法を弁護士が解説【正社員、パート社員版】
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「問題社員の解雇の方法について弁護士がわかりやすく解説」の動画でも、解雇方法や手順から注意点について詳しく解説しています。
4,【ケース別の対応例1】残業命令への違反についての対応
会社が行う残業の指示に従わない従業員への対応も、問題になることが多いケースの1つです。
これについては以下の大阪地方裁判所平成19年7月26日判決が参考になります。
参考判例:
大阪地方裁判所平成19年7月26日判決
事案の概要
電気設備工事業の会社において、椎間板ヘルニアによる腰痛のために早い時間の帰宅を希望し、残業を拒否し続けた入社2年目の従業員を解雇した事件です。
裁判所の判断
裁判所は、上司からの度重なる注意を受けても、残業の指示に従わず、同僚に残業を押し付けて帰宅することを続けた従業員について、会社がこの従業員を「雇用し続けることはできないと考えたことには一定の合理性を認めざるを得ない」などとして、解雇を有効と判断しています。
残業の指示に従わない従業員への対応方法
残業の指示に従わない従業員への対応については、まず、以下の点を確認してください。
- 「就業規則上、残業を命じられたら従う義務があることが明記されているかどうか」
- 「残業を命じるために必要な36協定が正しく締結されているかどうか」
そして、残業の指示に従わない従業員に対して懲戒や解雇を検討する場合は、さらに以下の点をチェックすることが必要です。
- 「従業員に対して残業が必要な理由を説明して説得する機会を設けたかどうか」
- 「従業員に体調不良や自宅での介護の必要性など、残業命令の指示に従うことが難しい特別の事情がないかどうか」
- 「仮に裁判になったときに、裁判所でなぜ残業が必要だったのか、残業をしないことによってどのような支障が生じたかを説明できるかどうか」
- 「仮に裁判になったときに、会社が残業の指示を何度も繰り返したのに従業員がこれに従ってこなかったことを立証できるかどうか」
▶参考情報:残業の指示に従わない従業員への対応方法については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
会社が従業員に残業を命じるためには、その前提として、「36協定」と呼ばれる労使協定が正しく締結され、かつ会社が命じる残業が法律上の残業規制の範囲内のものであることが必要です。
この点については以下で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
5,【ケース別の対応例2】会社の指導に従わない社員についての対応
会社の指導に従わない従業員への対応が問題になることがあります。
これについては、明治機械事件(東京地方裁判所令和2年9月28日判決)の事案が参考になります。
参考判例:
明治機械事件(東京地方裁判所令和2年9月28日判決)
事案の概要
産業用機械の制作、販売等の事業を営む会社が、20代前半の大卒男性を採用。
しかし、新人研修に参加した際、研修の外部講師に対して、「何故この項目を学ぶ必要があるのか」、「やりたくないので、やらなくていいですか」、「それって強制はできないですよね」と述べた。営業マナーの研修中も「こんなことをして営業はお客さんをだますのですよね」などと発言。生産部組立研修での作業がうまくいかないときには、突然大きな声を出して工具を放り投げ、担当社員から注意を受けた。
事業部に配属後も先輩社員から、太陽光発電の取得費用を軽減するための情報を調べて報告するよう求められ、「ネットを検索すると該当ページが出てくるのでそこを見てください」、「自分で調べた方が早いと思います」などと述べた。
上司からは、「基礎的事項を習得できず、上司や先輩社員の指導に従わず、内向的なところがあって相手の意図をくみ取ることが不得意で、相手を論破するような話法を多用することから、営業に向かず、少なくとも太陽光発電事業部にて業務を行うことは難しい」との評価を受けた。
会社は、この従業員について試用期間を3回延長した後、能力不足や他の従業員への悪影響を理由に解雇したという事案です。
裁判所の判断
裁判所は、以下の点を指摘して解雇を無効と判断し、会社を敗訴させています。
- 作業がうまくいかない場面で工具を放り投げていて、集中力や説明を聴きとって理解することに問題があった可能性が考えられるが、5日間にわたる生産部組立研修におけるものであるから、その評価については他の事情と併せて解雇事由に当たるか慎重に検討すべきである。
- 社会人経験がなかった従業員が入社後間もない研修等で学習に消極的な発言などがあったとしても、その評価については他の事情と併せて解雇事由に当たるか慎重に検討すべきである。
- 会社は、試用期間延長後、会議室にこの従業員一人を置いて専ら簿記の自習や新聞記事の閲読・報告等をさせており、適切な指導を実施して改善されるか否かを検討したと認めるに足りる証拠がない。
会社の指導に従わない社員についての対応方法
会社の指導に従わない社員についても、正しい方法で指導を行い、それでも改善できない場合は適切な退職勧奨により、雇用を終了させることを検討すべきです。指導に従わないからといって、パワハラにあたるような言動や退職強要にあたるような対応、あるいは不当解雇にあたるような対応をしてしまうと、自社の不利益となって返ってきます。
▶参考情報:業務命令を拒否して従わない場面での対応方法は以下の記事や動画でも解説していますのでご参照ください。
・業務命令を拒否して従わない社員の解決方法は?処分など対応方法を解説
・この記事の著者 西川暢春が、「指導に従わず論破しようとする社員の解雇!不当解雇になる?裁判例を解説」の動画で、今回紹介した裁判例に関して、「従業員に大きな問題があっても解雇が認められなかった原因」「試用期間を延長した場合の注意点」「正しい解決方法」などを詳しく解説しています。
6,業務命令違反を理由とする損害賠償について
従業員の業務命令違反に対して、会社側から損害賠償を請求する事例もありますが、ほとんどの判例では、損害賠償請求は認められていません。
参考判例:
平成24年11月20日東京地方裁判所判決
例えば、平成24年11月20日東京地方裁判所判決は、会社の業務命令に対する違反は不法行為になるがそれにより会社に損害が発生したとは認められないなどとして、会社を敗訴させています。
7,業務命令違反に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、業務命令に従わない従業員にお困りの企業の方に向けて、咲くやこの花法律事務所における問題社員対応についての企業向けサポート内容をご説明したいと思います。
サポート内容は以下の通りです。
- (1)業務命令違反、その他問題社員対応に関するご相談
- (2)弁護士による懲戒手続きの実施
- (3)退職勧奨や解雇の際の面談の立ち合い
- (4)解雇後のトラブルや懲戒処分後のトラブルに対する対応
- (5)顧問弁護士サービスによる問題社員対応サポート
以下で順番にご説明します。
(1)業務命令違反、その他問題社員対応に関するご相談
咲くやこの花法律事務所には、業務命令に従わない社員など、問題社員の指導方法や対応方法に精通した弁護士が多数在籍しています。
ご相談の際は、まず個別の事情を詳細にヒアリングしたうえで、事案ごとに、過去の事務所での対応経験も踏まえて、指導や懲戒、あるいは解雇など、実効性のある対応策をご提案します。
問題社員の指導、対応にお悩みの企業経営者、管理者の方はご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士による相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
(2)弁護士による懲戒処分手続きの実施
咲くやこの花法律事務所では、問題社員に対する懲戒処分手続きについてもサポートを行っています。
懲戒するべき事情があるかどうかの検討から、懲戒処分の言い渡しまでを弁護士が同席してサポートすることが可能です。
懲戒については、まず懲戒するべき事情があるかどうかについての法的な検討を正しく行うことが必要です。そのうえで、事前に懲戒処分通知書を作成することが必要です。
また、懲戒処分の言い渡しの場面では、従業員がその場で不満を述べたり反論をしてきたりすることがあります。無用なトラブルを防止するためには、懲戒処分の言い渡しの場に専門家である弁護士も同席することが効果的です。
咲くやこの花法律事務所では、労務トラブルに強い弁護士が懲戒処分の言い渡しの場に同席し、会社側の立場で適切な応答をするなどして、懲戒処分の言い渡しをサポートしています。
懲戒処分の言い渡しに不安があるときは、咲くやこの花法律事務所のサポートサービスをご利用ください。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士によるサポート費用
●初回相談料:30分5000円+税
●面談費用:時間や面談場所への距離に応じて、10万円~20万円+税程度
※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。
(3)退職勧奨や解雇の際の面談の立ち合い
咲くやこの花法律事務所では、企業のご要望に応じて、退職勧奨や解雇の際の面談への立ち合いも行っております。
退職勧奨や解雇の問題に精通した弁護士が立ち会うことで自信をもって、退職勧奨あるいは解雇を進めることが可能になります。
また、解雇の場面で重要な書面になる解雇理由書や解雇通知書の作成と発送についてもご依頼を受けています。
解雇の問題に精通した弁護士が書面作成に携わることによって、万が一、裁判等に発展した時のことも見越した書面作成が可能になります。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士によるサポート費用
●初回相談料:30分5000円+税
●面談費用:時間や面談場所への距離に応じて、10万円~20万円+税程度
※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。
(4)解雇後のトラブルや懲戒処分後のトラブルに対する対応
咲くやこの花法律事務所では、解雇した従業員あるいは懲戒処分をした従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も常時承っています。
解雇した従業員が不当解雇であるとして復職を求めたり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。
また、懲戒処分をした従業員が不当な懲戒解雇であると主張して、処分の撤回を求めてくるような場面でも、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。
懲戒処分後のトラブルや解雇後のトラブルでお困りの方は、早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。
咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士による対応費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:20万円~30万円+税程度~
●裁判時の対応着手金:45万円程度~
(5)顧問弁護士サービスによる問題社員対応サポート
咲くやこの花法律事務所では、業務命令に従わない問題社員の指導にお困りの企業を継続的にサポートするために、顧問弁護士サービスによるサポートも行っています。
顧問弁護士サービスによるサポートのメリット
- 指導方法や従業員対応についての疑問点をその都度電話やメールで弁護士に相談できる
- 業務命令の出し方や、懲戒処分についてもいつでも弁護士に電話で相談できる
問題社員の指導は継続的な取り組みが必要であり、弁護士にいつでも相談できる体制を作ることで、正しい対応を進めていくことが可能です。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用
●スタンダードプラン(月額顧問料5万円/相談時間制限なし)
- 契約前に担当弁護士との無料面談で相性をご確認いただくことができます(電話・テレビ電話でのご説明or来所面談)
- 来所していただかなくても、電話あるいはテレビ電話でお申込みいただけます。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細や顧問弁護士サービスの実績については以下のページをご参照ください。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの方はこちら
(6)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年10月22日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」業務命令違反など問題社員対応に役立つ情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587