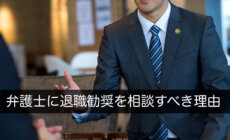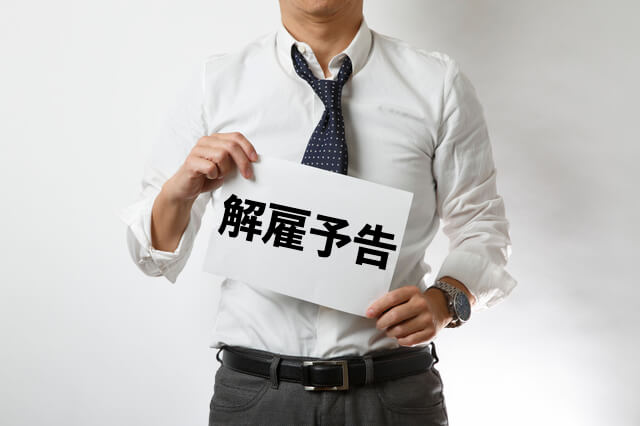
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
会社が従業員を解雇する場合、原則として解雇日の30日前までに解雇を予告することが必要です。
この「解雇予告」については、実際にやろうとすると、従業員への言い方に悩んだり、書類の作成方法がわからなかったりすることも多いのではないでしょうか?
今回は、従業員に解雇を予告する場合の、法律上のルールや具体的な言い方、伝え方、解雇予告の重要な注意点などについてご説明します。
企業が従業員を解雇する場面では、後日、解雇した従業員から訴訟を起こされる危険もあり、企業としてリスクの高い場面の1つです。解雇が不当解雇と判断されると1000万円を超えるような支払いを裁判所で命じられることもありますので、重要な注意点をおさえて慎重に進めることが必要です。
それでは見ていきましょう。
▶参考情報:なお、解雇予告をはじめとする解雇の全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。
▶【参考情報】解雇トラブルに関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」はこちらをご覧ください。
▼解雇予告について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
また労働問題に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,解雇予告とは?
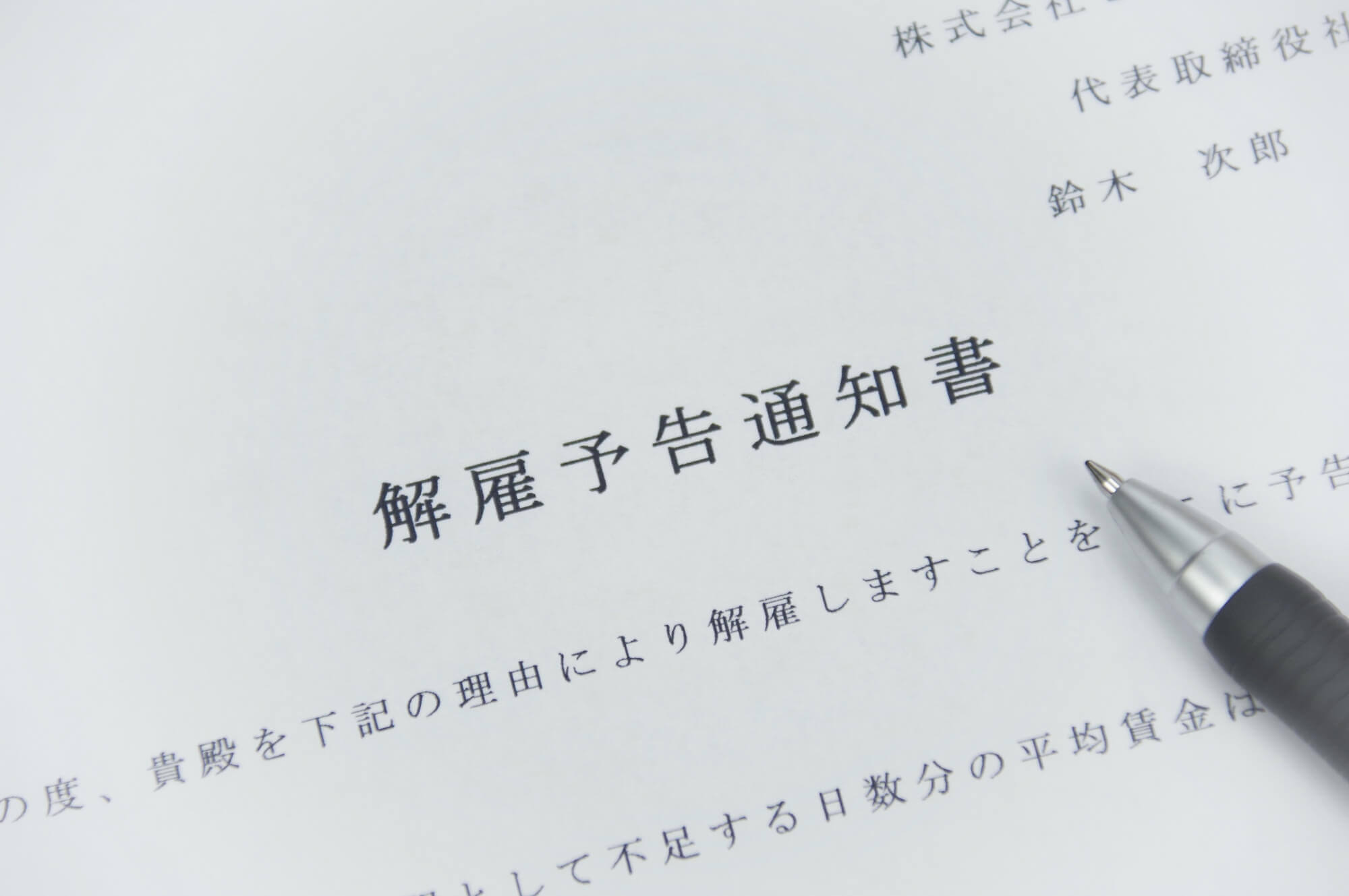
解雇予告とは、従業員を解雇する前に解雇を予告することを言います。「労働基準法」により例外的な場合を除き、従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告することが義務付けられています(労働基準法第20条1項)。ただし、解雇予告手当を支払うことにより、予告しないで解雇することも可能です。
(1)解雇予告の30日前の数え方は?
30日前の数え方は、休みの日も含めて30日前であれば問題ありません。勤務日だけを数えて30日以上前である必要はありません。土日が休みの会社では土日も含めて数えることになります。そして、この30日は、解雇予告をした日を含めずに数えます。例えば、6月30日に解雇する場合は、遅くとも5月31日には解雇の予告をする必要があります。30日前であればこれより前に予告することは問題ありません。
(2)解雇予告したら給与はどうなるの?
解雇予告をした後も、解雇の日までは雇用契約が継続しています。そのため、解雇の日までの期間については給与を支払うことが必要です。
2,解雇予告に関する法律上のルール

まず、最初に解雇予告に関する法律上のルールを確認しておきましょう。
前述のとおり、「労働基準法」により例外的な場合を除き、従業員を解雇するときは、30日前に予告することが義務付けられています(労働基準法第20条1項)。
これが、「解雇予告」です。ただし、会社は30日分の賃金(解雇予告手当)を支払えば、予告なく、解雇を言い渡した当日に解雇することができます。これを即日解雇とも呼ばれています。
即日解雇については、以下で注意点など詳しく解説していますのでご参照ください。
また、解雇を予告した日から解雇の日までの期間が30日に足りない場合は、足りない日数分の賃金(解雇予告手当)を支払えば、解雇することができます。
例えば、解雇を予告した日から解雇の日までの期間が20日の場合は、10日分の賃金を解雇予告手当として支払えば解雇することができます。
(1)解雇予告が必要ない場合
以下の場合は例外的に、法律上、解雇を事前に予告する必要はありません。
- 解雇予告手当として30日分の賃金を支払って解雇する場合(労働基準第20条1項)
- 日雇いの従業員で雇用開始後1か月以内に解雇する場合(労働基準法第21条)
- 試用期間中の従業員で雇用開始後14日以内に解雇する場合(労働基準法第21条)
- 解雇予告除外認定制度による除外認定を受けた場合(労働基準法第20条1項但し書き)
このうち、最後の解雇予告除外認定制度による除外認定を受けた場合については、この記事の「5,除外認定制度と解雇予告除外認定申請書について」で詳述します。
▶参考情報:労働基準法第20条の内容について、以下で解説していますのでご参照ください。
3,解雇予告の口頭での言い方、伝え方について

では、従業員に解雇の予告をする場合、どのような言い方、伝え方をすればよいのでしょうか?
解雇予告の基本的な手順は以下の通りです。
- 1,解雇の方針を社内で共有する。
- 2,解雇の理由をまとめたメモを作成する。
- 3,解雇予告通知書を作成する。
- 4,解雇する従業員を別室に呼び出す。
- 5,従業員に解雇を伝える。
以下で順番にご説明したいと思います。
(1)解雇の方針を社内で共有する
まず、解雇することを決めたら、従業員が「不当解雇である」などと主張してきた場合に会社が一丸となって対応していくためにも、その方針を社内で共有する必要があります。
会社の幹部や本人の直属の上司にも、その従業員を解雇することを伝え、事前に理解を求めておきましょう。
(2)解雇の理由をまとめたメモを作成する
次に、解雇の理由をまとめたメモを作成します。
これは、従業員に解雇の話をするときにできるだけ説得的で明確な説明をするための準備です。解雇の話をする場面で、従業員からどのような反応が返ってきても、冷静に自信を持って解雇の理由を説明する必要があります。そのためには、事前に解雇の理由を整理したメモを準備しておくことが必要になるのです。
メモは、これまで従業員を直接指導してきた上司にもヒアリングしながら、できる限り詳細で具体的なものを作りましょう。
(3)解雇予告通知書を作成する
次に、「解雇予告通知書」を作成することが必要です。
解雇予告は法律上は口頭で行うことも可能ですが、口頭で行うとあとで解雇予告の手続きが正しく行われたかどうかをめぐって争いになることがあります。
必ず書面を作成して従業員に交付しましょう。
解雇予告通知書の作成方法や交付方法については以下の記事をご参照ください。
(4)解雇する従業員を別室に呼び出す
解雇の予告は、会社の会議室など、普段の職場から離れた別室で行いましょう。
「話があるので来てください。」といって別室に解雇対象者を呼びます。
(5)従業員に解雇を口頭で伝える
従業員に解雇を口頭で伝えます。
具体的な話の仕方としては以下の例を参考にしてください。
参考例:
従業員に解雇を口頭で伝える時の具体的な話し方
1.解雇の話の切り出し方
「これまで、私からもあなたの上司の○○さんからも、あなたの仕事ぶりに会社が満足していないことを伝えて、改善するように伝えてきました。」と話を切り出します。
2.会社としても雇用を継続するための努力してきたことについて伝える
「去年の●月頃後には~という話をしましたし、今年の〇月ごろには~という話もしましたね。あなたの上司の○○さんも時間をとってあなたと面談をし、あなたに改善をお願いしてきました。しかし、結果として、十分に改善されていないと感じています。」などと、会社としても努力してきたが問題点が改善されなかったことを伝えます。
また、会社として本人の適性にあった部署を探すために配置換えなどをしている場合は、さらに「あなたが総務の仕事でミスを繰り返すので、別の部署に配置換えをして違う仕事もやってもらいましたが、新しい仕事もうまくいきませんでしたね。」などと話をします。
3.解雇を伝える
「そこで、残念ですが、社内で話し合った結果、会社としては、あなたを●月●日付けで解雇することにしました。」と解雇を伝えます。
必ず、解雇が何日付であるかを伝えることと、言いにくくても「解雇することにしました」というように解雇をはっきりと伝えることを忘れないようにしてください。
4.相手の反論や質問に対応する
従業員からは、解雇の理由についての反論や、あるいはさらに詳細な解雇の理由を説明する質問などがされることが想定されます。
その場合は、「(2)解雇の理由をまとめたメモを作成する」のところで作成したメモを確認しながら、冷静に説明をしましょう。
5.解雇の日までの業務について伝える
最後に解雇の日までの業務内容について伝えます。
特に、解雇した従業員の業務を後任者に引き継ぐ必要がある場合は、誰にどのように引き継ぐのかを具体的に伝えて指示しましょう。ただし、未消化の有給休暇が残っている場合に、従業員が有給休暇の消化を希望する場合は、法律上、有給休暇の消化を認める必要があります。
6.再度自主退職を促す
不当解雇の裁判リスクがある場面では、ここまで話した段階で裁判にかかる費用や労力を避け、またトラブルが長期化することを避けるために再度自主退職を促すことも検討に値します。
例えば、解雇後の生活資金としていくらか支払うことなどを提案して、自主退職を促すことも一つの方法です。
自主退職については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
7.自主退職に応じなければ解雇予告通知書を交付して、受領のサインをもらう
自主退職に応じなければ解雇予告通知書を渡します。
そして、解雇予告通知書のコピーに受領のサインをもらいます。従業員が解雇に反発して、解雇通知書を受領しない場合や受領のサインをしない場合は、解雇予告通知書を従業員の自宅に内容証明郵便で郵送しましょう。
▶参考情報:内容証明郵便の送り方は以下をご覧下さい。
一方、従業員が自主退職に応じるときは、必ず「退職届」を提出してもらいましょう。
以上が、解雇予告の具体的な手順となります。
解雇を従業員に伝える前に、自身でシミュレーションをしておくことをおすすめします。シミュレーションをしておくことで、漏れのないように話をし、また従業員に対して毅然とした態度を示すことができます。
冒頭でもご説明した通り、解雇予告は企業にとって重大なリスクのある場面です。もし、解雇予告の手順などで不安な点がありましたら、咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士までご相談ください。
4,解雇予告の重要な注意点
ここまで解雇予告の方法についてご説明しましたが、解雇予告にあたっては、会社として必ずおさえておかなければならない重要な注意点があります。
それは、「30日前に解雇予告をしたからといって不当解雇にならないわけではない」という点です。
30日前の解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いは従業員を解雇する場合に会社が守らなければならない最低限の手順にすぎません。解雇予告をしたからといって、あるいは解雇予告手当を支払ったからといって、解雇が必ず正当といえるわけではありません。
解雇が正当とされるためには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。
- 条件1:解雇が正当化される客観的な理由があること(解雇理由)
- 条件2:解雇のための手続きが正しく行われていること(解雇手続き)
条件1の解雇理由については、正当な解雇理由となるためには、解雇理由ごとに条件があり、それを満たしておく必要があります。
例えば、能力不足が理由で新卒者あるいは未経験者の従業員を解雇する場合は、「必要な指導や、適性を見るための配置転換を行った後も、勤務成績が不良であること」が正当な解雇理由となるための条件です。
その他のケースも同様に、解雇理由ごとに正当な解雇理由となるための条件があります。
具体的な条件は、以下の記事で詳しく解説していますので、確認してください。
次に条件2の「解雇の手続き」については、就業規則の確認が必要です。
特に、懲戒解雇の場合は、就業規則で、「解雇の前に従業員の弁明を聴くこと」や、「懲戒委員会を開くこと」を定めている会社も多くなっています。
懲戒解雇について詳しくは以下で解説していますので、参考にご覧下さい、
その場合、必ず、就業規則に定められた手続き通りの手順を踏んで解雇する必要があります。
(1)解雇予告の前に弁護士に相談が必要!
このように正しく解雇予告をしていたとしても、正当な理由がないのに解雇したり、就業規則に定められている手続きをとらずに解雇した場合は、不当解雇として会社が訴えられ、以下のように高額な支払いを命じられるケースが増えています。
事例1:
設計会社による従業員解雇事例(東京地方裁判所平成27年1月28日判決)
試用期間中の従業員の解雇について会社に「約750万円」の支払命令
事例2:
ミリオン運輸事件(大阪地方裁判所平成8年7月31日判決)
寝過ごしによる延着事故を理由とするトラックドライバーの解雇について会社に「約1180万円」の支払いを命令
事例3:
日本ヒューレット・パッカード事件(平成23年1月26日東京高等裁判所判決)
無断欠勤を理由とする懲戒解雇について会社に「約1600万円」の支払い命令
解雇については、企業経営の中でも重要なリスクのある場面の1つですので事前に必ず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士にご相談いただくことにより、解雇について正当な理由があるか、正しい手続きが取られているか、不当解雇と判断されるリスクがないかなどをチェックすることができます。
また、場合によっては、解雇の前に解雇理由を立証するための必要な証拠資料を集めておくことが可能になります。解雇後に従業員から訴えられるリスクを想定して、事前に解雇理由を立証する証拠を集めておくことは、会社を守るために非常に重要です。
不当解雇トラブルや裁判については、以下の記事で詳しくご説明していますので、併せてご確認いただきますようにお願いいたします。
5,解雇予告手当の計算方法
解雇を予告した日から解雇の日までの期間が30日に足りない場合は、足りない日数分の賃金(解雇予告手当)を支払うことが必要です。
解雇予告手当は、解雇対象となる従業員の「1日分の平均賃金」に「予告期間が30日に足りなかった日数」をかけることで計算することができます。
具体的な解雇予告手当の計算方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
6,除外認定制度と解雇予告除外認定申請書について
最後に労働基準法上の解雇予告の義務が免除される「解雇予告除外認定制度」についてご説明しておきたいと思います。
解雇予告除外認定制度とは、以下の点が解雇理由になる場合に、労働基準監督署に認定してもらうことにより、30日前の予告をしなくても解雇予告手当の支払いなしで解雇ができる制度です。
除外認定制度の対象となる解雇理由
- 会社内の盗みや横領を理由とする解雇
- 会社内で暴力をふるい、けがをさせたことを理由とする解雇
- 経歴詐称を理由とする解雇
- 2週間以上の無断欠勤による解雇
解雇予告除外認定の手続きの具体的な手続きは、以下の通りです。
(1)解雇予告除外認定申請書の書式
まずは、解雇予告除外認定申請書を労働基準監督署に提出することが必要です。
解雇予告除外認定申請書の書式は以下からダウンロードが可能です。
(2)提出先
提出先は従業員が勤務していた事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。本社で働いていた従業員でない場合は、実際に勤務していた場所が基準になることに注意してください。
(3)提出書類
提出書類は、解雇理由によって異なりますが、おおむね以下の通りです。
1,解雇対象者が自社の従業員であることがわかる資料
- 履歴書や労働条件通知書、雇用契約書、賃金台帳等
2,懲戒事由に該当することがわかる資料
- 懲戒解雇事由が定められている就業規則等
- 就業規則で懲戒の場合に懲戒委員会を開くことが規定されている場合は、懲戒委員会の議事録
3,除外認定制度の対象となる解雇理由に該当することがわかる証拠
その従業員が除外認定制度の対象となる解雇理由に該当することがわかる証拠を資料として提出することが必要です。
例えば、横領により除外認定を申請する場合は、その従業員が横領したことがわかる資料を提出する必要があります。また、本人が横領を認めた書類(自認書)を必ず提出する必要があります。
労働基準監督署は警察と違い、除外認定の際に、積極的に従業員に対して調査をしたり、あるいは横領の証拠を集めたりということはしてくれません。
そのため、本人が横領を認めた書類は会社で用意する必要があります。これが提出できなければ、現在の労働基準監督署の実務では、除外認定を受けることは難しいのが実情です。
(4)手続きの流れ
解雇予告除外認定申請書を提出すると、労働基準監督署から、どのような資料を提出しなければならないかの指示があります。
資料がそろった段階で、会社側担当者に対する事情聴取と解雇対象者に対する事情聴取が行われます。除外認定について結果が出るまで2週間から3週間程度の期間を要することが通常です。
この解雇予告除外認定申請の手続きについても、適切な証拠を提出しなければ、認定を受けることができませんので、弁護士に依頼することがスムーズです。
▶参考情報:解雇予告除外認定の制度について、認定基準をはじめ詳しい解説は以下の記事で解説していますのでご参照ください。
7,解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績
咲くやこの花法律事務所では、解雇に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。
咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。
▶成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例
8,解雇予告に関して弁護士へ相談をしたい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による、問題社員の解雇に関する企業向けサポート内容についてご説明したいと思います。
咲くやこの花法律事務所の弁護士による、問題社員の解雇に関する企業向けサポート内容は以下の通りです。
- (1)問題社員の解雇、退職勧奨のご相談
- (2)解雇や退職勧奨の際の面談の立ち合い
- (3)解雇予告通知書や解雇理由書の作成、発送
- (4)解雇後のトラブルに関する交渉、裁判
以下で順番に見ていきましょう。
(1)問題社員の解雇、退職勧奨のご相談
「咲くやこの花法律事務所」では、問題社員についての解雇や退職勧奨の事前のご相談を企業から常時お受けしています。
具体的には以下のような項目について、各企業からご相談をいただいています。
- 解雇前の証拠収集に関するご相談
- 解雇した場合のリスクの程度に関するご相談
- 解雇や退職勧奨の具体的な方法に関するご相談
- 解雇や退職勧奨の具体的な注意点のご相談
- 懲戒解雇か普通解雇かの選択に関するご相談
- 即日解雇か予告解雇かの選択に関するご相談
- 解雇後の手続きに関するご相談
- 解雇予告除外認定申請手続きあるいはその申請代行のご相談
事前に自社でよく検討しているつもりでも、思わぬところに落とし穴があることが常ですので、必ず解雇前にご相談いただくことをおすすめします。
(2)解雇や退職勧奨の際の面談の立ち合い
「咲くやこの花法律事務所」では、企業のご要望に応じて、解雇や退職勧奨の際の面談への立ち合いも行っております。
解雇の問題に精通した弁護士が立ち会うことで自信をもって解雇を進めることが可能になります。
弁護士による退職勧奨の立ち合いに関する実績例は以下をご覧ください。
(3)解雇予告通知書や解雇理由書の作成、発送
「咲くやこの花法律事務所」では、解雇の場面で重要な書面になる「解雇予告通知書」や「解雇理由書」の作成と発送についてもご依頼を受けています。
解雇の問題に精通した弁護士が、解雇の場面から書面作成に携わることによって、万が一、裁判等に発展した時のことも見越した書面作成が可能になります。
(4)解雇後のトラブルに関する交渉、裁判
「咲くやこの花法律事務所」では、解雇した従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も常時承っています。
解雇した従業員が不当解雇であるとして復職を求めたり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。
また、裁判においてもこれまでの豊富な経験を生かしてベストな解決に導きます。
「咲くやこの花法律事務所」には、これまで「問題社員の解雇や解雇後のトラブル対応」について、解決実績と経験が豊富な弁護士がそろっています。
解雇トラブルでお困りの方は、早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。
(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
解雇予告に関する相談や解雇に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士への相談サポート」をご覧下さい。
また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
9,解雇に関する法律のお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
解雇予告など解雇に関する法律のお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
10,まとめ
今回は、解雇予告に関する法律上のルール、解雇予告の具体的な手順、解雇予告手当の計算方法、除外認定制度についてご説明しました。
また、解雇予告の重要な注意点として、解雇については、正しい解雇予告をしたとしても企業にとって大きなリスクになりうる場面であることをご説明しました。
解雇予告をしてしまってから弁護士に相談しても対応できる選択肢が限られるのが実情です。解雇を本人に伝える前に弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
11,【関連情報】解雇予告に関する解雇のお役立ち記事一覧
今回の記事では、「解雇予告とは?わかりやすく徹底解説」についてご説明しました。
解雇予告に関しては、今回ご紹介したように正しい知識を理解しておかなければならず、方法を誤ると重大な不当解雇トラブルに発展したりなど、大きな解雇トラブルにつながる可能性があります。
そのため、それらのリスクを防ぐためには、今回ご紹介した解雇予告については必ずおさえておきましょう。また、その他にも解雇予告に関して合わせて確認しておきたい解雇に関連するお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。
・正社員を解雇するには?条件や雇用継続が難しい場合の対応方法を解説
・労働基準法による解雇のルールとは?条文や解雇が認められる理由を解説
・解雇理由証明書とは?書き方や注意点を記載例付きで解説【サンプル付き】
・能力不足の従業員を解雇する前に確認しておきたいチェックポイント!
実際に従業員を雇用されている会社では、解雇予告をしなければならないケースがあるかもしれません。そのため、「解雇予告の正しい知識と方法」を事前に理解しておくことはもちろん、万が一のトラブルなどが発生した際は、スピード相談が早期解決の重要なポイントです。
今回の記事のテーマにもなっている「解雇予告」については、「労働問題に強い弁護士」に相談するのはもちろん、普段から就業規則など自社の労務環境の整備を行っておくために「労働問題に強い顧問弁護士」にすぐに相談できる体制にもしておきましょう。
労働問題に強い咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容については、以下を参考にご覧ください。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら
また、顧問弁護士の必要性や役割、顧問料の相場などについて知りたい方は、以下の記事を参考にご覧ください。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年9月18日
 06-6539-8587
06-6539-8587