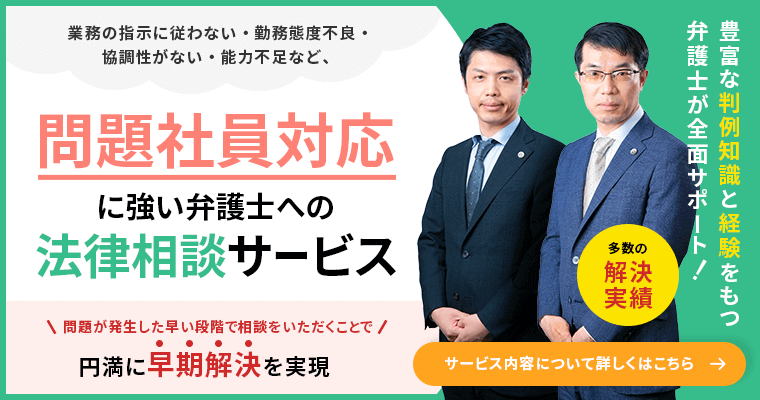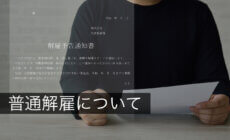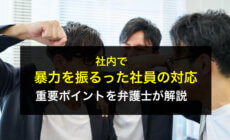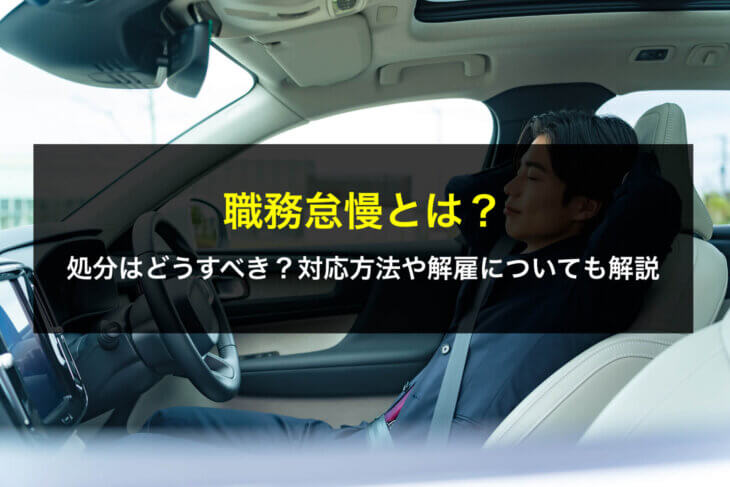
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
職務怠慢の問題がある従業員にどう対応すべきかお悩みではありませんか?
職務怠慢の問題がある従業員を放置したままでいると、業務に支障が出るだけでなく、社内の規律が乱れ、士気が下がるなど他の社員にも悪影響を及ぼします。そのため、早急に適切な対応をする必要があります。一方で、誤った対応をしてしまうと、職務怠慢に関する指導についてパワハラだとの主張を受けてしまったり、安易な解雇によって不当解雇のトラブルに発展するといったことにもなりかねません。
従業員の職務怠慢から起きる問題を解決するには、問題の放置や先送りをせず、初動対応から適切な指導、懲戒処分、改善されない場合は辞めてもらうまでのプロセスを「正しい対応方法」で実施できなければならないのです。
この記事では、職務怠慢に該当する行為の例や、職務怠慢の問題がある従業員への対応方法について詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、指導によっても改善できなかった場合の懲戒処分や解雇といった対応についても理解していただくことが可能です。
それでは見ていきましょう。
指導を重ねても従業員の職務怠慢の問題が改善しない場合、懲戒処分や解雇を検討することになります。ただし、これらの過程で対応を誤ると、指導がパワハラだと主張されたり、解雇が不当解雇だと主張されるなどして、大きな問題に発展し、収拾がつかなくなる恐れもあります。
必ず弁護士に相談したうえで、正しい方法で対応する必要があります。咲くやこの花法律事務所では、このような問題社員に関するトラブルについて事業者からのご相談を数多くお受けし、解決してきました。従業員の職務怠慢の問題でお悩みの事業者様は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
▶参考:咲くやこの花法律事務所のサポート内容や解決実績については以下もご参照ください。
▼従業員の職務怠慢の問題について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,職務怠慢とは?
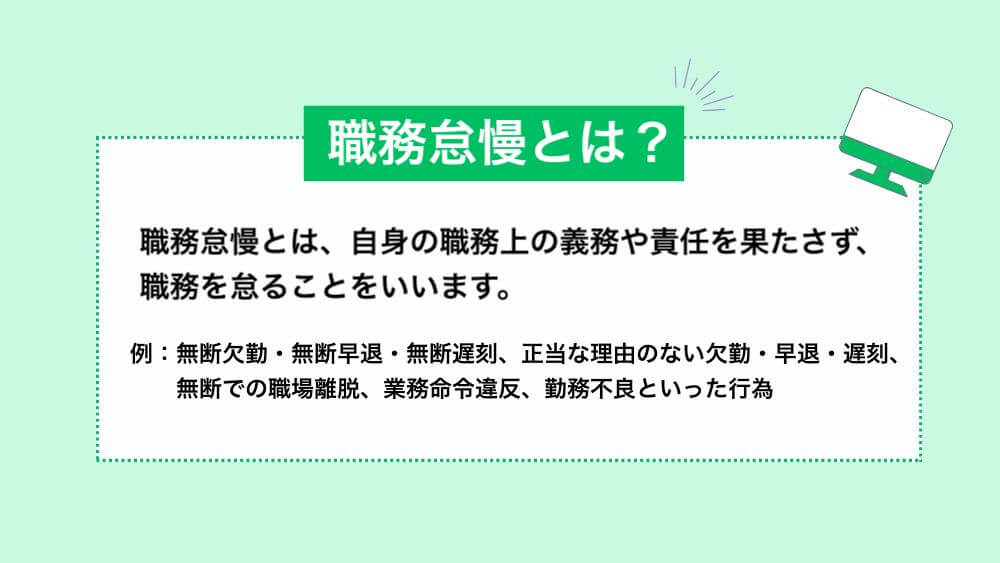
職務怠慢とは、自身の職務上の義務や責任を果たさず、職務を怠ることをいいます。具体的には、無断での欠勤・早退・遅刻、正当な理由のない欠勤・早退・遅刻、無断での職場離脱、業務命令違反、勤務不良といった行為があげられます。
(1)職務怠慢の言い換えや類語と意味の違い
職務怠慢の類語としては、「職務懈怠」「職務放棄」といった言葉があります。「職務怠慢」や「職務懈怠」が、一応、職務は遂行しているものの不十分または問題があることを指すことが多いのに対し、「職務放棄」は職務自体を放棄することを指します。
2,職務怠慢に該当する行為の例
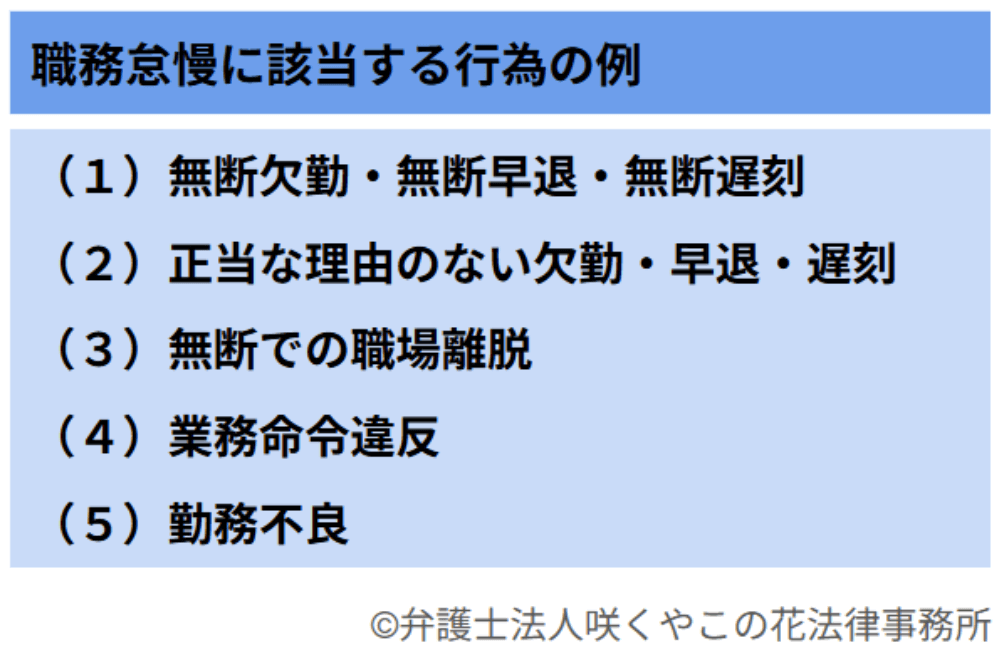
次に、職務怠慢に該当する行為の具体例について解説します。
(1)無断欠勤・無断早退・無断遅刻
従業員は、出勤日の始業時刻までに出勤し、終業時刻まで就業する義務を負います。出勤日に欠勤する場合や、早退する場合、遅刻する場合は、事前に勤務先の承諾を得なければならないことが原則です。これを怠って、無断欠勤・無断早退・無断遅刻をすることは、通常は職務怠慢にあたります。
▶参考情報:無断欠勤をする社員や遅刻が多い社員への対応については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(2)正当な理由のない欠勤・早退・遅刻
欠勤・早退・遅刻の前に勤務先に連絡していたとしても、正当な理由のない欠勤や早退、遅刻等は、職務怠慢にあたります。また、欠勤や早退・遅刻が体調不良を理由とするものであっても、診断書の提出を求められても提出しなかったり、診断書を提出してもその信用性が疑わしい場合は、職務怠慢にあたりうることも踏まえた検討が必要になります。
▶参考情報:欠勤が多い社員への対応については以下をご参照ください。
(3)無断での職場離脱
業務時間中に無断で職場を離れ、休憩や業務外の私的な行動をすることも職務怠慢にあたります。
具体例としては以下のような行為があげられます。
- 無断で職場を度々抜け出してパチンコをする
- 会社の許可なく社用車の中で長時間昼寝する
(4)業務命令違反
業務命令違反とは、正当な理由なく業務命令に従わないことを言い、指示された業務をしないこともこれに含まれます。また、ここでいう「業務命令」には、日常的な業務上の指示のほか、配転・出向等の人事命令、時間外労働等に関する命令、服務規律に関する命令等が含まれます。
業務命令違反が職務怠慢にあたる例としては以下のような行為があげられます。
- 報告書を期限内に提出しない
- 指示された業務を期限までに行わない
▶参考情報:業務命令違反については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(5)勤務不良
勤務中に職務を適切に遂行していない状態や、勤務態度等に問題がある状態のことをいいます。
以下のような行為は勤務不良に該当します。
- 仕事をさぼる
- 仕事の進行に極端に時間をかける
- 仕事中に居眠りをする
- 業務上のミスを繰り返す
なお、いくら従業員の勤務態度に問題があるからといって簡単に解雇はできないことに注意が必要です。後で不当解雇と判断されないためにも、従業員を辞めさせる場合は法律のルールを守った適切な対応をする必要があります。
▶参考情報:上記のような問題社員の対応については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
そのほか、上司が部下に対する指導を怠ったり、必要な監督を怠ること、部下に対する適切な労務管理を怠ることも、職務怠慢にあたります。
3,職務怠慢の問題がある従業員への対応や懲戒処分
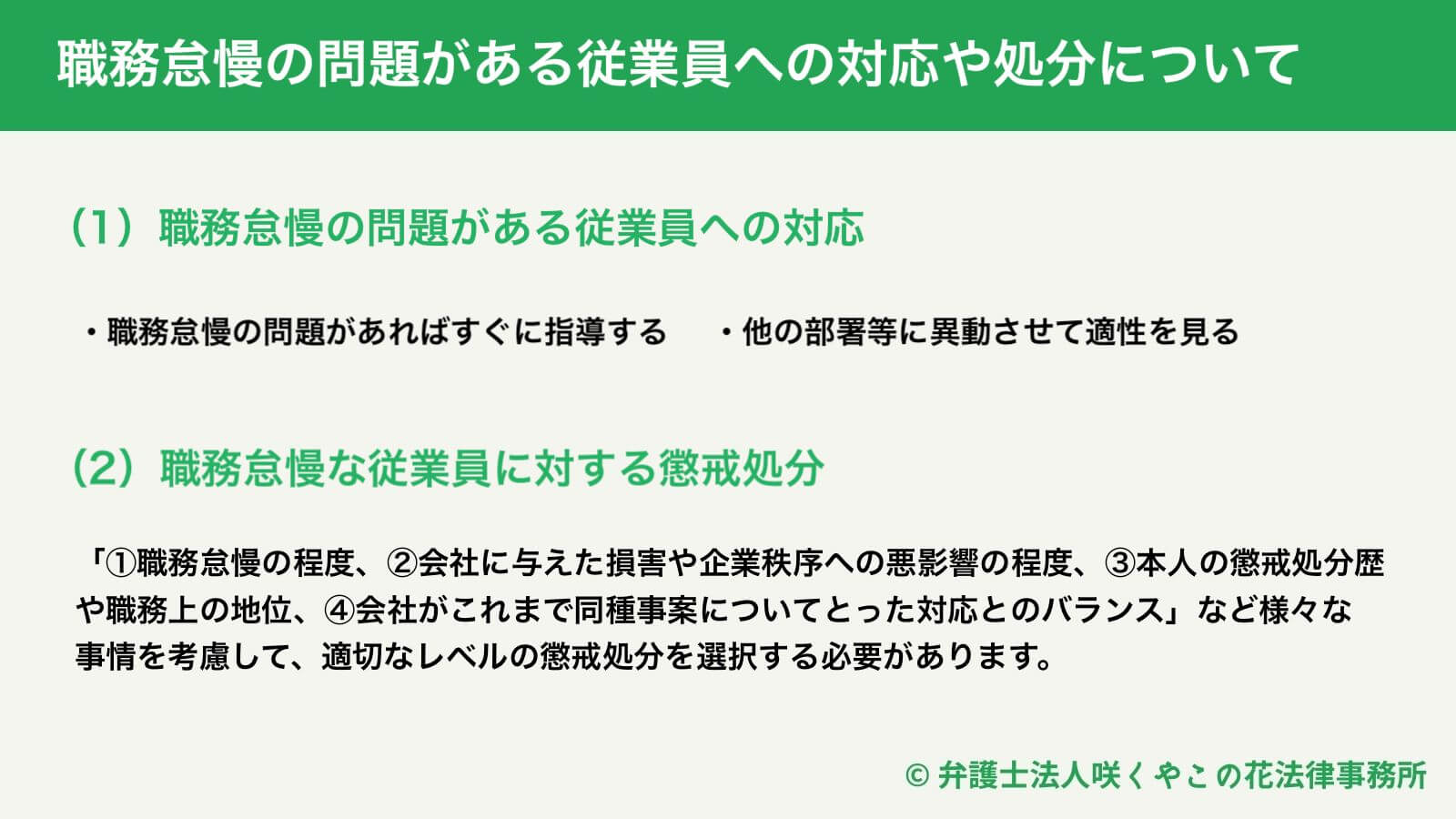
次に、職務怠慢の問題がある従業員への対応や懲戒処分について詳しく解説します。
(1)職務怠慢の問題がある従業員への対応
上記でご紹介したように、一概に職務怠慢といってもさまざまなパターンがありますが、ここでは各ケースに共通する対応方法をご説明します。
1,職務怠慢の問題があればすぐに指導する
最も大切なのは、職務怠慢の問題があったときに放置せずにすぐに指導することです。その場ですぐに指導しないと、後になって指導しても効果は期待できません。
指導する際は、まず問題の従業員に事情を聴き、「職務怠慢」にあたるのかを確認する必要があります。そのうえで、「職務怠慢」にあたる場合は、本来どのように取り組む必要があったのかを説明したうえで、端的に現状の問題点を指摘し、具体的な改善について伝える必要があります。
「新人以下だ」とか「無能だ」などといった本人の人格を否定するような侮辱的発言はパワハラ(パワーハラスメント)になりかねないため、するべきではありません。大声や威圧的な叱責を他の従業員に聞こえるような状況で行うことも避けるべきです。
なお、将来的に解雇することになった場合、単に職務怠慢にあたるというだけでは解雇は有効と認められないことが多いです。職務怠慢に対して、会社が必要な指導や懲戒処分を行ったがそれでも改善が見込めなかったということを主張する必要があります。
指導の事実を証拠として残すためにも、指導記録票を作成し、都度指導の内容を記録しておくことが必要です。
▶参考情報:問題社員に対する指導方法については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
2,他の部署等に異動させて適性を見る
複数の職種や部署がある場合は、他の部署や職種に配置転換してみて、適性を見ることも検討する必要があります。
この点については「職務怠慢な人はどこにいってもダメ」と考えもあり得るところですし、実際に「どこにいってもダメ」ということもあります。しかし、最終的に解雇等を検討する場合、他の部署等に異動させてそこでの適性を見るというプロセスを経ていなければ、解雇が無効とされる理由になってしまいます(東京地方裁判所判決平成28年3月28日 日本アイ・ビー・エム事件等参照)。また、業務の内容や上司が変われば仕事への向き合い方が変わることがあることも事実です。
なお、従業員を退職に追い込むことを目的とした配置転換や転勤命令は、業務上必要のない不当な目的による人事異動命令だとして違法となります。配置転換や転勤命令についてのルールを理解したうえで適切な方法で行うことが必要です。
(2)職務怠慢な従業員に対する懲戒処分
指導によっても職務怠慢の問題が改善しない場合、従業員に対する懲戒処分を検討することになります。懲戒処分には、「戒告・譴責・訓告」、「減給」、「出勤停止」、「降格」、「諭旨解雇」、「懲戒解雇」などがあります。
「①職務怠慢の程度、②会社に与えた損害や企業秩序への悪影響の程度、③本人の懲戒処分歴や職務上の地位、④会社がこれまで同種事案についてとった対応とのバランス」など様々な事情を考慮して、適切なレベルの懲戒処分を選択する必要があります。
ただし、懲戒処分には、就業規則上の根拠が必要になるなど、法律や判例により一定の制限が設けられています。ルールに違反した懲戒処分は、従業員から訴訟を起こされた場合に無効となったり、企業が賠償を命じられたりするリスクがあるため、注意が必要です。
▶参考情報:懲戒処分については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
懲戒処分を行う場合は、会社側の立場で専門的なサポートを提供する弁護士に事前にご相談いただくことをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしています。ご利用ください。
4,職務怠慢な従業員を解雇できる?
では、上記のような対応をしても職務怠慢が改善されない場合、従業員を解雇することはできるのでしょうか?
結論から言うと、解雇自体は可能です。ただし、十分な検討なく職務怠慢を理由とする解雇を行った場合、その解雇が無効とされるリスクも小さくありません。
従業員の解雇については、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)というルールがあり、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と法律に定められています。
この解雇権濫用法理は職務怠慢を理由とする解雇についても適用されます。職務怠慢を理由とする解雇の場合、解雇が有効とされるためには、以下の点が必要です。
- 1.職務怠慢について明確な業務命令を出し、それでも改善されなかったという事情があること
- 2.職務怠慢について十分な指導や懲戒処分、適性に合った職種への転換や業務内容に見合った職位への降格、一定期間内に業績改善が見られなかった場合の解雇の可能性をより具体的に伝えた上での更なる業績改善の機会の付与などの手段を講じたうえで解雇に至っていること
例えば、過去の裁判例として、以下のような判断事例があります。
参考裁判例:
日本アイ・ビー・エム事件(東京地方裁判所判決平成28年3月28日)
日本アイ・ビー・エムが大学院卒の勤続12年目の正社員を能力不足を理由に解雇した事案です。この従業員には、他の従業員より業務量が少ないため上司が業務を増やそうとしても自分は能力がないと言って拒否する、業績改善プログラムの実施も拒否する、上司との面談を避ける、会議に参加しない、業務中に居眠りをする、ジーパン・サンダル等で執務して注意を受けても改めない等の問題がありました。
●裁判所の判断
この事案において、裁判所は、解雇が「適性に合った職種への転換や業務内容に見合った職位への降格、一定期間内に業績改善が見られなかった場合の解雇の可能性をより具体的に伝えた上での更なる業績改善の機会の付与などの手段を講じることなく行われた」と指摘して、解雇は無効と判断し、会社を敗訴させました。
判断の理由として、裁判所は、①新たな業務に対して消極的であったとしてもそのような態度を続けると業務命令違反であるなどとして明確な指示がされていたとまでは認められないことや、②業務量が少ないとしてもその業務内容自体には問題があるとは認められないこと、③そのほかの問題行動は解雇事由となるほど重大なものとはいえないこと、④従業員の雇用について職種や勤務地の限定があったとは認められないことなどを挙げています。
▼参考動画:日本アイ・ビー・エム事件(東京地方裁判所判決平成28年3月28日)については、この記事の著者 弁護士 西川暢春が「職務怠慢・業務に消極的な社員!解雇はできる?弁護士が解説」の動画内で、裁判例を説明しながら、「職務怠慢や業務に消極的であることを理由とする解雇のリスク」「職務怠慢の問題がある従業員についての対応」について詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
どのくらい指導や職種転換、降格等の措置をとっていれば十分であると認めてもらえるのかといった点については明確な基準がなく、会社としては十分指導したと思っていたけれども、裁判で指導が不十分だったと判断されてしまうケースも少なくないのが実情です。
職務怠慢の問題がある従業員の解雇を検討する場合は、必ず弁護士に相談いただくことをおすすめします。
▶参考情報:解雇については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
5,職務怠慢を理由とする損害賠償請求は可能?
では、従業員の職務怠慢により、会社に損害が発生した場合、会社が従業員に対して損害賠償を請求することはできるのでしょうか。
労働者は会社(雇用主)と労働契約を結んでおり、従業員は職務を適切に遂行する義務(労務提供義務)があります。この義務に違反して、職務怠慢により会社に損害を与えた場合、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法第415条)または不法行為(民法第709条)による損害賠償請求が原則として可能です。
ただし、従業員に対する損害賠償請求については、「危険責任の法理」や「報償責任の法理」により制限されます。
「危険責任の法理」とは、使用者(会社)が事業のために従業員を用いて危険を生み出しているため、危険を生み出す者として使用者も損害を負担すべきであるという考え方です。また、「報償責任の法理」は使用者(会社)が従業員を用いて利益を得ている以上、その活動により損害が生じた場合は、使用者もその損害も負担すべきであるという考えのことです。
このような考え方から、職務怠慢で従業員に過失がある場合でも、それが故意や重大な過失によるものとまでは言えないと判断される場合、損害賠償請求自体が認められないケースもあります。また、従業員への請求自体は認められる場合でも、判例上、故意による加害行為の場合を除き、損害全額の請求は認められないことがほとんどです。
従業員が業務を懈怠したために損害が発生したとして、会社が従業員に対し損害賠償を請求した事例を一つご紹介します。
参考裁判例:
エーディーディー事件(京都地方裁判所判決 平成23年10月31日)
コンピューターシステム会社でシステムエンジニアとして勤務していた従業員が、ある時期から一日中パソコンの前で下を向いて座ったまま過ごすなどして、まともに業務を行わなくなったために業務が著しく遅滞してしまい、それにより取引先等との関係が悪化し売上が従来より減少したとして、会社が従業員に対し2034万円の損害賠償請求をした事案です。
●裁判所の判断
裁判所は、従業員に故意または重過失があったとは認められないこと、会社側が損害であると主張する売上減少やノルマ未達などはある程度予想できるところであり、報償責任・危険責任の観点から本来的に使用者が負担すべきリスクであると考えられること、会社の主張する損害額は2000万円を超えるものであり、従業員が受領してきた賃金額に比しあまりにも高額であることなどからすると、会社側が主張する損害は、結局は取引関係にある企業同士で通常に有り得るトラブルなのであって、それを労働者個人に負担させることは相当ではないため、会社の損害賠償請求は認められないと判断しました。
一方で、職務怠慢について故意や重大な過失がある事案では、従業員に対する損害賠償請求が認められています。
エーディーディー事件(京都地方裁判所判決平成23年10月31日)で、裁判所は、「労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在化するものであるといえる(報償責任)し、業務命令内容は使用者が決定するものであり、その業務命令の履行に際し発生するであろうミスは、業務命令自体に内在するものとして使用者がリスクを負うべきものであると考えられる(危険責任)ことなどからすると、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損害の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、労働者に対し損害の賠償をすることができると解される」と判示しています。
6,公務員の職務怠慢に関する告発や処分事例
次に、公務員の職務怠慢についてニュースになる例も少なくありません。
例えば、人事院が定める国家公務員の懲戒処分の指針では、職務怠慢は減給又は戒告の対象になると定められています。
▶参考:懲戒処分の指針について(人事院事務総長発)最終改正:令和2年4月1日職審-131
「勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。」
・参照元:人事院「懲戒処分の指針について」
公務員が職務怠慢で処分された事例として、以下のようなものがあります。
(1)東京都狛江市の事例
平成25年、福祉保健部の男性職員と、建設環境部の女性職員が勤務時間中に業務用パソコンを用いて極めて私的な文書のやりとりをしていた事案です。
狛江市は男性職員に対して停職5か月、女性職員に対して停職2か月の処分を科しました。
(2)熊本県熊本市の事例
令和6年、交通局の男性職員が決済を得ないまま書類を関係者に提出し、また、同書類を提出するにあたり公印の無断使用を計5回行った事案です。また、提出書類には積算の誤りがあったため、関係者への支払いに際して過大請求や過少請求が生じました。
熊本市は男性職員に対し、停職3か月の処分を科しました。
▶参照元:「熊本県熊本市の事例」の公表内容
(3)千葉県印西市の事例
令和4年4月から令和7年2月までの間に、市民部の男性職員が勤務時間中に職場を離脱し、1日4回程度、自身が管理責任者である公共施設内において喫煙行為を行った事案です。
印西市は、男性職員の行為は勤務態度不良に当たるとして、戒告処分を科しました。
▶参照元:「千葉県印西市の事例」の公表内容
公務員の懲戒処分については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(4)公務員が職務怠慢で処分されたケースで、処分の適法性をめぐり裁判で争いになった事例(東京地方裁判所判決平成27年6月27日)
防衛省の防衛事務官として勤務していた職員が分限免職処分を受け、その取り消しを求めた事案です。
この職員は日常的に以下のような問題行動を繰り返していました。
- 執務室で勤務せず、無断で女子更衣室に閉じこもって勤務する
- 指示された業務を遂行しない
- 他の職員に対し暴言を吐く
- 度々無断で職場離脱する
- 業務上の関係がないにもかかわらず毎日複数回(多いときは1日30回程)特定の職員の携帯電話に電話する
これらの問題行動により業務に多大な支障が出ていたため、防衛省は職員に対しメンタルヘルス外来への受診をすすめたり、何度も勤務態度を改善するよう指導を繰り返しましたが、改善は見られず、約5年間にわたり上記のような問題行動を繰り返していました。
●裁判所の判断
裁判所は、日々の指導や職場環境の変更、訓戒など、更正のために必要な措置を講じたものの改善が見られなかったことからすると、防衛省が行った処分には客観的で合理的な根拠があり、また、裁量権の範囲の逸脱や濫用等の違法があったとは言えないとして、本件処分は適法であると判断しました。
7,咲くやこの花法律事務所がサポートした職務怠慢トラブルに関する解決事例
咲くやこの花法律事務所では、従業員の職務怠慢などの問題社員対応に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。
咲くやこの花法律事務所がサポートした解決事例の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。
(1)遅刻を繰り返し、業務の指示に従わない問題社員を弁護士の退職勧奨により退職に至った解決事例
本件は、遅刻を繰り返し、業務の指示に従わない問題社員の退職勧奨について、咲くやこの花法律事務所が依頼を受け、従業員に退職するよう説得することで、最終的に退職を承諾してもらったケースです。
●解決結果
弁護士による退職勧奨の結果、1ヶ月分の給与の支払いと残っている有給休暇を買い取るという条件で、退職してもらい、解決することができました。
8,従業員の職務怠慢の問題に関して弁護士に相談したい方はこちら
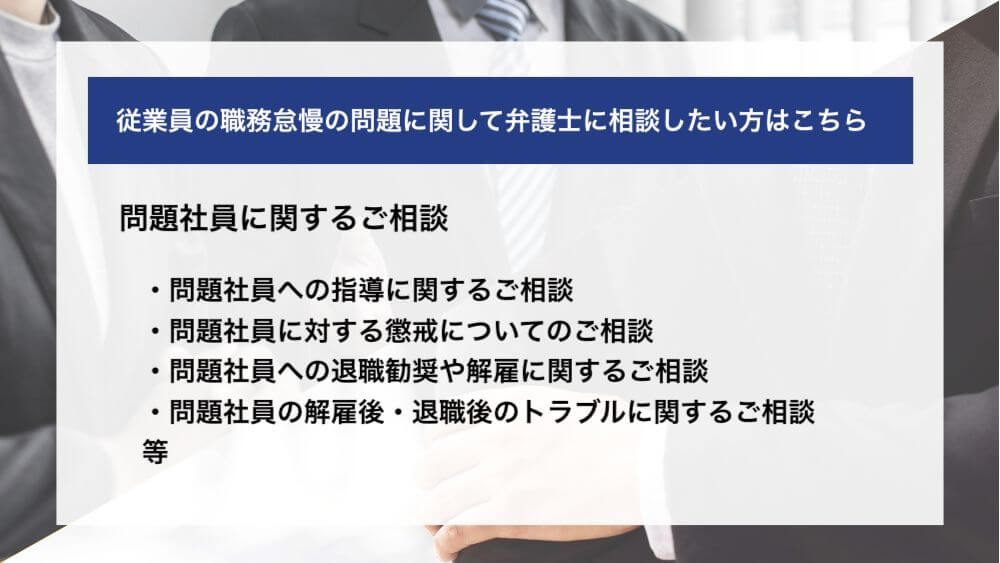
咲くやこの花法律事務所では、職務怠慢などの問題がある従業員への対応について企業側の立場でご相談をお受けし、解決してきました。最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。
▶参考:咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関する弁護士への相談サービスに関して、よくある相談事例をはじめ、実際にサポートした一部の実績紹介、弁護士によるサポート内容、弁護士に相談するメリット、弁護士費用について、以下の動画で詳しく解説しますので、あわせてご参照ください。
(1)問題社員に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、職務怠慢などの問題がある従業員への対応について、以下のご相談を承っています。
- 問題社員への指導に関するご相談
- 問題社員に対する懲戒についてのご相談
- 問題社員への退職勧奨や解雇に関するご相談
- 問題社員の解雇後・退職後のトラブルに関するご相談
事務所の解決経験を生かしてサポートします。お困りの際は早めにご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
※相談方法は、来所相談のほか、オンライン相談や電話相談も可能
(2)顧問弁護士サービス
咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに人事労務全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。
今回解説した職務怠慢な従業員に対する対応は、会社が日ごろから正しい労務管理を行っていることが前提となっています。例えば職務怠慢の問題がある従業員を懲戒する場合は、まず書面で明確に業務命令を出していることが前提になりますし、適切な懲戒処分についての規定を整備した就業規則が社内で周知されていることが必要になります。
従業員の職務怠慢の問題について正しい対応ができていなかったり、就業規則の整備に問題があるなど、会社の労務管理が適切にできていないと、いざトラブルが起きた際に対応できないということになりかねません。
いざというときに企業として必要な対応がとれるように、顧問弁護士のサポートを受け、日ごろから人事労務についての整備に取り組むことが重要です。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご覧ください。
(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
9,まとめ
この記事では、従業員の職務怠慢への対応や懲戒処分等について解説しました。
職務怠慢とは、自身の業務上の義務や責任を果たさず、職務の遂行を怠ることを言い、具体的には以下のような行為がこれにあたります。
- 無断欠勤・無断早退・無断遅刻
- 正当な理由のない欠勤・早退・遅刻
- 無断での職場離脱
- 業務命令違反
- 勤務不良
職務怠慢の問題がある従業員への対応としては、以下の点が重要です。
- 職務怠慢の問題があればすぐに指導する
- 他の部署等に異動させて適性を見る
- 懲戒事由にあたる場合は懲戒処分を行う
懲戒処分には、「戒告・譴責・訓告」、「減給」、「出勤停止」、「降格」、「諭旨解雇」、「懲戒解雇」などがあり、①職務怠慢の程度、②会社に与えた損害や企業秩序への悪影響の程度、③本人の懲戒処分歴や職務上の地位、④会社がこれまで同種事案についてとった対応とのバランスなど様々な事情を考慮して、適切なレベルの懲戒処分を選択する必要があります。そして、懲戒処分を経ても改善されないときは、解雇や退職勧奨による解決を検討することが必要です。
ただし、懲戒処分や解雇、退職勧奨等は、後で従業員から訴えを起こされるリスクがあるため、実施する際は事前に弁護士に相談の上、慎重に進めることをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所では、問題社員に関するトラブルについて、多くの事業者様からのご相談をお受けし、解決してきた実績があります。職務怠慢の問題についてお悩みの事業者様は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
10,【関連】職務怠慢などの問題社員に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「職務怠慢とは?処分はどうすべき?対応方法や解雇についても解説」について、わかりやすく解説しました。従業員の職務怠慢の対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連する問題社員に関するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・モンスター社員とは?問題社員の特徴や対応を事例付きで弁護士が解説
・やる気のない社員の特徴と対処法!クビは問題あり?【放置は悪影響です】
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年9月17日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」退職時の誓約書に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
 06-6539-8587
06-6539-8587